【全文】「ここに教会があるのはすばらしい」マタイ17章1~8節
みなさん、おはようございます。今日も共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。そして今日はこどもだけではなく信仰の大先輩の声もこの教会に響きわたりました。いつも信仰を支えて下さる神様に感謝します。
さて2月3月と地域活動と福音について考えてきました。今回が最後です。
私たちは月に2回、第3金曜日と第4金曜日に、「こひつじ食堂」というこども食堂を開催しています。なぜ金曜日の開催としたのかは、当初は深い意味はなく教会の他の行事との関係でそうなりました。こちら側の都合だったのですが、金曜日の開催というのも好評をいただいています。
こどもも大人も1週間でいろいろなことがあります。こどもたちの周りにいれば、忙しさに追われ、心配ごとはつきず、平穏な日は少ないものです。
その1週間が終わり、これから休みに入るのが金曜日の夜です。金曜日の夜は疲れているけどほっとできる日、ワクワクする日です。こどももちょっとだけ夜更かししていい日です。
忙しい1週間に疲れた人が、金曜日に教会に集います。食事をして、元気になって、励まされます。多くの利用者は次の日の朝の予定を気にせず、閉店までのんびりします。そしてまたそれぞれの場所へと向かってゆきます。楽しかった、おいしかったと言いながら帰ってゆきます。
私は繰り返しその光景を見ながら「ここに教会があるのはすばらしい」と感じます。月2回の金曜日、多くの人が教会に疲れた心を癒しに来るのです。きっと地域の人々も「ここに教会があってよかった」「ここに教会があるのはすばらしい」と思ってくれているはずです。つらいこと、苦しいことがあっても、ここで充電し、「おいしかった」「楽しかった」と言って、また現実に向かってゆきます。その背中を、私はそっと見守っています。
私たちクリスチャンはもとより、毎週日曜日に集い、疲れを癒し、励まされています。その喜びのサイクルを毎週ずっと味わっています。私には地域の人もそれに少しずつ似てきていると思います。私たちと同じ様に様々な現実の中から教会に集い、希望を受け取り、ここに教会があるのはすばらしい、そう感じて帰ってゆくのです。
いつかはわからないけれど、いつの日か利用者の方もイエス様に出会う日がくるでしょう。ずっと先かもしれませんが、日曜日に礼拝するサイクルに連なる人がもっと起こされるはずです。その時、きっとこども食堂よりももっと深い喜びを味わってもらえるはずです。
礼拝に集うこと、食堂に集うこと、私にはそれがどこか重なって見えています。きっとどちらも同じ様に神様に招かれる、教会に行く、神様が共にいる、励まされる、それぞれの場所に派遣されることなのではないでしょうか。
そして私は今日の個所も教会に集う事と共通していることがあると思います。今日は弟子たちの体験した山上の集いと、私たちの礼拝・こども食堂の共通点に目を向けたいと思います。礼拝もこども食堂もこの山上の集まりも、どれもが「ここにいるのはすばらしい」と思えることだということを見てゆきたいと思います。聖書を読みましょう。
今日はマタイによる福音書17章1~8節までをお読みいただきました。イエス様は弟子たちと共に高い山に登ったとあります。
1節に「高い山」に登ったとあります。マタイ福音書において山は非常に重要な場所です。イエス様はいつも大事なことを話す時は山に登りました。山上の説教がまさにそうです。それは礼拝をする場所、祈る場所のことです。日常とは少し違う場所です。イエス様は大事なことを祈る時はしばしば山に登りました。イエス様にとって山の上は、神聖な場所、祈りの場所、神との出会いの場所、愛を教える場所でした。
イエス様はそこに一緒に行こうと私たちを招いてくださっています。様々なことが起こる日常を離れて、そこへ行こうと招いています。これはイエス様から弟子たちを誘ったものでした。それはイエス様の招きでした。弟子たちは一人で山を登るのではありません。イエス様に先導されて登るのです。
このことは礼拝に参加する私たちとも共通しています。イエス様に「みんなついておいで」と招かれ、山の上の礼拝に集うのです。そしてこども食堂の利用者も同じです。さまざまなきっかけでこども食堂を知り、食事をしにきます。でもきっとそこにも神様の招きがあるのでしょう。自分で来ているように見えて、神様に招かれているものです。私たちもこども食堂の利用者も神様に招かれて集っています。
イエス様と共に山に登った弟子たちは、山の上でイエス様とモーセとエリヤが語り合い、光り輝く姿を見ることになります。モーセとエリヤは旧約聖書の中でもっとも神に熱心に従った人たちでした。イエス様もその人たちと並んで立っています。イエス様は輝いていました。
その時、弟子ペテロが言いました。私は本当にこの次の4節の言葉が好きです。ペテロは「私たちがここにいるのはすばらしいことです」と言いました。イエス様と出会い、そのすばらしさに感動して、ここに居てよかったと思ったのです。日常とは違う場所に呼び出されて、イエス様との時間を共にすることができて、よかったという意味です。
私は4節を現代の私たちに置き換えるなら「ここに教会があってよかった」「ここに教会があるのはすばらしいことだ」ということに、置き換えることができると思います。そしてその教会とは礼拝だけにはとどまりません「ここにこども食堂があってよかった」という思いも含まれるでしょう。
「私たちがここにいるのがすばらしい」という言葉からは、強い感動が強く伝わって来ます。そして「あなたはすばらしい」と言うだけではなく「あなたとここにいることができてすばらしい」という言葉は、そこから神様への感謝も伝わってきます。
ペテロはこれに対して何かしようと思いました。形に残るものにしようと思い、小屋を3つ建てようと提案をしました。しかし聖書にはそれが立てられたとは書いていません。おそらく必要ないと言われたのでしょう。天から「これに聞け」という声が聞こえました。それは、建物はいい、それより神の言葉を聞けという意味です。
私たちは誰よりも建物の大切さを知っています。ここに教会があるのはすばらしいともっと感じてもらえるように、教会を建て続けようとしています。でも最も大事なことは、イエス様に聞くことであるということを忘れないようにしましょう。私たちは建物に集まっているわけではありません。あるいは食べるために集まっているのでもないのです。イエス様に聞くことが、何よりも大事です。私たちは、神様の言葉を聞くために集まっています。
弟子たちはこれを聞いて、ひれ伏したとあります。ひれ伏したという言葉は、礼拝をしたという意味も含む言葉です。その言葉を聞いて礼拝したのです。そしてその礼拝ではなんとイエス様が弟子たちの手を握ったのです。そしてこう言いました「起きなさい、恐れることはない」。どれほどの励ましを受けたでしょうか。弟子たちはその言葉を聞いて、また山の下へ向かってゆきます。それは日常に戻るということです。もう一度それぞれにチャレンジをしたのです。
これもちょうど日常からイエス様に招かれて日曜日の礼拝に来ること、礼拝し励まされて日常へと戻ることに似ています。そして日常から食堂に招かれて、食事をして励まされて、日常へ戻ることと似ています。
この聖書個所の前後にも目を向けましょう。16章後半ではイエス様によって十字架と復活が暗示されています。17章の続きも再び、十字架と復活が暗示されています。この個所は苦難に挟まれた箇所です。苦難の合間に山に登り、祈り、安らぎと、希望を受け取っている箇所です。イエス様と弟子たちは苦難の中から山に登り、また山を下り苦難へと向かってゆきます。それは日常→礼拝→日常と同じサイクルです。そして日常→教会のこども食堂→日常と同じサイクルです。
弟子たちも私たちも同じです。それぞれに忙しさや痛みや、苦しみのある1週間です。でも私たちは今日ここに集いました。ここに集えることは何とすばらしい事でしょうか。私たちは今日も神の言葉との出会い、神様の言葉を聞きました。私たちはそこで励ましを受け取ります。今日ここでイエス様に手を握られるのです。そして私たちにも「起きなさい、恐れることはない」と語ってくださるでしょう。そしてまた次の1週間も共に歩もうと言われます。
私たちは本当に「ここにこの教会があるのはすばらしい」と感じています。神のみ言葉を聞き、希望を持ち、また歩み出せるこの場所があることに、心から感謝しています。私たちだけではなく多くの人々がこの教会で神の励ましを受け取り、それぞれの生活に戻ってゆきます。それぞれ大変な1週間ですが、ここでそのための神の希望をいただきます。
今日、イエス様は私たち一人ひとりの手を握り、『起きなさい、恐れることはない』と語りかけてくださっています。私たちはこの言葉を胸に、次の一週間も力強く歩み出しましょう。そしてこの教会をもっと「ここに教会があるのはすばらしい」と言われる教会、人々を招き、励ます教会にしてゆきましょう。
2か月間、地域活動と福音についてみてきました。多くの福音が地域への活動の中に含まれています。私たちは他者との関わりの中で福音を見つけることができるのです。たくさんの人に出会うと、たくさんの福音を見つけることができます。私たちはこれからもさまざまな行事を通じて、地域の人々と出会ってゆきましょう。お祈りいたします。
「ここに教会があるのはすばらしい」マタイ17章1~8節
「主よ、わたしたちがここにいるのは、すばらしいことです。」マタイ17章4節
私たちは第3・第4金曜日に、こども食堂を開催しています。忙しい1週間を送った人たちが、金曜日に教会の食堂に集い、食事をし、励まされ、またそれぞれの場所へと向かってゆきます。私はその光景を見て「ここに教会があるのはすばらしい」と感じます。きっと地域の人々もそう思ってくれているはずです。
礼拝に集うこと、食堂に集うこと、私にはそれが重なって見えています。きっとどちらも同じ様に、神様に招かれる、教会に行く、神様が共にいる、励まされる、それぞれの場所に派遣されることなのではないでしょうか。そして私は今日の個所も教会に集う事と共通していることがあると思います。聖書を読みましょう。
マタイ福音書において山は非常に重要な場所で、イエス様はいつも大事なことを話す時は山に登りました。イエス様にとって山の上は、祈りの場所、神との出会いの場所でした。イエス様は日常を離れてそこに一緒に行こうと私たちを招いてくださっています。このことは礼拝に参加する私たちとも共通しています。そしてこども食堂の利用者にも共通しています。
ペテロは「私たちがここにいるのはすばらしいことです」と言いました。現代の私たちに置き換えるなら「ここに教会があるのはすばらしいことだ」「ここにこども食堂があってよかった」ということに、置き換えることができます。
ペテロはそこに小屋を3つ建てようと提案をしました。しかし天から「これに聞け」という声が聞こえました。それは、建物はいい、それより神の言葉を聞けという意味です。私たちは誰よりも建物の大切さを知っています。でも最も大事なことは、イエス様に聞くことであるということを忘れないようにしましょう。
弟子たちはこれを聞いて、ひれ伏したとあります。ひれ伏したという言葉は、礼拝をしたという意味も含む言葉です。これは礼拝です。そしてこの礼拝ではイエス様が弟子たちの手を握って、こう言いました「起きなさい、恐れることはない」。弟子たちはどれほどの励ましを受けたでしょうか。弟子たちはその言葉を聞いて、また山の下、日常へと戻ってゆきました。これもちょうど日常からイエス様に招かれて日曜日の礼拝に来ること、礼拝し励まされて日常へと戻ることに似ています。そして日常から食堂に招かれて、食事をして励まされて、日常へ戻ることと似ています。
私たちは本当に「ここにこの教会があるのはすばらしい」と感じています。神のみ言葉を聞き、希望を持ち、また歩み出せるこの場所があることに、心から感謝しています。私たちだけではなく多くの人々がこの教会で神の励ましを受け取り、それぞれの生活に戻ってゆきます。
今日、イエス様は私たち一人ひとりの手を握り『起きなさい、恐れることはない』と語りかけてくださっています。私たちはこの言葉を胸に、次の一週間も力強く歩み出しましょう。そしてこの教会をもっと「ここに教会があるのはすばらしい」と言われる教会、人々を招き、励ます教会にしてゆきましょう。お祈りします。
【全文】「教会の未来と神の恵み」マタイ12章22~32節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。この礼拝でこどもの声が、そしてこの地域のこどもの声が響きます。そして私たちは未来でもこどもの声がする教会となることを目指してゆきましょう。
今日はこの後、来年度の計画を立てる総会が開催されます。今日の総会および5月の総会では主の晩餐、会堂建築、規約改正など特に重要な協議事項がありますので、会員の方はぜひ参加をしてください。私たちはキリスト教の中でもバプテストという民主主義を大事にするグループです。全員が遠慮なく議論しながら物事を決めていく教会です。特に議論が必要な課題は、建築のことです。私たちは、新会堂を建てるのか、それともこの会堂を修繕するのか、そしてそれぞれの場合どのように手を加えるのか良く議論しましょう。議論するとは一方的に意見を述べ合うことではなく、互いが考えを変え、受け入れ合うことです。私たちはそれぞれの意見を伝え、受け入れ合い、前に進んでゆきましょう。
立ち止まってもっとゆっくりと考えたいと思うかもしれません。時にはブレーキを掛けることも大事です。でも平塚教会は今が変化してゆくチャンスだと思います。そしてこのチャンスはいつまでも続くものではないでしょう。この時を逃さず、大胆な変化をしてゆきたいと思います。
建築の基本計画は5月中旬までに終える予定です。他の教会は10年かけることもあります。私たちの教会はあまりに議論が短いかもしれません。でも前に進みたいと思っています。それは私たちの教会は他の教会よりもありたい姿が明確になっているからです。他の教会は10年間ありたい姿を考えます。しかし私たちはこの教会を、この礼拝を、この仲間との交わりを続けてゆきたい、こどもの声がする教会にしたい、地域にもっと開かれた教会になりたい、こども食堂や広場を続けたい、そのようなありたい姿がはっきりしています。私たちは多少の違いはありますが、こどもを受け止めてゆくという方向で、すでに一致できています。そして平塚教会の場合、すでにそれに向けた取り組みも十分に始まっています。他の教会とは大きく状況が違うと思っています。だから短い期間できっと結論にできると思います。前に進みましょう。
私は実は他の心配をしています。それは、この問題は私たちの教会だけで決めるものではないということです。理事会の3分の2の賛成と連盟300教会の過半数の承認が必要です。他の教会に私たちの計画を訴え、賛同してもらわなければなりません。それはとても高いハードルです。私は実は教会の中の一致よりも、様々な立場や考え方を持った理事会や他の教会の賛同を得る方が難しいと思っています。来年度1年間をかけて、連盟の理事会と全教会を説得します。牧師や執事の対外的な働きが大きくなることを祈って欲しいです。次の1年は平塚教会のために、対外的な情報発信に軸足を置くことになりますが、それは平塚教会のためだけではなく、他の教会にとってもよい事例になると思います。どうぞお祈りください。
教会の中でもまだまだ細かな部分を皆さんと話し合ってゆきます。会堂の中はこれまでどおり履き替えるのか土足なのか、講壇の高さはどうするのか、答えのないことばかりを話し合ってゆかなければなりません。私たちは正解のない問題の中で、議論し、互いに受け入れ合い、互いに変わってゆきましょう。
今日の聖書から、私たちは議論し、互いに受け入れ合い、互いに変わってゆくこと、どんな時も神様が私たちを導いてくださるということについて考えます。聖書を読みましょう。
マタイによる福音書12章22~32節までをお読みいただきました。ある時、目が見えず話すこともできないという二重の障がいがある人がいました。生まれつきの障害だったのでしょうか?それとも昔は見ること、話すことができ、何かの事故や病気でそうなってしまったのでしょうか?わかりません。この人は一人でできないことが多い人だったかもしれません。どこへ行くにも常に人に誰かに手を引いてもらう必要がありました。他者とのコミュニケーションもとりづらかったことでしょう。イエス様はこの人を癒したとあります。それは神様の一方的な恵みによる癒しでした。
聖書にはこの人が良い人だった、悪い人だったという評価はどこにも記されていません。ただイエス様が癒したとしかありません。ここから感じるのは、神様は良い事をした人にだけ良いものを与えるお方ではないということです。ここでは神の愛と導きとは、人間に向けて一方的なものであるということが示されています。
私たちが聖書を読む時、そして生きる時、まずこの神様の恵みへの信頼が必要でしょう。神様はたとえ私たちが動けず、見えず、聞こえず、しゃべれなくなっても、私たちに良いものを与えてくれる方なのです。私たちは全員、やがて若さを失い、病になり、自由に動けなくなる日が来るでしょう。それぞれも、そして教会もそうかもしれません。いつか心の支えであった教会に来られなくなって、寂しいと思う時が来るかもしれません。でも忘れないでいたいのは、神様の恵みは状況に関わらず絶対に続くものだということです。何ができなくなっても、何があっても神様は必ず私たちに良いものを与えられるのです。私たちはこの信頼をもって聖書を読み、人生を生きてゆきましょう。
24節以降を見ます。イエス様はこの地域の病気の人、寂しいと思っている人を癒す働きをしていました。多くの人がそれを称賛しました。しかし一歩外にでれば、イエスの評価は様々でした。ある人は、あれは一見よい事のように見えて実は大きな誘惑が潜んでいる、気を付けなくてはいけないと言いふらしました。あれは神様の導きではない。目の前の人が喜ぶようなことをしているだけだ。間違ったことだと言ったのです。この発言は議論ではありません。それはただの拒絶と批判です。本当の議論とは、互いの考えを尊重し、共に変化することです。これは悪魔の力で悪魔を追い出しているというめちゃくちゃな論理、拒絶と批判でした。イエス様はそれに反論をしています。
イエス様は悪魔同士で、内輪争いがおきたら、立ち行かないではないかと語りました。これは非常に説得力のある内容でした。イエス様もイエス様に反対する人もみな、内輪もめ、拒絶と批判、分断の力の大きさを知っていたのです。イエス様と反対する人には意見の違いがありましたが、そこで両者が納得できたことがあります。それは内輪で争いは、力の強い悪魔でさえ立ち行かなくさせる力があること、内輪争いは人の力をそぐ大きな力があるという事でした。25節、どんな支配も、どんな国も、どんな町も家も、そしてどんな教会も内輪で争えば、荒れてはててゆく。その言葉は、敵味方の誰もが認める、大きな説得力があったのです。
私たちもこの後、熱心な議論をしてゆきたいと思っています。でも議論と他者を批判する内輪もめとは違います。きっとよく議論することと、拒絶と批判、分断の危うさを含みます。私たちはそれに立ち向かってゆかなければなりません。私たちはその時どのように内輪もめせずに、議論すべきでしょうか。私たちはまず一致していることに目を向けましょう。神様の愛は一方的で、どんな人にも恵み深い方だ、どんな時も神様が導いてくださる方です。どのような議論をしても、そしてたとえしなかったとしてもそれは変わらないということを忘れないでいましょう。私たちはすでに神様はどんな時も、どんな人にも愛を注ぎ、導いてくださるという最も重要な部分で、一致することができています。私たちは自分の希望が叶わないことがあるかもしれませんが、神様がすべての導いてくださることを信じる、そのことを土台に共に議論し、歩みましょう。
31節以降には、人間にはすべての罪と冒涜が赦されるとあります。赦されるとは、私たちのすべての失敗や不足をすべて受け止め、私たちが悔い改めて変わろうとする時、神様は必ず次のチャンスをくださるということです。神様は私たちが悔い改めて変わろうとする時、次は罪と冒涜ではなく、愛と励ましを語るようにと、私たちを何度でも赦してくださいます。私たちは何度でも悔い改め、変わることができるのです。何度でも変わることができる、それが神様の愛です。私たちは全ての問いに正解をしてゆくことはできないでしょう。教会も、お互いもたくさんの失敗をするでしょう。でも神様は私たちに、悔い改めながら、赦しをこいながら、前に進むようにと言っています。
そして赦されないことも挙げています。それは聖霊への冒涜です。神様の私たちへの赦しには際限がありません。しかしここでは聖霊への冒涜だけは赦されないと書いてあります。聖霊の冒涜、それは悔い改めずに、自分を変えずに前に進もうとすることと言えるでしょう。神様の愛と導きに目をむけず、自分は間違っていない、悔い改めと変化が必要ないと思って生きることは、神様の際限のない赦しへの拒絶です。際限のない神様の愛の前に、自分の貧しさ、欠けに目を向け、自分が変わってゆくということが大事です。私たちは難しい話の中で、大小の内輪もめが起こるでしょう。でも私たちは議論し、互いに悔い改めあい、互いに赦されながら、互いに変わってゆきましょう。そして思い通りにならなくても、絶対に神様の導きがあると信じ、前に進みましょう。
私はこの地域の人にも、私たちが多少の内輪もめをしながらも、互いに話し合う、互いに悔い改める、互いに赦されながら、互いに変わる姿を良く見て欲しいと思っています。お祈りします。
「教会の未来と神の恵み」マタイ12章22~32節
どんな国でも内輪で争えば、荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも、内輪で争えば成り立って行かない。 マタイによる福音書12章25節
今日はこの後、来年度の計画を確認する総会が開催されます。私たちはキリスト教の中でもバプテストという民主主義を大事にするグループで、議論しながら物事を決めていく教会です。今、特に大切な議論は新会堂を建てるのか、それともこの会堂を修繕するのかという点です。議論するとは意見を述べ合うだけではなく、互いが考えを受け入れ、変わってゆくことです。今日は、私たちは議論し、互いに受け入れ合い、互いに変わってゆくこと、どんな時も神様が私たちを導いてくださるということについて考えましょう。
マタイによる福音書12章22~32節までをお読みいただきました。イエス様は二重に障がいのある人を癒したとあります。それは神様の一方的な恵みによる癒しでした。神様は良い事をした人にだけ良いものを与えるお方ではありません。神様はたとえ私たちが動けず、見えず、聞こえず、しゃべれなくなっても、私たちに良いものを与えてくれる方なのです。私たちは全員、やがて若さを失い、病になり、自由に動けなくなる日が来るでしょう。それぞれも、そして教会もそうかもしれません。でも神様は何ができなくなっても、何があっても必ず私たちに良いものを与えられるのです。私たちはこの信頼をもって聖書を読み、人生を生きてゆきましょう。
24節の発言は議論ではなく、ただの拒絶と批判です。本当の議論とは、互いの考えを尊重し、共に変化することです。イエス様も反対する人もみな、内輪もめ、拒絶と批判による分断の力の大きさを知っていました。25節、どんな支配も、どんな国も、どんな町も家も、そしてどんな教会も内輪で争えば、荒れてはててゆくのです。
私たちもこの後、熱心な議論をしてゆきたいと思っています。しかし議論と他者の拒絶と批判による内輪もめとは違うものです。きっと議論することは、分断の危うさを含んでいます。
私たちはまず一致していることに目を向けましょう。神様の愛は一方的で、どんな人にも恵み深い方です。どんな時も神様が導いてくださるお方です。私たちはその最も重要な部分で一致することができています。私たちは自分の希望が叶わないことがあるかもしれませんが、神様がすべての導いてくださることを信じる、そのことを土台に共に議論し、歩みましょう。
私たちは何度でも悔い改め、変わることができます。神様の私たちへの赦しと愛には際限がありません。しかし自分は間違っていない、変わる必要ないと思って生きることは、神様の際限のない赦しへの拒絶です。際限のない神様の愛の前に、自分の貧しさ、欠けに目を向け、自分が変わってゆくということが大事です。私たちは難しい議論の中で、大小の内輪もめが起こるでしょう。でも私たちは議論し、互いに悔い改めあい、互いに赦されながら、互いに変わってゆきましょう。そして思い通りにならなくても、絶対に神様の導きがあると信じ、前に進みましょう。お祈りします。
【全文】「原発は罪です」マタイ12章33~37節
善い人は、良いものを入れた倉から良いものを取り出し、悪い人は、悪いものを入れた倉から悪いものを取り出してくる。 マタイ12章35節
今日は東日本大震災と原発事故を覚えながら礼拝します。人間は罪を持った存在です。自分自身が良い人間でないことを感じる機会はなんと多いことでしょう。そして今日注目したいのは、罪とは、個人個人のレベルに限らないということです。社会には一人一人の罪が積み重なり、凝縮された、社会全体の罪があります。それは社会の罪的な構造ともいえるでしょう。
「原発は罪です」なぜなら原発は私たちの便利な生活を支えるために、誰かが犠牲になるという罪の構造だからです。危険な廃棄物を10万年間安全に保管できる場所はありません。廃棄物が次の世代に命を脅かす深刻な負担を残すとわかっていながら、それを生み出し続けている原発は罪です。その原発は過疎地の人々にお金と引き換えに受け入れてもらいます。お金で不利益を押し付ける原発は罪です。
原発は核兵器と同じ原理です。核爆弾を最初に開発した科学者オッペンハイマーは広島・長崎で原爆が使われた後「物理学者は罪を知ってしまった」と言いました。
私たちはキリスト者として、この罪の連鎖をやめさせなくてはいけません。未来の命を守るために、お金で安全を買い取られ、危険を負わされる命のために、原発をやめなくてはいけません。このように原発は宗教とは関係ない問題ではありません。罪に関わる、大きな宗教的なテーマです。
マタイ福音書12章33~37節をお読みいただきました。33節には「木の良し悪しは、その結ぶ実で分かる」とあります。原発は便利な電気を生み出す一方で、深刻な事故を起こし、放射性廃棄物を今日も作り続けています。
35節には「善い人は、良いものを入れた倉から良いものを取り出す」とあります。原発のゴミは行く当てもなくとりあえず使用済み核燃料プールという倉に眠り、処理水のタンクはいっぱいになりました。処理水はもはや倉に納めることができなくなり海へと放出されています。悪い人は、悪いものを入れた倉から悪いものを取り出してくる、それはまさにこの原発のようです。
36節には私たちが「裁きの日には責任を問われる」とあります。私たちには将来の命への責任、今の命への責任があるのです。裁きの日、それは破滅が訪れる日ではなく、もっと先にある希望の日です。神様はこの地上をすべて善いもので満たし、完成させてくださる日に向けて、私たちを導いています。裁きの日とは、この世界が神様によって過不足なく完成させられる希望の日です。
やはり、罪ではなく、神様の希望に目を向けてゆきましょう。イエス様は抜け出すことのできない、罪から抜け出し、超えてゆかれる方です。そしてその先から私たちを導いています。神の願った行動をあなたが起こすようにと導いています。私たちがその罪から抜け出そうとするとき、必ず神様の助けがあります。私たちは平和で、命を大切にする社会を築く希望をもって、生きてゆきましょう。お祈りいたします。
「原発は罪です」マタイ12章33~37節
善い人は、良いものを入れた倉から良いものを取り出し、悪い人は、悪いものを入れた倉から悪いものを取り出してくる。 マタイ12章35節
今日は東日本大震災と原発事故を覚えながら礼拝します。人間は罪を持った存在です。自分自身が良い人間でないことを感じる機会はなんと多いことでしょう。そして今日注目したいのは、罪とは、個人個人のレベルに限らないということです。社会には一人一人の罪が積み重なり、凝縮された、社会全体の罪があります。それは社会の罪的な構造ともいえるでしょう。
「原発は罪です」なぜなら原発は私たちの便利な生活を支えるために、誰かが犠牲になるという罪の構造だからです。危険な廃棄物を10万年間安全に保管できる場所はありません。廃棄物が次の世代に命を脅かす深刻な負担を残すとわかっていながら、それを生み出し続けている原発は罪です。その原発は過疎地の人々にお金と引き換えに受け入れてもらいます。お金で不利益を押し付ける原発は罪です。
原発は核兵器と同じ原理です。核爆弾を最初に開発した科学者オッペンハイマーは広島・長崎で原爆が使われた後「物理学者は罪を知ってしまった」と言いました。
私たちはキリスト者として、この罪の連鎖をやめさせなくてはいけません。未来の命を守るために、お金で安全を買い取られ、危険を負わされる命のために、原発をやめなくてはいけません。このように原発は宗教とは関係ない問題ではありません。罪に関わる、大きな宗教的なテーマです。
マタイ福音書12章33~37節をお読みいただきました。33節には「木の良し悪しは、その結ぶ実で分かる」とあります。原発は便利な電気を生み出す一方で、深刻な事故を起こし、放射性廃棄物を今日も作り続けています。
35節には「善い人は、良いものを入れた倉から良いものを取り出す」とあります。原発のゴミは行く当てもなくとりあえず使用済み核燃料プールという倉に眠り、処理水のタンクはいっぱいになりました。処理水はもはや倉に納めることができなくなり海へと放出されています。悪い人は、悪いものを入れた倉から悪いものを取り出してくる、それはまさにこの原発のようです。
36節には私たちが「裁きの日には責任を問われる」とあります。私たちには将来の命への責任、今の命への責任があるのです。裁きの日、それは破滅が訪れる日ではなく、もっと先にある希望の日です。神様はこの地上をすべて善いもので満たし、完成させてくださる日に向けて、私たちを導いています。裁きの日とは、この世界が神様によって過不足なく完成させられる希望の日です。
やはり、罪ではなく、神様の希望に目を向けてゆきましょう。イエス様は抜け出すことのできない、罪から抜け出し、超えてゆかれる方です。そしてその先から私たちを導いています。神の願った行動をあなたが起こすようにと導いています。私たちがその罪から抜け出そうとするとき、必ず神様の助けがあります。私たちは平和で、命を大切にする社会を築く希望をもって、生きてゆきましょう。お祈りいたします。
【全文】「自分を変える神」マタイ15章21~28節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日も子どもたちと共に礼拝をしましょう。3月に入り年度末です。先日こひつじ食堂の利用実績をまとめていました。数字からわかることは2020年にこひつじ食堂を始めた当初、持ち帰りのお弁当ばかりが人気で、会堂で食事をする会食の人気が無くて困っていたということです。地域の多くの人が教会の中で食事をすることにあまり乗り気ではなかったのです。会堂の中で食事をしてもらえるように、コーヒーやデザートも付けました。最初は南集会室だけやっていましたが、会堂に子供用のテーブルを4個出すことにしました。さらに重いイスを動かして、子供用のテーブルを12個並べました。会食は当初は30名程度、それもほとんど関係者でしたが、今では100名が前日の予約でいっぱいになるようになりました。
教会に大きな変化が起きたと思います。毎週日曜日に礼拝だけにしか使っていないかった会堂は、みんなが月2回集まる食堂になりました。さらにカフェになって、お茶をしてゆっくりする場所になりました。はじめた当初からするとずいぶん教会の使い方、会堂の使い方が変わってきたと思います。この礼拝堂は、礼拝の場だけでなく地域との交わりの場へと大胆に変えられてきました。
いろいろな地域活動をしていますが、私たちは出会った人たちをすぐにキリスト教へと改宗させることを目的にしているわけではありません。むしろ変化が大きいのは教会の方です。いろいろな変化が教会の側に起っています。私たちは確かに今、地域に大きな影響を与えていでしょう。でも教会は一方的に相手を変える側ではありません。教会こそ変わってゆきました。教会は出会いによって、より柔軟に、より開かれた存在へと変わってゆきました。きっと私たちはこれからもっと地域の人と出会うことによって、変わってゆくのでしょう。
私自身も出会う人が増え、仕事内容が変わってきています。様々な人と出会い話をすることで、私の考えも変化してゆきます。教会の可能性、牧師の仕事の可能性に、新しく気付かされています。もしかすると最近の教会は少し変化が多いかもしれません。でもそれはきっと、今までよりもいろいろな人と出会っているからでしょう。出会いが私たちを変え、出会いが教会を変えてゆくのです。人々との出会いを通じて、私たち自身が変えられているのです。
これは、聖書の中にも見られる姿です。たとえば、今日読む聖書箇所では、イエス様ご自身がある女性との出会いを通して、驚くべき変化をしました。マタイによる福音書15章21~28節を読んでみましょう。イエス様がどんな出会いをしたのか、そしてイエス様自身がどのように変化したのかを見てゆきたいと思います。
聖書を読みましょう。福音書の中でイエス様が、誰か自分のところに来ないかと待っている姿は多くありません。ほとんどの場合、イエス様の方から出かけて行く、相手のところに飛び込んでゆくのかイエス様のスタイルです。そしてイエス様は訪ねた先々で、様々な出会いを体験しました。福音書とはイエス様と出会った人々の物語だとも言えるでしょう。
今日イエス様はティルスとシドンの地方に行かれたとあります。この町は貿易で栄えた港町で、いわゆる富裕層が住んだ町です。イエス様にしては珍しい訪問先でもあります。というのは通常イエス様は貧しい場所や、病気の人が集まる場所を訪ねて歩いたからです。今回はいつもと違って、海沿いの豊かな人々が住む街を訪ねました。でもそのように様々な場所に出向くのがイエス様です。そして今回はひときわ印象的な出会いをします。
今回イエス様はカナンの女性と出会ったとあります。このカナンの女性とは異邦人、つまりユダヤ教の神様を信じない異教の人でした。当時のユダヤ教では異教の人との交際や会話は禁じられていました。女性に対してならなおさらです。しかしイエス様は本当にいろいろな人と出会います。このカナンの女性の娘は、悪霊にひどく苦しめられていました。おそらく何かの病気で苦しんでいたのでしょう。イエス様の時代の人はしばしば、病を悪霊の仕業だと考えました。その町にイエス様が来ました。カナンの女性は「憐れんで欲しい」と頼みます。富裕層の町です。この女性もお金持ちだったでしょうか?でも、お金では解決できない病を持っていたのです。彼女はイエス様に訴えました。「主よ、憐れんでください」ここには叫んだと書いてあります。お腹の底からイエス様の救いを求めて叫び声をあげたのです。
しかし23節イエス様は何もお答えにならなかったとあります。なぜイエス様は黙ったままで、何もしてあげないのでしょうか?続く29節では大勢のガリラヤの人々、貧しい人々の病を治したのに、どうしてここでは黙ったまま、何もしないのでしょうか? そしてイエス様は24節ではっきりと言います「私はイスラエルの家の失われた羊にしか遣わされていない」と。それは、私はユダヤ人を導くために来たのであって、ユダヤ人以外の人、異教徒を導くために来たのではないという意味です。
女性はそれでも食い下がります25節、ひれ伏して、どうか、お助けくださいと嘆願をするのです。それでもイエス様は助けようとしません。さらに「こどものためのパンを、犬にやってはいけない」と言います。それは、私はまずユダヤ人のために活動をするのであって、他の宗教の人のためには活動しませんという意味です。パンとは神様の恵みです。こどもから食べ物を取り上げて犬に渡さないのと同じように、神様の恵みを異邦人には渡さないと答えました。
しかし女性はそれでも引き下がりません。犬だってテーブルの下に落ちたパンを食べるじゃないですか、少しだけ私にもその恵みを分けて下さいと言います。それはユダヤ人以外だって、神様の恵みにあずかってもいいではないかという訴えです。私も端っこの部分でいいから、落ちた余りものでいいから分けて下さい。神様の愛はもっと広くに及ぶはずですと言ったのです。
イエス様はこの女性の信仰に感心しました。イエス様は、神様は確かに分け隔ての無く、そのように広い愛をお持ちのお方だと、この女性の話を聞いて気付いたのです。そしてイエス様は「あなた信仰は立派だ」と言います。そう言ってイエス様は、他のユダヤ人、他の貧しい人々と同様に、このカナンの女性の娘の病を癒したのです。
この物語から感じることは、何でしょうか?それはイエス様自身が大きく変化をしているということです。イエス様は変わらないお方というイメージが強くあります。しかし今日の個所からわかることは、イエス様の信仰は出会った人、自分と信じる宗教が違う人との出会いを通じて、変わっていったのだということです。イエス様の信仰でさえ、出会いによって、変わっていったのです。イエス様はこのカナンの女を通じて気づきました。最初は黙っていました。でもイエス様はこの女性によって、神様は時分が思っているよりも、もっと大きな愛をもっている方だ、そう改めて気づいたのです。そしてそれは自分の役割にも直接関係することでした。イエス様はここで自分がユダヤ人のためだけにいるのではないと気づかされました。イエス様はこの女性によって大きく変えられてゆきます。この個所はイエス様が新しい出会いによって変えられてゆくという貴重な物語です。
さて、この物語を読んで、私たちは何を学べるでしょうか?ここでのイエス様の姿勢は、私たちの人生とも深く関係していると思います。私たちは時に、自分の考えや価値観に固執してしまうことがあります。しかし出会いは私たちの視野を広げ、新しい気づきをもたらすものです。イエス様がカナンの女性との出会いによって変えられたように、私たちもまた出会いを通じて変えられていくのではないでしょうか?私たちの人生も様々な出会いによって変わってゆくものでしょう。人生とは誰に出会ったかで決まってゆくものです。出会いはお互いの「こうであるべき」という形を崩してゆきます。
教会がこひつじ食堂によって、新しい出会いによって、大きく変えられたように、私たち一人一人の人生も出会いによって変えられてゆくのです。それはイエス様も経験をしたことでした。まして私たちはイエス様よりもっと変化の可能性に開かれているでしょう。イエス様でさえ変わることを選びました。私たちは、変らない神の愛を大事にしつつも、いつも変化の可能性に開かれていることに目を向けていたいと思うのです。いつも神様の愛の大きさに気付き、変えられてゆくものでありたいのです。
もしかすると私たちは相手を変えようとばかりしているかもしれません。怒ったり、ほめたりして、相手を変えようとばかりしています。でもこの物語でイエス様は、自分が変わるということを選ばれました。私たちの人生でもこのことを覚えておきましょう。相手を変えようとするばかりの私たちです。でも本当は、自分が変わってゆくという姿の中に、イエス様の生き方があるのかもしれません。
この個所を通じて、私たちは自分と異なる他者と出会いを、神様の導きによる変化の機会と捉えることができるでしょう。イエス様がそうされたように、私たちもまた、神様の愛と変化に心を開きながら生きていきましょう。
私たちは今週も、実に様々な人がいる場所に派遣されてゆきます。私たちはただ相手を変えるために派遣されるのではありません。私たちは出会いによって、私たち自身が変わることを期待され、派遣されてゆくのです。お祈りいたします。
「自分を変える神」マタイ15章21~28節
「婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願いどおりになるように。」そのとき、娘の病気はいやされた。 マタイによる福音書15章28節
こひつじ食堂を始めて教会に大きな変化が起きました。日曜日の礼拝だけにしか使っていないかった会堂は、みんなが月2回集まる食堂になりました。この礼拝堂は、礼拝の場だけでなく地域との交わりの場へと大胆に変えられてきました。いろいろな地域活動をしていますが、私たちは出会った人たちをすぐにキリスト教へと改宗させることを目的にしているわけではありません。むしろ変化が大きいのは教会の方です。教会は出会いによって、より開かれた存在へと変わってゆきました。きっと私たちはこれからも地域の人との出会いによって変わってゆくのでしょう。
これは聖書の中にも見られる姿です。たとえば、今日読む聖書箇所では、イエス様ご自身がある女性との出会いを通して、驚くべき変化をしました。マタイによる福音書15章21~28節を読んでみましょう。
ティルスとシドンの地方は貿易で栄えた、富裕層の町です。カナンの女性とは異邦人、つまりユダヤ教の神様を信じない異教の人でした。当時のユダヤ教では異教の人との交際や会話は禁じられていました。女性に対してならなおさらです。しかしイエス様は本当にいろいろな人と出会います。カナンの女性は「憐れんで欲しい」と頼みます。お金では解決できない病を持っていたのです。
しかしイエス様は黙ったままです。そして24節でははっきりと、私はユダヤ人を導くために来たのであって、ユダヤ人以外の人、異教徒を導くために来たのではないと言います。女性はそれでも食い下がります。少しだけ私にもその恵みを分けて下さい、ユダヤ人以外だって、神様の恵みにあずかってもいいではないか、神様の愛はもっと広くに及ぶはずですと言ったのです。
イエス様はこの女性の信仰に感心しました。イエス様は、神様は確かに分け隔ての無い、広い愛をお持ちのお方だと、この女性との出会いを通じて改めて気付いたのです。この物語からイエス様自身が大きく変わる姿を見ます。イエス様の信仰は出会った人を通じて、変わっていったのです。
この物語を読んで、私たちは何を学べるでしょうか?出会いは私たちの視野を広げ、新しい気づきをもたらすものです。イエス様がカナンの女性との出会いによって変えられたように、私たちもまた出会いを通じて変えられていくのではないでしょうか?私たちの人生も様々な出会いによって変わってゆくものでしょう。教会がこひつじ食堂によって、新しい出会いによって、大きく変えられたように、私たち一人一人の人生も出会いによって変えられてゆくのです。
私たちは、変らない神の愛を大事にしつつも、いつも変化の可能性に開かれていることに目を向けていたいと思うのです。もしかすると私たちは相手を変えようとばかりしているかもしれません。でも本当は、自分が変わってゆくという姿の中に、イエス様の生き方があるのかもしれません。お祈りいたします。
【全文】「点と天ー小さな愛の希望ー」マタイ5章17~20節
みなさん、おはようございます。今日も礼拝を共にできることを主に感謝します。私たちの教会は、子どもの声が響く教会です。今日も、命の息吹を感じながら礼拝を捧げましょう。今月は「地域活動と福音」をテーマにお話をしています。
私たちの教会ではホームレスの方々の支援をしています。先日も、教会が提供するシェルターを利用される方がいました。公的な援助は多くありますが、まだそれが届かないケースもまた多くあります。そのような方に対して1泊から2泊ですが寝泊まりできる場所を提供しています。
先日はある60代の男性がシェルターを利用しました。私が畳の上に布団を敷き、「今日はここでゆっくり休んでください」と伝えると、その方はほっとした表情で「まるで天国のようです」とつぶやきました。私は笑いながら「天国はもっといい場所ですよ」と答えました。そして続けて、「これまで大変な日々を過ごされたのでしょう。ここがどん底ではなく、新しい出発点です。天国はそのもっと先にありますよ」と励ましました。人生の様々な課題に直面した人が教会を訪れます。このたった一泊の宿の提供で彼をとり巻いている難しい状況が変わることはないでしょう。長い人生の中でこの一泊は点のような出来事でしょう。
でもそれは本人にとっては一筋の光を見たような、天国とも思えるような経験だったのかもしれません。たった一晩ですが、この一泊は彼の人生にとって忘れられないものになったでしょう。彼は体を休め、十分な食事をとりました。そして力を取り戻した彼は自分の未来ともう一度しっかり向き合うことを決めました。彼は新しい決心をして旅立ってゆきました。私は困ったこと、危険に思うことがあれば、また連絡をするように、ここに逃げて来るようにと伝えました。彼は「そのような場所があることはとても心強い」そう言って旅立ってきました。その後のことは何も知りません。彼を支えたのは、たった1泊の寝る場所でした。
こひつじ食堂は月2回、1食200円で食事を提供しています。人間には月30日で90回の食事が必要です。食べることに事欠く人にとって、月にたった2回しかない食事の提供はどれだけ生命の維持に役立つでしょうか。たった2回、食事を200円でできたところで何か生活が変わるでしょうか?私たちの活動は、大きく大変なものに見えますが、それぞれの人生の中では点の様な、小さなものです。でもたくさんの人がこの食事を楽しみにしています。私が見ていると、利用者の方は1ヶ月の間に2回楽しみがある、また会おうと言い合える仲間ができる、それが1ヶ月の生活の支えになっているように見えます。人間の生活とはそのような小さなこと、小さな点に支えられているものなのです。
月1回のホームレスの方への炊き出しも同じでしょう。路上で生活している人に、月に1回食べ物を提供したところで、生活の状況が変わるわけではありません。たった1食です。でもいままでこの食事会は多くの人が自立するきっかけとなってきました。出来るならば太くて長い支援をしたいものですが、私には小さな点の様な支援しかすることができません。でも小さな点が誰かの人生を変えてゆくと言うことは大いにある事です。私たちは、互いの小さな行動に支えられて生きています。それはまるで点のようです。
私たちにとって些細なことでも、誰かにとっては大きな励ましとなることがあります。それは時に、天国のような希望をもたらします。月に数回のわずかな働きであっても、それが人を支え、前向きにし、生きる力となるのです。私たちの教会は、そんな「小さな愛の点」を大切にする教会です。私たちは点の様な小さな存在ですが、神に愛され、誰かを励ます存在です。私たちは小さな点だけれども、精一杯生きてゆきましょう。私たちは点の様な活動を続けてゆきましょう。今日は聖書から点の大事さについて考えたいと思います。小さな点が大きな愛につながっていること、それが天につながっていることを考えてゆきましょう。
今日はマタイによる福音書5章17~20節をお読みいただきました。旧約聖書には確かに事細かに、戒律が書かれています。イエス様の新しい教えを聞いた人の中には、戒律の様な細かなこと、小さなことはもうやめてしまっていいのではないかと考えた人がいました。イエス様の大きな愛に比べて、旧約聖書の愛はとても小さくて、もう必要が無いのではないかと考えたのです。このような考え方は特にイエス様の地上の生涯の後、弟子たちの間で強くなってゆきました。旧約聖書は全部いらないという意見まで出ました。これはキリスト教の歴史上でも大きなうねりとなった時期がありました。
しかしイエス様は今日の個所でこう言っています。18節「律法の文字から一点一画も消え去ることはない」。旧約聖書の文字は消えない、消してはならない、永遠に変わらないと言ったのです。旧約聖書の大切さを伝えました。
しかし一方でイエス様は旧約聖書のすべての戒律をこれまでどおりちゃんと守りなさいと言ったわけではありませんでした。イエス様はこれまでの戒律をもう一度、愛を基準にしてとらえなおす様に教えたのです。イエス様は律法の中にある、愛に目を注ぎ大切にするようにと教えているのです。律法や戒律と言えば、特に深い意味がなく、ただ書いてあること文字通り、無批判に守るもの、そのような印象があるかもしれません。でもそれは誤解です。律法を大切にして心から守っている人にとって、それはただ無意味なものではありません。そこに愛を見出すからこそ、守っているのです。
例えば一番大切にされた律法は安息日を守るということでした。安息日とは意味もなく、ただ何もしてはならない日ではありません。それは神様に感謝をする日です。シェルターにいるように体を休め、自分としっかりと向き合うための日です。神様に感謝し、家族や仲間との時間との関係を考える日です。これは特に忙しく生きる現代の私たちが失ってしまっている大切な時間でしょう。安息日を守るとはそのような生き方の選択なのです。律法にはたくさんの愛が含まれていました。神への愛、人への愛が含まれていました。律法を捨てるとは、それさえも、古めかしいこととして捨ててしまうことです。それはイエス様の愛の教えと大きく矛盾することでしょう。
また律法は誰かをがんじがらめにするためにも悪用されました。愛し合うためにあるはずの律法が、いつの間にか「誰が出来ていないか」「誰が清くないか」と人を縛るために悪用されるようになりました。
もちろんイエス様はこのまま文字通り、律法を守り続けなさいと言っているのではありません。5章のこの後の部分は、当時人々の間で当たり前に守られていた律法について新しい解釈で語られています。
この後「〇〇するな」が繰り返されます。腹を立ててはならない、姦淫してはならない、離縁してはならない、誓ってはならないなどが続きます。それらをどれも新しく解釈をしなおしています。愛の基準で受け止め直しています。この後に続く「腹を立ててはならない」という律法は、礼拝よりも仲直りする愛を優先させようと解釈しています。そのようにイエス様は律法を新しく、愛によって解釈しなおしたお方です。イエス様は律法を愛の視点からもう一度見直し、愛の視点から新しく解釈をし直そうとしているのです。時代や状況、関係性によって何が愛かは変わって来る、その愛を示そうとしているのです。
言い換えるならこうです。律法をするにしろ、しないにしろ「そこに愛はあるんか?」ということです。小さな律法にもそこに愛が含まれていて、そこに含まれる愛が失われないかをイエス様はそれに注目をしたのです。
イエス様は、「律法の一点一画も消え去ることはない」と語られました。それは、律法の中にある小さな愛に注目しよう。それを軽んじてはいけないということです。どんなに小さな愛でも、愛は人を大きく支えます。だからこそ、イエス様は古い教えも愛の視点でもう一度見直し、大切にすべきだと訴えたのです。小さな愛を見過ごさず、大切にしよう、それが5章のイエス様の新しい律法解釈でした。
私たちの周りを見回してみます。太くて大きな愛には自然と目が行くかもしれません。でも私たちの周りにどんな小さな愛があるでしょうか?どんな一点一画の愛があるでしょうか?私たちはその愛にどのように支えらえているでしょうか。私たちはそれに目を向けて生きてゆきましょう。
私たちの教会自体も小さな点のような教会です。でも私たちは誰かを支え、誰かを愛し、誰かに生きる力を与えている教会です。そしてこれは教会だけに言えることではないでしょう。きっとあなたもそうなのです。あなたも点のように小さい存在かもしれません。でもきっと誰かの生きる支えになっています。あなたの小さな愛の行動はきっと誰かを支え、励ましています。
そしてもうひとつ大事なことは、点は小さくても、ひとつも失われてはいけないということです。私たちは互いに小さな点であるのだけれども、互いに大切な点です。イエス様は一つの点も失われない世界を目指したのです。私たちは点のように小さくても愛の業を大事に続けてゆきましょう。大きくしたり、長くしたりするのは大事なことですが、小さな愛もそれと等しく大切なものです。
私たち一人一人も一点一画の様な存在です。でも神様は、あなたは点の様な存在だけれども大切だと伝えています。あなたはここから、そこから絶対に失われてはいけないのだと言います。私たちもそのように互いを大切にしあってゆきましょう。きっと私たちの点の様な愛は、神様のおられる天につながっているはずです。お祈りをいたします。
「点と天ー小さな愛の希望ー」マタイ5章17~20節
「はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。」 マタイによる福音書5章17~20節
今月は「地域活動と福音」をテーマにお話をしています。先日はある方が教会のシェルターを利用しました。たった一晩の宿泊で彼をとり巻いている難しい状況が変わることはないでしょう。でもそれは本人にとっては一筋の光を見たような、天国とも思えるような経験だったのかもしれません。
こひつじ食堂は月2回、炊き出しは月1回、私たちには小さな点の様な支援しかすることができません。でも小さな点のような些細なことでも、誰かにとっては大きな励ましとなることがあります。それは時に、天国のような希望をもたらします。私たちの教会は、そんな「小さな愛の『点』」を大切にする教会です。今日は聖書から小さな点が大きな愛『天』につながっていることを考えてゆきましょう。
イエス様の新しい教えを聞いた人の中には、戒律の様な細かなこと、小さなことはもうやめてしまっていいと考えた人がいました。しかしイエス様は旧約聖書の大切さを伝えました。同時にイエス様はこれまでの戒律をもう一度、愛を基準にしてとらえなおす様に教えました。イエス様は律法の中にある愛に目を注ぎ、律法を愛の視点からもう一度見直し、新しく解釈し直そうとしているのです。
イエス様は、「律法の一点一画も消え去ることはない」と語りました。それは、律法の中にある小さな愛に注目しよう。それを軽んじてはいけないということです。どんなに小さな愛でも、愛は人を大きく支えます。だからこそ、イエス様は古い教えも愛の視点でもう一度見直し、大切にすべきだと訴えたのです。小さな愛を見過ごさず、大切にしよう、それが5章のイエス様の新しい律法解釈でした。
例えば安息日とは、意味もなく、ただ何もしてはならない日ではありません。それは神様に感謝をする日です。シェルターにいるように体を休め、自分としっかりと向き合うための日です。神様に感謝し、家族や仲間との時間との関係を考える日です。これは特に忙しく生きる私たちが失ってしまっている大切な時間でしょう。
この後「〇〇するな」が繰り返されます。「腹を立ててはならない」という律法は、礼拝よりも仲直りする愛を優先させようと解釈しています。
私たちの周りにどんな一点一画の愛があるでしょうか?私たちはその愛にどのように支えらえているでしょうか。私たちの教会自体も小さな点のような教会です。でも私たちは誰かを支え、誰かを愛し、誰かに生きる力を与えている教会です。そしてそれは教会だけではありません。きっとあなたもそうなのです。あなたも点のように小さい存在かもしれません。でもきっと誰かの生きる支えになっています。あなたの小さな愛の行動はきっと誰かを支え、励ましています。
イエス様は小さな一つの点、愛も失われない世界を目指したのです。私たちも小さくても、互いを大切にしあってゆきましょう。きっと私たちの点の様な愛は、神様のおられる天につながっているはずです。お祈りをいたします。
【全文】「愛の種を惜しみなく」マタイ13章1~8節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声と足音から命を感じながら一緒に礼拝をしましょう。
今月は私たちが地域に向けて行っている活動と聖書について考えたいと思っています。私たちの教会では毎月2回こひつじ食堂というこども食堂を開催しています。こひつじ食堂はこどもだけではなく、誰かと一緒に食事をしたいと思っている人のためにも開催されています。200円で、おいしい食事を、温かい関係の中で食べることが出来ます。たくさんの方に愛されて、毎回200食を超える利用があります。私たちはこの活動を、イエス・キリストの愛の教えの実践と位置付けています。この活動を通じていつか私たちの背景にある「愛」が伝わることを願っています。しかし私たちはこの活動によって信者を獲得しようと思っているわけではありません。
私たちのこひつじ食堂は種まきに似ていると言えるでしょう。教会の中で、温かい関係に囲まれる食事の経験と思い出は、人々の心にしっかりと残るはずです。それはきっと記憶に焼き付いてゆくでしょう。まさしく種がまかれたような経験でしょう。その人たちが私たちの背景にある信仰について、すぐに理解し神に従うわけではありません。すぐに花が咲いて実ができるわけではないのです。全員がそうなるわけでもないのです。でも私たちは種を蒔き続けます。こども食堂は、教会はこんなに楽しくて、助け合いとやさしさが詰まっていて、こどもを連れてきてよくて、緊張しなくていい、自分らしくあっていい場所だと伝えています。きっと神様の愛はたくさんの種として惜しみなくまかれています。
様々な活動をしていると、キリスト教の関係者からは「そのうち何人が礼拝にきましたか?」と聞かれる時があります。私は自信を持って「ほとんどいませんよ」と答えています。そして「でも続けてゆけば、きっといつか何かが起ると思う」と答えています。教会で毎回楽しく食事をしているこどもたちが、やがてつらい思いをしたとき教会を思い出してくれるでしょうか?やがて自分がこどもを育てるようになったとき、こども食堂の愛はより深く分かるはずです。ずいぶん先のことかもしれませんが、私たちはそれに期待をしています。
わかりませんが、やがて神様の愛を、もっとしっかりと知りたいと思う日が来るでしょうか。そのことに期待して活動をする、それが種を蒔くということです。あるいは直接この教会に戻ってこなくてもいいとさえ言えるでしょう。その人がこひつじ食堂で知った他者へのやさしさを持って、人生を生きてくれたら、それで十分な実りと言えるでしょう。中には一期一会で今回限りの出会いということもあります。でも私たちは期待して、希望を持って種を蒔き続けてゆきたいのです。いつか神様がその種を芽吹かせてくださるでしょう。私たちはそのことに期待し、未来に希望をもって活動を続けてゆきましょう。
そのように考えていると、かくいう私自身の仕事、牧師の働きも種まきかもしれません。毎週宣教をして、みなさんの何かがすぐに変わるというわけではなさそうです。誰でも今日聞いて明日から変われるわけではありません。でも私は種を蒔きます。宣教の内容はすぐに忘れてられてしまいます。でも何度でも種を蒔きます。なかなか芽吹かないかもしれませんが、希望をもって種を蒔きます。
今日はそのことを、みなさんと聖書から見たいと思います。あきらめず、希望をもって、惜しみなく愛の種をまくことを一緒に考えたいと思います。聖書を読みましょう。
今日はマタイによる福音書13章1~9節をお読みいただきました。実は18節以降にこのたとえ話の解釈が記されています。教会では伝統的に18節以降に基づいて、あなたの心は神に対してどんな状態かを問いかけてきました。
あなたの心は聖書の言葉を聞いても受け入れず、忘れ、雑念に囲まれている。あなたはなんと愚かな罪人だろうか。まるであなたの心は硬いアスファルトに覆われているようで、神の言葉を受け入れない。あなたは良い心に変わり、神を受け入れなさい、そう教え諭してきました。私たちの教会も似たように教えて来たかもしれません。もっと恐ろしいと思う解釈は、同じ様に神の言葉を聞いても、それを受け入れるのは4分の1であり、神を受け入れない4分の3には厳しい罰があるというものです。ここまでくるとかなり危うい解釈です。
実は18節以降の解釈は、イエス様からしばらく後の時代の人が加えた解釈ではないかという見方が増えてきています。18節以降の解釈は一旦置いて、1~8節だけに注目をした解釈が試みられるようになってきました。それは、イエス様がガリラヤの農村地帯で育った背景から考える解釈です。イエス様はきっと4種類の人間の運命について話したのではありません。おそらく、もっと素朴な農村での経験に基づいて、種がどこに落ちるかよりも、惜しみなくまかれることに重点を置いたでしょう。
2000年前の種まきについて考えてみましょう。当時の種まきはいまよりずっといい加減に行われていました。今は土に肥料を与え、良く耕し、種を植え、土を被せ、水をまき、目が出るのを待ちます。しかし当時の種まきもっと簡単です。種を握って、畑に直接ばらまき、芽が出るのを待ちます。まるで節分の豆まきです。今よりずっと、大雑把で、生産効率は悪かったと言われます。そんな風に投げて蒔けば時には畑以外の場所に落ちたりしました。茨の中に落ちたこともあったでしょう。種を蒔いて土を被せないので、鳥が食べるのは当然です。いま私たちが想像する農業、種まきよりもずっと、おおらかで、いいかげんで、だいたいの作業でした。
イエス様はこのような種まきをイメージして語っています。一粒一粒ずつ、大事にうえていく感じではありません。気前よく、だいたいの感じで、ひと握りの種をバーッと投げて蒔くのです。それは多少失敗してもいい、多少鳥に食べられてもいいという蒔き方です。精密に、一つの無駄なく、失敗のない蒔き方ではありません。それがイエス様の種まきです。そしてイエス様は種に素朴な期待を寄せています。たくさんまいて、たくさんの収穫を期待したのです。「芽を出せ実れ」「芽を出せ実れ」と唱えながら種をわしづかみにして、ばら蒔いたのです。イエス様はこのように、種を蒔くことをイメージしました。イエス様の種まきは、とにかく徹底的に蒔くという方法です。
このことからイメージをしましょう。イエス様はこのように、あなたにも種を蒔くお方です。イエス様はあなたにたくさんの種を蒔いてくださいます。あなたの心がどんな心かは関係ありません。イエス様は「あなたの心には蒔いても無駄かな?」そう思っても、気にしません。イエス様はとにかくたくさん蒔いてくださいます。イエス様はひとりにひと粒ずつ種を蒔くのではありません。種をわしづかみにして、気前よくばら蒔いてくださるのです。イエス様は誰がいい人で誰が悪い人かをより分けて、種を蒔くという心の狭い方ではありません。イエス様は誰に蒔いたら芽が出そうか、よく吟味して種を蒔くお方ではありません。イエス様はとにかく種を蒔くお方です。そしてイエス様は希望をもって種を蒔いています。芽を出し、育ってくれるようにと願い、大きな希望を持って、惜しみなく種を蒔いています。
当時の収穫は、10倍になればいい方だったそうです。1をまた来年に残して、9を食べて生活をしました。収穫が30倍や60倍、ましてや100倍になることは想像できないことでした。でもイエス様はそれぐらいの期待をしながら蒔いたのです。
私たちの食堂はそのような種まきに近いと思います。誰かが私たちの信仰に気付くかどうか、それはわかりません。でも私たちは気づいてくれそうな人にだけ種を蒔くのではありません。私たちはとにかく無条件に愛をばら蒔くのです。愛を惜しみなくまくのです。そしていい加減ではなく、祈りながら、いつかたくさんの芽をだすと希望を持ちながら、100倍になることを期待して、祈りながら蒔くのです。それが私たちのこひつじ食堂なのではないでしょうか?
こども食堂以外にも、私たちそれぞれの生き方も考えましょう。私たちは人生においてどんな種のまき方をしているでしょうか?私たちの人生はもしかすると、1粒蒔いて、芽がでるかどうかを試す、そんなことばかりしているかもしれません。私たちの生き方は愛を惜しんで一粒ずつ蒔くような生き方になっていないでしょうか。自分の蒔いた一粒の愛が無駄にならないように、よく相手を吟味してから、一滴の愛を注ぐような生き方をしていないでしょうか?ちびちび愛を注いで、いちいち実りがあるかどうかを勘定していないでしょうか?愛を注いだ人から、すぐに見返りの愛を求める生き方になっていないでしょうか。
私たちはイエス様の種まきを見習いましょう。イエス様は気前よく私たちを愛して下さるお方です。それは相手の失敗も織り込み済みです。でもきっとうまくいく、きっと愛は100倍に増える、そう神様に信頼し、たくさん蒔くのです。なんどもチャレンジするのです。そのように神様を信頼して愛の種を蒔くのです。
私たちはどのように種を蒔きながら、生きてゆくでしょうか。イエス様は今日も私たちに惜しみない愛を、種を蒔いてくださいます。私たちも希望をもって、種を蒔く、気前よく他者に愛を注ぐ、そんな生き方をしてゆきましょう。お祈りいたします。
「愛の種を惜しみなく」マタイ13章1~8節
イエスはたとえを用いて彼らに多くのことを語られた。「種を蒔く人が種蒔きに出て行った。蒔いている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。」マタイによる福音書13章3~4節
こひつじ食堂は私たちにとってイエスの愛の教えの実践です。私たちは信者を獲得するためではなく、いつかこの「愛」が伝わることを願っています。
私たちのこひつじ食堂は種まきに似ていると言えるでしょう。やがてつらい思いをしたとき、あるいは自分がこどもを育てるようになったとき、こども食堂の愛はより深く分かるはずです。ずいぶん先のことかもしれませんが、私たちはそれに期待をしています。いつか神様がその種を芽吹かせてくれる、私たちはそのことに期待し、未来に希望をもって種を蒔き続けてゆきましょう。今日はあきらめず、希望をもって、惜しみなく愛の種をまくことを一緒に考えます。
2000年前の種まきはいまよりずっといい加減に行われていました。種を握って、畑に直接ばらまき、芽が出るのを待ちます。まるで節分の豆まきです。一粒一粒ずつ、大事にではなく、気前よく、ひと握りの種を投げて蒔くのです。それは多少失敗してもいい、多少鳥に食べられてもいいという蒔き方です。
イエス様はこのように、あなたにもたくさんの種を蒔くお方です。イエス様は「あなたの心には蒔いてもムダかな?」と思ってもとにかくたくさん蒔いてくださいます。ひとりにひと粒ずつ種を蒔くのではありません。種をわしづかみにして、気前よくばら蒔いてくださるのです。イエス様は誰に蒔いたら芽が出そうか、よく吟味して種を蒔くお方ではありません。イエス様はとにかく種を蒔くお方です。芽を出し、育ってくれるようにと願い、大きな希望を持って、惜しみなく種を蒔いています。
私たちの食堂はそのような種まきに近いと思います。私たちはとにかく無条件に愛をばら蒔くのです。祈りながら、いつかたくさんの芽をだすと希望を持ちながら、100倍になることを期待して、祈りながら蒔くのです。それが私たちのこひつじ食堂なのではないでしょうか?
私たちは人生においてどんな種のまき方をしているでしょうか?私たちの生き方は愛を惜しんで一粒ずつ蒔くような生き方になっていないでしょうか。自分の蒔いた一粒の愛が無駄にならないように、よく相手を吟味してから、一滴の愛を注ぐような生き方をしていないでしょうか?ちびちび愛を注いで、いちいち実りがあるかどうかを勘定していないでしょうか?愛を注いだ人から、すぐに見返りの愛を求める生き方になっていないでしょうか。
私たちはイエス様の種まきを見習いましょう。イエス様は気前よく私たちを愛して下さるお方です。それは相手の失敗も織り込み済みです。でもきっとうまくいく、きっと愛は100倍に増える、そう神様に信頼し、たくさん蒔くのです。なんどもチャレンジするのです。そのように神様を信頼して愛の種を蒔くのです。その愛を受けて私たちはどのように他者に愛の種を蒔き、生きるのでしょうか。お祈りします。
【全文】「徹底的平等主義者イエス」マタイ21章12~16節
それから、イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。マタイ21章12節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声を聞き、命を感じながら一緒に礼拝をしましょう。
今月と来月は地域活動と福音について考えてゆきたいと思います。この宣教以外でも、それぞれに語り合っていることかもしれませんが、改めて地域活動と福音について分かち合いたいと思います。
先日焼肉の食べ放題に行ったのですが、3つの価格帯のコースがありました。3000円、4000円、5000円くらいのコースです。私たちは3000円の一番安いコースを頼みました。おいしかったのですが、気になったのは、隣のテーブルの人は高いコースを頼んでいて、なんだかこちらのテーブルよりおいしそうな壺に入ったお肉や大きなデザートがどんどん運ばれてきていました。あれを食べたいと思っても、3000円コースでは頼むことができなかったのです。おいしかったけど、ちょっと悲しい気持ちになって帰ってきました。外食の頻度や価格帯は、私たちの間にある格差をはっきりと表す場面かもしれません。
私たちの教会ではこども食堂をしていますが、振り返ってみて、この食堂はかなり平等な食堂なのではないかと思いました。だれでも1食200円です。でもその価値以上のおいしいものを食べることが出来ます。しかも全員同じメニューというのも重要です。全員が同じ値段で同じメニューを食べます。これは意外と少ない機会です。私はこの食堂の特徴は、とても平等な食事会なのだと言うことに気付きました。こひつじ食堂で100円追加すると料理がグレードアップできるというアイディアはどうでしょうか?収益は改善しそうです。適正な対価を払っているので、大人は受け入れるかもしれません。でもきっと感性の鋭いこどもたちから、ずるいとか、不平等だとか、反対の声が上がるでしょう。この食堂は平等であるべきだということ、みんなが何となく感じ、期待してくれているでしょう。今まで気付かなかったのですが、私たちの食堂は平等であることを大切にしているのです。
礼拝をすべき神聖な場所で、にぎやかな飲食をすることは、不信仰なことに見られるかもしれません。静寂と祈りの場所であるべき会堂が、食べこぼしや、油で汚れます。でも、私たちはこの食事が、福音宣教の一つ、私たちの信仰の一つだと思って大切にしています。
そしてこの食事は全員が神様の前に等しく、平等であることをよく表している食事です。きっとイエス様も、会堂で食事などけしからんと怒るのではなく、この平等な食事を見て喜び、楽しく加わってくださるのではないかと思います。なぜならイエス様も格差や差別に反対し、平等を愛したお方だからです。今日はイエス様が平等を行動で体現した姿を聖書から見てゆきましょう。
マタイによる福音書21章12~16節をお読みいただきました。当時のエルサレムの神殿はユダヤ教の信仰の中心でした。神殿にはたくさんの献金や献げ物が集まりました。しかしこの献げ物の行先には問題がありました。特権階級の祭司たちがその献金で贅沢な暮らしをしていたのです。貧しい人々からの心からの献げ物で貴族のような生活をしていたのです。
図にあるように、神殿の一番外側の「異邦人の庭」では、献げ物を販売するお店が並びました。牛や羊を献げることが良い事とされたが、貧しい人は鳩を献げました。また神殿では献金は古いお金を使うことと決められていたため、両替人も多くいました。これはどれも神殿公認の商売でした。場所代も払ったでしょう。人々は貧しくてもみな精一杯を献げました。しかしその献金は祭司たちの贅沢な生活を支えるために使われてゆきました。
イエス様はその神殿に乗り込みました。かなり激しい様子でイスをひっくり返し、そこで働いている人を神殿から追い出しました。イエス様が神殿から商売人や両替人を追い出した理由は、神殿で商売をすると神殿が汚れるからではありません。もともとこれは祭司にも公認された商売です。
ではイエス様が神殿から商売人と両替人を追い出した理由は何でしょうか?それは貧しい人からの献金で、祭司が贅沢な生活をしているという、経済的な搾取に反対をしたからでした。いわば神殿の集金システムを批判したのです。それはお金を集めて贅沢をしている祭司への反抗でした。イエス様はみんなの見ている前で、この神殿の集金体制をぶっ壊すぞというパフォーマンスをしたのです。俺は神殿が貧しい人を苦しめ、格差を生んでいるのが気に入らないのだ。そんな神殿はいらないとアピールをしたのです。もっと豊かに生きるため、格差と差別のない平等な社会の実現のために、イエス様は象徴的に、商人たちを追い出したのです。イエス様は豊かさと、平等を求めたのです。
この行動に祭司たちは激怒しました。神殿で汚れたことをするのはやめようという運動、純粋な信仰の運動だったら、祭司たちも納得したでしょう。私たちの間でもイエス様の行動は従来「宮清め」として、神殿から汚れを取り除く行動だと理解されてきました。しかしその解釈は無理があります。神殿を清めようとした人を殺す必要はありません。祭司たちがなぜイエス様を殺そうと思ったのか、それはイエスが切り込んでしまったのが、神殿の搾取体制だったからです。特権階級の既得権益に踏み込んでしまったからでした。祭司たちにとってどんな大義があったとしても、自分たちの利権への批判は容認できないことだったのです。イエス様もそこを批判する危険は承知だったでしょう。この行動にはそのような搾取と格差に反対し、平等を求めるという意味がありました。
神殿ではもうひとつ深刻な問題がありました。それは差別の問題です。神殿は図の通り、いくつもの壁で仕切られていました。その壁はまさに差別・階級の象徴でした。その壁は清さによって、外国人はここまで、女はここまで、男はここまで、祭司はここまでと区切られていました。神殿は誰でも中に入ることが出来る場所ではなく、むしろ差別を生み出していた場所だったのです。このように人間の間ではすぐに差別や階級が生まれます。清い人がいるなら、清くない人がいるのです。汚れた人、劣った人という差別は人間によって作られるのです。
商売が行われていたのは異邦人の庭です。そして、異邦人の庭にすら入ることが許されない人もいました。それは障がいを持った人です。目の見えない人、足の不自由な人、それは汚れていると差別され、一番外側の門さえ入ることが許されなかったのです。
しかし14節によればイエス様の行動の後、事件が起きます。門の中に決して入って来てはいけない、神殿を汚すと差別された人が神殿の中に入ってきたのです。元々の言葉を見ると、目の見えない人も、足の悪い人もどちらも複数形です。イエス様の行動の後、異邦人の庭に、汚れていると言われてきた障がいを持った人が、大勢、きっとなだれのように入って来たのです。差別され、神殿に出入りすることを禁じられた人々が、差別と階級を乗り越えて、イエス様のそばにやってきたのです。
さらにイエス様の行動で注目するのは、異邦人の庭でその人々を癒したという点です。正しい順序は、神殿の門の外で癒し、障がいがなくなり、汚れと言われるものがなくなってから、入るべきでした、しかしイエス様は、差別された人を先に門の中に招き入れてから、神殿の中で癒したのです。このようにイエス様は差別に反対する姿勢、徹底的な平等主義を行動によって示したのです。この一連の宮清めと呼ばれる場面は、聖所を汚れから清めたのではなく、格差と搾取と差別に反対をした、イエス様が徹底して平等を訴えた象徴的な行動だったのです。
そしてそれは神殿の特権階級を激怒させました。特権階級の祭司は、既得権益と階級構造を揺るがす奴に容赦しませんでした。このようにしてイエス様は十字架に掛けられてゆくことになります。イエス様の行動がこの個所で表しているのは、この世界は徹底的に平等になれというメッセージです。
さて、現代にも様々な格差や搾取、階級社会とも言える不平等があるでしょう。経済格差はますまる広がりです。正社員と非正規社員の待遇の違いはほとんど階級社会です。上級国民という言葉もあります。このような格差に社会は不満を高めています。障がい者の差別もまだまだ身近なものです。今もいろいろなところに格差や差別、階級社会があるでしょう。人々は徹底的な平等を救いとして求めています。
もしイエス様が今のこのような社会を見たらならどうするでしょうか。怒って、そこをめちゃくちゃにするでしょうか。そんな搾取おかしい。そんな差別おかしいと。階級を打ち破ったでしょうか。それはきっと危険なことです。
聖書を読む私たちは今をどのように生きてゆくことができるでしょうか。イエス様の求めた徹底的な平等を私たちも実現したいと思います。日本で世界で、この平等を実現したいと思います。時間はかかるでしょう。でも私たちの教会の中で、この礼拝でならすぐに実現、体現できるでしょう。この教会には清い人も、清くない人もいません。階級のような上も下もありません。私たちは等しく、互いを尊重し合う仲間でいましょう。
私たちはその平等をこの教会だけではなく、地域に広げてゆきましょう。こひつじ食堂や様々な活動を通じて、イエス様が求めた徹底的な平等が実現する世界を、この教会から広げてゆきましょう。お祈りします。
「徹底的平等主義者イエス」マタイ21章12~16節
それから、イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。マタイ21章12節
今月と来月は地域活動と福音について考えます。外食の頻度や価格帯は、私たちの間にある格差をはっきりと表します。そのような中でこひつじ食堂はかなり平等なのだと気づかされました。全員が同じ料金200円で、同じものを食べます。でもその価値以上ものを食べることができるからです。
礼拝をすべき神聖な場所で、にぎやかな飲食をすることは、不信仰なことに見られるかもしれません。でも、私たちはこの食事が、福音宣教だと思って大切にしています。この食事は全員が神様の前に平等であることをよく表している食事です。
きっとイエス様も、会堂で食事などけしからんと怒るのではなく、この平等な食事を見て喜び、楽しく加わってくださるでしょう。なぜならイエス様も格差や差別に反対し、平等を愛し、共に食事をすることを愛したお方だからです。今日はイエス様が平等を行動で体現した姿を聖書から見てゆきましょう。
当時のエルサレム神殿にはたくさんの献金や献げ物が集まりました。しかし特権階級の祭司たちはその献金で贅沢な暮らしをしていました。イエス様が神殿から商売人や両替人を追い出した理由は、神殿で商売をすると神殿が汚れるからではありません。貧しい人からの献金で、祭司が贅沢な生活をしているという、経済的な搾取に反対をしたからでした。いわば神殿の集金システムを批判したのです。
神殿ではもうひとつ深刻な問題がありました。それは差別の問題です。神殿はいくつもの壁で仕切られ、その壁はまさに差別・階級の象徴でした。そして障がいを持った人は異邦人の庭にすら入ることが許されませんでした。
14節によればイエス様の行動の後、事件が起きます。門の中に決して入って来てはいけない、神殿を汚すと差別された人が神殿の中に入ってきたのです。イエス様の行動の後、障がいを持った多くの人々が、差別と階級を乗り越えて、イエス様のそばにやってきたのです。さらにイエス様は、差別された人を先に門の中に招き入れてから、神殿の中で癒しました。このようにイエス様は差別に反対する姿勢、徹底的な平等主義を行動によって示したのです。
既得権益と階級構造を揺るがすこれらの行動は神殿の特権階級を激怒させました。このようにしてイエス様は十字架に掛けられてゆくことになります。
現代にも様々な格差や搾取、階級社会とも言える不平等があるでしょう。人々は徹底的な平等を救いとして求めています。もしイエス様が今のこのような社会を見たらならどうするでしょうか。聖書を読む私たちは今をどのように生きてゆくことができるでしょうか。イエス様の求めた徹底的な平等を私たちも実現したいのです。私たちの教会からその平等を、この地域に広げてゆきましょう。お祈りします。
【全文】「翔んで、ガリラヤ」マタイ4章12~16節
みなさんおはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。今日も私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちと一緒に礼拝をしましょう。
2015年に「翔んで、埼玉」という映画が公開され大ヒットしました。この映画は東京都民から埼玉県民が差別を受けているというコメディー映画です。埼玉県民は東京都民から「ダさいたま」「クさいたま」「いなかくさい」と差別され、屈辱の日々を送っていました。そんなある日、埼玉出身でアメリカからの帰国子女である主人公が埼玉解放戦線を率いて、千葉解放戦線と協力して差別を続ける東京都知事を失脚させるというコメディーです。見下されていた人々が手を取り合い、解放を勝ち取っていく姿は、笑いと涙のあふれるストーリーです。このように現実の世界になんとなくある、埼玉への偏見をコメディーとして取り上げ、逆転させた映画として話題になりました。続編も公開され、今度は滋賀県民が大阪府民に差別されるという設定になっています。
いつの時代も人々は地域に優劣をつけようとします。聖書の時代にもそのような地域間の意識は大きくありました。そして今よりずっと差別的な取り扱いを受けました。パレスチナ地域は大きく分けて南北に3つの地域に分けられます。一番南のユダヤはイスラエルの首都エルサレム、ユダヤ神殿のある都会です。イスラエルの歴史と宗教の中でいつも中心的な役割を果たしていたのがユダヤ地方です。外国からの移住民が少なく、私達こそ純粋なユダヤ人だという意識の強い地域でした。その北側、中部にあたるのはサマリア地方です。この地域は、歴史的に外国からの侵略と他民族の移住が繰り返され、混合人種・混合文化・混合宗教の土地でした。聖書にもサマリア人が登場しますが、やや印象の悪い人という前提で書かれている箇所が多くあります。
さらにその北側、北部にあるのがガリラヤ地方です。ガリラヤもサマリア同様に、何百年も様々な国に代わる代わる支配され、その度に様々な宗教が持ち込まれました。混合人種・混合文化・混合宗教の土地でした。イエス様の時代からみると、ガリラヤがユダヤの一地方となったのは最近のことでした。ガリラヤ地域の最大の特徴は肥沃な大地だったということです。山から流れる豊富な水で農業が盛んな穀倉地帯でした。当時のパレスチナ地域の人々はアラム語という言葉を話していました。祭儀にはヘブライ語を使いましたが、日常はアラム語で会話をしました。ガリラヤの人々は訛りが強かったと言われています。ペテロもガリラヤ訛りだと言われたという箇所があります。それに対して文化的な反動もありました。差別されたこともあって、逆にユダヤ教徒の過激派も生まれるようになりました。ユダヤ教愛国主義者がガリラヤから起こることもありました。
エルサレムの人々はガリラヤに対して訛りの強い、農村地帯のド田舎という印象を持っていたでしょう。4章15節には「異邦人のガリラヤ」とあります。つまりガリラヤの人はユダヤ人ではないとさえ言われたのです。エルサレムの人がガリラヤをはっきりと見下している箇所は、ヨハネ福音書7章41節と52節です。イエスをメシアだと言う者がいるのに対して「メシアはガリラヤからでるだろうか」とあります。さらに52節にはガリラヤの出身なら預言者・メシアでないことはわかる」という言葉もあります。これが当時の人々が持っていたガリラヤに対する印象です。ガリラヤは田舎で、訛っていて、良いものは出ない場所でした。エルサレムの人々からは相当見下されてきた場所でした。イエス様はそのような場所で育ったのです。
イエス様がガリラヤで育ったことには、どんな意味があるでしょうか。今日はそのことをご一緒に見てゆきましょう。そこにはきっとクリスマスと同じくらい大きな恵み、希望があるはずです。
今日はマタイによる福音書4章12~17節をお読みいただきました。イエス様はガリラヤの中でもさらに小さな村ナザレで育ちました。そしてガリラヤ地方から東のヨルダン川周辺でヨハネの活動に加わりました。しかし徐々にヨハネとは距離を感じるようになったのでしょう。ヨハネが逮捕されたのをきっかけに、ガリラヤに戻り、イエス様の伝道が始まりました。イエス様は見下されていたガリラヤで育ち、そこから伝道を始められました。そこはエルサレムの人々からは相当見下されてきた場所でした。そこからイエス様は宣教を始めたのです。
15節を見ます。イエス様の活動は中心地エルサレムから見てはるかかなたの、異邦人の町から始まりました。16節では、ガリラヤの人々は暗闇に住む民と呼ばれています。暗闇とは、忘れられた場所です。そこに住む人々はいつも見過ごされてきました。ガリラヤはいつもだれからも注目されない、見過ごされてしまう、みんなから忘れられてしまう場所でした。イエス様はそのような場所に光を当てるために、活動を始めました。光り輝く神殿のある、エルサレムではなく、日のあたらないガリラヤから活動をはじめたのです。16節ではさらにガリラヤの人々は死の陰の地に住む民と呼ばれます。それはまさに死と隣り合わせの人を指します。辺境の地ガリラヤに住む人々は、いつも見捨てられ、見殺しにされ、見下され、様々な国々に支配されてきました。死と隣り合わせだったのです。イエス様は、その死の陰の地に住むガリラヤの人々に、光となったのです。イエス様は太陽が昇るように、夜が明ける様に、人々に現れたのです。
イエス様が見下されたガリラヤの地で宣教を始めた事、このことの意味を私たちはもう少し心に留めた方が良いかもしれません。私たちはクリスマスから1ヶ月が経ちましたが、私はイエス様が家畜小屋で生まれたのと同じくらいの意味が、イエス様がガリラヤから宣教を始めたということにあると思います。その共通点はメシアとして、とても似つかわしくない場所で人生と活動が始まるということです。イエス様はもっとも無力な存在である赤ちゃんとしてこの地上に生まれてきました。そしてイエス様はパレスチナ地域の中でもっとも田舎である、中心ではない周縁であるガリラヤから宣教を始めました。
この二つには共通していることがあるでしょう。それは明るく、光輝く場所からスタートしたのではないということ、人間の期待とは大きくかけ離れたところから始まったということです。暗い場所から始まったのです。
でも信仰とはそのようなものです。光り輝く奇跡から始まる信仰は多くありません。信仰は暗闇、良いことが一つもない、そのような時や場所から始まるものです。満たされて充実している毎日よりも、傷つき不足し、不十分さを感じる時に、場所に信仰は生まれてくるものです。そのことはみなさんもよくお分かりでしょう。
私たちは覚えておきましょう。信仰とは私たち個人個人の心の端から中心へと向かって始まってゆきます。初めから中心に生まれてくるものではなく、私たちの心の隅、私たちの内面で見落としていた部分から信仰が始まるのです。私たちが自分自身の目をむけたくない場所から、そこが光で照らされるように信仰が始まるのです。いま私たちの心で目をむけたくない部分、暗い場所はどこでしょうか?イエス様はそこを選んで来られます。その心に光を当て、そこから始めて私たちを導いてくださるのです。
私たち個人の中だけではなく、共同体の中でもそういえるかもしれません。信仰とは思いもよらない人から、場所から教わるものです。イエス様の光は苦しんでいる人、逆境の人、行きづまっている人、見下されるような人から訪れるのです。幸せそうな人から福音が広がるのではないのです。イエス様は苦労し、見下され、見向きもされない人を用いて、福音を広げるお方だとも言えるでしょう。イエス様の光が暗闇から広がるのです。
個人や共同体のなかだけではなく、バプテスト連盟という枠組みでも考えてみましょう。バプテスト連盟にもたくさんの教会がありますが、教会のある地域は偏っています。バプテスト連盟の約4割の教会は東京と福岡にあります。その中で私たちは関東の西のはての教会です。平塚教会は連盟の歴史に名前を刻んできた教会ではないかもしれません。目立たない教会です。でもきっと地理的・歴史的中心でないことは私たちの励ましになるでしょう。イエス様は中心からのみ宣教を始める方ではありません。平塚のような周縁の地からも中心へ向けて宣教をしてゆくのです。平塚教会は目立たない教会かもしれませんが、神様の働きはここから始まるのです。
そしてさらに加えるならば、イエス様は復活の後、ガリラヤでまた会おうと言われます。ガリラヤは復活のイエスと出会い、弟子たちの信仰の再スタートの場所にもなりました。失意の中で再び信仰に立つ場所になりました。信仰はガリラヤで始まり、失敗し、再びガリラヤでスタートするのです。復活のイエス様とガリラヤで出会った弟子たちは、新たな使命に生きる力を得たのです。そのようにしていつも信仰は、人々の注目の集まる中心ではなく周縁から、高みからではなく、低みからスタートするのです。
イエス様はこのように、中心からではなく忘れられた場所、目立たない場所から宣教を始めたお方です。イエス様の福音は、私たちの心の隅、暗闇から始まります。私たちが見落としている場所、人から始まります。注目されている中心から離れた場所から始まります。私たちはそのことを覚えて歩みましょう。お祈りします。
「翔んで、ガリラヤ」マタイ4章12~16節
「ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川のかなたの地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の陰の地に住む者に光が射し込んだ。」
マタイによる福音書4章15~16節
2015年に「翔んで、埼玉」というコメディー映画が大ヒットしました。東京の人々から「ダさいたま」と差別され、見下されていた埼玉県人が解放を勝ち取っていく、笑いと涙のあふれるストーリーです。
今も昔もいつの時代も人々は地域に優劣をつけようとします。ガリラヤ地方は人種・文化・宗教の混合した土地でした。そして山から流れる豊富な水で農業が盛んな地域でした。人々は訛りが強かったと言われています。エルサレムの人々はガリラヤに対して訛りの強い、農村地帯のド田舎という印象を持ち、見下されていました。イエス様はそのような場所で育ったのです。
マタイ4章15節にもあるとおり、イエス様の活動は中心地エルサレムから見てはるかかなたの場所から始まりました。16節では、ガリラヤの人々は暗闇に住む民と呼ばれています。ガリラヤはいつも見過ごされ、忘れられてしまう場所でした。イエス様はそのような場所に光を当てるために活動を始めました。光り輝く神殿のある、エルサレムではなく、日のあたらないガリラヤから活動をはじめたのです。
16節ではさらにガリラヤの人々は死の陰の地に住む民と呼ばれます。辺境の地ガリラヤに住む人々は、いつも見捨てられ、見殺しにされ、見下され、様々な国々に支配されてきました。イエス様は、その死の陰の地に住むガリラヤの人々に、光となったのです。イエス様は太陽が昇るように、夜が明ける様に、人々に現れたのです。
イエス様が見下されたガリラヤの地で宣教を始めた事、このことの意味を私たちはもう少し心に留めた方が良いかもしれません。クリスマスと、イエス様がガリラヤから宣教を始めたことの共通点は、メシアに似つかわしくない場所で人生と活動が始まるということです。それは明るく、光輝く場所からスタートしたのではないということ、人間の期待とは大きくかけ離れたところから始まったのです。
でも信仰とはそのようなものです。光り輝く奇跡から始まる信仰は多くありません。信仰は暗闇、良いことが一つもない、そのような時や場所から始まるものです。信仰とは自分自身の目をむけたくない場所が光で照らされるように信仰が始まるのです。私たち共同体の信仰もそうです。私たちは信仰を、思いもよらない人、場所から教わるものです。イエス様の光は苦しんでいる人、逆境の人、行きづまっている人、見下されるような人から訪れるのです。
イエス様は復活の後、ガリラヤでまた会おうと言われます。ガリラヤは復活のイエスと出会い、弟子たちの信仰の再スタートの場所にもなりました。失意の中で再び信仰に立つ場所になりました。信仰はガリラヤで始まり、失敗し、再びガリラヤでスタートするのです。そのようにしていつも信仰は、人々の注目の集まる中心ではなく周縁から、高みからではなく、低みからスタートするのです。お祈りします。
「それぞれの孤独のグルメ」放送について
このたび平塚バプテスト教会のこども食堂を題材にしたドラマが全国放送されることになりました。このようなことからも私たちの活動が広がっていくことを願っています。平野牧師も登場予定です。ぜひみなさまもご視聴ください。
番組名:「それぞれの孤独のグルメ」テレビ東京開局60周年連続ドラマ 孤独のグルメ特別編 ドラマ24
主演:松重豊
放送日:11月8日(金)24時12分~ 30分
放送局:テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
予告編:https://youtu.be/WKX27IoQvK4?si=vUNSX0i-JWbxt2T6
再放送日:1月26日(金)
放送局:BSテレ東
平塚教会のこども食堂を舞台にし、様々な出会いと、孤独でない共食をテーマにした内容となっています。会堂内で撮影され平塚教会の取り組みの紹介にもなっています。放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」「TVer」にて見逃し配信が開始されます。
【全文】「捨てない献身」マタイ4章18~22節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できることを主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声を聞きながら一緒に礼拝をしてゆきましょう。
キリスト教では牧師を目指すことを献身(けんしん)と呼びます。それはキリスト教の中で特に美しく、とても喜ばしい決断だとされています。私がこの献身をする時に何回か言われた言葉が印象に残っています。それは「これまでのことは捨てて、神様に従いなさい」という言葉でした。確かに牧師になるにあたって私は、多くの人が持っているものや、目指していることを捨てたかもしれません。同世代の仲間と比べると、出世や収入や住宅ローンとは縁遠くなったでしょう。神様に向けてこれまでとは違う人生を歩み出すことは、たくさんのことを捨てるような気になります。
でも私は神様に従うとは必ずしも何かを捨てることではないと感じています。私自身が神様に従ったとき、すべてを捨てて従ったわけではないのです。当然ですが私は家族も貯金も持ち物も経験もすべてを持ったまま牧師になりました。ほとんど今までのものを捨てずに献身をしたのです。でも献身というとやはり何かを捨てることだというイメージがあるようです。私は献身において、捨てる事が美化されすぎていると感じています。私はお寿司屋さんから牧師に転職をしました。もう魚をさばく経験は必要ないと思いました。しかし神様は、それを子ども食堂で用いてくださいました。私がもう使わない、捨てていいと思ったことでさえ、神様は用いて下さっています。それが私の献身です。捨てたものがあまりない献身です。
確かに私の心の中には、捨てるべきものはまだまだたくさんあるでしょう。でも私は何かを捨てるために献身をしたのでありません。むしろ得るために献身をしています。神様の恵みをもっと得るために、欲張って献身をしています。私は神様に従うこと=捨てることではないと思いますし、そのようなイメージを変えゆきたいと思っています。
教会に集うみなさんはどうでしょうか?礼拝に出席する、出席し続けることも神様に従う献身です。献身は牧師だけのものではありません。礼拝出席も立派な献身です。今日、礼拝に集う皆さんにはいろいろな事情があったでしょう。体調や時間、家族との関係、いろいろな事情があるものです。でも例えば今日みなさんは、家族を捨てて礼拝に来たわけではありません。
夫から『俺と教会とどっちが大事なんだ』と言われることがあるかもしれません。しかし私たちは家族を捨てて礼拝に来たのではありません。むしろ家族との関係をより良くするために礼拝に集っているのです。夫は自分が捨てられたように感じるのでしょう。でも私たちは夫を捨てて礼拝しているのではありません。私たちは今日、家にいる家族と新しい関係を願って礼拝をしているのです。家族を捨てるためではなく、家族をもっと愛するために。もっと一週間を頑張れるように、今日ここで礼拝しているのです。それが私たちの集まりです。
教会の存在も同じだと言えるでしょう。教会は社会との関係を断って存在をしているのではありません。世間の人からは、教会は社会と隔絶して存在をしているように見えるかもしれません。でも特に私たちの教会はそうではありません。私たちの教会は社会との深い関係を望んでいます。新しい関係を望んでいます。社会の中で暮らす、様々な人と新しい関係にされることを願って、祈り、礼拝をしています。私たちは地域との関係を捨てて礼拝しているのではなく、いままでよりもっと深い関係を願って礼拝をしています。そのことが少しでも伝わったら嬉しいです。
きっと聖書は私たちに何かを捨てて、神に従う事、礼拝することを求めているのではないでしょう。聖書は私たちが大切にしているものを、大切にしたまま、新しい関係を求めて、神様に従うことを求めているのでしょう。私たちはそんな風に神様に従えないでしょうか。今大切にしているものを、大切にしたまま、もっと大切にしながら、神様に従うことができないでしょうか。そのことを考えたいと思います。今日も聖書を読みましょう。
今日はマタイによる福音書4章18~22節までをお読みいただきました。この個所には弟子たちがどのようにイエス様に従うようになったのかが書かれています。ある日、ペテロとアンデレは漁をしていたところ、突然イエス様が現れて「私について来なさい」と言われました。これはイエス様の招きです。私たちの信仰とは私たちの理解や決心を超えた、招きであることが書かれています。それはこの礼拝も同じです。遠くから車やバスで来ていても、一生懸命に自転車をこいで来ていても、神様に招かれて礼拝に集っています。私たちは神様に招かれて教会に来ているのです。
20節には「二人はすぐに網を捨てて従った」と書いてあります。網は漁師にとって、とても大切なものです。漁師は自分の網を人には触らせないと聞いたことがあります。網は漁師にとって自分の仕事や人生、生活を象徴するものです。聖書によれば弟子はそれをきっぱりと捨てたのです。この個所からでしょう、神様に従う時には、たくさんのもの、すべてのものを捨てなければならない、そう言われてきました。
しかし神様に従うとは本当に捨てることなのでしょうか。22節には、舟と父は残して行ったとあります。網は捨てたけど舟は捨てなかったのです。あげあしを取るようですが、舟の方が価値は大きいはずです。なぜ舟は捨てなかったのでしょうか。
実は20節の「捨てる」と22節の「残す」は、どちらも同じギリシャ語で『ἀφίημι(アフィエイミー)』という言葉です。この言葉は新約聖書に150回ほど登場するよく使われる言葉です。この言葉は「捨てる」という意味と「残す」という意味の両方を持ちます。さらにそれ以外にも「赦す」「そのままにしておく」という意味もあります。
ですから「網を捨てた」そして「舟と父を捨てた」とも訳すことができ、そう翻訳しているものもあります。しかしこの「親を捨てる」という翻訳はさすがにひどいでしょう。おそらく翻訳の上でもそう考えて、網を捨てて、舟と家族を残したと翻訳をしたのでしょう。
本来の翻訳の幅を考えれば、網も捨てずに残して従った、舟と父をそのまま残して従ったとも訳すことができます。無理に大切なものを捨てたと訳す必要はありません。網と舟と父をそのまま残して、そしてもちろんまた帰って来るつもりで従ったのです。私は「網も舟も父もそのまま残して従った」そのような翻訳がよいと思っています。
もちろん私には捨てなくてはいけないものがたくさんあります。私の中にある悪い思い、罪、ゆがんだ欲望を捨て去る必要があります。しかし私たちは大切にしているものまで捨てる必要はありません。家族やこれまでの人間関係を大切にすることはイエス様の教えでもあります。自分の大切にしていることを大切にし続けてよいのです。キリスト教の信仰はただ捨てるばかりではありません。神様はそれを「大切に取っておきなさい」と言っています。大切にとっておいて、一時的にそれをそのまま残しておいて、そして私たちは神様に従うのです。聖書から私たちの献身をそのように理解することができます。
この礼拝という献身がまさにそうでしょう。私たちは家族や仕事あらゆるものとの関係を捨てて、礼拝に来たのではありません。私たちは家族や友人や職場での新しい関係を願って、でも今日はそれを残して、今日この礼拝に集ったのです。私たちは決してそれを捨ててはいません。
「捨てない献身」マタイ4章18~22節
イエスは、「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父親のゼベダイと一緒に、舟の中で網の手入れをしているのを御覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに、舟と父親とを残してイエスに従った。マタイによる福音書4章19~22節
キリスト教では牧師を目指すことを献身(けんしん)と呼びます。神様に向けてこれまでとは違う人生を歩み出すことは、たくさんのことを捨てるような気になります。でも神様に従うとは必ずしも何かを捨てることではありません。
みなさんの礼拝出席も立派な献身です。今日みなさんは、家族を捨てて礼拝に来たわけではありません。家にいる家族と新しい関係を願って礼拝をしているでしょう。教会の存在も同じです。教会は社会との関係を断って存在をしているのではありません。私たちは地域といままでよりもっと深い関係を願って礼拝をしています。
きっと聖書は私たちに何かを捨てて、神に従う事、礼拝することを求めているのではないでしょう。聖書は私たちが大切にしているものを、大切にしたまま、新しい関係を求めて、神様に従うことを求めているのでしょう。
聖書に目を向けます。ある日、ペテロとアンデレは漁をしていたところ、突然イエス様が現れて「私について来なさい」と言われました。20節には「二人はすぐに網を捨てて従った」と書いてあります。この個所から神様に従う時には、たくさんのもの、すべてのものを捨てなければならない、そう言われてきました。
しかし22節には、舟と父は残して行ったとあります。網は捨てたけど舟は捨てなかったのです。実は20節の「捨てる」と22節の「残す」は、どちらも同じギリシャ語で『ἀφίημι(アフィエイミー)』という言葉です。この言葉は「捨てる」とも「残す」とも翻訳できる言葉です。翻訳の幅を考えれば、網も舟も父も捨てずに、そのまま残して従ったとも訳すことができます。無理に大切なものを捨てたと理解する必要はありません。自分の大切にしていることを大切にし続けてよいのです。
私たちは家族や仕事あらゆるものとの関係を捨てて、礼拝に来たのではありません。私たちは家族や友人や職場での新しい関係を願って、でも今日はそれを残して、今日この礼拝に集ったのです。私たちはそれぞれの場所での関係がより、うまくいくことを願って礼拝をしましょう。
そしてイエス様の招きは、自分のためだけではない人生を、他者に仕え、他者を愛する人生を送らないか?と語り掛けてます。それは自分の大切なことを大切にしながら、他者をもっと大切にする、そのような招きです。
私たちは今ある大切なものを抱きしめながら、神様に従ってゆきましょう。そして自分のことだけではなく、他者への愛と祈り、他者の大切にしているものを守ることに時間を使う生き方を選び取ってゆきましょう。イエス様はそのように私たちを招いているのではないでしょうか?お祈りします。
【全文】「悪魔は存在するのですか?」マタイ4章1~11節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声と足音を聞きながら、一緒に礼拝をしましょう。今月1月はイエス様が生まれた後の生涯を見てゆきます。
牧師をしているとキリスト教に関する様々な質問を受けることがあります。先日は「悪魔は本当に存在するのですか?」と聞かれました。この質問は何度か受けたことがあります。ある時はオカルトに興味がある人から、またある時は幻覚が見えてしまう病を持つ人から、またある時は自分の犯した罪や行動に悩む人からの質問でした。皆さんは「悪魔は存在するのか?」という質問をされたら、どのように答えるでしょうか?私は短く「悪魔は存在しません」と答える様にしています。しかし聖書には確かに悪魔が登場します。今日読んだ4章1節にもはっきりと登場します。聖書の悪魔は人格、自分の考えを持っていて、自由に飛び回ることができます。そして人間を誘惑します。人々に取り憑いて、人の体を操って、悪い事をさせます。それが悪魔という存在です。聖書にははっきりと悪魔が存在している様に書かれています。
しかし本当にこのような独立した人格のような悪魔は存在するのでしょうか?私個人は悪魔というモチーフを使った比喩であると理解をしています。愛や慈しみとは正反対の考えをしたり、行動をとることを、悪魔と象徴的に表現をしたのだと考えています。悪魔という実体、そのものが存在したのではありません。非人間的な行動、人の尊厳と愛を踏みにじることをした人が象徴的に悪魔と呼ばれたのです。あるいは人々の中にあるそのような悪、それが塊となったような現象全体を悪魔と象徴的に呼んだのです。
一方、悪魔そのものは存在しなくても、今も当時も悪魔的、悪の塊のようなことは数多く存在します。食べ物を捨てる人と食べることができない人がいるという不平等はもはや悪魔的な状況です。人を殺し合うという戦争は、人間が悪魔的存在にならないとできないことです。悪魔が乗り移って戦争をするのではありません。人間が人間の決断として悪夢のような戦争を起こすのです。気候変動も人間の悪魔的な行動の結果と言えるでしょう。例えば、化石燃料を多く使う先進国の利益優先の政策が、貧しい国々を洪水や干ばつといった苦しみに追い込んでいます。先進国のCO2排出が悪魔のように、人々を苦しめています。これらを見て思うのは、悪魔そのものよりも、悪を省みない人間の方が恐ろしいということです。
悪魔が人間を乗っ取り、そそのかして悪い事をしているのではありません。人間が罪人であり、人間が悪魔の様な行動を起こすのです。人間の罪が、人を悪魔の様にしてゆくのです。だから特定の誰かが悪魔なわけではありません。人間一人一人が少しずつ罪を犯し、それが大きな方向に動き出すとき、戦争や、不平等や、気候変動、悪魔の所業のようなことが起こるのです。戦争は悪魔が見ても驚くほどの邪悪さです。戦争をしている人間を見れば、悪・罪がその内側にあることが分かるでしょう。人間の罪が集まり、大きな悪となるとき、それは悪魔のように見えます。しかしそれは外から来るのではなく、私たち自身の内側から生じるのです。
そのような罪深い私たちには神様の言葉が必要です。悪へと傾きそうになるのを、押しとどめる、愛と慈しみの言葉が必要です。私たちの中にある悪を打ち砕く、神の言葉が必要なのです。今日は聖書からそのことを見てゆきたいと思います。
マタイ4章1~11節までをお読みいただきました。イエス様はその活動を始めて間もなく、荒野に旅立ちました。そしてそこで40日間の断食をしました。何も食事を食べなかったのです。すると誘惑するのもの、悪魔が来て、イエス様にこう言ったとあります「石をパンに変えてみろ」。この言葉、この誘惑はどのような意味を持つでしょうか?この質問で悪魔はイエス様に何か悪い事を言っているでしょうか?「石をパンに変えてみろ」のどこが、悪いのでしょうか。どこか悪魔なのでしょうか?ここに潜む悪は何でしょうか?
この中に潜む悪は、奇跡による即席の解決を期待するという悪でしょう。イエス様は断食を終えてパンが欲しかったはずです。悪魔はそれに対して、奇跡を起こして、魔法の様に解決すればいいと言ったのです。あなたの奇跡を使えば何でもすぐに、パッと解決できるはずと言ったのです。しかしイエス様はそれを断りました。自分一人のパンを食べればよいだけなら、目の前の石をパンに変えれば済んだでしょう。しかしパンを必要としたのはイエス様だけではありませんでした。もっと深い問題があったのです。当時、他にも多くの人が食べることができずにいました。飢えと飢饉が蔓延していたのです。それは悪魔の仕業ではありませんでした。金持ちが穀物を独占し、貧しい人々が食べることが出来なかったからです。それは人間の仕業です。王たちは戦争ばかりして、農地は荒れ果てていました。だから飢えている人がいたのです。
その問題の解決には奇跡は必要ありません。いえ、これは奇跡で解決をしてはいけない問題です。人びとにパンが行き渡るような、平等な社会、分かち合う社会、平和な社会が有れば飢えは無くなりました。奇跡より必要とされたのは社会の変革でした。しかし悪魔は、悪魔的な存在は言いました。「そんなもの、石をパンに変えればすぐに解決さ」と。奇跡では何も解決をしないのです。ここで必要とされているのは、石を変えることではありません。私たち人間を変えることです。人間が変わること、本当はそれが必要とされているにも関わらず、悪魔は「石の方が変わればいい」と言うのです。
悪魔的な存在はいつも私たちを、問題の本質から、罪から、目をそらせようとします。ただ目の前のパンを増やせばいいという考えは恐ろしい考えです。出来事に向き合わず、すぐに表面的なとりつくろいをしようとする人間の罪がここに現れているのです。
イエス様はそれに対して何というでしょうか。イエス様は4節「人はパンのみで生きるのではない。神の言葉によって生きる」と言います。イエス様は石をパンに変えるのではなく、み言葉によって人間を変えること、そのことによって問題を解決しようとするのです。
6節も同様です。悪魔の生き方は奇跡だけを期待する生き方です。投げやりな生き方です。人間が変わることをしようとせず、神がどうにかするだろうと期待する、運まかせの生き方です。イエス様はそこで言います。7節「主を試してはならない」。神様が都合の悪いことのすべて解決をしてくれる、そう簡単に思うなということです。イエス様は、神様にただ運を任せるのではいけないのだと言っています。
9節にも誘惑があります。その誘惑は与えられた力を人々のために使うのではなく、私利私欲のために使うという誘惑です。私たちの中全員にその悪はあるでしょう。自分の思い通りにしたい。身内をひいきしたい。自分の思い通りに相手に動いて欲しい。自分のものにしたい。そのような悪が私たちの中にあります。それが少しずつ集まって、塊になると、大きな分断と対立、争いが起きます。そのような悪、誘惑にひれ伏す人、指導者は沢山います。
イエス様はそのような誘惑をきっぱりと否定しました。10節、私たちは「共に神に仕える者」だと言うのです。それは、私たちは神様の前に平等に立ち、神様を一緒に礼拝するという意味です。私たちは平等で、共に礼拝する仲間です。私たちには上下は無く、誰かが独占せず、分かち合うのです。私たちは互いを尊重し合うのです。イエス様の「あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ」という答えは、人間は神様の前で、互いに平等で、尊重し合う存在だという答えだったのです。
ここまで見て来たとおり、悪魔の提示する解決方法はどれも、即席の解決方法です。悪魔とはつまり即席の神学とでも言えるでしょう。なんでもすぐに、表面的に解決をしようとし、悪に蓋をし、人間に変化を求めない姿勢、それが悪魔の考え、即席の神学です。しかしイエス様はことごとく、この即席の神学を否定します。イエス様は、即席の解決よりも、神の言葉が大事だと言います。毎日毎日、食事を食べる様に、少しずつ神様の愛の言葉を聞いて生きる事が重要だというのです。
そのように私たちは神様の言葉によって、私たちは少しずつ変えられ、共に生きるようになります。このプロセスは時間がかかりますが、イエス様が示されたのは、このような人間の変革による解決です。それは悪魔の提示する解決方法よりも、ずっと時間がかかるでしょう。でもイエス様は神様の言葉によって変えられた人間が、新しい生き方をするという解決方法を求めたのです。共に神に祈り、平等で互いを神に仕える者として尊重する関係を求めたのです。そして、その前にもはや悪、悪魔は立つことが出来ませんでした。離れ去って行ったのです。
もう一度質問の答えを繰り返します。悪魔そのものはいません。物事を悪魔のせいにしてはいけません。そのような即席で簡単な見方、解決方法こそ、悪魔的な発想です。私たちも時に、問題を奇跡や即席の解決に任せたいと思うことはないでしょうか?現実に向き合うことは大変で、逃げたくなる時もあるでしょう。しかし、神様はそのような私たちを変えるために、愛の言葉を与えてくださるのです。
私たちに求められているのは、神様の言葉を聞くこと、そして変わることです。神様の言葉を聞いて、目の前の出来事と向き合うことです。解決に向けて働くことです。神様が私たちに求めているのは、奇跡を待つことではありません。神様は私たちがみ言葉を聞き、その生き方を変える事を願っているのです。神様はその言葉によって、私たちを変えて下さるお方なのです。私たちはその言葉を聞き、共に歩みましょう。お祈りします。
「悪魔は存在するのですか?」マタイ4章1~11節
誘惑する者が来て、イエスに言った。「神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。」イエスはお答えになった。「『人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる』と書いてある。」 マタイ4章4~5節
「悪魔は本当に存在するのですか?」この質問に対して私は「悪魔は存在しません」と答えています。しかし聖書の悪魔が登場し、人格があり、自由に飛び回り、人間を誘惑し悪い事をさせます。本当にこのような悪魔は存在するのでしょうか?
悪魔という実体、そのものが存在したのではありません。非人間的な行動、人の尊厳と愛を踏みにじることをした人が象徴的に悪魔と呼ばれたのです。一方、悪魔そのものは存在しなくても、悪の塊のようなことは数多く存在します。世界の不平等や戦争は人間が悪魔的存在にならないとできないことです。それは悪魔の仕業ではなく、人間が罪人であり、人間の悪魔の様な行動です。
悪魔はイエス様に「石をパンに変えてみろ」と言います。この中に潜む悪は、奇跡による即席の解決を期待するという悪です。食べ物の不足は奇跡ではなく、すべての人にパンが行き渡るような、平等で平和な社会をもって解決すべきです。奇跡より必要とされたのは社会の変革です。しかし悪魔は「石の方が変わればいい」と言うのです。悪魔的な存在はいつも私たちを、問題の本質から目をそらせようとします。
イエス様はそれに対して4節「人はパンのみで生きるのではない。神の言葉によって生きる」と言います。イエス様は石をパンに変えるのではなく、み言葉によって人間を変えることによって問題を解決しようとするのです。
6節も同様です。悪魔の生き方は奇跡だけを期待する生き方です。神様が都合の悪いことのすべて解決をしてくれる、そう簡単に思ってはいけません。9節にも誘惑があります。自分の思い通りに相手に動いて欲しい。自分のものにしたい。そのような悪が私たちの中にあります。イエス様はそのような誘惑をきっぱりと否定しました。そして10節、私たちは「共に神に仕える者」だと言うのです。それは、人間は神様の前で、互いに平等で、尊重し合う存在だという答えでした。
悪魔の提示する解決方法はどれも、即席の解決方法です。イエス様はことごとく、この即席の神学を否定します。イエス様は、即席の解決よりも、神の言葉が大事だと言います。毎日毎日、食事を食べる様に、少しずつ神様の愛の言葉を聞いて生きる事が重要だというのです。そのように私たちは神様の言葉によって、私たちは少しずつ変えられ、共に生きるようになります。
悪魔そのものはいません。物事を悪魔のせいにしてはいけません。そのような即席で簡単な見方、解決方法こそ、悪魔的な発想です。私たちも時に現実に向き合うことは大変で、逃げたくなる時もあるでしょう。しかし、神様はそのような私たちを変えるために、愛の言葉を与えてくださるのです。私たちに求められているのは、神様の言葉を聞くこと、そして変わることです。神様はその言葉によって、私たちを変えて下さるお方なのです。お祈りします。
【全文】「難民だったイエス」マタイ2章13~23節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちの教会はこどもの声がする教会です。こどもたちと一緒に礼拝をしましょう。こどもたちの声は私たちの教会にとって命と平和の象徴です。そしてもちろんこの世界にとっても命と平和の象徴でしょう。
国連の統計によれば、紛争や気候変動により故郷を追われた難民の数は日本の人口と同じ約1億2000万人に達しています。世界の難民の数は12年連続で過去最高を更新し、増加し続けています。難民の中には17歳以下のこどもが多く含まれています。難民の40%がこどもだと言われます。5000万人のこどもが住む家を追われ、難民となっているのです。難民はパレスチナ、アフガニスタン、シリア、ベネズエラ、ウクライナなどで多く発生しています。戦争や内戦によって、気候変動や飢餓によって多くの難民が生まれています。大変大きな数字ですが、これらの数字にまとめられてしまった一人一人に人生があったはずです。この数字の一人一人の人生に数えきれない悲劇があったでしょう。大切な人の死、家族や友達との別れ、育った町を捨てて逃げなくてはならなかった悲しみを想像します。私たちの世界はちっとも平和になりません。この世界の現実を悲しく思います。
日本は難民に厳しい国だと言われます。日本では年間1万人以上が難民申請をしますが、難民として受け入れられるのは、たった300人ほどです。ほとんど受け付けていません。追い出しているのと変わらないと言えるでしょう。日本で難民として受け入れられたわずかな人々も、文化の壁や経済的困難の中にいます。私たちは文化や経済の違いを超えて、難民を受け入れ、共存できる国になりたいと思います。痛みを持ち、住む場所のない人と共に生きる社会になりたいと願っています。
10月に教会に来られた佐々木和之さんはアフリカ・ルワンダで平和を教えておられますが、その学生の中には紛争によって難民となった学生も数名いるそうです。学費の支払いに苦労しながらも、平和を学びたいと言って大学に通っています。難民だった彼らが、暴力ではなく平和を学び、平和の大切さを伝えてゆく者となる、そのような話に心を支えられています。
イエス様が示されたのは、力に力で対抗するのではなく、愛と平和によって世界を変えるという道でした。これは、今私たちが向き合っている難民問題にも通じるのではないでしょうか。小さなことかもしれませんが、愛に基づく行動を選び取ることで、イエス様が示した平和を実現していけるのです。
私たちの世界は紛争や気候変動によって人生を左右される人がたくさんいる世界です。この世界のどこで神様を見つけたら良いのでしょうか。今日は、神様は悲しみの中に居る人と、また戦火を逃れてきた人と共にいるということを見たいと思います。神様は困難に追われ苦しむ人と共にいることをみてゆきます。聖書を読みましょう。
今日はマタイによる福音書2章13~15節をお読みいただきました。イエス様が生まれた後、エジプトに逃げなければいけなったという話です。当時も、そして今もパレスチナの支配は軍事力によって行われました。民主主義ではなく、一番強い軍事力を持つ者が王となる軍事政権でした。だからイエス様の生涯には、その誕生から戦争の影がまとわりつきます。ヘロデは猜疑心、人を疑う気持ちが強かったと言われています。誰も信じることができなかったのです。いつも自分は誰かに追い落とされて失脚するのではないかと恐れていました。暴力で奪った権力は暴力でしか守ることができません。彼は常に暴力への恐怖と不安を感じていました。ヘロデは自分の地位を狙っていると感じた人がいたなら、親族でも容赦なく殺してゆきました。
ヘロデの権力への執着は、パレスチナに住むこどもたちに対しても容赦なく向けられてゆきました。16節には、ベツレヘムで新しい王になるこどもが生まれたと聞き、2歳以下のこどもを一人残らず殺したとあります。残酷な王です。この権力者は、自己保身の王であり、暴力的な王でした。庶民はいつもこのような権力者に翻弄されていました。人々は救いを求めていました。人々の求めた救いとは平和であり、こどもたちを含めたすべての命が守られていくことでした。そのような場所に救い主イエス・キリストは生まれたのです。
イエス様の誕生は軍事的指導者、自己保身、暴力に象徴されるヘロデとは対極的なものでした。イエス様は強大な力に対して、力のない無力な姿でこの地上に生まれました。そしてイエス様は迫りくる暴力に、暴力で立ち向かうのではありませんでした。イエス様は戦うことではなく、逃げることを選びました。その姿は現代の難民と同じ姿です。それは小さく弱い、難民の姿です。危険から逃げざるを得ない、権力の前に最も弱い存在でした。
クリスマスはイエス様が幼子としてこの地上に生まれたことを伝えています。そしてそれに続くこの個所ではさらに、その幼子イエスが権力から逃れ、難民とならなければいけなかったことを示しています。多くのこどもが殺されました。その中でイエス様は生き残りました。イエス様は虐殺生存者という意味でサバイバーです。虐殺の生き残りの一人でした。多くの同じ世代の人が殺され、難民となり、その生き残りがイエス様だったのです。イエス様は多くのものを背負って生きたでしょう。他の人の人生を背負って生きたのです。そしてその地上の生涯でイエス様は政権に対する復讐ではなく愛と平和を訴えて、歩みました。イエス様は平和についての教えを数多く残しています。
イエス様の生い立ちが、平和の大切さを語らせたはずです。難民であった彼が、虐殺からのサバイバーであった彼が平和を語ることには大きな重みがあったはずです。多くの仲間が死ぬ、殺されるあの戦争、虐殺をもう二度としてはいけないと教えて歩いたのです。復讐ではなく、敵と思えるような相手を愛するようにと教えて歩いたのです。この物語はイエス様が平和をどれだけ大切に思っているのかということを示しています。
そして同時にこの物語は、私たちはこの世界でどこに神様を見出したらよいのかという答えにもなっています。私たちの神様は、戦争のただなかにおられるのです。私たちの神様は苦しむ者と共におられるのです。神様は難民の姿でこの地上を生きたのです。神様は苦しみのただなかに生まれて来られたのです。そのような場所に私たちは神様を見出すことができるのです。
神様は紛争や飢餓によって住む場所を追われた人を通じて問いかけています。神様は逃げている人、飢えた人、渇いた人、旅をしている人としてこの地上におられるのです。私たちはその人々の中に神様を見出すように、招かれています。私たちの世界は相変わらずまだヘロデのような凶悪な権力者・独裁者がたくさんいます。それらが民主的なリーダーに代わるように祈ります。でもきっとヘロデ、あの独裁者は世界に何人かいるあの人々だけではありません。
私たちの心の内側にも向き合いましょう。きっと私たちは自分の心の中にもヘロデを見つけることができるでしょう。他者を受け入れず、追い出し、自分を守ろうとする思いは、私たちに小さく、少しずつあるものです。誰にでも自分の思い通りにしようと強引になることがあるものです。それをキリスト教では罪と呼びます。私たちは全員そのような罪をもった罪人です。いつも他者の苦しみを受け止めず、追い出し、自分を守ろうとばかりしています。苦労している他者の人の言葉に耳を傾けず、その姿をしっかりと見ようとしていません。相手の苦しみを心で受け止めていないのです。私たちはヘロデだけを悪とするわけにはいかないでしょう。この世界、この私の中にヘロデがいます。この物語は、この世界の、この私の罪に気づくように訴えています。
私たちの世界は平和を実現することが出来るでしょうか。私たちはイエス・キリストを見つめそれを考えましょう。イエス様がそれを教えてくれるはずです。馬小屋の姿だけではなく、難民だった姿もイエス様のあり方だったのです。現代の難民とかつての難民イエス・キリストの両方に目を留める時、私たちは神様を見つけることができるでしょう。そして平和を実現してゆく者へと変えられてゆくでしょう。
神様がなぜこのような難民というあり方を選ばれたのか、なぜこのような時代を選ばれたのか、なぜこの場所を選ばれたのか不思議に思います。でもイエス様はこのようなあり方と場所を選び、お生まれになりました。私たちの神様とはそのような神様です。苦しみ、悲しみ、逃げ、孤独の中に共にいることを選ぶのです。
きっと神様がいないから悲しみがあるのではないでしょう。きっと悲しみのあるところにこそ神様が共にいるのです。そしてそれは私たちの人生でも同じです。あなたの人生には苦しみも悲しみもあるでしょう。逃げなければいけない時もあるでしょう。でも神様は確かにその時、あなたと共におられるのです。だから希望を持って生きてゆきましょう。
神様がそこにいます。暴力のただなかに幼子として、無力な存在でおられます。戦うのではなくそこから逃げる存在として神様がおられます。神様はそのようにして無力な私たちと共にいて下さるのです。そして私たちに愛と平和を教えているのです。それが私たちの神様なのです。この愛に従って歩んでゆきましょう。
小さな命が世界を変えていったように、私たちの小さくても互いのためにすること、小さくても愛を伝えてゆくこと、それが世界を変えてゆくはずです。お祈りいたします。
「難民だったイエス」マタイ2章13~23節
「ヨセフは起きて、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。」
マタイによる福音書2章14~15節
国連の統計によれば、紛争や気候変動により故郷を追われた難民は1億2000万人に達し12年連続で過去最高を更新しています。難民の40%がこどもです。この数字の一人一人の人生に数えきれない悲劇があったはずです。日本は難民に厳しい国です。私たちは文化や経済の違いを超えて、難民を受け入れ、共存できる国になりたいと思います。この世界のどこで神様を見つけたら良いのでしょうか。今日は、神様は悲しみの中に居る人と、また戦火を逃れてきた人と共にいるということ、神様は困難に追われ苦しむ人と共にいることをみてゆきます。
暴力で奪った権力は暴力でしか守ることができません。ヘロデは自分の地位を狙っている者は親族でも容赦なく殺してゆきました。ヘロデの権力への執着は、こどもたちに対しても向けらます。この権力者は、自己保身の王であり、暴力的な王でした。人々の求めた救いとは平和であり、こどもたちを含めたすべての命が守られていくことでした。そのような場所に救い主イエス・キリストは生まれたのです。
イエス様の誕生は軍事的指導者、自己保身、暴力に象徴されるヘロデとは対極的なものでした。イエス様は強大な力に対して、力のない無力な姿でこの地上に生まれました。イエス様は逃げることを選びました。その姿は現代の難民と同じ姿です。多くのこどもが殺されました。その中でイエス様は生き残りました。イエス様は虐殺生存者という意味でサバイバーです。難民、虐殺からのサバイバーであった彼が平和を語ることには大きな重みがあったはずです。そしてイエス様は復讐ではなく、敵と思えるような相手を愛するようにと教えて歩いたのです。この物語はイエス様が平和をどれだけ大切に思っているのかということを示しています。
そして同時にこの物語は、私たちはこの世界でどこに神様を見出したらよいのかという答えにもなっています。私たちの神様は苦しむ者と共におられるのです。神様は難民の姿でこの地上を生きたのです。神様は苦しみのただなかに生まれて来られたのです。そのような場所に私たちは神様を見出すことができるのです。
私たちの心の内側にも向き合いましょう。きっと私たちは自分の心の中にもヘロデを見つけることができるでしょう。誰にでも自分の思い通りにしようと強引になることがあるものです。それをキリスト教では罪と呼びます。私たちは全員そのような罪をもった罪人です。この世界、この私の中にヘロデがいます。この物語は、この世界の、この私の罪に気づくように訴えています。
現代の難民とかつての難民イエス・キリストの両方に目を留める時、私たちは神様を見つけることができるでしょう。そして平和を実現してゆく者へと変えられてゆくでしょう。小さな命が世界を変えていったように、私たちの小さくても互いのためにすること、小さくても愛を伝えてゆくこと、それが世界を変えてゆくはずです。お祈りいたします。
「ヘビとの共存」
みなさん、あけましておめでとうございます。今年一番最初の朝を、神様を礼拝することから始めることができるのは素晴らしい事です。今年も心からの礼拝を神様に献げてゆきましょう。私たちは今年もこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声に導かれて一緒に礼拝をしましょう。
十二支によると今日からヘビ年です。干支は東洋の思想であり、キリスト教とはあまり関係のないものです。しかし、この時期はいろいろなところでかわいいヘビのイラストを見かけます。干支の世界観では、脱皮して成長するヘビに「再生する力」や「無限の可能性」があり、知恵や金運を生み出すと考えられてきたそうです。こうしたことからヘビが脱皮した皮をおサイフに入れておくと金運が上昇するという言い伝えがあるそうです。そして中でもキレイに形の崩れていないヘビの抜け殻を持っていると金運が上がるそうです。干支によれば、このようにヘビ年というのは縁起のいい年だそうです。
ヘビは縁起が良いという話を聞いていて、聖書のヘビはどうだろうかと考えました。実は聖書にもヘビがたくさん登場しますが、ほとんどが否定的な存在として登場をします。聖書の中でもっとも印象的なヘビは創世記3章に登場するヘビです。このヘビはしゃべって人間をだまします。人間は神様の教えをヘビにそそのかされて、破ってしまうのです。ヘビはそのために神様の呪いを受けて、地を這って生きるようになったとあります。他の個所でもヘビは全世界を惑わす存在(ヨハネ黙示録12章)と言われたりしています。聖書の中でヘビは悪魔の代表とされ、汚れた動物であり絶対に食べてはならないと、も言われています。縁起がいいとする文化がある一方で、聖書の中でヘビはあまりにも悪者にされおり、ちょっとかわいそうな気がしています。
街ではヘビを祝っているのにも関わらず、聖書では邪悪な存在として現れます。私たちはどのようにヘビを受け止めたらよいでしょうか。ヘビ年を迎えたらよいでしょうか。ヘビと共存したらよいでしょうか?実は聖書の中でもごくまれなケースですが、ヘビを肯定的にとらえている箇所があります。例えばイエス様は「蛇のように賢くなれ」と言いました。そして今日のイザヤ書でもヘビが登場します。今日は邪悪なものとしてだけではない、共に生きる存在としてのヘビを聖書から見てゆきたいと思います。ヘビとの共存を考えます。そしてこの個所から今年1年、神様が私たちに与えて下さる力について考えたいと思います。聖書を読みましょう。
今日はイザヤ書11章3~9節をお読みいただきました。3節には「彼」とあります。「彼」とは誰のことでしょうか。キリスト教では伝統的にイエス・キリストのことと解釈をしてきましたが、決してそれに捕らわれる必要はありません。聖書には彼としか書いていない以上、解釈は自由です。あなたのこと、私のこととしても解釈できます。誰かが霊に満たされるのではなく、あなたが霊に満たされると解釈しましょう。聖書はみなさんが霊に満たされる、つまり神様の見えない力に満たされると言っています。
みなさんは見えない力に満たされるのです。それはみなさんの内側から湧いてくる力ではありません。それはどんなに自分の中に探しても見つかりようのない力です。その見えない力が外側から神様からあなたにやって来るのです。神様はあなたを、見えない力で満たしてくださるお方です。
見えない霊の力に満たされるとどうなるのでしょうか。3節の後半を見ます。聖書によれば、あなたは見たもの、聞いたものだけで判断しないようになります。私たちは日々、目に見えるもの、耳に聞こえるものに左右されて生きています。でも神様からの力で満たされると、4節弱い人に正当な裁きを行う様になります。
これはどんな意味でしょうか。あなたはその力を受けると目と耳だけで判断しないようになります。聞こえない物を聞き、見えない物を見るようになるのです。つまりそれは、誰かの声にならない声を聞き、誰かの表面化しない苦しみを想像するようになるということです。弱い人の立場から物事を見て、想像することができるようになるということです。体の弱い人、立場の弱い人、弱くされている人に寄り添うことができるようになるということです。神様はそのような見えない力を、あなたに与えてくださいます。そのような力であなたを満たしてくださるのです。
唇が死に至らせるともあります。もちろん本当に相手を死なせてしまう力が与えられるわけではありません。神様は私たちに立場の弱い人に目を向け、助ける、そのような神様の力を与えられるのです。
5節を見ましょう。「正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる」とあります。正義を腰の帯とするとは、正義を私たちの人生の中心に置くようになるという意味です。正義とは何でしょうか?私たちは正義と聞くと、悪者に罰が与えられることを想像しがちです。正義の味方、ヒーローが敵を暴力的にやっつける姿を正義と考えがちです。でも神様の正義はそのような暴力的な正義ではありません。聖書の正義とは私たちの思う正義とは少し違います。聖書の正義は平和や公平と近い概念です。聖書の正義は共存の概念です。
私たちの世界では政治、経済、裁判、教育、人権あらゆる場面で独占や偏りがあります。でも聖書の正義は、それらに偏りが無い状態です。立場の弱い人、貧しい人の立場からの視点で公平であるということが聖書の正義です。私たちは神様から力をいただくと、その正義・公平さを人生の中心に置くようになるのです。都合のよい話ではなく、真実を追い求める様になるのです。やられていた人がやり返すのではなく、共存をする様になるのです。
6節を見ましょう。まさにこれが聖書の正義が実現した世界です。『狼は小羊と共に宿り豹は子山羊と共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ その子らは共に伏し 獅子も牛もひとしく干し草を食らう』とあります。ここで描かれているのは、弱い者と強い者が、富める者と貧しい者が共存してゆく世界です。神様の正義とはこのように様々な立場の人が共存共栄してゆける場所のことです。弱肉強食ではない場所、それが神様の霊に満たされた時に起るのです。
それが今年、みなさんが満たされる力です。神様は他の誰でもないあなたに、このような世界を実現する力で満たしてくださるのです。あなたは神様の示す正義の力で心が満ち溢れます。そしてあなたは様々な偏りの中で、平和と公平を追い求めるようになるのです。
神様から見えない力をもらい、正義・立場の弱い人からみた公平を追い求めてゆく時、そこでは単に立場の逆転が起こるだけではありません。こひつじを殺していた狼が、今度は反対にこひつじが狼を殺す番が来るという事ではありません。今度は子牛がライオンを倒すのではないのです。
聖書は、本来共存が難しい者同士が共に生き、共に寝て、共に育つという風景を描いています。そして小さいこどもがそれを導くようになると言っています。それが正義に満たされた世界なのです。神様はこのような正義の世界を求め、私たちにその実現のための力を与えて下さるのです。
8節を見ましょう。ヘビが登場します。『乳飲み子は毒蛇の穴に戯れ幼子は蝮の巣に手を入れる』聖書には赤ちゃんがヘビとも仲良くできるという描写です。私たちには神様の正義を実現する力が与えられます。そしてそのようにして実現する世界は、悪魔の代表と言われるヘビと仲良くできる世界なのです。
聖書はヘビを悪魔の代表のように扱う場面が多くあります。しかし、今日の個所ではヘビと共存できると言われます。ただ悪魔と言われている相手を踏みつけにして、亡きものとするなら簡単でしょう。しかし神様はそれを求めてはいません。そのような相手とも共存できる、あなたはその力に満たされると教えているのです。
私たちの世界では様々な衝突や対立があります。私たち個人個人の生活の中でも様々な衝突や対立があるでしょう。しかし、聖書はあなたがたは霊で満たされると言います。あなたを満たすのは排除の霊ではなく、正義の霊、共存共栄の霊です。その力であなたは満たされ、相手をやっつけるのではない方法で、共に生きていく力が与えられるのです。それが今年、私たちが神様からいただく力です。
そして私たちには今年、失敗もあるかもしれません。誰かに迷惑をかけることもあるかもしれません。きっとあるでしょう。でも神様は大きな失敗をして、たとえヘビのように否定をされても、きっとそれでも共に生きる道、共存の道を備えて下さいます。私がヘビの様になってしまう時も、神様は私に小さなこどもの命を通じて、私たちを導いてくださるのです。
9節、神様のそのような知恵はあまねく大地を覆います。神様は選ばれた人にだけ、その知恵をあたえるのではありません。海の水のように、大地のように、神様はすべての人をその力で満たしてくださるのです。
今年1年、あなたは神様の見えない力で満たされるでしょう。そしてあなたは正義と公平・平和を追い求めるようになるでしょう。それは狼を捕まえ、蛇を踏みつけにする生き方ではありません。神様は敵と思える相手とも、共存と平和の道へと導いてくださるでしょう。共に生きる1年があなたには実現するのです。神様の力が海を覆う水のように、あなたの心を満たします。そのことを信頼して新しい1年を歩みましょう。お祈りします。
「ヘビとの共存」
乳飲み子は毒蛇の穴に戯れ 幼子は蝮の巣に手を入れる。イザヤ11章8節
みなさん、あけましておめでとうございます。今年一番最初の朝を、神様を礼拝することから始めることができ感謝です。十二支によると今日からヘビ年です。ヘビ年というのは縁起のいい年だそうです。聖書にもヘビがたくさん登場しますが、聖書では神様の呪いを受けた動物、全世界を惑わす存在、悪魔の代表とされています。聖書でヘビはあまりにも悪者にされおり、ちょっとかわいそうです…。聖書の中にはヘビを肯定的にとらえている箇所があります。今日はヘビとの共存を考えます。
3節の「彼」とはあなたのこととしても解釈できます。あなた神様の見えない力に満たされます。その力を受けると目と耳だけで判断しないようになります。つまりそれは、誰かの声にならない声を聞き、誰かの表面化しない苦しみを想像するようになるということです。弱い人の立場から物事を見て、想像することができるようになるということです。弱くされている人に寄り添うことができるようになるということです。神様はそのような見えない力を、あなたに与えてくださいます。
5節、私たちは正義を、正義の味方・ヒーローが敵を暴力的にやっつける姿と考えがちです。でも神様の正義はそのような暴力的な正義ではありません。聖書の正義は平和や公平と近い概念です。聖書の正義は共存の概念です。やられていた人がやり返すのではなく、共存をする様になるのです。
6節はまさに聖書の正義が実現した世界です。弱い者と強い者が、富める者と貧しい者が共存してゆく世界です。神様の正義とはこのように様々な立場の人が共存共栄してゆける場所のことです。聖書は、本来共存が難しい者同士が共に生き、共に寝て、共に育つという風景を描いています。そして小さいこどもがそれを導くようになると言っています。それが正義に満たされた世界なのです。
8節にはヘビが登場します。聖書はヘビを悪魔の代表のように扱う場面が多くあります。しかし、今日の個所ではヘビと共存できると言われます。
私たちの世界、個人個人の生活の中には様々な衝突や対立があるでしょう。しかし、聖書はあなたがたは霊で満たされると言います。あなたを満たすのは排除の霊ではなく、正義の霊、共存共栄の霊です。その力であなたは満たされ、相手をやっつけるのではない方法で、共に生きていく力が与えられるのです。それが今年、私たちが神様からいただく力です。そして私たちには今年、失敗もあるかもしれません。神様は大きな失敗をして、たとえヘビのように否定をされても、きっとそれでも共に生きる道、共存の道を備えて下さいます。
今年1年、あなたは神様の見えない力で満たされるでしょう。そしてあなたは正義と公平・平和を追い求めるようになるでしょう。神様は敵と思える相手とも、共存と平和の道へと導いてくださるでしょう。共に生きる1年があなたには実現するのです。神様の力が海を覆う水のように、あなたの心を満たします。そのことを信頼して新しい1年を歩みましょう。お祈りいたします。
【全文】「神と星に導かれて」マタイ2章1~12節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝をお献げできること、主に感謝します。2024年の最後の主日礼拝です。今日も私たちはこどもの声がする礼拝を続けましょう。
今年も一年間たくさんの礼拝をささげることができました。みなさんはどんな一年だったでしょうか。教会のことを振り返ると、いろいろな事のあった一年でした。何よりも嬉しいのはバプテスマ式だったでしょう。一番のビックニュースでした。転入会した方も2名おられました。何十年ぶりかに教会に戻ってきた方がおられたり、スペイン語での証しもありました。仲間が増えたことは何より嬉しい事です。
他にもたくさんの出来事がありました。工藤静香のミュージックビデオの撮影や、孤独のグルメのテレビ撮影もありました。大口の寄付やクラウドファンディングの達成というのもありました。こひつじカフェも始まりました。どれも1年前の計画に無かった事で、1年前には予想できないことがたくさん起こった年でした。
1年前の信徒会や、執事会の記録も見直していました。地域協働プロジェクトの申請が理事会に否決されたのは1年前でした。私たちはこの制度を使って土地売却し、発展的な会堂修繕ようとしていました。しかしそれは理事会で否決されてしまいました。私たちは納得できない思いもありながらも、新しい制度作りの過程で繰り返し意見を表明してきました。新しい規約の素案ができていますが、そこには私たちの要望が多く組み込まれています。これも1年前に想像していたこととは大きく違う結果になっています。
今の私たちは1年前に目指した場所とは、かなり違う場所に到着しているような気がします。私たちが神様のために、誰かのために、地域のために立ち上がろうとするとき、今まで決して起こらなかったことが起きたのです。私たちは1年間本当によく頑張りました。自分達をほめてあげたいのですが、でもそれだけではありません。このこと全体が神様の導きだと思います。神様の導きとしか言えないことがたくさん教会で起った1年でした。
予想もしないことがたくさん起き、私たちの旅路は変更を繰り返してばかりです。でもそれは今、希望へとつながっています。教会に起きたこれらの事は偶然ではなく、すべて神様に導かれ起きたのです。
もちろん私たちの旅はまだまだ終わりません。これからが本番です。来年、再来年の計画を作っています。でもきっとまた計画にないことがたくさん起こるでしょう。私たちの計画を超える、神様の導きがあるでしょう。私たちの人生はそのように、計画通りにはゆきません。でもかならず神様が導いてくださるのです。
教会に集う恵みは、このような神様の導きを強く実感できることでしょう。教会に集うと、教会が神様に導かれているという実感をもつことができます。そしてきっと私の人生も導かれていると実感できるでしょう。教会を通じて、共に集う人の人生を通じて、私たちの人生が導かれていると感じることができるでしょう。それは教会に集う人の恵みです。
次の1年も、教会も人生も、思い通りにはならないでしょう。私の予測通り、計画通りにはならないでしょう。それが人生です。
でもその変更こそ、神様の導きかもしれません。神様は必ず私たちを導いてくださるお方です。神様はこれまで私たちを不思議な道に導いてくれたように、来年も私たちを導いてくださいます。そのようなことを強く感じる1年でした。1年間、神様が導いてくださったことを感謝しています。今日も聖書を読みます。聖書の物語から神様の導きを見てゆきましょう。
マタイによる福音書2章1~12節をお読みいただきました。今日の個所では占星術の学者が登場します。彼らはイスラエルの人々にとって脅威でした。占星術の学者といえば東側の大帝国からくる、位の高い人でした。東側の国とはこれまで何度も戦争をしてきました。東の人が来るということは悪いことが起こる前兆です。
そして何より、彼らは星占いといういかがわしい方法によって未来を予測し、未来の計画を決めるという人でした。ユダヤ人から見ると、学者たちは決して尊敬できる人ではありませんでした。恐怖と軽蔑のまなざしを向けるべき人でした。そのような学者たちがある時、ひときわ輝く星を見つけました。これまで星の動きを正確に予測してきた人が、いままでとは全く違う動きと輝きをする新しい星を見つけたのです。学者にとってそれは大きな予想外、大きな計画外の出来事でした。
占星術によれば、その星は新しい王の誕生を示す星でした。学者たちは新しい王が生まれたことを確かめ、拝みに行くために、計画には無かった旅に出ることにしたのです。東の文明から、イスラエルまでの旅は数百キロに及んだはずです。未来を正確に予測する学者たちが、計画にはない長い旅に出発をしました。しかもそれは星の輝きが頼りだったのです。
まず学者たちはヘロデ王を訪ねました。新しい王が誕生するなら王家に誕生するのだろうと予想したからです。2節ヘロデ王に「新しい王はどこにいますか?拝みに来たのです」と尋ねました。しかしそこに新しい王は誕生していませんでした。ようやくイスラエルに着いた彼らは計画を変更しなければいけませんでした。今度はエルサレムの人々に聞いて回ったのでしょうか。首都エルサレムの人々なら何か知っているはずだと予測したのでしょう。しかしエルサレムの人々は不安がるばかりで、何も知らなかったのです。
学者たちは、ヘロデ王から新しい王はベツレヘムで生まれるということを聞きました。ベツレヘムは決して大きな町ではありませんでした。再度、学者たちは計画を変更し、ベツレヘムへ向かいました。しかし今度は家がたくさんあり、どこの家に新しい王が生まれたのか、見分けがつきませんでした。予測ができませんでした。しかしそこでもまた星の光が導きました。星の光は学者たちをイエス様の生まれた家の前まで導き、止まったのです。占星術の学者たちは、そこでようやくイエス様に出会うことができました。旅の出発をしてからイエス様に出会うまでに学者たちの計画と予想は一体何度、覆され、変更されたでしょうか。もう数えることができません。その度ごとに行き先が変わってゆきました。
しかしそのような変更は神様の導きによって起こされたものでした。新しい王、イエス・キリストに出会うことができたのは、まさに神様の導きだったのです。神様は何度も何度も、学者たちの計画を変更させ、学者たちをイエス様の元に導いたのです。彼らは神様の導きによって、何度も計画を変更し、ようやくイエス様に出会うことができたのです。
学者たちはイエス様に3つのプレゼントを渡しました。これでようやく自分の家に帰ることができそうです。ほっとしたでしょうか。しかしこの旅は最後まで神様の導きによって、計画が変更されます。当初の計画はヘロデに会って新しい王について報告をしてから帰る計画でしたが、夢のお告げに従って、ヘロデに会わずに別の道を通って帰ることにしたのです。このように学者たちは繰り返し計画を変えられ、自分たちの予測とまったく違う旅をしたのでした。それは星によって導かれた旅、神様によって導かれた旅だったのです。
さらにこの物語には、もう一つの予想外が隠されています。イエス様を見つけたのは、東の大帝国からくる、いかがわしい占星術師だったということです。新しい王はイエスラエルの王様が見つけたのではありませんでした。新しい王は救い主を求め続けたイスラエルの人々が見つけたのでもありませんでした。予想もつかない人が、信じる宗教さえ違う人が、新しい王イエス様を見つけたのです。これはイスラエルの人々にとってもまったく予想外のことでした。神様の導きとはこのようなものでした。徹底的に人々の計画通り、予想通りにはいかなかったのです。神様の計画に振り回された学者たちもかわいそうです。
この物語は私たちの人生にも当てはまるでしょうか。私たちの1年もこのようなものだったのでしょう。私たちは計画を立てましたが、計画通り、予想通りにはいかなかったことがたくさん起こりました。それは神様が私たちを導き、何度も計画の変更を迫った結果だったのでしょう。
私たちの1年も、振り返ると様々なことが起きた1年でした。それぞれ全く計画外で、予想外でした。しかしそれは確かに神様の導きだったと思います。私たちの1年は何度も計画が変更される占星術の学者の旅のようでした。でもそのような1年だったからこそ、なおさら私たちは神様の導きを強く感じることができた1年となったでしょう。
さて次の1年がはじまります。次の1年私たちはどんな星を見つけ、どんな旅に出るのでしょうか?どんな出来事が待っているのでしょうか?心がくじけるような変更もあるかもしれません。しかし確かなことは、私たちは神様の大きな導きの中に生きているということです。私たちは今年神様の大きな導きの中で1年を過ごしました。教会もひとりひとりもそのように神様に導かれた1年でした。
次の1年もきっとそうでしょう。予想ができないことは不安な事でもありますが、私たちにはまた様々なことが起こるでしょう。私たちに自分たちの計画や予測を超えて、また明るく輝く星が示されるでしょう。共にそれを目指して、旅路を出発しましょう。次の1年も旅の計画は何度も変更されます。私たちは占星術の学者のように何度も旅路を変更し、紆余曲折するでしょう。でもそれこそが神様の導きなのです。私たちはこの1年の神様の導きに感謝し、来年も神様の導きを共に歩んでゆきましょう。お祈りをいたします。
「神と星に導かれて」マタイ2章1~12節
ところが「ヘロデのところへ帰るな」と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰って行った。
マタイによる福音書2章12節
今年も一年間、様々な出来事がありました。バプテスマ式、転入会、テレビ撮影、寄付、こひつじカフェ・・・。1年前には予想できないことがたくさん起こった年でした。地域協働プロジェクトの申請が理事会に否決されたのは1年前でした。私たちは納得できない思いもありましたが、新しい制度には私たちの要望が多く組み込まれています。これも1年前の想像とは大きく違う結果になっています。
今の私たちは1年前に目指した場所とは、かなり違う場所に到着しているような気がします。これら全体が神様の導きだと思います。神様の導きとしか言えないことがたくさん教会で起った1年でした。もちろん私たちの旅はこれからが本番です。でもきっとまた計画にないことが起こるでしょう。私たちの計画を超える、神様の導きがあるでしょう今日も聖書の物語から神様の導きを見てゆきましょう。
占星術の学者は星占いによって未来を予測し、未来の計画を決めるという人でした。そのような学者たちがひときわ輝く星を見つけました。これまで星の動きを正確に予測してきた人が、いままでとは全く違う動きと輝きをする新しい星を見つけたのです。学者にとってそれは大きな予想外の出来事でした。
学者たちは計画にはない長い旅に出発し、まずヘロデ王を訪ねました。しかしそこに新しい王は誕生していませんでした。彼らは計画を変更しなければいけませんでした。首都エルサレムの人々なら何か知っているはずだと予測しました。しかし彼らは何も知りませんでした。再度、学者たちは計画を変更し、ベツレヘムへ向かいました。しかし今度は家がたくさんあり、どこの家に新しい王が生まれたのか予測ができませんでした。そこでもまた星の光が導きました。星の光は学者たちをイエス様の生まれた家の前まで導き、止まったのです。占星術の学者たちは、そこでようやくイエス様に出会うことができました。旅の出発をしてからイエス様に出会うまでに学者たちの計画と予想は一体何度、覆され、変更されたでしょうか。しかしそのような変更は神様の導きによって起こされたものでした。この旅は最後まで神様の導きによって、計画が変更されます。夢のお告げに従って、ヘロデに会わずに別の道を通って帰ることにしたのです。学者たちは繰り返し計画を変えられ、自分たちの予測とまったく違う旅をしました。それは神様と星に導かれた旅だったのです。
この物語は私たちの人生にも当てはまるでしょうか。私たちは計画を立てましたが、計画通り、予想通りにはいかなかったことがたくさん起こりました。それは神様が私たちを導き、何度も計画の変更を迫った結果だったのでしょう。
私たちは次の1年どんな星を見つけ、どんな旅に出るのでしょうか?確かなことは、私たちは神様の大きな導きの中に生きているということです。私たちの計画や予測を超えて、また明るく輝く星が示されるでしょう。共にそれを目指して、旅路を出発しましょう。来年も神様の導きを共に歩んでゆきましょう。お祈りします。
【全文】「孤独に生まれた神」ルカ2章1~7節
みなさん、こんばんは。今日はようこそキャンドル礼拝にお越し下さいました。この教会の牧師の平野と申します。私たちの教会はこの礼拝をこどもと一緒持っています。こどもたちの声や足音もこの礼拝の一部です。命の音を感じながら一緒に礼拝をしましょう。
今年、私たちの教会は「孤独のグルメ」というドラマでとりあげられて、大きな注目を集めました。私たちの運営するこども食堂がモチーフとなり、輸入雑貨販売の主人公が急にこども食堂のボランティアをすることになったり、両親が海外出張しているこどもが寂しくてこども食堂に食べに来たり、妻に先立たれた夫が手作りの食事を食べにこども食堂に来たりするというドラマでした。このドラマは主人公がいつも孤独に、一人で食事をするのがお決まりなのですが、今回に限り「孤独ではない」設定となりました。初めて出会う3人が一緒に時間を過ごし食事をしたのです。よいドラマだったと思っています。こども食堂を通じて、普段の教会の温かさも伝わったと思っています。
教会とは何かにすがりたいと思っている人だけが集まる場所、深い悩み事がある人だけが集まる場所ではありません。さまざまな人が集まっています。教会の雰囲気は、さまざまな人が集まることによって織りなされています。その雰囲気のひとつは「孤独ではない」という雰囲気です。教会に来れば誰かに会うことができます。誰かと一緒に食事をすることができます。ともに時間を過ごし、食事をすれば、気分が明るくなったり、元気が出てきたりするものです。教会は誰かと共に時間を過ごす場所として、孤独ではない場所として建っています。
何回か教会のそのような雰囲気の中にいると「ああ、神様に守られている」と感じることがあるでしょう。私は友人や仲間に囲まれている。でもそれだけではない。もっと大きな、もっと深いものに包まれていると感じることができるでしょう。みなさんにもぜひ今日はその雰囲気を感じ取って帰って欲しいと思っています。また教会には様々な行事があります。どれもたくさんの人が集まる行事です。きっと私には仲間が共にいるということ、私には神様が共にいるということを感じることができると思います。今日はお読みいただいた物語から、孤独と神様の存在について、一緒に考えてゆきましょう。
***
絵本と聖書を読んでいただきました。絵本の中で、生まれてきた赤ちゃんが神の子イエス・キリストです。私たちの心と魂を救ってくれる存在です。
聖書によればイエス・キリストの父と母は出産が迫っているにも関わらず、旅に出なければいけませんでした。大変な旅です。そして旅先で泊まる場所が無かったとあります。誰も助けてくれなかったのです。そしてさらに旅先で産気づき出産を迎えることになりました。生まれたこどもは飼い葉桶、動物にエサをやるための箱に入れられたとあります。このことから母マリアは家畜小屋で出産をしたのではないかと伝承されています。何と言う出産でしょうか。
絵本では安らかな出産だった様に描かれていますが、現実に家畜小屋で出産する母マリアはどれだけの不安を感じながらの出産だったでしょうか。旅先の出産、家畜小屋での出産、それは不衛生で、十分な支援の無い出産だったでしょう。誰の助けもない夫婦二人だけの驚くほど孤独で困難な出産でした。まずマリアは思ったでしょう。「こんな時、夫はちっとも役に立たない」「夫は何もわかっていない」。そんな声が聞こえてくるようです。
家族がたくさんいる中での出産ならばどれほど心強かったことでしょうか。せめてもう一人、励ましてくれる仲間がいたらどれほど心強かったことでしょうか。しかしマリアたちは孤立無援の出産を体験しました。現実はこのような安らかなものではなく壮絶なものだったでしょう。
私たちはこのように生まれてきたのが神様と等しい存在、イエス・キリストだと信じています。神の子イエス・キリストはこのように地上に生まれてきたのです。生まれてきたのは孤独な場所でした。神の子イエス・キリストは孤独な出産の現場で生まれてきたのです。それが本当のクリスマス物語だったのです。
みなさんはこの物語からどのようなことを感じるでしょうか。一人で苦難を乗り越えるのは大変なものです。仲間の大切さを感じるでしょう。人生で大事なものは共に歩む仲間です。ここでは共に生きる仲間の心強さが語られているでしょう。
そしてもうひとつこの物語は、神様がどこに、どんな場所にいるのかということも教えてくれます。つまりそれは、神様は孤独の中に来て下さるということです。神の子イエス・キリストはにぎやかな場所に生まれたのではありませんでした。イエス・キリストは孤独で、助けの足りない、まさにその場所を選んで生まれてきたお方だったのです。神様はこの出産によって、神様は孤独の中に共にいるお方であることを表したのです。神の子ならばもっと華々しく生まれることもできたでしょう。しかし神の子は孤独な場所に生まれることを選んだのです。それが神様のあり方だったのです。
私たちの周りにはたくさんの孤独があります。出産、子育て、学校、職場、家庭、食事、介護、さまざまな場所に孤独が存在します。そのような孤独のある場所に、神様は来て下さるお方です。神様は孤独にいるその心に生まれ、その心に共にいてくださるお方なのです。そして神様は人と人とを結びつける場所に導いてくださるでしょう。みなさんにもこの神様が共にいるのです。
今日、みなさんはキャンドルをひとつずつ持っています。それは消えそうで不安になる小さな光です。ひとつでは孤独なさみしい光です。でもそこに神様が共にいて下さいます。そして神様は孤独ではない場所に、たくさんの光が集まる場所に導いてくださるでしょう。それが今日です。今日神様はこのキャンドルのような私に共にいて下さり、美しいもので私たちを穏やかにしてくださるのです。神様はきっとこれからも今日のように、美しく、穏やかな気持ちにする場所へと私たちを導いてくださるでしょう。その様にして今、神様は私たちと共にいて下さるのです。
神様は孤独と思える場所に共にいて下さるお方です。どうぞそれを感じて帰ってください。お祈りをいたします。
「孤独に生まれた神」ルカ2章1~7節
彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
ルカによる福音書2章6~7節
今年、私たちの教会は「孤独のグルメ」というドラマでとりあげられて、大きな注目を集めました。このドラマは今回に限り「孤独ではない」設定となりました。こども食堂を通じて、普段の教会の温かさも伝わったと思っています。
教会の雰囲気は、さまざまな人が集まることによって織りなされています。そのひとつは「孤独ではない」という雰囲気です。教会に来れば誰かに会い、誰かと一緒に食事をすることができます。教会は孤独ではない場所として立っています。何回か教会のそのような雰囲気の中にいると「神様に守られている」と感じることがあるでしょう。
聖書によれば、神の子イエス・キリストが生まれてきたのは孤独な場所でした。孤独な出産によって、神様は孤独の中に共にいるお方であるということを表したのです。私たちの周りには出産、子育て、学校、職場、家庭、食事、介護、さまざまな場所に孤独が存在します。そのような孤独のある場所に、神様は来て下さるお方なのです。神様は孤独にいるその心に生まれ、その心に共にいてくださるお方なのです。神様は孤独と思える場所に共にいて下さるお方です。今日はどうぞ孤独でない教会でそれを感じてお帰りください。
【全文】「恐れず、迎え入れなさい」マタイ1章18~25節
みなさん、おはようございます。今日もこうしてクリスマス礼拝を共にお献げできること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。こどもたちの声、命の声に囲まれながら、共に礼拝をしましょう。
みなさんもきっとそうだと思いますが、この後の食事会を楽しみにしています。私たちはこの後の持ち寄りの食事会を愛餐会(あいさんかい)と呼んでいます。これは互いを思う、愛を確かめ合う食事会です。
いろいろな人がいろいろなメニューを持ってきています。この食事会が楽しいのは、色とりどりのメニューが同時にテーブルの上に並ぶことです。この食事会は一人一人が違うものを持ち寄って集まることが大事だからです。もちろん時々かぶってしまうこともありますが、それは似ていても、ひとつとして同じものがない、違う味です。そしてこの愛餐会は食べながら、あなたの作ったものがおいしいと言い合う会でもあります。みんながお互いの笑顔を想像しながら作りました。誰かのことを思って何かを準備する、これが愛ではないでしょうか。これが愛餐会です。愛餐会は一品では、一人ではできない集まりです。みんながみんなを思い合って集まり、分かち合うことが愛になるのです。
私たちは愛し合うということを難しく考えすぎているかもしれません。愛し合うということは、この食事のようなことです。誰かを思って準備すること、ひとりひとりの違いが大事であること、分かち合うこと、お互いのことをお腹の中に迎え入れ、受け入れ、ほめ合うということ、それが愛なのです。相手を私たちのお腹、心に迎え入れることが愛なのです。愛餐会は料理を通じてお互いを迎え入れる象徴です。それは教会の本質とも言えるでしょう。何も持って来ていない人もどうぞ、食べて帰ってください。私たちはそれぞれ、互いの違いを大切に思い、お腹で受け止め、心でそれを受け入れてゆきます。その時私たちは楽しさを覚えるのです。料理の中には食べた事のないもの、苦手なものもあるでしょう。無理に食べる必要はありませんが、チャレンジするともしかしたらおいしいかもしれません。ぜひいろいろな物を食べて、いろいろなものを受け止めて欲しいと思います。
私たちの教会は今年、実に様々な人を迎え入れました。礼拝だけではなく、こども食堂やカフェ、こどもの行事やテレビの撮影もありました。たくさんの方が来てくれることは嬉しいことです。私たちの教会では、いつもどの集会もだれでも来ていいのだということをアピールしています。教会は信じている人、ちゃんとした人、礼拝する人だけが来る場所ではありません。毎週集う人のためだけの場所でもありません。いろいろな人が、いろいろな気持ちを持ち寄って集まるのが教会です。教会には嬉しい人、悲しい人、泣いている人、笑っている人が来ます。キリスト教を信じている人も疑っている人もいます。ドラマに出た場所を見たくて来たい人もいます。学校のレポートの課題で来た人もいます。その気持ちはまるで愛餐会の料理のように色とりどりです。でも教会とはそのようにいろいろな人を迎え入れる場所なのです。教会は愛餐会のテーブルに様々な料理が並ぶように、様々な人を迎え入れてゆく場所なのです。
教会は、着飾ったり、背伸びしたりする場所ではなく、素直な自分でいられる場所であって欲しいと思っています。この人たちの前だったら正直でいいかなと思える教会になりたいのです。ここだったら自分の傷を見せても笑われないと思われる場所でありたいです。ここなら自分と向き合えると思える、教会はそういう場所でありたいです。このあとの楽しい食事の前に聖書の話をします。聖書から愛を聞きます。今日は聖書からお互いを受け入れ合うことを考えたいと思います。聖書を読みましょう。
マタイによる福音書1章18~25節までをお読みいただきました。ヨセフという人に注目をします。ヨセフには結婚の約束した相手マリアがいました。しかしヨセフは婚約者マリアが自分以外の人のこどもを妊娠したと聞きました。ヨセフは当然、縁を切ろうと思いました。婚約を破棄しようと思ったのです。しかし天使が現れて「その妊娠は聖霊によるものだ」ということを聞きます。それは不思議な出来事でした。そして天使はこういったのです「恐れず、妻マリアを迎え入れなさい」。なんということでしょうか。それを受け入れ、迎え入れることとはどんな困難なことでしょうか。
ヨセフは正しい人だったとあります。ヨセフは正しい人だからこれを迎え入れることができたのです。正しい人とはどんな人のことでしょうか。聖書の正しさとは「正義」や「義」とも表現されます。聖書の正義とは何でしょうか。我々の思う正義ならすぐにイメージできるでしょう。それは正義の味方というイメージです。正義の味方は悪い事をした人に、罰を与え、やっつけます。悪者にぎゃふんと言わせてやるが正義です。悪への鉄槌が正義です。私たちの正義、この正しさによれば、マリアは罰、制裁を受けるべき存在でしょう。当時、不貞の罪は死罪の可能性もありました。私たち人間の正しさによれば、マリアが罰を受けるはずだったのです。
しかしヨセフはそうしませんでした。ヨセフは正しい人、正義の人でした。実は聖書の「正義」「正しい」には、私たちのイメージする罰を与えるという意味はありません。聖書の「正義」「正しい」という言葉は公平とも似ている言葉です。貧しくされている人や、立場が弱い人が守られるという意味です。貧しくされている人や、立場が弱い人が守られることが正義、正しいことなのです。
ヨセフがどうして、このことを受け入れようと思ったのか、それはもしかするとヨセフは第一にお腹のこどもを守るということを考えたのかもしれません。いろいろな事情があったでしょう。しかしお腹のこどもには何の責任もないことです。ヨセフはきっとお腹のこどもを第一に考え、守ろうとしました。ヨセフは大人の都合で殺されてしまう小さな命を守ろうとしたのです。ヨセフがまず守ろうとしたのは、お腹の子どもの命です。それが神様の目に正しいことだったのです。ヨセフはこのような意味で正しい人でした。神様の正義に目を向け行動をしました。ヨセフは正しく、正義の人だったからこそ、立場の弱い、こども命に目を向けました。
天使の告知も信じたでしょうか。ヨセフはマリアのことも信じ、守ろうとしました。それが正しいことだと思ったのです。こどもの命とマリアを守ることが正義だとおもったのです。「恐れず、迎え入れなさい」という恐ろしい言葉を受けて、それを決心しました。その決心が愛を教えるイエス様を育んだのです。それによってイエスは生まれることができました。ヨセフが受け入れがたい事実を受け入れる、迎え入れる決断によって、救い主は生まれたのです。ヨセフのように立場の弱い人を守ろうとすること、そのひとを受け止め、迎え入れてゆくこと、それが神様にとっての正義でした。そしてその正義によって、イエス・キリストは地上に生まれたのです。
ヨセフがこのようにこどもとマリアを受け入れ、迎え入れた様子を見て、果たして私はそのように、他者を迎え入れる存在になっているだろうかと思いました。私は他者に、人間の正義を振りかざして、拒絶していないか、無関心になっていないかと思わされます。自分の正義ばかりを振りかざし、彼のようには他者を受け入れられない自分を見つけます。
私たちのこの教会はどうでしょうか?様々な気持ちや状況に置かれた人がこの教会に集います。それを迎え入れることが出来ているでしょうか。私たちの教会もヨセフの様に、様々な事情をもった人を迎え入れることができる教会になりたいと感じます。教会は信じている人だけのものではありません。教会は地域の食堂だけでもありません。教会はさまざまなメニューがテーブルの上に並ぶ愛餐会のように、様々な人が同時に集まります。みんな違うから良いのです。
そしてそれは品評会ではありません。互いを受け入れ、迎え入れ、ほめ合う食事会です。そのような教会になりたいと思います。さまざまな人々が集まれば、いろいろな衝突が起きますが、私たちはその出会いを恐れずに、お互いを迎え入れあいたいのです。たくさんの人がいて、出会いがあれば苦手があるかもしれませんが、それでも互いを迎え入れ、互いを受け入れ、互いを大切にしあう仲間となりたいと思っています。
きっと天使は教会にもこういうでしょう「恐れず、迎え入れなさい」。この声を聞き、私たちの教会はお互いを迎え入れあってゆきましょう。もちろん私たち一人一人の生活の場所でもそうです。様々な価値観があります。それを受け入れ合ってゆきましょう。世の中の正義に振り回されず、聖書の正義・他者を守るという正義に生きてゆきましょう。
この個所から神様と私たちの人生の関係も考えます。私たちの人生には驚くことや苦労が起きるものです。でも神様は私たちにそれを迎え入れるように言っています。私たちにそれから逃げ出さずに向き合う様に言っているのです。そして私たちが異なる他者を恐れずに受け止める事、迎え入れる事も勧めています。神様の正義、小さい命を守ることを神様は私たちに期待しているのです。
そして何よりまず神様が先に私たちのことをも受け入れ、迎え入れ、愛してくれているのでしょう。神様は私たちが誰か、何かを迎え入れるよりも何倍も温かく、私たちを受け入れて下さっているのでしょう。神様は私たちをそのように愛してくださっているのです。神様とはそのような方です。私たちはこの神様を信じ、愛し合い、迎え入れあいましょう。お祈りいたします。
「恐れず、迎え入れなさい」マタイ1章18~25節
主の天使が夢に現れて言った。「ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい」。
マタイによる福音書1章20節
この後の持ち寄りの食事会、愛餐会(あいさんかい)を楽しみにしています。愛し合うということは、この食事のようなことです。誰かを思って準備すること、ひとりひとりの違いが大事であること、分かち合うこと、お互いのことをお腹の中に迎え入れ、受け入れ、ほめ合うということ、それが愛なのです。愛餐会は料理を通じてお互いを迎え入れる象徴です。それは教会の本質です。
私たちの教会は今年、様々な人を迎え入れました。いろいろな人が、いろいろな気持ちを持ち寄って集まるのが教会です。教会は愛餐会のテーブルに様々な料理が並ぶように、様々な人を迎え入れてゆく場所です。教会は、着飾ったり、背伸びしたりする場所ではなく、素直な自分でいられる場所であって欲しいと思っています。
楽しい食事の前に聖書から愛を聞きます。今日は聖書からお互いを受け入れ合うことを考えましょう。
ヨセフは婚約者マリアが自分以外の人のこどもを妊娠したと聞き、縁を切ろうと思いました。しかし天使が現れて、こう言ったのです「恐れず、妻マリアを迎え入れなさい」。ヨセフは正しい人・正義の人だからこれを受け入れました。正しいとは何でしょうか?我々の思う正義は悪い事をした人に罰を与える、悪への鉄槌が正義です。しかし聖書の「正義」「正しい」には、私たちのイメージする罰を与えるという意味ではなく、貧しくされている人や、立場が弱い人が守られるという意味です。。
もしかするとヨセフは第一にお腹のこどもを守るということを考えたのかもしれません。それが神様の目に正しいことだったのです。ヨセフは正しく、正義の人だったからこそ、立場の弱い、こども命に目を向けました。そしてヨセフはマリアのことも信じ、守ろうとしました。それが正しいことだと思ったのです。
ヨセフがこのようにこどもとマリアを受け入れ、迎え入れた様子を見て、果たして私はそのように、他者を迎え入れる存在になっているだろうかと思いました。自分の正義ばかりを振りかざし、彼のようには他者を受け入れられない自分を見つけます。私たちのこの教会はどうでしょうか?私たちの教会もヨセフの様に、様々な気持ちをもった人を迎え入れることができる教会になりたいと感じます。さまざまな人々が集まれば、いろいろな衝突が起きますが、私たちはその出会いを恐れずに、お互いを迎え入れあいたいのです。きっと聖霊は教会にもこういうでしょう「恐れず、迎え入れなさい」。この声を聞き、私たちの教会はお互いを迎え入れあってゆきましょう。
私たちの人生には驚くことや苦労が起きるものです。でも神様は私たちにそれを迎え入れるように、向き合う様に言っているのです。そして何よりまず神様が先に私たちのことをも受け入れ、迎え入れ、愛してくれているのでしょう。私たちはこの神様を信じ、愛し合い、迎え入れあいましょう。お祈りいたします。
【全文】「背中で語る福音」マタイ11章2~19節
イエスはお答えになった。「行って、見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。
マタイによる福音書11章4節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝に集められたこと、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会、こどもと一緒に礼拝する教会です。今日もこどもたちと共に礼拝をしましょう。もうすぐクリスマスです。クリスマスは、キリスト教や教会が最も注目を集める季節です。クリスマスという機会を通じてたくさんの人にキリスト教・クリスチャンに触れ、神様のことを知って欲しいと思っています。
先日ある方と「多くの人の持っているクリスチャンのイメージ」という話をしました。日本にクリスチャンは1%未満と言われますから、多くの人にとってクリスチャンと出会う機会は少ないものです。クリスチャンへのイメージもテレビで見るものに影響されるのでしょう。マザーテレサ、清廉、熱心、人格者というイメージがあるかもしれません。といったイメージがあるでしょうか。クリスチャンに対してそのようなイメージと期待を頂けることは嬉しい事ですが、同時にそのようなイメージにそぐわない自分に葛藤をします。深い話ができる時間と関係があればこの葛藤を説明できるでしょう。「隣人愛を大切にしたいと思っているのだけれど、本当はあなたと同じ迷いの多い、罪深い人間だ」と伝えることができます。でもそのような関係になるまでには長い時間がかかります。
キリスト教のことはインターネットで検索してもわかりづらいものです。キリスト教を知るには日常生活の中でクリスチャンと出会うことがもっとも重要です。日常でクリスチャンと出会えば、本当のクリスチャンのことが分かるでしょう。自分と変わらない生活をし、変わらないことで悩み、変わらないことで失敗をしていることが分かるはずです。そしてちょっと違う部分にも気づくでしょうか。私たちは、愛し合おうとする姿勢において、少しだけ異なります。他者を愛そうという姿を見て、これがクリスチャンなのかと思ってもらえるでしょうか?
キリスト教やクリスマス、クリスチャンのことを知らない人にとって、本物のクリスチャンである皆さんとの出会いはとても貴重な体験です。隠れて生きるのではなく、私たちはイメージを演じるのではなく、その方たちに、私たちがほとんど変わらない、でも少しだけ違うということを知って欲しいです。
私たちは他の人と少しだけだけど、大きく違うことがあります。それは愛し合おうとするということです。お互いを大切にしあおうとするということです。その違いを言葉で説明することは難しく、多くの時間がかかるでしょう。私たちはまず自分の背中で、自分の日頃の行動を通じて、愛し合うことを伝えてゆく必要があります。私たちが他者を愛するという姿勢が、私たちの背中から伝わり、キリスト教が、福音が伝わっていったら嬉しいと思っています。クリスマスの機会、特にクリスチャンに注目が集まっています。私たちは今週も、愛し合う姿を証しする、そのような1週間を過ごしましょう。今日はイエス様に従った人々から、どのように人々に福音が広がってゆくのかを見てゆきます。そして私たちはどのように生きてゆくべきなのかを考えたいと思います。聖書を読みましょう。
マタイによる福音書11章2~19節までをお読みいただきました。イエス様と同じ時代、バプテスマのヨハネという人がいました。バプテスマのヨハネは逮捕され監獄に入れられていました。そして彼は信仰において確かめたいことがありました。それは「イエスは救い主なのかどうか」ということです。それを聞くためにイエス様に直接、弟子を派遣しました。
イエス様の周りには様々な人がいたと記録されています。聖書の文字通りに、病気が治った人がいるのかどうかはわかりません。本当に病気が治ったかどうかわわかりません。でも確かなのは、イエス様がそのような傷つき、痛み、悩みを持つ人と一緒にいたということです。イエス様に従った人々とは、宗教的な勉強をたくさんして、信仰熱心で、人格者たちばかりだったわけではありませんでした。イエス様に従った人々は、傷つき、弱さを抱えた人々でした。イエス様はその人々と共に過ごすことで、励ましと希望を与えていたのです。
そこにヨハネの弟子たちが来て聞きます。「来るべき方は、あなたですか?」弟子たちイエス様が人々が待ち望んだ救い主、キリスト、すべての人を救う神であるかを確認しようとしたのです。それに対してイエス様はこう返事をしています「見聞きしていることを伝えなさい」。この回答はおもしろい回答です。〇か×かはっきりさせず、見たままが答えだと回答しました。投げやりな回答にも見えますが、そうではありません。自分が救い主であるかどうか、口では何とでも言えるものだったからです。実際にイエス様の時代には、私はキリストだと自称する人がたくさんいました。イエス様は言葉であれこれ説明をしようとしませんでした。「あなたの見たままが答えですよ」と言ったのです。それは自分でその人と出会って確かめるようにという意味です。直接答えるのではなく、イエス様と出会った人を見て、判断するようにと言ったのです。
果たしてイエス様は弟子たちの何を見せようとしたのでしょうか。そしてヨハネの弟子たちは何を見て帰ったのでしょうか?病気が治ったこと、耳の聞こえない人が聞こえるようになったことでしょうか。イエス様はそのような奇跡を見て信じなさいと言ったのでしょうか?私はそうではないと思います。きっとイエス様は癒された人々のその後の姿、生き方、背中を見るようにと言ったのだと思います。イエス様のそばにいた人々は病気や障がい、経済力によって社会から追いやられ、見放され、イエス様のもとに来た人でした。その人々はイエス様に愛され、受け入れられてゆきました。やがて癒された人々は今度はイエス様の様に他者を愛し、受け入れ合おうとしたはずです。イエス様の群れは仲間を愛し合う共同体となってゆきました。イエス様はヨハネの弟子たちに、それを「見よ」言ったのではないでしょうか。神様に愛された人が、今度はお互いを愛し合う姿を見よと言ったのではないでしょうか。そこにはお互いの病をいたわり合い、分かち合い、助け合う姿がありました。イエス様はヨハネの弟子たちに対して、自分が救い主かどうかは、このように人々が互いに愛し合っている様子を見ればわかると言ったのです。これは面白い答えです。人々が愛し合っている姿を見れば、私が神の子・キリストであることがわかるという答えです。
今の私たちに重ねたらどうなるでしょうか?私たちは神様に癒され、支えらえる者として、この人々と同じ様にイエス様のそばに生きています。そしてイエス様のもとに誰かが来て、あなたは本物かと問うとします。そうするとイエス様はまた言うでしょう。「この人たちを見ればわかる」。神が本物であるかは、クリスチャンを見ればわかるということです。教会を見ればわかるということ、私たちを見ればわかるということです。私たちと出会えばわかるということです。私たちはそのような立派な信仰者ではないかもしれませんが、でもイエス様は私たちと出会えばきっと神のことがわかると言っているのです。キリストが本物かは、出会った人の生き様で示されます。私たちはキリストに変えられた者、キリストに従う者です。その私たちは神様から、人々と出会う者とされています。私たちはイエス様に癒され、励まされて終わりではないのです。イエス・キリストの証人として、人々と出会う役割が与えられています。人々と出会い、愛し合う姿を見せる、共に生きる姿を見せる、それがイエス様を本物だと証しすることになるのです。行動で示し、背中で語る、それが福音を伝える方法です。
私にはそんなことできないと思うでしょう。もちろんそれは、身の丈にあった範囲で良いはずです。私たちは相手のイメージを演じる必要はありません。多くの人と同じ悩みを背負って生きています。その中で自分がイエス様に出会ってどう生きているのか、どのように他者を愛し生きているのか、その実践が福音を伝えてゆくこと、そのものなのです。
17節からは「笛を吹いたのに踊ってくれない」「葬式なのに悲しんでくれない」とあります。おそらくこれは、自分のイメージに合った行動をして欲しいというたとえです。自分が楽しい曲を吹いたら踊って欲しい、葬式の歌を歌ったら、悲しんで欲しいという期待です。人々は相手に対してそのように勝手に様々な期待、イメージを持っています。キリストに対してもそうでした。きっとお酒は飲まないだろう、ご飯はたくさん食べないだろう。徴税人や罪人とは関係しないだろう。そのような期待とイメージがありました。でもイエス様はそのイメージに応えたのではなく、打ち破っていきました。人々の勝手なイメージに囚われず、愛を実践したのです。期待に応えるのが私たちの役割ではありません。私たちの役割は私が神に愛され、大切にされているように、他者を愛し大切にする、その姿を背中で見せてゆくことです。それによってキリストが本物であると伝えられるのです。
私たちはどう生きるかを考えます。私たちは神様を信じない人と同じ様に苦しみを生きています。でも私たちは、互いを愛し合うこと、大切にしあうことにおいて他の人と少しだけ違う生き方をします。神様はそのように私たちが葛藤する姿、愛し合う姿を通じて、福音を広げるお方です。そして私たちは出会いの中に生かされています。信仰を飾らない生き方が、信仰者として愛し合うあなたの姿が、イエス様を本当の神だと証しするのです。
クリスマスは多くの人がキリスト教への関心、クリスチャンへの関心を向ける時期です。私たちはただ愛し合うという姿によって、キリストが救い主であることをそれぞれの場所で証ししてゆきましょう。お祈りします。
「背中で語る福音」マタイ11章2~19節
イエスはお答えになった。「行って、見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。
マタイによる福音書11章4節
クリスマスは、キリスト教や教会が最も注目を集める季節です。キリスト教のことはネットで検索してもわかりません。キリスト教を知るには日常生活の中でクリスチャンと出会うことがもっとも重要です。キリスト教のことを知らない人にとって、本物のクリスチャンである皆さんとの出会いはとても貴重な体験です。
私たちは他の人と少しだけ、大きく違うことがあります。それは愛し合おうとするということです。私たちが他者を愛するという姿勢が、私たちの背中から伝わり、キリスト教が、福音が伝わっていったら嬉しいと思っています。今日はイエス様に従った人々から、どのように人々に福音が広がってゆくのかを見てゆきます。
イエス様に従った人々は、傷つき、弱さを抱えた人々でした。イエス様はその人々と共に過ごすことで、励ましと希望を与えていました。そこにヨハネの弟子たちが来て「来るべき方は、あなたですか?」と聞きました。それに対してイエス様は「見聞きしていることを伝えなさい」と返事をしました。イエス様は言葉であれこれ説明をしようとしませんでした。「あなたの見たままが答えですよ」と言ったのです。それは自分でその人と出会って確かめるようにという意味です。
果たしてイエス様は弟子たちの何を見せようとしたのでしょうか。きっとイエス様は癒された人々のその後の姿、生き方、背中を見るようにと言ったのだと思います。人々はイエス様に愛され、受け入れられてゆきました。やがて癒された人々は今度はイエス様の様に他者を愛し、受け入れ合おうとしたはずです。イエス様の群れは仲間を愛し合う共同体となってゆきました。イエス様はヨハネの弟子たちに、それを「見よ」言ったのではないでしょうか。イエス様はヨハネの弟子たちに対して、自分が救い主かどうかは、このように人々が互いに愛し合っている様子を見ればわかると言ったのです。これは面白い答えです。
今の私たちに重ねたらどうなるでしょうか?イエス様はキリストが本物かは、出会ったクリスチャンの生き様で示されると言うでしょう。私たちはイエス様に癒され、励まされて終わりではないのです。人々と出会い、愛し合う姿を見せる、それがイエス様を本物だと証しすることになるのです。行動で示し、背中で語る、それが福音を伝えることになるのです。
私たちはどう生きるかを考えます。私たちは神様を信じない人と同じ様に苦しみを生きています。でも私たちは、互いを愛し合うこと、大切にしあうことにおいて他の人と少しだけ違う生き方をします。神様はそのように私たちが葛藤する姿、愛し合う姿を通じて、福音を広げるお方です。
クリスマスは多くの人がキリスト教への関心、クリスチャンへの関心を向ける時期です。私たちはただ愛し合うという姿によって、キリストが救い主であることをそれぞれの場所で証ししてゆきましょう。お祈りします。
【全文】「近すぎるくらい近い神」マタイ13章53~58節
みなさん、おはようございます。今日も共に礼拝できること主に感謝します。2本目のろうそくに明かりをともし、クリスマスまでの日付を数えています。私たちはこどもの声がする礼拝を続けています。今日もこどもたちの声を聞きながら、一緒に礼拝をしましょう。
もうすぐ平塚に引っ越してきて7年になります。私は一か所に長く住んだ経験があまりありません。人生で10回以上の引っ越しを経験しました。これまで深い近所付き合いというものにあまり経験がありませんでしたが、平塚では近所の方との交流を楽しんでいます。平塚市の人口は約20万人で、ここ豊原町の人口は約1000人ほどだそうです。7年ですが、住んでいるといろいろな人に関わる機会があります。今年は町内会の組長が回ってきました。なんとなく地域の人の顔がわかるようになってきました。
小さな町内会です。いろいろな人間関係や問題がありながらも、うまくやっているようです。豊原町はまだ地域の触れ合いが残る良い町だと思っています。このくらいの人数がなんとなく顔が分かってちょうどよいものです。小さい頃から平塚・豊原町で育った人々は、あそこの家はこうだとか、どこそこの人はこうだと、驚くほど地域の人ことをよく知っています。それは長年の交流が積み重ねなのでしょう。この町が人と人との距離感がとても近く、温かい場所であることを実感します。
やはりなんでも聖書の時代と重ね合わせてしまいます。当時のパレスチナの人口は50万~100万人くらいのだったのではと言われます。ガリラヤにも数万人規模の人口の都市がいくつか存在したようです。考古学的な発掘によればガリラヤのカファルナウムは人口1500~2000人、ナザレは500人以下の村だったと推測されています。ナザレは町内会ほどの小さな村だったのです。多くの村では中央に広場があり、その周辺を家が取り巻くかたちで集落を形成しました。広場は公共の空間で村人たちの話し合いやお祭の場所になりました。家は集合住宅で、数家族が住む長屋のような家が多くあったそうです。中庭もあり、そこは家族や隣人との交流場所で、共用のかまどや水槽などが置かれていました。当時の人々の暮らしを思い浮かべて、想像をします。
イエス様はこのナザレでどのように暮らし、育ったのでしょうか。ナザレの人々にとってイエス様はごく普通の人だったようです。55節には「この人は大工の息子ではないか」とあります。ナザレの人は聖書で伝えられている神秘的なクリスマス物語について、何も知らないようです。イエス様は普通の男の子、小さい村の近所のこどものひとりだったのです。イエス様はナザレという500人以下の町で集合住宅に住む、長屋の子どもでした。今の私たちから見ると家族の様な交流のある共同生活の中に生きていたはずです。ナザレの人々は、自分たちの村、まるで小さな町内会のようなコミュニティから、世界を救う宗教指導者が生まれることを想像できなかったのでしょう。
ナザレのあるガリラヤ地方は、豊かな穀倉地帯でした。農村地域だったのです。聖書にはペテロの言葉が「ガリラヤなまりだ」と言われる場面があります。エルサレムなどの都会に住む人にとってガリラヤはそのような小さな田舎町、とるに足らない町でした。異邦人のガリラヤという言葉もあります。異邦人との交流が多かったガリラヤからは、良いものは出ないと言われていました。旧約聖書にはいろいろな町の名前が無数に登場しますが、ナザレという町の名前は一度も登場しません。そのような歴史に登場しない町、小さな町の、共同住宅に住む、普通の男の子が、ある日預言者として、様々なことを教えだしたのです。奇跡を起こし始めたのです。
ナザレの住民の反応は容易に想像できるでしょう。いつもイエス様が駆け回っていたナザレ村の広場に、大人になったイエス様の姿があります。それは昔から変わらない光景です。「あそこにいるのはマリアの子イエスだろ。知っているよ」。イエス様はそのような距離感で一緒に暮らした人々に現れました。だから57節にもあるように「人々はイエスにつまずいた」のです。受け入れられなかったのです。それはそうです。それは信じられないでしょう。なぜなら距離感が近すぎるからです。憧れの町エルサレムで生まれた救い主なら信じたかもしれません。しかし、まさか小さな自分の住んでいる、誰からも見向きをされない小さな村から、預言者・救い主が登場するとは信じることが出来ませんでした。しかももともとよく知っている、自分たちと一緒に過ごしていたこども・イエスが救い主だなんて、とても信じられなかったのです、人々は奇跡が起きようとも、教えが素晴らしかろうとも信じなかったのです。だってそれがイエスだったからです。彼らにとってイエス様は距離感が近すぎたのです。
ナザレでは特に強くこのような反応がありました。しかしこれはナザレだけでおきた反応ではありません。この反応は他の地域での先取りとして起きています。イエス様はどこに行っても、あのガリラヤから?あのナザレから?ナザレってどこ?と言われたはずです。何百年も待った人が、ガリラヤからナザレから生まれるはずはない、今この時、自分の目の前に居るわけがない。見た目とか意外と普通なのね。みなそう思ったでしょう。何百年も待った救い主が、自分の前に居る、それぞれの救い主イメージとはかけ離れていました。ただ普通の人間が目の前に、近くにいただけだったのです。その距離感は近すぎました。きっと私たちがそこにいてもそう思ったのでしょう。
もしかして私たちがそこに居たら「あなたが救い主のはずがない」と他の人々と共に怒ったかもしれません。そんなうそつきは十字架に掛けろと一緒に叫んだかもしれません。イエス様の十字架には侮辱する看板が立てられたと言われています。それは「ナザレのイエス、ユダヤ人の王」という看板でした。その看板はナザレからユダヤ人の王が出るはずがないという侮辱だったのです。しかし、多くの人が復活の後、イエス・キリストは救い主であったということを認めるようになりました。
さらに復活のその後まで見通すと、イエス様は復活の後、ガリラヤに行くと言います。やはりまたガリラヤなのです。それは、神様が私たちの日常の中、見過ごされがちな場所にこそ現れるというメッセージの表れではないでしょうか。人々が魅力を感じる中央ではなく、人々が見過ごしている場所、ガリラヤでまた会おうと言います。イエス様は再びガリラヤを選んだのです。
この物語は、私たちにとって神様とはどのような方なのかを示唆しています。それはつまり、神様とは私たちにとって近すぎるくらい、近いお方であるということです。今ではない、ここではない、この人ではない、そう思う場所に、神様は現れるのです。それが神様の在り方なのです。クリスマス物語で私たちは知っています。神様と等しいお方、イエス・キリストは人知れずに馬小屋で生まれ、他の人と同じ様にナザレで育ち、地域の中で育ったのです。そしてその後、待ち望んだ救い主とは、そのように私たちに近いあり方ではないと十字架に掛けられたのです。しかしそれが本当の神様の在り方でした。ガリラヤの人はあまりにも近すぎる神、自分のイメージと違う神に人々は困惑しました。それが2000年前に起きたことでした。
この物語を私たちの物語として聞きましょう。神様とは私たちの近くにいる存在です。それは近すぎるほどに近くにいる存在なのです。まだ私には神様なんて来ない、こんな私に神様なんて来ない、そう思っている方は注意が必要です。そう思う人の心に神様はもうすでに近すぎるほどに来ているのです。今ではない、まだ私には神が来ていないと思う方も、注意が必要です。もうそこにすでに神様は近すぎるほどに来ています。イエス・キリストを、これは私の思う神の姿ではないと思う方にも注意が必要です。神様はそのようにして十字架に掛かったお方なのです。十字架の姿であなたの近くにすでにおられます。
神様はこのように私たちのイメージを超える場所と、時間に現れるお方です。そしてそれは輝かしい姿ではないのでしょう。その距離感も私たちの心に近すぎるくらい近くにすでにいるのです。ここではない、今ではない、私ではないと思う場所にこそ、神様は現れるのです。
私たちはアドベントの2週目を迎えています。神の一人子イエスは、この地上の貧しいガリラヤのナザレで生まれ、育ちました。ごく普通のこどもとして育ちました。神の子であるにも関わらず、そのようなあり方選びました。それは神様は私たちのすぐそばに、近くにおられるという象徴となっています。イエス様は私の心に近すぎるくらい、近くにいるのです。私たちの神様はそのようにして、私たちと共にいて下さり、私たちを導いてくれるのです。
クリスマスをそのことを感じながら迎えてゆきましょう。私たちのすぐ近くに神様がいます。私たちのすぐ近くに神様の愛があります。それを私たちの普段の生活の中で感じ取ることができるでしょうか。私たちの生活の中で神様が近くにおられることを探してゆきましょう。私たちは見過ごされがちな場所に、隅に追いやられた場所に、寂しいと思う場所にきっと神様がいる、その存在を見つけることができるはずです。アドベントが近づいてきています。神様の愛は、私たちに近づいてきています。神様はいつも近すぎるくらい、私たちの近くに居て下さるお方です、そのことを忘れずにアドベントを過ごしましょう。お祈りをいたします。
「近すぎるくらい近い神」マタイ13章53~58節
この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。
マタイによる福音書13章55節
今日も共に礼拝できること主に感謝します。クリスマスまでの日付を数えています。ここ平塚市豊原町の人口は約1000人ほどだそうです。豊原町内会は小さな町内会ですが、まだ地域の触れ合いが残る良い町です。このくらいの人数がなんとなく顔が分かってちょうどよいものです。小さい頃から平塚・豊原町で育った人々は、驚くほど地域の人ことをよく知っています。それは長年の交流が積み重ねなのでしょう。この町は人と人との距離感がとても近く、温かい場所です。
なんでも聖書の時代と重ね合わせてしまいます。考古学的な発掘によればナザレは500人以下の村だったと推測されています。ナザレは町内会ほどの小さな村だったのです。村の家は集合住宅で、数家族が住む長屋が多くあったそうです。イエス様はこのナザレで育ちました。ナザレの人は神秘的なクリスマス物語について、何も知らないようです。イエス様は普通の男の子、小さい村の近所のこどものひとりだったのです。長屋の子どもでした。
ナザレの人々は、自分たちの村、まるで小さな町内会のようなコミュニティから、世界を救う宗教指導者が生まれることを想像できなかったのでしょう。ナザレの住民の反応は容易に想像できます。イエス様が駆け回っていたナザレ村の広場に、大人になったイエス様の姿があります。イエス様はそのような距離感で一緒に暮らした人々に現れました。だから57節にもあるように「人々はイエスにつまずいた」のです。受け入れられなかったのです。なぜなら距離感が近すぎるからです。
これはナザレだけでおきた反応ではありません。この反応は他の地域での先取りとして起きています。もしかして私たちがそこに居たら「あなたが救い主のはずがない」と他の人々と共に怒ったかもしれません。そんなうそつきは十字架に掛けろと一緒に叫んだかもしれません。さらに復活のその後まで見通すと、イエス様は復活の後、ガリラヤに行くと言います。やはりまたガリラヤなのです。
この物語は、私たちにとって神様とはどのような方なのかを示唆しています。それはつまり、神様とは私たちにとって近すぎるくらい、近いお方であるということです。まだ私には神様なんて来ない、こんな私に神様なんて来ない、そう思っている方は注意が必要です。そう思う人の心に神様はもうすでに近すぎるほどに来ているのです。神様は私たちのイメージを超える場所と、時間に現れるお方です。
その距離感も私たちの心に近すぎるくらい近くにすでにいるのです。ここではない、今ではない、私ではないと思う場所にこそ、神様は現れるのです。
クリスマスをそのことを感じながら迎えてゆきましょう。私たちのすぐ近くに神様がいます。それを私たちの普段の生活の中で感じ取ることができるでしょうか。私たちが見過ごしてしまいそうな場所に神様がいいます。私たちはきっとその存在を見つけることができるはずです。お祈りをいたします。
【全文】「無期限の希望」マタイ24章36~44節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、神様に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの命の声を聞きながら、命を感じながら礼拝をしてゆきましょう。今日から12月です。1年はとても早いものだと感じます。みなさんの1年はどんな1年だったでしょうか?私は忙しい1年で、あっという間でした。こひつじ食堂やこひつじカフェ、テレビの撮影、神学校の講師など、忙しい1年でした。毎日「いついつまでに」というように何かの日付に追われたり、誰かに「何日までになるべく早く」と急ぐようにせかしたりした1年でした。きっとみなさんも、それぞれに、何かに追われながら過ごした1年だったのではないでしょうか?
教会には今年、こどもの誕生の知らせもありました。もちろんこどもの誕生については絶対にせかしてはいけません。こどもの誕生について、その日付は人間の手で決めることができません。そのプロセスには神様の計画が含まれており、私たちにはその奇跡を静かに、そして祈って、待つという役割が与えられています。こどもたちの成長についても同じことが言えるでしょう。私たち人間がこどもの成長のスピードを決めることはできません。私たちは誕生や成長に日付を決めたり、せかしたりしてはいけないのです。こどもの成鳥には待つこと、祈ることが大事です。私たちはすぐに日付を決めたくなるものですが、大きな希望こそ、それがいつなのかわからないものなのです。そしてこどもたちをよく見ると、すでに様々な成長をしています。いつかいつかと思ううちに、すでにこどもが成長しているということも多いものです。
あと3週間後の12月25日にはクリスマスがやって来ます。残された時間は全員同じです。私たちはそれを遅く感じたり、早く感じたりします。誰も時期を早めることはできませんが、それは必ずやってきます。私たちのクリスマスには、日付がついています。それはあと何日すればという楽しみでもあります。でも違う希望もあります。それは日付の無い希望です。本当の希望とは日付がないものなのかもしれません。私たちは病気が治る日や、困難が終わる日、人の生まれる日を具体的に知ることはできません。
でもその中で私たちは前に進む希望を見出してゆきます。いつだかわからないけど、必ず起こるという約束のある希望が私たちを前に進ませてゆくのです。そしてその希望にはきっともうすでに始まっている部分があるのではないでしょうか。今日は日付の無い希望について、そしてすでに始まっている希望について考えたいと思います。
今日はマタイによる福音書24章36~44節までをお読みいただきました。聖書の時代の人々も忙しく、あっという間の1年を過ごしていたでしょう。今日の個所からは当時の人々の忙しい生活が透けて見えてきます。38節以降、人々は食事の準備をしたり、結婚式をしたり、災害がおきたり、畑仕事をしたり、忙しく生活をしていました。彼らには何百年も待っていることがありました。それは救い主の誕生です。自分たちの魂を支える存在、自分たちの生活を支える存在である救い主が登場するのを、ずっと待っていたのです。彼らもクリスマスを待ち望んでいたのです。
同じクリスマスを待つということでも、私たちの時代の待ち方とは大きな違いがありました。それは、いつ来るかわからなかったという違いです。私たちはクリスマスが毎年来る、12月25日という日付を知っています。しかし当時の人にはそれがわからなかったのです。それは43節、まるで泥棒のように、あるいは突然帰って来る主人のように、いつ起こるのかわからないものだったのです。その出来事はいつ来るのか、誰も知らない、思いがけない時に起るものだったのです。36節「その日、その時を誰も知らなかった」とあるとおりです。
いつ来るかわからないものを待つというのは、どれだけたいくつで、どれだけ長く感じたでしょうか。いつかいつかと先延ばしされ、約束が忘れられていると感じたかもしれません。さらに現代の私たちは、予定や締切に追われる日々が当たり前です。だからこそいつ起こるかわからないことに対して、希望を見出すのが難しいはずです。日付の無い約束は、口先だけの約束に感じるかもしれません。苦しい時、せめてそれがいつ終わるのか、その日付さえ分かれば、先が見えさえすれば、それまで我慢することができるものです。日付こそ希望のように思います。でも一番初めてのクリスマスはそうではありませんでした。人々はいつ起こるかわからないことを、希望にしていました。本当に起こるかわからない事を希望にしていたのです。慌ただしい生活の中で、人々はそれを信じていました。そしてそれは何百年も続く、息の長い希望となりました。救い主の誕生をずっと待ち続けることが、彼らの信仰だったのです。
私はこのことから、息の長い希望を持つことの大切さを思います。予定外の出来事、日付の予想できないことが私たちに期待や感動を与えるときがあります。それは日付の無い希望、期限の無い希望です。私たちは何月何日という日付はないけれども、でも確実に訪れる希望を信じます。その希望は日付がないからこそ、長く続くのです。それは日付が分からなくても必ずやって来る希望です。やがて必ず来ると約束されている希望を信じる、それが信仰なのです。その信仰は私たちに息の長い希望を与えます。
信仰によって、息の長い希望を持った人は日々の歩みの根底に希望を持つ者となります。いいことが起きた日はいい日、悪いことが起きた日は悪い日ではないのです。息の長い希望を持つとき、毎日が一日一日が神様の希望に近づいてゆく、感謝の一日になるのです。私たちはこの先に神様が私たちに約束している希望があることを信じ、待ちましょう。イエス様はいつ来るかわからないその希望を待つようにと私たちに伝えています。それはこどもの出産と成長のように、日付を決めることができない、息の長い希望です。
イエス様はこの話を弟子たちに向けて話しています。そして弟子たちもまた救い主を待っていました。しかし彼らの目の前には、すでに救い主イエス・キリストが立っていました。ずっと待ち続けていた人はすでに目の前にいたのです。いつか必ず来ると何百年も待っていた希望は、実はすでに自分たちの目の前にあったのです。実はその希望はもう始まっていたのです。待ち望んだ希望は彼らの目の前ですでに始まっていたのです。
私たちはこのような希望のあり方も心にとめておきましょう。すでに私たちには神様の希望が実現し始めているのです。それはまだ完成はしていません。でも私たちの希望はすでに私たちの目の前に、私たちの心にすでに来ているのです。もう実現しかかっているのです。その兆し、そのカケラ、小さな希望は私たちの日々の中にも見いだせるのでしょう。
このように私たちには様々な希望があります。まず私たちは希望と聞いて、はっきりと日付がいついつと決まった希望を想像するでしょう。しかし希望はそれだけではありません。神様が準備している希望には日付がありません。私たちはずっと先にある希望を待ちましょう。はるか先にある約束を忘れずに、目を覚ましていましょう。いつ来るのかわかりません。でもいつの日か、私たちの心に、あの人の心に、この場所に、神様が来られ、イエス様が来られ、すべてを完全なものとする日が必ず来るのです。そしてすでにそれは、私たちの目の前に来ているのです。すでにその希望は私たちに起こり始めているのです。そのことを信じて歩みましょう。
もうひとつ、待つということについても考えます。イエス様は今日とは別の場面でも「目を覚ましていない」と言いました。それは十字架に掛かる前のゲッセマネにおいてです。イエス様が別の場所で祈っている間、弟子たちに「目を覚ましているように」と言いました。今日と同じように「目を覚ましているように」と教えたのです。しかし弟子たちは眠ってしまいました。再び来られたイエス様はもう一度弟子たち言いました「目を覚まして“祈っていなさい”」。今度は具体的に「祈っていなさい」と付け加えたのです。今日の個所も同じ意味を持っているでしょう。イエス様の教える「待つ」とはただ単に待つ、じっとしている、寝て待つということではないのでしょう。「目を覚ましていなさい」とは祈って待ちなさいという意味です。イエス様は希望を寝て待て、座って待てと言っているのではありません。イエス様はその希望を祈って待ちなさいと教えられているのです。祈って神様の時が、神様の業が起こるのを待ちなさいと言っているのです。私たちは祈って、希望がくることを待ちたいのです。そのようにして目を覚ましていたいのです。
私たちはこの後、主の晩餐という儀式を持ちます。この儀式はパンとブドウジュースを飲んで、イエス様が私たちに来るという約束を思い出すために、すでに来ているということを知るために行われます。その約束を忘れないために行われます。そしてその後、マラナ・タという讃美歌を歌います。このマラナ・タとは、「主が来ますように」という意味です。この賛美歌は希望が来ますようにという歌です。希望がやがて来ること、希望がすでに来ていることを覚えてこのパンを食べましょう。私たちは祈って、この希望のパンをいただきましょう。そして新しい希望の約束を信じ続けてゆきましょう。お祈りします。
「無期限の希望」マタイ24章36~44節
だから、あなたがたも用意していなさい。
人の子は思いがけない時に来るからである。マタイ24章36~44節
今年も毎日のように「いつまでに」という何かの日付に追われた一年でした。一方、こどもの誕生の日付は人間の手で決めることができません。私たちにはその奇跡を静かに、祈って待ちます。私たちのクリスマスには、日付がついています。でも違う希望もあります。それは日付の無い希望です。いつだかわからないけど、必ず起こるという約束のある希望が私たちを前に進ませてゆくのです。そしてその希望にはきっともうすでに始まっている部分があるのではないでしょうか。
当時のユダヤの人々は救い主の誕生を何百年も待っていました。同じクリスマスを待つということでも、日付を知っている私たちと違い、当時の人はまるで泥棒のように、あるいは突然帰って来る主人のように、いつ起こるのかわからないものだったのです。いつ来るかわからないものを待つというのは、どれだけたいくつで、どれだけ長く感じたでしょうか。日付の無い約束は、口先だけの約束に感じるかもしれません。苦しい時、せめてそれがいつ終わるのか、その日付さえ分かれば、先が見えさえすれば、それまで我慢することができるものです。日付こそ希望のように思います。それでも人々はいつ起こるかわからないことを、希望にしていました。
そしてそれは何百年も続く、息の長い希望となりました。救い主の誕生をずっと待ち続けることが、彼らの信仰だったのです。息の長い希望を持つことの大切さを思います。何月何日という日付はないけれども、でも確実に訪れる希望を信じます。息の長い希望を持った人は日々の歩みの根底に希望を持つ者となります。毎日が一日一日が神様の希望に近づいてゆく、感謝の一日になるのです。私たちはこの先に神様が私たちに約束している希望があることを信じ、待ちましょう。
弟子たちもまた救い主を待っていました。しかしずっと待ち続けていた人はすでに目の前にいたのです。いつか必ず来ると何百年も待っていた希望は、実はすでに自分たちの目の前にあったのです。私たちはこのような希望のあり方にも心にとめておきましょう。すでに私たちには神様の希望が実現し始めているのです。もう実現しかかっている小さな希望が私たちの日々の中にも見いだせるでしょう
この個所から待つということについても考えます。イエス様は希望を寝て待てと言っているのではありません。イエス様はその希望を祈って待ちなさいと教えられているのです。私たちは祈って、希望がくることを待ちたいのです。そのようにして目を覚ましていたいのです。
私たちはこの後、主の晩餐という儀式を持ちます。これはイエス様が私たちに来るという約束を思い出すために、すでに来ているということを知るために行われます。その約束を忘れないために行われます。希望がやがて来ること、希望がすでに来ていることを覚えてこのパンを食べましょう。そして新しい希望の約束を信じ続けてゆきましょう。お祈りします。
クリスマスのイベントへのご招待
クリスマスに向けて教会では様々なイベントを開催しています。どのイベントもどなたでも参加可能です。ぜひお集まりください!
12月14日(土)10時30分~12時 こどもクリスマス(讃美歌と工作)
12月17日(火)10時~17時 こひつじカフェ(だれでも来れるカフェ)
12月19日(木)10時30分~12時 こひつじひろばクリスマス(0~3歳向け)
12月20日(金)17時~19時 こひつじ食堂(こども&地域食堂)
12月22日(日)11時~14時 クリスマス礼拝&お楽しみ会(礼拝と食事会)
12月24日(火)19時30分~20時30分 キャンドル礼拝(ろうそくを持って礼拝)
12月27日(金)17時~19時 こひつじ食堂(こども&地域食堂)
【全文】「その配慮が神」マタイ6章1~4節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝いたします。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちと一緒に礼拝をしましょう。
今日は地域活動と福音について考える最後の回です。これまで私たちの取り組んでいるこども食堂から見えてくる福音について考えてきました。今日もこの視点から聖書を読んでゆきたいと思います。
こども食堂には100名以上のボランティアさんが参加してくださっています。参加の前のオリエンテーションとして教会のことや、こども食堂の活動の趣旨について30分くらいの説明をしています。ボランティアを希望する人のほとんどが、初めて教会に来たという方たちです。この説明はこども食堂のことだけではなく、キリスト教を紹介する機会、福音宣教の機会にもなっています。ボランティアの方への説明の中で、一番丁寧に説明をしているのは、私たちのこども食堂は貧しい人専用の食堂ではないということです。私たちの食堂は貧しい人が集まっているという雰囲気にしたくないのだという説明に時間を割いています。
もちろん私たちはまず食事をするのにも困る、貧しい人にこの食事が届いたらよいと思っています。しかしもし私たちが貧しい人は、どうぞ集まって下さいと言ったとしたら、おそらく私たちの食堂には誰も来ないでしょう。
誰でも貧しい人の集まる場所に自分が行くという行為は、大変大きな抵抗感があります。自分の尊厳が打ち砕かれるような気がするものです。貧しい人は来て下さいという言葉は、かえって相手を「自分はまだ人様のやっかいになるほど落ちぶれてはいない」「私はそんな場所には絶対に行きたくない」という気持ちにさせるものです。それではかえって食事を必要としている人に届きません。この食事が貧しい人に届けばよいと思っているからこそ私たちはこの食堂を貧しい人専用にしないことを大事にします。明るく、楽しく、誰でも利用できる雰囲気だからこそ、いろいろな人がたくさん来て、その中の一部に困っている人が利用できるのです。
そしてさらにそもそも人の困りごととは多様なものです。経済的な困窮だけではなく、子育ての行き詰まり、日常の寂しさなどがあります。そのさまざまな困りごとのためにこども食堂を使ってもらっていいと思っています。
このような説明をボランティアを始める方にしています。この説明を事前にしないとボランティアの方から「なんだここは。困ってそうな人が一人も来ていないじゃないか」と誤解されてしまうからです。私たちはもちろん貧困の解消に強い関心を寄せてこの食堂をしていますが、だからこそその人たちのためだけにしない工夫が必要です。いろいろな人が、いろいろな課題がありながらも、それを表にせず、楽しく集うことができる、そこに私たちの食堂の良さがあります。
本当に困っている人が来ているのかという批判もありますが、知りません。これだけ楽しく集まっているのだから、きっとみんなの何かを埋めているはずです。みんなの心の穴を埋めているでしょう。お財布の穴を埋めているでしょう。利用者自身が何を埋められているのか気付かないくらいがちょうどよいのです。そのようにして教会はみんなの一部になっています。
この考え方は聖書の教えとも重なると思っています。今日は、イエス様が困っている人と出会う時、どうすればよいかを教えている箇所を読みます。一緒に聖書を読みましょう。
今日はマタイによる福音書6章1~4節をお読みいただきました。イエス様の時代にも、多くの生活困窮者がいました。私たちが高い税金に苦しんでいる様に、当時の人々も高い税金に苦しみ、貧しい人がたくさんいました。特に聖書にはやもめ、いまでいう単身女性、シングルマザーが経済的に貧しい状況に追いやられたことを記しています。これも現代と同じです。人々は苦しんでいました。
そのような時代、ユダヤの人々には助け合いを大切にする文化がありました。おそらく今よりも助けられることを「ありがたい」とか「めずらしく、希なこと」ととらえることはなかったでしょう。自分たちは助けあって当然である、助けることと助けられることが当たり前の日常だったからです。日本にもかつてはそのような文化があったでしょう。今は失われつつあります。
ユダヤでは助け合うという機会が多かったからこそ、助け合いに関するトラブル、助け合いの悪用も多くありました。そして助け合いの知恵もありました。今日イエス様は助け合いにおいて一番してはいけないことと知恵を教えています。内容を見てゆきましょう。
イエス様は貧しい人に対して、人前で支援を行う事を禁止しました。人を助けるのに、わざわざ人の目に着くところでする、ラッパを鳴らして、目立つように良い事するということを、一番してはいけないことだと教えたのです。それは貧しい人を利用した、自己顕示であり、お金で周囲から良い評価を買おうとする、偽善の行為です。イエス様はそれを善い行いではないと言いました。そのような行為をするのは偽善者だと言いました。それは本当にそうだと思います。
そして今日はもう一歩踏み込んで、この個所を読んでみたいと思います。こども食堂の経験から読んでゆきます。この個所を貧しい人の立場、善行を施される側の立場に立って読みたいと思います。
ある日、貧しい自分を助けてくれるという人が現れました。その人は私がボロボロの服を着ていたから貧しいと分かったのでしょうか?本当は身なりだけでも、みんなと同じでいたいものですが、もはやそれもできないほど、貧しかったのです。本当は人を助ける側に回りたいけれど、今は恥も外聞も捨てて、この人に助けを求めるしかないようです。
自分を助けてくれるという人は、私を人が集まる街角や、会堂に連れていこうとします。そこではラッパの音が響きます。みんなの注目が集まります。そしてみんなの前でまるで表彰状の贈呈式のように、施しを渡されます。助けを受けた人はみんなの前で、その人に大げさに感謝の言葉を言わねばならない雰囲気が充満します。あなたは命の恩人だ、一生この御恩は忘れない、あなたは何て良い人なのだと言わねばならないのです。そのような施しを誰が受けたいと思うでしょうか。そのような方法で本当に困った人が助けを受け取るでしょうか?私だったらどんなに困っていても、私の尊厳を奪う、そのような支援は受け取りたくありません。
イエス様はそのように人の前で支援をしようとする人に言いました「はっきり言って、そういう支援をする人は残念です」と。そしてイエス様は、良い事をするときは、自分の右の手のことが左の手にわからないくらい、周りに絶対に知られないように、助けるべきだと教えています。イエス様は手助けをする際は他の人に悟られることなく、手助けをするようにと言っているのです。イエス様の教えには手助けをする前提に、相手の尊厳に対する配慮があります。この話はただ、自己満足な支援をするなという教えにとどまっていません。イエス様は相手の尊厳への配慮があって、初めて手助けにつながるのではないかということを、ここで投げかけています。人前で手助けをし、相手の尊厳を貶めてしまっては、本当の手助けにつながらないのだと言っているのです。
この話にはイエス様のそのような考えも含まれたでしょう。この話は、私たちの生きる上で大切なことを教えています。それは誰かに手助けをするときは、相手への配慮と相手の尊厳を何よりも大切にすべきであるという教えです。相手への配慮と尊厳を大切にし、他の人にわからないように、自分の左手にもわからないくらい、配慮をしてその支援を行うべきだということです。そうでないと善い行いは成立しないのです。この言葉はそのような知恵を私たちに教えてくれています。こども食堂が貧しい人専用でなく、明るい雰囲気で行われることはここにルーツがあるでしょう。
さて、この教えを私たちの内面にもっと広げて考えてみましょう。神様は私たちにも良い物を備え、与えて下さるお方です。神様は私たちに何か良い物を下さる時、人々の目の前で、私たちに渡すようなお方ではありません。神様は良い物を下さる時、密かにそれを下さるのです。それはきっと人々の目の前で、ほら神様を信じていて良かったでしょと証明するような方法で与えられるものではありません。神様は福引が当たった時の様なベルを鳴らして人々の注目するような方法で、恵みを与えて下さるのではないのです。
神様は右手が左手のすることを知らないように、私たちにはひそかに良い物を下さるお方です。私たちが誰にも知られたくない心の中に、神様はそっと贈り物を下さるお方なのです。私たち一人一人の心の中に、他の誰にもわからないように、私たちにすばらしいものを下さるのです。私たち一人一人はそのような密かな恵みをいただいています。他の人が気づかない、もしかして私自身も気づかない恵みを頂いているのです。
今日はこの後クリスマスの飾りつけをします。教会をきらびやかにしてゆきます。でも本当に良い物は、私たちの心の誰にも知られない、知られたくない場所に、そっと神様から与えられてゆくのです。それが神様の配慮です。神様は、私たち一人ひとりの心にそっと寄り添い、密かな恵みを授けてくださいます。その配慮に倣い、私たちもまた、誰かの心にそっと寄り添う活動を続けたいと願っています。
私たちのこひつじ食堂も神様の配慮をこの地上で実現するそのような活動をとして続けてゆきたいと願っています。お祈りします。
「その配慮が神」マタイ6章1~4節
施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。
マタイ6章3節
こども食堂から見えてくる福音について考えています。ボランティアの方への趣旨説明では、私たちの食堂は貧しい人が集まっているという雰囲気にしたくないと説明をしています。誰でも貧しい人の集まる場所に行くということは自分の尊厳が打ち砕かれるような気がするものです。それは「私はそんな場所には絶対に行きたくない」という気持ちにさせ、かえって食事を必要としている人に届きません。だから食堂を貧しい人専用にしないことを大事にします。明るく、楽しく、誰でも利用できる雰囲気だからこそ、困っている人が利用できるのです。
そのようにして教会はみんなの心の穴、お財布の穴を埋めています。利用者自身は何を埋められているのか気付かないかもしれません。でもそれでいいのです。この考え方は聖書の教えとも重なると思っています。今日は、イエス様が困っている人と出会う時、どうすればよいかを教えている箇所を読みます。
イエス様の時代にも、多くの生活困窮者がいました。ユダヤの人々には助け合いの知恵がありました。今日イエス様は助け合いにおいて一番してはいけないことと知恵を教えています。イエス様は貧しい人に対して、人前で支援を行う事を禁止しました。それは貧しい人を利用した、自己顕示であり、お金で周囲から良い評価を買おうとする、偽善の行為です。
今日はもう一歩踏み込んで、こども食堂の経験から、貧しい人の立場、善行を施される側の立場に立って読みたいと思います。この個所でイエス様は手助けをする際は他の人に悟られることなく、手助けをするようにと言っているのです。イエス様の教えには手助けをする前提に、相手の尊厳に対する配慮があります。この話はただ、自己満足な支援をするなという教えにとどまっていません。イエス様は相手の尊厳への配慮があって、初めて手助けにつながるのではないかということを、ここで投げかけています。それは誰かに手助けをするときは、相手への配慮と相手の尊厳を何よりも大切にすべきであるという教えです。
この教えを私たちの内面にもっと広げて考えてみましょう。神様は私たちに何か良い物を下さる時、人々の目の前で、私たちに渡すようなお方ではありません。神様は良い物を下さる時、密かにそれを下さるのです。神様は右手が左手のすることを知らないように、私たちにはひそかに良い物を下さるお方です。私たちが誰にも知られたくない心の中に、神様はそっと贈り物を下さるお方なのです。
本当に良い物は、私たちの心の誰にも知られたくない場所に、そっと神様から与えられてゆくのです。それが神様の配慮です。神様は、私たち一人ひとりの心にそっと寄り添い、密かな恵みを授けてくださいます。その配慮に倣い、私たちもまた、誰かの心にそっと寄り添う活動を続けたいと願っています。こひつじ食堂も神様の配慮を地上で実現する活動をとして続いてゆくことを願っています。お祈りします。
【全文】「世を愛する教会ー公共神学ー」マタイ5章38節~48節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちの教会はこどもの声がする教会です。今日もこどもたちと一緒に礼拝をしましょう。10月と11月は地域活動と福音というテーマで宣教をしています。先月、西南学院に訪問した際に、ある学生から一冊の本を教えてもらいました。それは稲垣久和の『閉鎖日本を変えるキリスト教 公共神学の提唱」という本でした。さっそく読んでみたのですが、大変興味深い内容でした。私たちの教会が取り組む『こひつじ食堂』や『こひつじひろば』『こひつじカフェ』で日々感じる思いを、この本では『公共神学』として明確に表現していました。今日はこの公共神学を紹介し、神様の愛の豊かさについて、そして私たちがどのようにその愛を広げてゆくべきかについて考えたいと思います。
この本では社会全体を『個人と集団』『自己と他者』という2つの軸で4つに分類しています。縦の軸は他者と自己、公と自己ともいえるでしょう。左上には行政や学校が位置づけられます。公的な集団で、社会全体の利益をもとめる集団です。一方左下は私的な集団です。主に企業や塾などが当てはまるでしょう。私的な集団として自己の利益を追求していきます。右上にいるのは他者や公が強いが、集団ではなく個人を対象にした共同体です。NPOや労働組合がここにあてはまるでしょう。最後の右下は公と反対の自己、そして個人の事柄の領域です。家族や教会がここに当てはまります。教会・信仰とは個人の自己の最も奥深くにあるものでしょう。教会は人の内面を専門としています。
そして最近、教会以外の他の3つのグループは垣根を超えて活動をしています。企業がNPOのようなことをしたり、NPOが企業のようなことをする場面があります。NPOが行政のような働きをすることが増えています。さらにそれぞれは専門を持ちながらも、他のグループと連携・協力をしています。それは単にどちらかが一方的に手伝っているのではなく、相互が協力することで、自分たちの専門分野をより発展させています。様々な形で垣根を超えること、連携することが始まっています。
一方、教会はどうでしょうか。この本の理解によれば教会は自己・個人という枠組みの中に居続けようとしています。他の領域に対して、この世的な事として垣根を越えようとしてきませんでした。他の領域と協力をしようともしませんでした。しかしこの本では、教会ももっと垣根を超えて他の領域に進出したらよいと言っています。その理由は他の領域に取り組むことで、教会の自分たちの専門分野がより発展していくからです。私たちの中心であり、専門であり、最も大切にしていることは内面のことです。でも私たちと違う領域に出会ってゆく、そこに進出することで教会はさらに発展することができると言っています。
私はこひつじ食堂がまさにそのような取り組みに位置づけられると思いました。こども食堂は本来NPOがすることかもしれません。でも私たちの教会がその活動に取り組むことで、他者と関わることで、福音と愛がさらに広がるのです。今まで教会が行かなかった領域で私たちの信仰・価値観が広がってゆくのです。著者は、日本の教会が抱える閉塞感を打開するには、各教会が他の領域に積極的に関わることが大切だと述べています。
そして著者は日本社会にキリスト教がなかなか浸透しないのは、クリスチャンの意識と信仰が内向きで、防御的過ぎることに問題があるのではないか?もっと教会は、他の領域で影響力を発揮してはどうか?と勧めています。
社会と教会は対立するものではありません。またまったく関係ないものでもありません。教会が「この世」と呼ぶ、自分たちと違う領域に様々な接点を持つことにチャレンジをすることで、私たちの福音と愛はますます広がっていくはずです。私たちの地域活動がまさにそれです。私たちはこれまでの教会の概念から、少しはみ出して活動をしています。でもそのことが福音と愛の広がりにつながっているのではないでしょうか?今日はこのように私たちは自分たちの領域をはみ出して、福音と愛を伝えようということ、世を愛そうということを一緒に考えたいと思います。聖書を読みましょう。
今日はマタイ6章38~48節をお読みいただきました。イエス様が私たちに「敵を愛しなさい」と教えた箇所です。現代も古代も「隣人を愛し、敵を憎め」というのは社会の常識でしょうか。しかし聖書は旧約聖書からずっと敵を愛するように教えています。イエス様も新約聖書においてあらためて、そしてさらに発展的させて、敵と思える人にも愛を深めるように、私たちに教えています。それは敵を愛し、迫害するもののために祈りなさいと教えています。
私たちクリスチャンはこの教えの前にどのように生きているでしょうか?今までもしかしてこの世のこと、社会のことを、教会とは別のこととして、敵視してきたかもしれません。この世のことを、私の個人の内面や、自分の信仰とは関係ないものとしてきたかもしれません。でも今日イエス様は、自分と異なる他者を愛するようにと教えています。イエス様は今日、自分と異なる他者を愛するようにと教えています。つまり、私たちとは異なる社会の領域の人々に対しても愛をもって接するよう導いているのです。
もしかすると、反対にこの世の人々からは、私たちの領域以外からは、私たちのことが敵に思えることもあるかもしれません。統一教会をはじめとしたさまざまな宗教が、人の気持ちに付け込んで、お金を巻き上げています。宗教は怖い。平塚バプテスト教会も同じではないかと誤解され、敵視されているかもしれません。でも私たちは、教会のことを誤解している人、教会のことを知らない人を愛したいと願っています。きっとこのままだと、私たちが自分たちの領域から一歩踏み出さなければ、教会がその人と接点を持つことはまず無いでしょう。でも私たちが、私たちの方からその人が暮らす領域に出てゆきます、必要に応えてゆきます。そしてそのようにして出会う時、はじめて教会への誤解が解けたり、私たちの信仰を知ったりするようになるのです。福音と愛が伝わり始まるです。私たちはこの領域に飛び込んでくる人を待っているだけではいけないのです。
イエス様の活動はまさにそのような活動でした。イエス様は旅をしながら福音と愛を広げました。自分から相手を訪ねて歩きました。そして訪ねた先で今日の教えのように、イエス様は、神様はクリスチャンだけに恵みを与えるのではないと教えました。神様はクリスチャンだけを愛しているのではありません。イエス様は、誰にでも太陽が登るように、誰にでも雨が降るように、神様の愛はすべてのひとにあまねく注がれると教えたのです。それが神様の愛です。イエス様はそのように自分たちと違う人に福音を愛を伝えたのです。その教えは一般社会の教えとは大きく違うものでした。しかしその異質な教えが、人々の心に残ったのです。多くの人がその教えに共感をしたのです。
教会の中というのは、いろいろな問題がありながらも、多くの人が互いに愛し合っています。教会の人同士が愛し合うことは当然と言えるでしょう。仲間同士が愛し合うというのは誰でもしていることです。私たちに教えられていることは、教会の仲間だけでなく、他の領域に出て行って、そこでも他者を愛しなさいということです。教会の仲間を愛するように、その外の領域でも、他者を愛しなさいということです。
48節で私たちは完全なものとなるようにと言われています。それはもっと福音と愛が社会、世界に大きく広がるように、完全にゆきわたるようにせよという意味でしょう。私たちは教会の中だけで愛し合うだけではなく、私たちの愛を他の社会の領域にもっと広げてゆくようにと示されています。それこそが伝道と言えるのではないでしょうか。ですから、この世との関わり、私たちの地域への活動は教会にとって二次的な「おまけ」ではありません。私たちの中心である信仰をより広げてゆくために、私たちの自身の信仰をより豊かなものにするために、愛を広げるために必要な活動なのだと思います。
私たちが世に出る時、周囲とは違う独特の価値観を持っていることに、私たち自身が気づくでしょう。この世界では38節のような「目には目を、歯には歯を」という価値観が支持され、広がっています。でも私たちの正典は、それは間違っていると教えています。暴力に暴力で立ち向かうな、必要とする者には必要とする以上のものを与えよ、寄り添うべき人に徹底的に寄り添うようにと教えています。他者、地域の人々がこのような異質な価値観、愛と出会うとき、福音が伝わるのでしょう。私たちはこれからも地域への活動を教会の二次的な活動としてではなく、愛を広げるための活動として取り組んでゆきましょう。
そして、私たち一人一人が毎週置かれている場所のことも考えます。私たち自身も、もともと教会の中だけで生きているのではありません。教会から派遣されて、それぞれの場所で生きています。そこで皆さんはキリスト教の価値観に基づいて生きるでしょう。その時に様々な領域の人に出会うでしょう。そのようにして他者と出会う時に、福音と愛が広がってゆくのです。教会もそれと同じです。
私たちは教会の中で互いに愛し合いましょう。そしてこの愛を教会の外にも、違う領域にも広げてゆきましょう。その時、出会いがありイエス様の愛を伝えてゆくことになるのでしょう。お祈りをいたします。
「世を愛する教会ー公共神学ー」マタイ5章38節~48節

稲垣久和の『閉鎖日本を変えるキリスト教 公共神学の提唱」という本を読みました。この本では社会全体を『個人と集団』『自己と他者』という2つの軸で4つに分類しています。教会は人の内面に関わることを専門としています。最近、教会以外の3つのグループは垣根を超えて協力し、自分たちの専門分野をより発展させています。一方、教会は自己・個人という枠組みの中に居続けようとしています。この本では、教会ももっと垣根を超えて他の領域に進出し出会ってゆくことで発展することができるはずだと言っています。私はこひつじ食堂がまさに他の領域に進出する取り組みに位置づけられると思いました。
今日はマタイ6章38~48節をお読みいただきました。今まで私たちはこの世のことを教会とは別のことととして、敵視してきたかもしれません。でも今日イエス様は、自分と異なる他者を愛するようにと教えています。私たちとは異なる社会の領域の人々に対しても愛をもって接するよう導いているのです。反対に私たちの領域以外からは、私たちのことが敵に思えることもあるかもしれません。さまざまな宗教が、人の気持ちに付け込んで、お金を巻き上げています。平塚バプテスト教会も誤解され、敵視されているかもしれません。私たちが自分たちの領域から一歩踏み出さなければ、教会がその人と接点を持つことはまず無いでしょう。私たちは私たちの方からその人が暮らす領域に出てゆきます。そのようにして出会う時、はじめて教会への誤解が解けたり、私たちの信仰を知ったりするようになるのです。
イエス様の活動はまさにそのような活動でした。イエス様は旅をしながら福音と愛を広げました。自分から相手を訪ねて歩きました。そしてイエス様は、誰にでも太陽が登るように、誰にでも雨が降るように、神様の愛はすべてのひとにあまねく注がれると教えたのです。それが神様の愛です。イエス様はそのように自分たちと違う人に福音を、愛を伝えたのです。
教会の人同士が愛し合うことは当然です。私たちに教えられていることは、教会の仲間だけでなく、他の領域に出て行って、そこでも他者を愛しなさいということです。私たちの地域への活動は教会にとって二次的な「おまけ」ではありません。私たちの中心である信仰をより広げてゆくために、私たちの自身の信仰をより豊かなものにするために、愛を広げるために必要な活動です。
私たちは教会の中で互いに愛し合いましょう。そしてこの愛を教会の外にも、違う領域にも広げてゆきましょう。その時、出会いがありイエス様の愛を伝えてゆくことになるのでしょう。お祈りをいたします。
【全文】「誇らずに共に生きる」マタイ3章1~17節
みなさん、おはようございます。今日も共に礼拝をできること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日も一緒にこどもたちの声を聞きながら礼拝をしましょう。先月と今月は地域活動と福音というテーマで聖書を読んでゆきます。私たちの教会では月2回のこども食堂をしています。経済的に困っているこどもだけではなく、子育てに追われる保護者や、寂しい思いをしている高齢者、誰かと会いたい人、そんな人が集って、みんなで食事をしています。
こども食堂をしていると、様々な団体から寄付や調査の依頼やお知らせが届きます。先日は「NPO法人アトピッコ地球の子ネットワーク」という団体から手紙をもらいました。私も初めてこのような団体の存在を知ったのですが「NPO法人アトピッコ地球の子ネットワーク」はアトピー・アレルギーを持つ人とその家族を支援する団体だそうです。手紙にはその団体からの切実な要望が記されていました。それはこども食堂にも食物アレルギーへの配慮を求める内容でした。こども食堂が必要なこども、こども食堂に行きたいこどもの中には、アレルギーを持つ子供もがいます。しかし多くのこども食堂ではアレルギー対応が不十分です。ある食堂の看板には「アレルギーの方はご遠慮下さい」と書いてあり、中には「アレルギーの方はお断りします」とまで書いてある食堂もあるそうです。こども食堂は小規模な民間団体の運営で限界もあると思うが、必要なこどもがいることを理解し、もう一歩対応してくれないかという要望でした。
そしてその団体はアンケートに答えると、アレルギーフリーの食事セットをプレゼントするとのことでした。それを保管しておいて、アレルギーのこどもが来たら対応をして欲しい。それを使って、こども食堂の看板を「アレルギーの方お断り」ではなく「アレルギーの方には対応する食事を準備している」と書き換えてくれないかとありました。素晴らしい活動だと思い、アンケートに答えました。食材がもうすぐ届くでしょう。
私たちの教会でもこれまで「アレルギー対応はしていません」と毎回の看板やメニューに記載していました。実際に200食を作りながらアレルギーに対応することは難しいものです。でも保管できる別の物を準備しておくという少しの努力で、表記の方法や利用できる人が増えるという事を教えていただきました。
地域の方に平塚バプテスト教会は素晴らしい活動をしているとほめていただく機会が増えました。平塚バプテスト教会に誇らしい思いを持ちます。でもまだこれで完成ではないのです。まだまだ配慮できるのに、配慮していない自分自身に気付かされています。そのことを悔い改めます。食堂にたくさんの人が来ているからこそ、私たちは少数への対応は無理と言ってしまう、言えてしまうのです。私たちはもう一歩、少数者への配慮をしてゆきたい、そう思っています。
少数者を置き去りにしてしまう私たちです。もっとできることがあるはず、それを心にとめながらこれからの活動をしたいと思います。私たちも「アレルギーには対応していません」から「アレルギーの方には別のものが準備できます」と表記を変更しようと思います。もちろん少数者への配慮はこの食堂だけではなく教会全体のこととしても考えたい事柄です。そして少数者への配慮は教会だけではなく、私たちそれぞれの日常生活の中で目を向けてゆきたい事柄です。今日はこのことをきっかけにして、聖書を読みたいと思います。
さて今日はマタイによる福音書3章1~17節をお読みしました。今日の聖書の個所と食物アレルギー、少数者への配慮はどんな関係があるでしょうか。
イエス様がまだ公の活動を始める前、バプテスマのヨハネという人がいました。彼の元には大勢の人が集まっていました。彼は町から離れ荒野に住み、いなごと野蜜をたべて生きていました。5節~7節を見るとユダヤ全土からたくさんの人が集まったとあります。そしてその中にはファリサイ派とサドカイ派の人もたくさんいたとあります。
ファリサイ派とはユダヤ教の多数派です。たくさんの人がファリサイ派の指導の下に生きていました。サドカイ派とはいわゆる貴族のような人々で、当時のエリートです。彼らには誇りがありました。9節「我々の父はアブラハムだ」という誇りです。自分たちは選ばれた者であり、自分達は尊敬されていて、正しい事をしている、すばらしいことをしているという自覚があった人々だったのです。
自分たちに誇りをもった彼らにバプテスマのヨハネは言います。「そんなものは神様からしたら石ころみたいなものだ」。自分の先祖に対する誇り、人の誇りや、選ばれた者という意識、それらは神様にとって本当にたいしたものではないと言ったのです。神様は石ころのようにそれをすぐに創ることができ、すぐに壊せるものだと言ったのです。
ヨハネの元にはバプテスマを希望する人たちが集まりました。ヨハネのバプテスマとはどんな意味だったのでしょうか。諸説ありますが、例えばバプテスマは当時外国人が、ユダヤ教に改宗・入信するときに行われていたと言われます。改宗・入信の儀式だったのです。しかしファリサイ派の人もサドカイ派の人ももちろんすでにユダヤ人です。生粋のユダヤ人です。血筋のよい人です。多数派、エリート、正しい人です。ユダヤ人で高い自己評価を持つ彼らには本来バプテスマはまったく必要ありませんでした。しかし彼らの一部はバプテスマのヨハネの教えに呼応して、本来改宗・入信の儀式であるバプテスマを受けようとして集まってきました。彼らは、自分が正しい、自分が誇らしいという思いを捨て、バプテスマを受けようとしたのです。今まで自分たちが誇ってきたものを捨てる、バプテスマを受けようとしたのです。
そのバプテスマは人や世界を、これまでの正しさや誇りといった高みから見るのではなく、悔い改めや信仰の始まりといった低みから見直そうという運動でした。バプテスマを受け、人と世界を低い場所からもう一度見直す、それがバプテスマのヨハネが勧めた活動でした。それがバプテスマの意味でした。彼らがバプテスマの前に告白した罪とは、外国人や他宗教の人を見下してきた罪だったでしょう。少数派を軽んじたこと、自分が絶対正しいと思ってきた罪だったでしょう。彼らはその罪を告白し、バプテスマを受けて、新しい人生を歩もうとしたのです。高みからではなく、低みから人と世界を見る生き方に方向転換しようとしたのです。
13節以降はイエス様が登場します。イエス様も一部のファリサイ派、サドカイ派のように、このバプテスマのヨハネの運動に賛同したお方でした。イエス様もバプテスマを受けたのです。私たちは驚くかもしれません。イエス様こそ自分を誇るべき神の子だったはずです。14節のヨハネも「私の方が受けるべきだ」と言い、ためらっています。しかしイエス様は悔い改めて低みに行くことは「正しいこと」であり「私たちにふさわしい」のだと言います。誇っても誇りきることのできない神の子イエスが、誇ることを捨てる、そのことから地上での活動をスタートしたのです。そしてその時天が開き、霊が「これは私の愛する子、わたしの心に適う者」と称えました。誇らずに、低みに身を置く、このような生き方を始めることを霊がほめたたえたのです。
この後のイエス様の活動もこのバプテスマの延長線上にあると言ってもいいでしょう。イエス様はその後の生涯で自分を誇り、その権威によって人々を従わせたのではありませんでした。イエス様は人気が出て多数派になったのではありませんでした。ただ貧しい人、罪人と言われ差別された人、病に苦しむ人を訪ね、目を向け続けてゆきました。その人たちと食事をし、同じ場所で時を過ごしたのです。そしてイエス様はその後、十字架に掛かられてゆきます。バプテスマよりさらに低い場所へと向かわれていったのです。十字架に掛けられた姿はこの地上でもっとも呪われた者の姿でした。イエス様は最後、この地上でもっとも残酷な姿になりはてたのです。
しかし、その十字架こそ、人々の絶望ではなく希望となりました。イエス様は人々の絶望の中に、共にいるという希望となったのです。イエス様は高みから私たちを見下ろして、善悪を判断し、審判を下そうとしているのではありません。イエス様は今も誇るのではなく、低みから、十字架から私たちを見ているのです。共にいるのです。
私たちはイエス様の歩みからどのように生きるかを考えます。私たちの地域活動は人々に支持されています。私たちはそれを誇らしいと思います。多くの方が私たちの活動を支持してくれています。
でも私たちは誇る気持ちを脇に置きましょう。私たちはバプテスマを受け、イエス様に従う者であることを思い出しましょう。どんなにたくさんの人が来ても、人気がでても、低みへ追いやられた人、端に追いやられた人、寂しい思いをしている人を忘れずにこれを続けてゆきましょう。それがバプテスマを受けた者の歩みです。それがイエス様の十字架を支えとする者の歩みです。
私たちはそれぞれの生活においても、同じことが言えるでしょう。みなさんには誇るべきすばらしいものがあります。しかし私たちは誇らずに共に生きてゆきましょう。いつも私たちが置かれた場所で、困っている人、見過ごされている人、さみしい思いをしている人に目を向けてゆきましょう。イエス様のように、その人と共に過ごし、その人たち食べ、歩んでゆきましょう。お祈りをいたします。
「誇らずに共に生きる」マタイ3章1~17節
悔い改めにふさわしい実を結べ。 マタイによる福音書3章8節
地域活動と福音というテーマで聖書を読んでいます。私たちの教会のこども食堂はこれまで看板に「アレルギー対応はしていません」と記載していました。でも保管できるアレルギー対応食品を準備しておくという方法で表記の方法や利用できる人が増えることを教えてもらいました。
地域の方に平塚バプテスト教会は素晴らしい活動をしているとほめていただく機会が増え、誇らしく思います。でもまだまだ配慮していないことに気付かされ、そのことを悔い改めます。食堂にたくさんの人が来ているからこそ、少数への対応は無理と言ってしまうのです。もう一歩少数者への配慮をしてゆきたいと思っています。
もちろん少数者への配慮は食堂だけではなく教会全体のこととしても、私たちそれぞれの日常生活の中でも目を向けてゆきたい事柄です。今日はこのことをきっかけにして、聖書を読みます。
バプテスマのヨハネという人がいました。彼の元には大勢の人が集まっていました。ファリサイ派やサドカイ派の人々には誇りがありました。9節「我々の父はアブラハムだ」という誇りです。自分たちは選ばれた者であり、尊敬され、正しい事をしている、すばらしいことをしているという自覚があった人々でした。
そのような中でヨハネのバプテスマは、自分が正しい、自分が誇らしいという思いを捨てるという意味を持ちました。彼のバプテスマは人や世界を、これまでの正しさや誇りといった高みから見るのではなく、悔い改めや信仰の始まりといった低みから見直そうという運動でした。彼らは人々を見下してきた罪を告白し、バプテスマを受けて、新しい人生を歩もうとしたのです。
13節以降はイエス様がバプテスマを受けます。イエス様こそ自分を誇るべき神の子だったはずです。しかし神の子イエスが、誇ることを捨て、地上での活動をスタートしました。この後のイエス様の活動もこのバプテスマの延長線上にあります。イエス様は多数派になったのではありませんでした。ただ貧しい人、罪人と言われ差別された人、病に苦しむ人を訪ね、目を向け続けてゆきました。その人たちと食事をし、同じ場所で時を過ごしたのです。そしてイエス様はその後、十字架に掛かられてゆきます。バプテスマよりさらに低い場所へと向かわれていったのです。
しかし、その十字架は人々の絶望ではなく希望となりました。イエス様は人々の絶望の中に、共にいるという希望となったのです。イエス様は高みから私たちを見下ろして、善悪を判断し、審判を下そうとしているのではありません。イエス様は今も誇るのではなく、低みから、十字架から私たちを見ているのです。
私たちの地域活動は人々に支持されています。そしてみなさん自身にも誇るべきすばらしいものがあります。しかし私たちは誇らずに共に生きましょう。いつも私たちが置かれた場所で、見過ごされている人に目を向けてゆきましょう。イエス様のように、その人と共に過ごし、食べ、歩んでゆきましょう。お祈りをいたします。
【全文】「みんな神に愛されている」 マタイ25章34~46節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝、召天者記念礼拝をもてること主に感謝します。お久しぶりの方も共に集うことができてうれしいです。私たちはこどもの声がする教会です。小さいこどもも一緒にこの礼拝をしたいと思っています。声や足音がするかもしれませんが、それも礼拝の一部です。小さな命を感じながら礼拝をしましょう。
今日は特に天に送った仲間たちを覚える召天者記念礼拝です。誰しも仲間を天に見送ったという経験があるでしょう。その寂しさは何年経っても変わらないものです。私たちはその別れの寂しさを抱えながら、思い出を抱えながら、引きずりながら生きています。そして時々、あの時もっと自分ができることがあったはずという思いも起こるものです。もう少し私が優しくできれば、もう少し最後くらい一緒にいれば、そのような後悔もあるかもしれません。その思いも一緒に、神様に礼拝をささげましょう。
私は写真の方々すべてを詳しく存じ上げているわけではありません。それぞれの方はどんな人生だったのでしょうか。皆さんの思い出を聞かせて下さい。中にはたくさん良い事をした人がいるでしょうか、大きな功績を残した人、表彰された人もいるでしょうか。あるいは誰かに頼り、誰かにお世話をされるばかりの人もいたでしょうか。亡くなった方々はいまどこでどのように過ごしているでしょうか。私は、キリスト教は良いことをした人は死んだ後に天国へ行く、悪いことをした人は死んだ後に地獄へ行くという宗教ではないと思っています。もしそうだとしたら神様はアウトかセーフかを判断するただの審判員です。キリスト教は良い人が天国、悪い人が地獄に行くその判断基準ではありません。人の長い一生は善悪のどちらかに振り分けることはできないものです。
では、人は死後どうなるのでしょうか。私は、神様はすべての魂をそのもとに迎え、安らぎを与えてくださると信じています。ですから、故人が苦しんでいるのではないかと心配する必要はありません。
キリスト教では死のさらに先に、復活するという信仰を持っています。もう一度生き返るという復活ではなく、死のさらに先にある出来事として、復活があります。復活とは神様がこの世界を完全なものにされる時、私たちも新しい命を受けるということです。いつの日か神様は国々を超えて、生と死をも超えて完全な平和を起こしてくださる時がきます。死んで天におられる方々にも、まだその先に希望の時が待っているのです。亡くなった方にも、今なお希望と新しい命が待っているのです。私たちにはそんなに先のこと、死後のことを想像するのは難しいかもしれません。でも天に召された方々は、次の希望を持っています。そのことを覚えておきましょう。
そしてやがて私たち自身も死を迎える時が来るでしょう。そのことを不安や恐ろしく思うかもしれません。でもその時は私たちの命と魂も同じ様に、神様が受け止めてくださる時です。地獄に行く、裁きにあうという心配はいりません。その時、私たちは神様のもとにある平安に向かってゆく時です。私たちはその最期の日まで精一杯生きてゆきましょう。
今日も聖書を読みましたが、この個所を読むとやはり良いことをした人は天国に行く、悪いことをした人は地獄に行くのではないかと思うかもしれません。しかしこの話は本当に死んだ後のことを語っている話でしょうか。この話にははっきりと死んだ後のことという前提がありません。いえむしろ、この話は生きている者に語り掛けている話です。今、どう生きるべきかを問いかけています。聖書のメッセージの中心は死後の裁きではありません。この話から私たちが考えるべきことは、地上に残された私たちがどのように生きるべきなのかということです。
故人を神様の元に見送った私たちは、どう生きるべきなかこの話から考えましょう。私たちは天に見送った方が神様の元に安らかにいることを信頼し、そしてこの話から、残された私たちが、残された人生をこの地上でどのように生きるべきなのかを考えたいと思います。この話を、神様から地上の私たちに送られた、励ましとして受け取って読んでゆきましょう。聖書を読んでゆきます。
今日はマタイによる福音書25章31節~46節までをお読みしました。物語をもう一度見ましょう。ある時、一人の王様がいました。王様は右側にいた人に国全体に値するほどの良い物を与えようとしています。なぜなら困っていた時に私を助けてくれたからだと言います。右側の人々は驚きました。そうです、王様はこれまで生活に困ったことなどなかったからです。だからこそ助けたことがないと思ったのです。王様は何不自由ない生活を送っていたはずです。助ける必要は全くありませんでした。食べ物が無くて困っている時などありませんでした。しかしそこで王様は「最も小さいあの人にしたことは、私にしたことと同じだ」と言いました。私ではなく、あの人にやさしくしたことは、私にやさしくしたことと同じだと言ったのです。
そして反対の話も出てきます。王様の左側にいた人への話です。左側の人には何か悪いものが与えられようとしています。王様はあなたたちは私が困っている時に助けてくれなかったと言います。左側の人々も驚いたはずです。彼らは王様に一生懸命仕えていました。王様がのどが渇いたと言えば一目散に水を届けてきました。食事も着替えもすべてお世話をしてきたのです。しかし、王様はそこで「もっとも小さいあの人にしなかったことは私にしなかったのと同じだ」言います。私ではなく、あの人にやさしくしなかったことが、私にやさしくしなかったことと同じだと言ったのです。
この話は私たちの生き方について語られているものです。右側の人も左側の人も王様になら仕えて当然だと思ったでしょう。誰もが一生懸命、王様のお世話をしたのでしょう。おそらくそれは自分にも跳ね返ってくるからです。どちらの人も王様の世話は、自分の処遇や身分のために、抜かりなくしたはずです。しかし右側の人と、左側の人で大きく違ったことがありました。それは王様以外の人々への態度でした。王様は自分に従うことは当然であり、自分以外の人々への態度を問題にしたのです。王様は人々がもっとも小さい者へどのように接しているのかを厳しく見ていたのです。
「もっとも小さい者」とはどんな人のことでしょうか。体が小さな子どもたちとも読めるでしょう。小さいこどもに、どのように接しているかと言われています。また助けを必要としている人や社会的に弱い立場に置かれた人々とも読めるでしょう。小さい人というよりも、小さくされている人と理解した方がよいかもしれません。ゆがんだ社会構造の中で、自分らしく生きることが出来ない人ともいえるでしょう。生きづらさを感じるような人も含まれるでしょう。きついお仕事を続けている人や、体や体調が思うようにいかない人も含まれるでしょう。私たちは本当に様々な場所で、小さくされている人と出会うはずです。
私たちはそのような人々への接し方で、死後に天国に行くか、地獄に行くかが決まるわけではありません。聖書はそのような天国と地獄を伝えようとしているのではありません。聖書の中心は、神様は私たちがそのような小さくされた人にどのように接しているのかを、厳しく見ておられるということです。
私たちの命は地上の生涯を終えた後、必ず神様が安らぎの中で受け止めてられてゆきます。それはどんな人生を送ったとしても恵みとして与えられます。だから私たちは安心しましょう。そしてそれと同時に、神様はこの地上に残された私たちに、最も小さいものに目を注ぎ、生きてゆくようにと言っています。
これは地上に残された私たちへのメッセージです。神様は、あなたたちはこの地上の残された人生で、小さい者・小さくされた者に目を向けてゆきなさいとおっしゃっています。私たちが良い事をするのは、決して私たちが天国に行くため、自分の死後のためではありません。私たちはどんな人生を送っても必ず、神様が一方的な愛で私たちは受け止めてくださいます。私たちに全員に神様からのその約束と恵み、愛があります。
そして神様は私たちを愛すると同時に、私たちにも他者を愛することを求めておられます。私たちも神様のように、人を愛し、人を助けて生きるようにと伝えられているのです。神様は、私たち一人ひとりを無条件に愛し、守ってくださることを約束しています。その愛を受けた私たちも、他者を愛し、支え合う生き方が求められているのです。
私たちは今日も神様の愛を受けて生きています。神様の愛は死んでも続きます。私たちはそれを信じます。そして私たちはいつまでも愛されているからこそ、その愛を地上で他の人々と分かち合って生きてゆきましょう。キリスト教は愛の宗教です。恵みの宗教です。神様はすべての人を愛し、すべての人に安らかな死後を準備してくださっています。安心して仲間を見送りましょう。
神様の愛それは永遠の愛です。永遠の愛に包まれた私たちも、他者への愛を持って生きてゆきましょう。神様がすべての人を愛し、受け止めるように、私たちもすべての人を愛し、受け止めてゆきましょう。特にこの地上でもっとも小さい者、もっとも小さくされた者、見過ごされている者に愛を注いでゆきましょう。
神様はすべての命を引き受け、無限の愛と慈しみを注がれます。だから私たちも愛し合って生きましょう。お祈りをいたします。
「みんな神に愛されている」 マタイ25章34~46節
『はっきり言っておく。この最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。』
マタイによる福音書25章40節
今日は召天者記念礼拝です。私はキリスト教を良いことをした人は死んだ後に天国へ行く、悪いことをした人は死んだ後に地獄へ行くという宗教ではないと思っています。では人は死後どうなるのでしょうか。私は、人は死後、すべての魂が神様にのもとに迎えられ、安らぎを与えられると信じています。ですから、故人が苦しんでいるのではないかと心配する必要はありません。
キリスト教では死のさらに先に、復活するという信仰も持っています。復活とは神様がこの世界を完全なものにされる時、すべての人が新しい命を受けるということです。天に召された方々も、まだ復という次の希望も持っています。
そしてやがて私たち自身も死を迎える時が来るでしょう。私たちは最期の日まで精一杯生きてゆきましょう。
今日も聖書箇所は死んだ後の話をしているのではありません。この話は生きている者に語り掛けている話です。私たちはこの話から、天に見送った方が神様の元に安らかにいることを信頼し、そして残された私たちが、この地上でどのように生きるべきなのかを考えたいと思います。
聖書の物語を見ます。右側の人も左側の人も王様になら仕えて当然です。誰もが一生懸命、王様のお世話をしたのでしょう。しかし右側の人と、左側の人で大きく違ったことがありました。それは王様以外の人々への態度でした。王様は人々がもっとも小さい者へどのように接しているのかを厳しく見ていました。
「もっとも小さい者」とはどんな人のことでしょうか。それは小さいこども、助けを必要としている人、社会的に弱い立場に置かれた人、社会構造の中で自分らしく生きることが出来ない人ともいえるでしょう。私たちは本当に様々な場所で、小さくされている人と出会うはずです。私たちはそのような人々への接し方で、死後に天国に行くか、地獄に行くかが決まるわけではありません。しかし神様は、私たちがそのような小さくされた人とどのように接しているのかを、厳しく見ておられます。
これは地上に残された私たちへのメッセージです。神様は、あなたたちはこの地上の残された人生で、小さい者・小さくされた者に目を向けてゆきなさいとおっしゃっています。私たちが良い事をするのは、決して私たちが天国に行くため、自分の死後のためではありません。
「癒しと和解の恵み」ヨハネ20章19~29節
「だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される。だれの罪でも、あなたがたが赦さなければ、赦されないまま残る。」 ヨハネ20章19~29節
私たちは、ある時は他者に傷つけられ、またある時は他者を傷つけながら生きています。一度生まれてしまった対立関係、そして、心の中に沈潜した敵意や憎しみから癒されること、すなわち、他者と和解することは、とても困難な、しかし、大切な課題です。私たちは30年前に大虐殺が起きたルワンダで平和と和解の働きに仕えながら、その課題の困難さをひしひしと感じながら生きてきました。
ヨハネによる福音書の20章では、復活されたイエスが自分を見捨てた弟子たちと再び出会っていく物語りが描かれています。そこでイエスは驚くべき言葉を弟子たちに語られました。「父がわたしをお遣わしになったように、わたしもまたあなたがたを遣わす」(21節)。そしてその後、弟子たちに息を吹きかけられました。その息とはイエスご自身の霊、聖霊です。それは、イエスの命、愛と赦しの霊です。そして、弟子たちに赦し合って生きる共同体を築き、赦しと和解のために人々を執成していくようにとの任務を授けられたのでした。
23節には、イエスの謎めいた言葉が記されています。「だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される。だれの罪でも、あなたがたが赦さなければ、赦されないまま残る。」時としてこの言葉は、聖霊を与えられた弟子たちが、罪を犯した人々を赦したり赦さなかったりする権限を与えられたという解釈がなされるようです。しかし私は、むしろこのみことばの中に、イエスが私たちに「赦しと和解という希望をゆだねられた」という福音を見るのです。神による罪の赦し、そして、神と人間との和解は、主イエスの十字架を通して成し遂げられました(エフェソ2:11-22)。しかし、人間同士の赦しと和解は、私たち人間にゆだねられているのです。
私は主イエスが、傷つけられ「赦せない」と思っている人々に対して、赦しを義務として負わされるような方ではないと信じています。赦しは神から来る恵みなのです。心と身体に深い傷を負わされながらも生き残った者、サバイバーによる赦しは、イエスですら要求されるようなものではありません。人間の努力によって出来るようになるものではない。それはただ、神ご自身が癒しと共に、恵みとして与えてくださるものなのです。
罪ある私たち人間が、神によって赦されたことも恵みです。その赦された私たちが赦すことの出来る者へと変えられていくことも恵みです。赦しが恵みとして神から与えられることによってのみ、私たちは赦すことのできる者になるからです。そして、私たちが何者かを傷つけたにも関わらず、その被害者の方に赦していただけるとするならば、私たちはその方を通して神の「恵みとしての赦し」を受け取るのです。しかし、この赦しの恵みを、それぞれの立場にある私たちが受け取るかどうかは、私たち一人一人にゆだねられているのです。赦しと和解、それは、十字架にかかられ、三日目に、傷を負ったままの姿で復活された主イエスが、私たちにゆだねられた希望なのです。
#佐々木和之
「私が弱いとき、そのときこそ私は福音を伝えることができる」コリントの信徒への手紙二12章9節
わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ
コリントの信徒への手紙二12章9節
私たちはいま世界で起きている惨状を前にして戸惑い苦しみながら「なぜ戦争を止められないのか」と嘆く。しかし力で解決しようとして強さを求める姿勢が問題であり、それは信仰の強さを求める姿勢も無関係ではない。そこで「弱さを誇る」という言葉に込められたパウロの思い、信仰に注目したい。
パウロの働きによって地中海沿岸の都市に多くの教会ができ、多くのギリシア人キリスト者が生まれた。しかし教会の中に現れた熱狂的な人々が自分たちはもう救われて「完全な者」になったと誇り、エルサレムから来た人々が割礼を受けてユダヤ人になり、律法に従わなければならないと説いた。霊において完全になったと誇る人々はその霊的な強さを誇り、ユダヤ主義者は律法を守る強い信仰で得られる強い力を誇った。そんな力を誇る人々に対してパウロはこれまでの自分の苦労を語った上で「自分自身については、弱さ以外に誇るつもりはありません」と断言する。また「キリストは弱さのゆえに十字架につけられました」と語るようにパウロにとって十字架は弱さの象徴。律法では木にかけられた者は呪われた者。十字架刑で処刑されたイエスは神から呪われた者であり、神から見捨てられた者となる。そのイエスを神は引き上げられた。9-10節の「力」「強い」と訳されている言葉は、動詞になると「〜できる」という意味になる。何ができるのか、それは「人の心を動かすこと」すなわち「福音を伝えること」。つまりパウロが言おうとしているのは、自分自身が弱いときこそ、あの十字架につけられたキリストが自分の中に働いて、自分もまた福音を伝えることができるということ。
私たちは「クリスチャンはこうあるべきだ」という無意識のイメージを持っていないか。できているときは誇らしく感じ、できないと「信仰が弱くなった」と落ち込む。しかしイエスが十字架に磔にされている姿は、何もできない姿。神から見捨てられた呪われた姿。しかしそのイエスをこそ神は引き上げた。つまりこれができるから、これをしているから神が人を認めるのではない。まず神がこの私たちを愛している。パウロもまた弱さの中でその神の愛を伝えようとした。私たちは教えを守り、義しく過ごす事が信仰で、その姿が証しだと考える。しかしこのできない、惨めな私だからこそ、その私を愛される神のすばらしさを伝えることができる。そしてその愛に応えたいから神に従いたい。従うアピールをしたから神が私たちを愛されるのではなく、まず赦されている、その愛に応えたいのだ。自分の義しさを貫こうとするのではなく神の前で頭を垂れ、神の言葉を聞くように相手の言葉を聞き、自分の信仰を誇るのではなく神の愛を誇り、その愛が自分に注がれていると同じように相手にも注がれていると、分かち合っていきたい。
【全文】「収穫感謝礼拝」マタイ15章32~39節
みなさん、おはようございます。今日も共に礼拝できること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。教会にはこどもたちの声が響き、命の喜びにあふれています。今日もこどもたちの命と一緒に礼拝をしましょう。
10月11月は地域活動と福音というテーマで宣教をしてゆきます。また今日は10月16日の世界食糧デーに合わせてこの礼拝を、収穫感謝礼拝としています。収穫に感謝するということを考える時、私たちの教会で運営しているこども食堂「こひつじ食堂」に多くの食品の寄付が集まっていることを思い出します。たくさんの方が教会に収穫を持ち寄って来て下さることに大変感謝しています。先日は自分の家の田んぼで作ったという平塚産のはるみの新米の寄付をいただきました。とても香りのよいご飯でした。平塚で獲れたシイラやブリ、マグロの寄付を頂きました。最近では寒川のパン工場からもパンの寄付をもらっています。それぞれみなさん、決してお金や時間に余裕があるわけではないのに、私たちの食堂に寄付をしてくださっていることに、本当に心から感謝しています。
こども食堂に参加すると、この食べ物がどこでどのように育てられたのかを、いつもの食卓よりも強く感じるようになります。命を強く感じるとも言えるでしょう。そして食べ物に命を感じ、大切にするようになります。感謝するようになります。こども食堂はそのように食べ物と命に特別に感謝する、その体験をする場所になっています。
こども食堂の寄付に感謝し、みなさんと一緒に食事をしていて改めて感じるのは、クリスチャンこそ特に食べ物と命に感謝する機会が多いということです。クリスチャンは食前の祈りを大切にしています。教会の食事ではもちろん、家での食事でも、外食でも祈ります。日本では食前に感謝の祈りをすることは非常に珍しいことで、クリスチャンの最大の特徴とも言えるでしょう。私たちは食前の祈りで生産者の人に感謝すると同時に、それだけではなく、食べ物を神様が与えて下さったものとして感謝の祈りをします。
食べ物を前にして生産者に感謝するのはわかる気がしますが、私たちはなぜ神様に感謝をするのでしょうか。それはキリスト教ではすべての命は神様が創造したものだと考えるからです。そして私たちは神様が創造したその命を食べています。だから私たちは食前の祈りで、神様が私たちに命を与えて下さったことへ感謝を表しています。私たちが食前に神様に感謝の祈りを献げることは、とても大事な習慣ではないでしょうか?私たちはこの感謝と祈りを大切にしてゆきましょう。私たちは生産者への感謝と、食べ物への感謝、神様の創造した命への感謝を毎食ごとに覚えて祈ってゆきましょう。
まだ食前に祈っていないという方、例えば私はこんな風に祈っています。「神様、今日もみんなでごはんを食べれること感謝します。世界に平和と食べ物がゆきわたしますように」またカトリック教会ではこのような食前の祈りが紹介されています。「父よ、あなたのいつくしみに感謝してこの食事をいただきます。ここに用意されたものを祝福し、わたしたちの心と体を支える糧としてください」。私たちは食前の祈り、神様への感謝を改めて大切にしましょう。
そして、今日の午後は信徒会が行われます。パンとぶどうジュースをのむ儀式である主の晩餐について意見交換をする予定です。先日の濱野先生との学びによれば、この主の晩餐にも、神様からの食べ物、神様の創造への感謝という要素が含まれるそうです。私たちは主の晩餐でも、神様から食べ物が与えられていることに感謝しましょう。私たちにある食べる物も、飲むものも、着るものも、仕事も、家族も、友達も、命全体が神様からの恵みです。神様は私たちの必要をすべて満たしてくださる方です。今はまだそうではなくても、必ず満たされることを信じ、感謝しましょう。私たちは神様からのあらゆる収穫に感謝をしましょう。今日は聖書からイエス様が感謝している場面を見ます。その物語から、神様に収穫を感謝するということを考えたいと思います。
今日はマタイによる福音書15章32~39節をお読みいただきました。聖書にはこの4000人の食事と似た内容の、5000人の食事が記録されています。2つの似た伝承がある理由については諸説ありますが、1回の大人数の食事の出来事が別々に伝承されたという説が有力です。でも私はこの出来事が本当に2回か、それ以上あったのではないか、様々な場所で繰り返し起きていたのではないかと思っています。このような出来事は何度も繰り返し起きていて、それが聖書に2回記されたのです。私たちの食堂が何度も何度も寄付をもらって食事をすることができているように、きっとイエス様も何度も人々と、このような奇跡の食事をしたはずです。こひつじ食堂の体験からそう感じています。
今日まず注目をしたいのは、従っていた群衆の現実です。イエス様に従っていたのは、食べ物を持っていない人々でした。イエス様に従ったのは、仕事を中断しても大丈夫な経済的、時間的余裕のある人ではありませんでした。もう食べ物を何ももっていない。お金もない。行く当てもないという貧しい人が、イエス様に従ったのです。解散して家に帰って食べればよいとありますが、この群衆は家に帰れば食べる物があったのでしょうか?あるいは家そのものがあるのかどうかもわからない人でした。イエス様はこのような生活に困った人たちを追い返しはしませんでした。ここで一緒に食事をしようとしました。共に食事をするということは、人々との連帯を表明するという意味がありました。共に食事をすることは、一緒に生きてゆこうという、イエス様の意志の表れでした。
今日は特にイエス様の祈りに注目をしたいと思います。36節にはイエス様が「パンと魚を取り、感謝の祈りをとなえて、これを裂き、弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った」とあります。この言葉は主の晩餐の時に祈る定型文でもありますが、中でも注目したいのが、イエス様がここで食前の感謝の祈りを唱えたということです。
この食前の感謝の祈りはどのような祈りだったのでしょうか。しかし果たしてこの状況は感謝に値する状況だったでしょうか。4000人に対して、7つのパンと魚しかありません。私ならば神様に感謝よりも、不足を訴えたでしょう。神様もっと欲しいです、神様全然足りません、神様最低あといくつは必要です、そう願いが先立った祈りをしたでしょう。しかし、イエス様は違いました。イエス様はこんな少ないものに感謝の祈りを唱えたのです。どう考えても少なすぎる食べ物に感謝を示したのです。
イエス様が感謝したのは、まずこの食べ物を寄付してくれた人に対してでしょう。その善意と温かい気持ちに感謝をしたでしょう。パンと魚を寄付した人も、きっと裕福でたくさん持っていたわけではありませんでした。イエス様は寄付してくれた温かい気持ちに感謝をしました。そして人に対して感謝する同時に、それ以上にここで神様に対しての感謝を祈ったのです。
イエス様はここで何よりも神様に感謝の祈りを献げました。それはすべての恵みは神様からのものだからです。
そしてこの食べ物をよく見ます。それらの多くはもともと命でした。穀物も魚もすべては命でした。神様に創造された大切な命でした。イエス様はここで、神様がこの命を創造し、この命を私たちがいただくということに感謝をしたのです。
イエス様は地上に人間として生まれました。そしてイエス様は神様の創造した命を食べて生きたのです。イエス様は食べる前にその命に感謝して祈ったのです。この食べ物が、神様からの恵み・神様の創造した命であったからこそ、イエス様は神様に感謝したのです。イエス様はこのように神様に向けて、その命を食べることに深く感謝をしたお方でした。
私たちもすべての恵みが、すべての命が神様の元から来ると信じています。私たちに与えられた食べ物の多くも、神様が創造した命です。驚くべきことに私たちは神様が創造した命を食べて生きています。普段それを感じることはできないかもしれません。でも私たちが食前に祈るとき、それを思い出すことができます。私たちが誰かから食べ物をもらったとき、それを分かち合ったとき、私たちが命を食べていることを深く感じることができます。私たちは命に感謝して、神様に感謝して、それを頂きましょう。そのようにして私たちの命はつながっているのです。
イエス様が命に感謝して祈り、配ると、パンが増えたとあります。順序が大事でしょう。増えたから配ったのではありませんでした。少ないもの大切にし、分かち合った時、それが増えたのでした。この出来事は人々の中には強烈な記憶として焼き付けられ、聖書に記載されました。そしてこのような出来事はきっと1回だけではなく、何回も繰り返し起きたのでしょう。聖書には2回記されました。そして後に、これは私たちの主の晩餐へとつながってゆくことになります。
イエス様の感謝の祈りに目を向けました。私たちはただ収穫物に感謝するだけでなく、その背後にある生産者の努力に感謝をしましょう。そして神様からの豊かな恵み、私たちが神様の創造した命を食べていることに感謝しましょう。私たち自身の命に心から感謝しましょう。神様の愛が私たちのすべてを満たしてくださいます。私たちは食前の祈るたびにその神様の愛を深く感じましょう。食前の祈りを大切に続けてゆきましょう。私たちには足りないものがたくさんあります。でも神様は、私たちを必ず良いもので満たしてくださるお方です。私たちは収穫と命に感謝しましょう。お祈りをいたします。
「収穫感謝礼拝」マタイ15章32~39節
そこで、イエスは地面に座るように群衆に命じ、七つのパンと魚を取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。
マタイによる福音書15章35~36節
今日は10月16日の世界食糧デーに合わせてこの礼拝を、収穫感謝礼拝としています。私たちの教会で運営している「こひつじ食堂」に多くの食品が寄付されることに感謝しています。頂いた食べ物が、どこでどのように収穫されたのかを聞くと、食べ物の命を強く感じます。そして食べ物に命を感じると、感謝の気持ちが深くわいてきます。こども食堂はそのように食べ物と命に特別に感謝する場所です。
クリスチャンは食前に感謝の祈りをする習慣を持っています。私たちは食前の祈りで生産者の人に感謝すると同時に、それだけではなく、食べ物を神様が与えて下さったものとして感謝の祈りをします。キリスト教ではすべての命は神様が創造したものだと考えます。そして神様が創造した命を食べることを感謝して祈ります。食前の祈りは神様が私たちに命を与えて下さったことへの感謝の表現です。私たちはこの感謝と祈りを大切にしましょう。今日は聖書からイエス様が感謝している場面を見ます。その物語から、神様に収穫を感謝するということを考えましょう。
今日は特にイエス様の食前の感謝の祈りに注目します。この食前の感謝の祈りはどのような祈りだったのでしょうか。イエス様が感謝したのは、まずこの食べ物を寄付してくれた人に対してでしょう。そしてそれ以上に神様に対しての感謝を祈ったのです。それはすべての恵みは神様からのものだからです。
そしてこの食べ物をよく見ます。それらの多くはもともと命でした。穀物も魚もすべては命でした。神様に創造された大切な命でした。イエス様はここで、神様がこの命を創造し、この命を私たちがいただくということに感謝をしたのです。
イエス様は地上に人間として生まれました。そしてイエス様は神様の創造した命を食べて生きたのです。イエス様は食べる前にその命に感謝して祈りました。イエス様はこのように神様に向けて、その命を食べることに深く感謝をしたお方でした。
驚くべきことに私たちは神様が創造した命を食べて生きています。普段それを感じることはできないかもしれません。でも私たちが食前に祈るとき、それを思い出すことができます。私たちが誰かから食べ物をもらったとき、それを分かち合ったとき、私たちが命を食べていることを深く感じることができます。私たちは命に感謝して、神様に感謝して、それを頂きましょう。そのようにして私たちの命はつながっているのです。
私たちはただ収穫物に感謝するだけでなく、その背後にある生産者の努力に感謝をしましょう。そして神様からの豊かな恵み、私たちが神様の創造した命を食べていることに感謝しましょう。私たち自身の命に心から感謝しましょう。神様の愛が私たちのすべてを満たしてくださいます。私たちは収穫と命に感謝しましょう。私たちは食前の祈るたびに神様の愛を深く感じましょう。お祈りをいたします。
【全文】「こどもの声がする教会」マタイ7章9~12節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。こどもたちの声が私たちの礼拝の特徴です。今日もこどもたちと一緒に礼拝をしましょう。
10月から2か月間は地域活動と福音というテーマで宣教をしたいと思っています。時が過ぎるのは早く、2024年度も半分が過ぎました。今日は特に半年前に私たちが主題聖句とした聖書のみ言葉と「こどもの声がする教会」という標語をもう一度確認したいと思います。
私は自分のこどもには、できるだけいろいろな体験させ、良い教育を受けさせたいと思っています。体験や教育は一度受けると無くならないものです。こどもたちの将来にどんな困難があっても、貧しくなっても、それは無くなりません。体験と教育が人生を切り開いてゆくはずです。できるだけ良い体験をこどもたちして欲しいと思います。特に礼拝の体験は大切にして欲しいと思います。大きくなればそれぞれに優先したいことや事情がでてくるでしょう。今、こどもと共に礼拝できる時を大切にしたいと思います。
私自身のこどもに限らず、大人とこどもが共に福音を分かち合い、一緒に礼拝をできることは大人にもこどもにも素晴らしい体験です。こどもと共に礼拝をするとこどもたちの声が聞こえます。私たちはそのようなこどもの声がする礼拝をしましょう。
また自分や教会のこどもに限らず、地域のこどもたちにも良い物をたくさん残したいと思います。教会は地域のこどもたちにとって、今はまだこひつじ食堂の場所、ただごはんを食べる場所かもしれません。でもこひつじひろば、こひつじ食堂などを通じて多くのこどもたちが教会を訪れるようになりました。教会はこどもを通じて地域に関わり、地域の必要に応えることで、教会が地域と共にあること、神様が共にいるという証しをしています。今後もたくさんのこどもをこの教会に招き、地域のこどもたちのにぎやかな声が響きわたる教会にしてゆきましょう。これを続ければ、きっとそのうち何人かは大人になって教会に訪ねてくるはずです。心と体、魂の支えを必要とした時に、この教会を思い出すはずです。できるだけおいしい食事、思い出に残る食事と体験してもらいたいと思っています。この教会が続くことは、きっと地域の人の魂を支えることにつながるはずです。
もちろん今の時代のこどもだけが良ければ良いのではありません。私はこの教会を次の世代、こどもたちに受け渡し、ずっと続いていって欲しいと思っています。この教会は湘南・平塚の地で自由な福音理解を伝える場所として貴重です。例えばこの建物や教会の制度をできるだけ良い状態で、こどもに残したいと思います。この建物や運営の制度をこのままで次の世代に渡してゆくわけにはいきません。さまざまな修繕や改善が必要です。教育館は解体しなければいけません。次の世代に迷惑をかけたくないのです。私たちは教会を次の世代・こどもたちが安心して集い、礼拝し、運営できる場所として引き継ぎたいと思います。できるだけ良い物をこどもたちに残したいと思います。
教会には会堂修繕の必要やそれに伴う土地売却の課題など、様々な検討課題があります。でもきっとこれからの平塚教会は、こどもたちに関わり、未来に良い物を渡そうとする活動の中で、新たな道が示されてゆくでしょう。未来でも教会でこどもの声がするように祈り、働きましょう。このような思いで私たちは2024年度の標語を「こどもの声がする教会」としています。それには3つの意味があります。一つ目は礼拝でこどもの声がする教会、2つ目は地域のこどもの声がする教会、3つ目は未来でもこどもの声がする教会です。
私たちはこどもに少しでもよいものを与えたいという強い熱意があります。こどもと礼拝をしたい、地域のこどもとも関わりたい、未来のこどもにも良い物を渡したいという熱意があります。今日の聖書の言葉によれば、神様は私たちの熱意を上回る熱意をもっています。神様は私たちがこどもに良い物を与えようとする、それをさらに上回る良い物をくださると約束してくださっています。今日はこのことを聖書から確認し、これからの教会のこと、こどもの声がする教会のことを考えてゆきましょう。
今日はマタイによる福音書7章9~12節をお読みいただきました。9節~11節はとてもわかりやい話でしょう。この個所によれば、神様は私たちを愛し、良い物を準備してくださっているお方です。私たちがパンを欲しがるこどもにパンを、魚を欲しがるこどもに魚を与えるように、神様は必要なものを与えて下さるお方です。私たちがこどもと次の世代に熱意を持って良い物を残そうとするのと同じように、それ以上の思いで、神様は私たちに、こどもたちに良い物を準備してくださっています。私たちは必ずその恵みにあずかるのです。今は私たちには必要な物が不足しています。私自身もこの教会も足りないものがたくさんあります。きっとみなさんも同じでしょう。足りないことばかりです。でも神様は私たちに必要な物があれば、良い物を下さると約束をしています。私たちは“とりあえず”それを信じましょう。たくさんの良い物が私たちに備えられていることを期待し、もうしばらく信じましょう。神様の約束は今、様々な物が不足している私たちの希望です。
12節に目を向けます。11節までは私たちは神様から良い恵みを受けとる存在だと語られていました。表題にもあるとおり、求めるものが与えられること、良い物が神様に与えられることが語られていました。しかし12節では話の流れが大きく変わります。神様からの恵みを受ける話から、他者への実践を求める命令へと展開しています。「だから」の次には「〇〇しなさい」というイエス様からの命令が書かれています。それは「あなたのしてもらいたいことを、人にするように」という命令です。イエス様は神様が私たちに必ず良い物を与えてくださることを明らかにすると同時に、だからこそ、私たちこそ他者に良い物を与えるようにと命令しているのです。この「だから」が大切です。私たちは恵まれている「だから」他者に良い物を与えるのです。ここではそのような命令がされています。私たちはただ良い物を受け取るだけの存在ではないのです。恵まれているだけの存在ではないのです。イエス様は恵まれている、だからこそ良い物を他者に手渡してゆけと言われているのです。私たちはこの命令を実践しましょう。例えば私たちはこどもたちに一番良い物を、一番良い状態で渡してゆきましょう。イエス様はそれを私たちが他者になすべきことだと命令をしているのです。
「人にしてもらいたいことをしなさい」これは格言の様な言葉ですが、似た格言は世界中に伝わっています。しかし私たちが良く聞くのは「人にされて嫌なことは、自分もしない」ということかもしれません。聖書は「人にされて嫌なことをしない」からもっと踏み込んで、愛の実践を命令しています。嫌なことをしないだけではなく、人に良い物を与えなさいと命令しています。私たちは今よりもう一歩踏み出して良いものを誰かに渡してゆきましょう。
12節の最後は「これこそ律法と預言者である」とあります。これは、ほかならぬ他者に良い物を渡すことが、次の世代に良い物を渡してゆくことが、律法の実践であるという意味です。イエス様は聖書の教え律法を、難しい戒律とは考えていませんでした。隣人に良い物を渡してゆく、隣人に良い事をしてゆく、この愛の実践をしないさいという命令がイエス様の律法理解です。イエス様の律法理解はこの点で一貫しています。他にもイエス様はマタイ22章で律法の学者に律法でどれが最も重要な教えかを聞かれてこう答えています。第一に神を愛すること。心を尽くし精神を尽くし、思いを尽くし神を愛すること。そして第二に、隣人を自分と同じように愛することと答えています。22章でもここと同じ指針が指し示されています。
まとめます。私たちには不足するものばかりです。自分の人生のことも、こどものことも、この教会のことも足りないものがたくさんあって、とても心配です。私たちは今の自分やこどもや教会に必要なものを祈り求めます。生きる糧、心の支え、魂の支えになるものを神様に求めます。神様は私たちを愛し、大切に思っています。だからきっと私たちには良い物が与えられてゆくでしょう。そう信じています。そして「だから」私たちは隣人と必要なものを分かち合ってゆきましょう。神が私たちに良い物を備えて下さっているように、次の世代が必要としているものを、できるだけよい状態で渡してゆきましょう。それが愛なのではないでしょうか。
私たちはこの主題聖句と、「こどもの声がする教会」という標語をもって歩んでいます。私たちは礼拝をするとき、神様が私たちに良い物を準備していることを思い出すことができるでしょう。そして特にこどもと共に礼拝をするとき、私たちもこどもに精一杯の良い物を渡してゆこうという気持ちになるでしょう。だから私たちはこどもの声を聞きながら礼拝をしましょう。
私たちは一緒に祈りましょう。教会の仲間の必要が満たされるように、仲間に良い物が与えられるように祈りましょう。そして私たちの教会は地域のこどものためにこの教会を開いてゆきましょう。私たちが与えられている良い物を、地域と、地域のこどもと分かち合ってゆきましょう。そしてこの教会を未来に残していけるように、ともに考えてゆきましょう。お祈りします。
「こどもの声がする教会」マタイ7章9~12節
だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。
マタイによる福音書7章12節
2か月間、地域活動と福音というテーマで宣教をします。こどもには、できるだけいろいろな体験させたいと思います。大人とこどもが共に礼拝することは双方にとって素晴らしい体験です。こどもと共に礼拝をするとこどもたちの声が聞こえます。私たちはそのようなこどもと共にする礼拝をしましょう。また地域のこどもたちにも良い物をたくさん残したいと思います。多くのこどもたちが教会を訪れるようになり、きっとそのうち何人かは大人になって教会に訪ねてくるはずです。地域のこどもの声が響く教会してゆきましょう。そしてこの教会を次の世代も安心して集い、礼拝し、運営できる場所として引き継いでゆきましょう。できるだけ良い物をこどもたちに残しましょう。
これからの平塚教会は、こどもたちに関わり、未来に良い物を渡そうとする活動の中で、新たな道が示されてゆくでしょう。このような思いで私たちは2024年度の標語を「こどもの声がする教会」としています。
私たちはこどもに少しでもよいものを与えたいという強い熱意がありますが、今日の聖書の言葉によれば、神様は私たちの熱意を上回る熱意をもっています。
今日は私たちの年間主題聖句マタイ7章9~12節を読みます。今は私たちには必要な物が不足しています。でも神様は良い物を下さると約束をしています。私たちはそれを信じましょう。
12節からは神様からの恵みを受ける話から、他者への実践を求める命令へと展開しています。私たちはただ良い物を受け取るだけの存在ではありません。恵まれている、だからこそ良い物を他者に手渡してゆけと言われているのです。私たちはこの命令を実践しましょう。例えば私たちはこどもたちに一番良い物を、一番良い状態で渡してゆきましょう。「人にされて嫌なことは、自分もしない」よりもう一歩踏み出して、良いものを渡してゆきましょう。
イエス様の律法理解は一貫しています。同じマタイ22章でも第一に神を愛し、第二に、隣人を自分と同じように愛することを勧めています。ほかならぬ他者に良い物を渡すことが、律法の実践なのです。
私たちはこの主題聖句と「こどもの声がする教会」という標語をもって歩んでいます。私たちは礼拝をするとき、神様が私たちに良い物を準備していることを思い出すことができるでしょう。そして特にこどもと共に礼拝をするとき、私たちもこどもに精一杯の良い物を渡してゆこうという気持ちになるでしょう。だから私たちはこどもの声を聞きながら礼拝をしましょう。教会の仲間の必要が満たされるように祈りましょう。地域のこどものために祈りましょう。教会を未来に残していけるように祈りましょう。お祈りします。
【全文】「教会とパレスチナ」イザヤ62章1~5節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝に招かれたこと、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこども達の平和の声を聞きながら、一緒に礼拝をしましょう。8月9月は平和について考えてきました。今日は平和について考えるシリーズの最終回です。これまでイザヤ書を2か月間読み、様々な面から平和について考えてきました。平和についてどんなことをお感じになったでしょうか?今日はイスラエルとパレスチナの戦争と私たちの教会との関係を考えます。そのことを通じて、私たちがどのような信仰を持ち、平和を目指しているのかを考えたいと思います。
イスラエルとパレスチナの戦争について、日本のキリスト教の教会は比較的穏健で、極端にイスラエルを支持する教会は少ないように感じます。しかし世界のキリスト教信者の中には、イスラエル国を積極的に応援する人々が多くいます。いわゆる福音派とか、キリスト教右派と呼ばれたりするグループの中に、イスラエルを積極的に支持する人が多くいます。イスラエル側に立つという立場をはっきりと表明する人がいます。多くの場合、その人たちがイスラエルの側に立つと表明する背景には信仰があります。その信仰は聖書の権威を強調する信仰です。私たちも聖書には権威があると思います。しかし畏敬の念や大切にする気持ちだけではなく、聖書に書いてあることを、その文字通りに受け取っていくことを重視する信仰を持っている人がいます。たとえば聖書の中に、神はイスラエルを祝福している、この土地をユダヤの人々に与えると約束しているという記述があれば、それをそのまま理解します。それはイスラエルによるパレスチナ地域の軍事的支配を支持するという解釈につながってゆきます。このような考えはシオニズムとも呼ばれます。私たちの教会の身の回りでは少ないかもしれませんが、アメリカでは大きな非常に大きな勢力です。
私たちの教会はどうでしょうか。イスラエルと、パレスチナのどちらの側に着くでしょうか?おそらく私たちの聖書理解ではどちらの側にもつかないというのが答えでしょう。戦争をしている、殺し合っている二つの集団がいます。私たちの聖書理解では、神様はどちらか一方の正しいとされる方に、勝利を約束する方ではありません。神様は暴力で物事を決めようとするどちらのグループも誤りとし、そのような暴力を最も嫌われるお方です。私たちもイスラエルとパレスチナの双方が間違っていると考えます。
この問題が複雑なのは、イスラエルにはユダヤ教徒が多く、パレスチナにはイスラム教徒が多いという宗教的な背景もあります。しかしキリスト教の教会は傍観者ではいけません。歴史的にユダヤ教徒を迫害したのはキリスト教国であり、後にこの土地はユダヤ人のものであると誤った約束をしたのもまたキリスト教国でした。キリスト教はまたどちらかを応援することで、またこの問題を複雑にしようとしています。どの宗教、信仰を持つにせよ、人間の愚かさは普遍的です。私たちは宗教を超えて平和を実現することができるのでしょうか。私たちキリスト教の教会はどのようにこの平和に関わることができるでしょうか。私たちはどのように聖書を読むのでしょうか?この問題から考えたいと思います。
私たちには聖書を文字通りではなく、歴史や文脈に応じて解釈することが求められます。そして、強い者ではなく、傷ついた人々や虐げられている人々に目を向けて聖書を読むことが重要です。神様が彼らのそばにいることを感じるでしょう。今日の聖書の個所を一緒にお読みしましょう。
今日はイザヤ書62章1~5節までをお読みいただきました。当時イスラエルの民は戦争に負け、遠い場所に強制移住をさせられていました。シオンとはエルサレムのことです。この62章は、強制移住が終わりようやく故郷に戻ることができた時代の言葉です。強制移住を終え、王様から自分たちの故郷に帰還する許可がでました。人々は希望をもってイスラエルに戻ります。しかし町は戦争で荒廃し、ボロボロになっていました。戦争に振り回された後の、新しい生活への期待と不安の中に届けられた神様の言葉です。
ある立場の人たちは、この個所は神様が現在のイスラエル国を支持していると解釈します。神様はイスラエルのために黙っていないという言葉を、パレスチナとイスラエル国の戦争において、イスラエル側が正しいという根拠にしています。諸国の民はあなたの正しさ知るようになるとは、中東や世界の各国がイスラエル国の方が正しいと認めるようになると解釈をしています。聖書を文字通り解釈することで、神様はイスラエルの側に立つと考え、パレスチナへの軍事的支援が正しいことと解釈されています。
しかし私たちは聖書を現代の国家イスラエル国に結び付けて読むことはありません。この話を、イスラエル国にではなく、私たち人間全体に向けて語られている言葉として受け止めます。そこが大きな解釈の違いでしょう。私たちはこの個所を現在のイスラエル国とは結びつけず、人間全体への語り掛けと理解します。私たちはこの個所をどう理解したら良いでしょうか。私は戦争に疲れ果てた人々の視点から理解したいと思います。これまでに考えてきた神様の平和に照らして理解したいと思っています。この神様の言葉を戦争に傷ついた人への励ましの言葉、希望の言葉として受け取りたい、今日はそのような視点で読みたいと思います。
1節にある「わたし」とは神様の事です。神様は決して口を閉ざさない、決して黙さないお方です。「彼女」とはイスラエル国家だけを指すのではなく、私たち人間全体のことです。神様は一部の人間だけが輝き、他の大勢の人間が暗く沈んで生きる世界を望んではいません。神様はすべての人間が松明のように、明るく光り輝くことを願っておられます。それが叶うまで、黙っていない方なのです。神様は暗さの中にいる人々のために光を、み言葉を注いでくださるお方です。人間から徹底的に光を奪うのは戦争です。人間から光、希望、夢、命を奪ってきたのが戦争です。しかし神様の言葉が戦争に光を照らします。人間同士の戦争で傷ついた人にとって、最も強い心の支えになるのは、神様の言葉です。神様の言葉と光はいつも私たち全員に注ぎます。その神様の言葉は、止まることのない平和の言葉です。神様は平和に向けて沈黙しないお方です。神様はどちらの側にもつかず、すべての人の平和に向けて黙っていないお方です。神様は私たちに平和を語り続けているお方です。
2節には「諸国の民はあなたの正しさを見る」とあります。語られているのは私たちが正義で、向こうが悪だということではありません。語られているのは、神様の正しさを全員が見るようになるということです。人間の決める正しさ、人間の決める平和はいつも不完全です。人間は自分たちの力で正しさと平和を実現することができないのです。今は不条理で、不合理で、不平等で、戦争があります。しかし完全である神様の正しさと、神様の平和の実現は必ず全員に来ます。誰一人漏れることなく来るのです。人間にはどうしても実現できない平和な世界が来るのです。神様が全員に正しさと平和を起こしくださる時を「終末」と呼びます。終末とは世界が破滅する時や悪人に裁きが下る時ではなく、神様の正しさと平和が全地を覆う時です。その時、世界は新しい名前で呼ばれるような、新しい世界が始まります。神の希望が、光が、平和が全地にあまねく満ち溢れる時です。この個所はその終末、完全な平和が、私たちには必ず来る、全員がそれを見る日が必ず来ると言っています。これは平和の約束です。あなたたちには必ず平和がくるということ。私たちはその終末の時に希望を持っています。
3節は傷ついた人々が回復される約束です。「あなた」とは、戦争に傷ついた人々のことです。あなたのような傷ついた人がやがて冠、王冠となるとあります。冠とは、誰が王であるか、誰が一番偉いのかを示すしるしです。つまりこれは戦争で傷ついた人々によって王が立てられるということです。傷ついた人が王を指名してゆくのです。それこそが平和の王の在り方です。戦争の勝利が王冠になるのではありません。王を建てるのは戦争で傷ついた庶民だということです。神様は戦争に傷ついた人たちが平和を求めて新しい王を建てることを望んでいるのです。私たちも文字通り受け取るのではなく、傷ついた人から戦争と、平和と、新しい王を見つめてゆくことが大事です。
4節と5節、人は誰かに捨てられたように思うことがあるかもしれません。でも決して神様の前において、人は見捨てられることがありません。神様は私たちと一緒にいてくださいます。神様が結婚したパートナーのように私たちと共にいてくださるのです。人の結婚にはうまくいかないこともあります。不完全なもので、平和とはいかないものです。しかし神様は違います。神様は私たちとずっと共にいて下さるお方です。
私たちは聖書から平和に生きる方法を聞いてきました。2か月間どのような平和を考えたでしょうか?神様は平和について、黙っていないお方です。神様は口を閉ざさず、平和を語り続けて下さるお方です。私たちは神様の正しさと平和を追い求め続けてゆきましょう。私たちも平和の大切さを語ることを止めないでいましょう。私たちは戦争を見る時、傷ついた人に目を向けましょう。傷ついた人が平和の王を選ぶ世界にしてゆきましょう。私たちの世界には神様が共にいてくださいます。私たちは不完全です。でも神様の平和を求めましょう。これからも諦めずに平和を祈ってゆきましょう。お祈りします。
「教会とパレスチナ」イザヤ62章1~5節
シオンのために、わたしは決して口を閉ざさず
エルサレムのために、わたしは決して黙さない。イザヤ書62章1節
8月9月は平和について考えています。イスラエルとパレスチナの戦争について、世界のキリスト教信者の中には、イスラエル側に立つという立場をはっきりと表明し、積極的に応援する人々が多くいます。背景には聖書に書いてあることを、その文字通りに受け取っていくという信仰があります。たとえば聖書の中に、神はイスラエルにこの土地を与えると約束しているという記述があれば、それをそのまま理解します。いわゆるシオニズムはアメリカで非常に大きな勢力です。
私たちの聖書理解では、神様は暴力で物事を決めようとするどちらのグループも誤りとし、そのような暴力を最も嫌われるお方です。私たちはイスラエルとパレスチナの双方が間違っていると考えます。私たちには聖書を文字通りではなく、歴史や文脈に応じて解釈することが求められます。そして、強い者ではなく、傷ついた人々や虐げられている人々に目を向けて聖書を読むことが重要です。
聖書を読みましょう。この個所を文字通り、現代のイスラエル国に結び付けて読むのではなく、私たち人間全体に向けて語られている言葉として受け止め、戦争に疲れ果てた人々の視点から理解しましょう。
1節にある「わたし」とは神様の事です。神様はすべての人間が松明のように、明るく光り輝くことを願っておられます。神様はそれが叶うまで、黙っていないお方です。人間から徹底的に光を奪うのは戦争です。人間同士の戦争で傷ついた人にとって、最も強い心の支えになるのは、神様の言葉です。神様の言葉と光はいつも私たち全員に注ぎます。その神様の言葉は、止まることのない、平和の言葉です。
2節、人間の決める正しさと平和はいつも不完全です。しかし完全である神様の正しさと平和の実現はやがて必ず全員に来ます。神様が全員に正しさと平和を起こしてくださる時を「終末」と呼びます。終末は平和の約束です。必ず平和がくるということ。私たちはその終末の時に希望を持っています。
3節は傷ついた人々が回復される約束です。これは戦争で傷ついた人々によって王が立てられるということです。傷ついた人が王を指名してゆくのです。それこそが平和の王の在り方です。平和の王を建てるのは戦争で傷ついた庶民なのです。
4節と5節、人は誰かに捨てられたように思うことがあるかもしれません。でも決して神様の前において、人は見捨てられることがありません。
私たちは聖書から平和に生きる方法を聞いてきました。神様は平和について、黙っていないお方です。神様は口を閉ざさず、平和を語り続けて下さるお方です。私たちは神様の正しさと平和を追い求め続けてゆきましょう。私たちも平和の大切さを語ることを止めないでいましょう。私たちは戦争を見る時、傷ついた人に目を向けましょう。傷ついた人が平和の王を選ぶ世界にしてゆきましょう。これからも諦めずに平和を祈ってゆきましょう。お祈りします。
「『傍観者』にならないで」ルカ10章25~37節
彼は答えた。「『心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のように愛しなさい』とあります。」
ルカによる福音書10章27節
私はバブル期に証券会社で働き、この世ですべてを失った経験から神様に出会い、今は東京バプテスト神学校神学専攻科で学んでおります。また同時に、これからの教会牧会には心理学が大変重要になると感じ、並行して通信制大学で心理学を学んでいます。心理学を学んでいると、聖書と結びつく箇所がたくさんあります。今日の聖書の箇所である「善いサマリア人のたとえ話」もそのような箇所の一つです。宣教題にしました「傍観」とは「岩波国語辞典」によると、「(手出し・口出しをせず)その場でながめること。当事者でないという立場・態度で見ること。」とあります。追いはぎに襲われた人を助けなかった祭司やレビ人は正に「傍観者」でした。この話はたとえ話ですが、今日は1964年に実際にアメリカで起こった「キティ・ジェノヴィーズ事件」という多くの人の見ている前で起こった凶悪犯罪を参照し、なぜそのようなことが起こるのか、ということを聖書の視点と心理学の視点から見てまいりたいと思います。
私たちも、日常生活の中で誰かの助けを必要としている人に遭遇することがあります。しかし、多くの人はサマリア人のように行動できるでしょうか?「他にも人がいるから大丈夫だろう」「急がなければ大切な用件に遅刻しそうだ」などの理由で見過ごしてしまうことはないでしょうか?
このような心理学における「傍観者効果」という現象は、多くの人が見ている状況で誰も行動を起こさない心理状態を言います。これは責任が分散されることや、誰かが助けるだろうという思いから、行動を躊躇してしまう等の原因で起こります。
このサマリア人の行動は、単なる親切心に留まらない愛の実践です。元々、ユダヤ人とサマリア人は仲が悪かったのですが、イエス様の時代は特にひどかったようです。しかしこのサマリア人はその様な自分の感情や立場を度外視して「その人を憐れに思い」助けるという、まさにキリストの愛の姿を示しました。
イエス様は、このたとえ話を通して「隣人」とは元々備えられているものではなく、自分から作るものであると、そしてそのためにはどのように行動すれば良いかを教えてくださいます。律法学者たちは「隣人」を同族や同胞と限定的に考えていましたが、イエス様は民族や宗教を超えてすべての人が「隣人」と成り得るのだ、と教えてくださいました。
私ももう「傍観者」にはなりたくありません。心理学は、このような聖書の中にある人間の心の奥底を捉えた深い真理を科学で証明しようとする学問である、ということを改めて実感しています。
また教会は、愛の実践を促し、互いに支え合う共同体です。教会で経験した愛を通して、私は自分自身が「新しい命」を得るという経験をしました。それは、教会の人々が私の「傍観者」とならず、愛を示してくださり、私を「隣人」として、具体的に行動してくださったおかげなのです。(堀端洋一)
【全文】「主のあしあと」イザヤ書46章1~4節
わたしはあなたたちの老いる日まで 白髪になるまで、背負って行こう。
わたしはあなたたちを造った。わたしが担い、背負い、救い出す。
イザヤ書46章4節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できることを神様に感謝します。私たちは「こどもの声がする教会」です。こどもの声は私たちに命の存在を教えてくれる平和の象徴です。今日もこどもたちの声を聞きながら礼拝をしましょう。今日は礼拝の中で高齢者祝福祈祷の時を持ちます。平和というテーマからは少し離れるかもしれませんが、示された聖書からお話をしたいと思います。
子どもたちの声が平和の象徴だと言っているように、高齢者の方々の命もまた、深い平和の証しです。悲惨な戦争を体験し誰よりも平和の大切さを知っている命です。戦争の後の混乱を生かされてきた命です。高齢者も平和のしるしです。こどもと高齢者の命は平和のしるしです。小さな命も、高齢者の命もその時その時、神様がいつも導いてくださいます。今日は神様が私たちの人生を導いてゆくということについて考えてゆきたいと思います。「あしあと」という有名な物語があります。聖書の中の話ではありませんが、神様の愛と支え、導きを良く表している、美しいたとえ話です。
「あしあと」
ある夜、わたしは夢を見た。わたしは、主とともに、なぎさを歩いていた。暗い夜空に、これまでのわたしの人生が映し出された。どの光景にも、砂の上にふたりのあしあとが残されていた。ひとつはわたしのあしあと、もう一つは主のあしあとであった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、わたしは、砂の上のあしあとに目を留めた。そこには一つのあしあとしかなかった。わたしの人生でいちばんつらく、悲しい時だった。このことがいつもわたしの心を乱していたので、わたしはその悩みについて主にお尋ねした。「主よ。わたしがあなたに従うと決心したとき、あなたは、すべての道において、わたしとともに歩み、わたしと語り合ってくださると約束されました。それなのに、わたしの人生のいちばんつらい時、ひとりのあしあとしかなかったのです。いちばんあなたを必要としたときに、あなたが、なぜ、わたしを捨てられたのか、わたしにはわかりません。」主は、ささやかれた。「わたしの大切な子よ。わたしは、あなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みの時に。あしあとがひとつだったとき、わたしはあなたを背負って歩いていた。」
この話は聖書の話ではありませんが、私たちの神様のことを良く表しています。私たちはつらく悲しい時、神様が助けてくれないで、一人で人生を歩んでいるように思うかもしれません。でもそれは違います。私たちがつらくて一人で歩いていると思う時、神様が私たちを背負って歩いてくれているのです。私たちの人生に一つのあしあとしかなかったら、それはきっと神様が私たちを背負ってくださったしるしなのです。聖書にはいくつか、この話のモチーフになるような箇所があります。今日の個所も神様が私たちを背負うというイメージです。今日の聖書箇所を見てゆきましょう。
今日はイザヤ書46章1~4節をお読みいただきました。イザヤ書は激しい戦争の時代に書かれた書物です。特にこの46章が書かれたのは、イスラエルの人々がバビロニア帝国という大国との戦争に負けた後だったと言われます。戦争に負けた後、人々は強制的に移住させられました。数百キロも離れた場所に、手を縛られて、歩いて連れていかれ、知らない土地に強制的に住まわされたのです。今も昔も、戦争に負けた国の人間は動物や物のように扱われます。イスラエルの人々は、神はどこに居るのかと嘆き悲しみながら歩いたでしょう。
1節にはベルやネボとあります。ベルやネボとはバビロニア帝国で信仰されていた神々のことです。バビロニア帝国では、この神々が天地を創造したと信じられていました。人々はその神々を石や木で掘り、街中に飾っていました。聖書ではこのように、神の姿を石や木で掘って拝むことが禁止されています。これを偶像崇拝の禁止と呼びます。日本では仏像がたくさんあり、多くの人がそれに手を合わせて拝んでいます。しかしキリスト教ではそういった神の像を造って、拝んではいけないと言われます。なぜだと思うでしょうか?
一つの理由は、神様の願い・御心を、自分の欲望と混同しないようにするためと言えるでしょう。人間が神様の形を掘り出せば、神様を人間の理想を詰め込んだ姿にするでしょう。かっこよくて、強くて、背が高い、きらびやかな姿にするでしょう。そうすれば神様は人間の思い通りの姿になります。そして掘り出して便利なことは、神様をどこにでも好きな場所に持ち出せるということです。例えば王様のところに置けば、王様と神が近い存在だと表すことができます。戦争に神の像を連れて行けば、神様が自分たちの戦争を応援していることになります。あるいは小さくしてポケットに入れればどこにでも連れて行けるようになります。
しかし注意していないと、神様を人間の思い通りになる存在にしてしまうでしょう。人間は神様のことを自分たちの都合に合わせて姿や形、大きさを変え、私たちの意のままの存在にしてしまうのです。どこにでも持っていけるのは聖書の神様ではありません、神様はそのように私たちの思い通りに、願いをかなえてくれる存在ではありません。だから聖書は神様の姿形を造って拝むことを禁止しています。
聖書によれば神様は私たちが見えていなくても、いつも一緒にいる存在です。だから形や像にする必要がないのです。形にしてはいけないのです。神様は私の願いごとをかなえてくれるのではないのです。神様の願いがこの地上でかなうために、私たちは用いられるのです。だから神様を形にする必要がないのです。それが聖書の信仰です。見えないけれど確かに共にいて下さるのが神様です。
イスラエルの人々は戦争に負け、異国に連れていれ、異教の神の像を見て、もういちど自分たちの信仰を問い直したはずです。そしてなぜ自分体がそれを造らないのかを考えたはずです。そして気づいたでしょう。私たちの願いは叶わなかったけれど、きっと神様は私たちに良い計画を準備してくださっているはず。私たちの願いとは違うけれど、神様の姿・形は見えないけれど、神様はいつも一緒にいてくれるはず、彼らはそう思ったでしょう。そう思わなければ悲しみに耐えることができなかったでしょう。
そのときイザヤを通じて神様の言葉が響いたのです。1節にはこうあります。今形にされているバビロンの神は、きっといつか他の荷物と同じように運ばれていくだろうと。疲れた動物があの神の像をひっぱることになるだろうと言っています。
姿・形に彫り出され動物にひいてゆかれる神は、聖書の神の特徴と大きく違います。聖書の神様は人間や動物に担ぎ上げられて、運ばれてゆく神様ではありません。聖書の神様はその反対です。聖書では神様が人間を背負うのです。私たちや動物が神を背負うのではありません。神様が私たちを背負うのです。それが聖書の神様の特徴です。
聖書の神様は私たちを背負う神様です。神様が私たちの人生を背負っています。私たちは神様の背中に乗って、運ばれている存在なのです。そして3節にはそれは生まれる前からそうだとあります。「あなたは生まれた時から負われ、胎を出た時から担われてきた」とあります。神様は生まれた時から私たちを背負っているということです。4節、そしてそれは髪の毛が真っ白になるまで続くのです。神様は生まれた時から、死ぬ時まで、そして死んだ後も私たちを背負ってくださるのです。それが聖書の神様です。神様が私たちを背負うとはどんなことでしょうか。それは私たちだけでは前に進めない時、神様が私たちを支え導いてくれるということです。
それは先ほど紹介した「あしあと」の話のようです。神様は私たちが運ぶのではありません。神様が私たちを背負って運んでくださるのです。私たちが前に進めない時、神様が私たちの心と魂を支えて、背負って歩んでくださるのです。それが私たちの神様です。今日の聖書の個所もそれを伝えようとしています。
私たちの人生はひとりでは生きていけないものです。そして自分ひとりでは背負いきれないものがあります。家族のこと、仕事のこと、健康のこと、自分の心のこと、自分一人ではどうにもできず、背負いきれず前に進むことができない時があります。私たちの人生にはそのような重荷や悲しみ失敗があります。
私たちの神様はその時、確かに私たちを支えてくださるお方です。私たちが立てない時、支えて、背負ってくださるお方です。私たちはその神様を支えにして生きます。心の支え、魂の支え、生活の支えとして生きます。神様によって人生が願ったとおりになるわけではありません。でも私たちは神様が支え導いてくれると信じながら歩むのです。つらい時は神様が一緒にいたことがわからないものです。振り返ってもひとりだったように感じるものです。でも本当は神様はずっと私たちの人生に、共にいて下さるのです。
このことをこどもたちにも伝えたいと思っています。これからずっと神様が一緒に歩き、つらい時あなたを背負ってくれるのだと。そして高齢者のみなさんと分かち合いたいとも思っています。みなさんの人生はきっとそうだったはずです。振り返ってみると一人のように思える時があったかもしれません。でもその時も神様がみなさんと一緒に歩み、皆さんを背負って、歩いてくださっていたのです。そして神様はこれからもみなさんを背負って歩いてくださるのです。私たちにはこのように神様が共にいて下さいます。だから安心してこれからも歩んでゆきましょう。お祈りします。
「主のあしあと」イザヤ書46章1~4節
わたしはあなたたちの老いる日まで 白髪になるまで、背負って行こう。
わたしはあなたたちを造った。わたしが担い、背負い、救い出す。
イザヤ書46章4節
礼拝の中で高齢者祝福祈祷の時を持ちます。今日は神様が私たちの人生を導いてゆくということについて考えます。「あしあと」という有名な物語があります。この話は聖書の話ではありませんが、神様の愛と支え、導きを良く表している美しいたとえ話です。私たちはつらく悲しい時、神様が助けてくれないで、一人で人生を歩んでいるように思うかもしれません。でも神様は私たちを背負って歩いてくれているのです。聖書にはいくつか、この話のモチーフになる箇所があります。
イザヤ書46章1~4節の時代、イスラエルの人々はバビロニア帝国との戦争に負け強制移住させられました。移り住んだ先にはバビロニアの神々が石や木で掘られ、街中に飾ってありました。
聖書は神の姿を石や木で掘って拝むこと(偶像礼拝)を禁止しています。一つの理由は、神様の願い・御心を、自分の欲望と混同しないようにするためです。人間が神様の形を掘り出せば、神様を人間の理想を詰め込んだ姿にします。どこにでも好きな場所に持ち出します。しかし注意していないと、神様を人間の思い通り、意のままの存在にしてしまいます。神様はそのように私たちの思い通りに、願いをかなえてくれる存在ではありません。だから聖書は偶像礼拝を禁止しています。
聖書によれば神様は私たちが見えていなくても、いつも一緒にいる存在です。見えないけれど確かに共にいて下さるのが神様です。姿・形に彫り出され動物にひいてゆかれる神は、聖書の神の特徴と反対です。聖書では神様が人間を背負うのです。
神様が私たちの人生を背負っています。私たちは神様の背中に乗って、運ばれている存在なのです。3節にはそれは生まれる前から死ぬ時までだとあります。そしてきっと死んだ後も私たちを背負ってくださるのです。それが聖書の神様です。
神様が私たちを背負うとは私たちだけでは前に進めない時、神様が私たちを支え導いてくれるということです。それは先ほど紹介した「あしあと」の話のようです。
私たちの人生はひとりでは生きていけないものです。私たちの神様はつらい時、確かに私たちを支えてくださるお方です。私たちはその神様を支えにして生きます。心の支え、魂の支え、生活の支えとして生きます。神様によって人生が願ったとおりになるわけではありません。でも私たちは神様が支え導いてくれると信じながら歩むのです。
このことをこどもたちにも伝えたいと思っています。これからずっと神様が一緒に歩き、つらい時あなたを背負ってくれるのだと。そして高齢者のみなさんと分かち合いたいとも思っています。みなさんの人生もきっとそうだったはずです。私たちにはこのように神様が共にいて下さいます。だから安心してこれからも歩んでゆきましょう。お祈りします。
【全文】「平和のために行動をしよう」イザヤ書40章1~8節
谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。
険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。 イザヤ書40章4節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。こどもたちの声は平和のしるしです。今日もこどもたちの声に包まれながら礼拝をしてゆきましょう。
8月・9月は平和について考えています。今日は沖縄の伊江島という小さな島から平和の本質を考えたいと思います。平和とは単に戦争が無い状態のことを指すのではありません。もっと深い意味を持っています。平和とは戦争がないことに加えて、もっと人々が自由で、平等な様子を言うのだということを考えたいと思います。
1945年、沖縄ではアメリカ軍との激しい地上戦が繰り広げられました。なかでも伊江島では激しい戦闘が行われました。伊江島の人々は日本軍から人間扱いされませんでした。住民は日本軍に箱型爆弾を背負わされ、上陸した戦車への特攻を命じられました。逃げる住民も米英は鬼畜だと教えられ、投降せず集団自決を強制されました。そのような激しい戦いがあったのが伊江島です。
戦争が終わり伊江島は平和になったでしょうか?そうではありませんでした。今度はアメリカ軍から人間扱いされません。アメリカ軍は占領した伊江島に爆撃の練習をするための飛行場を作ることにしました。住民たちは反対をしますが、うその契約書にサインをさせられ、アメリカ軍は土地を奪いました。アメリカ軍は接収に反対する住民がまだ住んでいる家をブルドーザーで壊してゆきました。住民たちにはほとんど補償はないまま、畑は飛行場にされ、自分の畑に入れば射殺されるか、爆弾が落ちて来るという状況でした。家と畑を奪われた住民たちは、生きるためにソテツという猛毒の草を食べ、米軍の落とした不発弾を拾って鉄くずを売って暮らしていました。不発弾が爆発して命を奪われる人もたくさんいました。伊江島は戦争が終わった後も爆弾が身近でした。戦争中は爆弾から逃げていた人々は、戦争が終わって今度は鉄くずを求めて爆弾を追いかけました。人々の生活は戦争中は日本軍によって、戦後はアメリカ軍によって貧しくされ続けたのです。
アメリカ軍の強引な土地接収に抗議運動が行われるようになりました。抗議運動を率いた一人に阿波根昌鴻という人がいました。彼はクリスチャンでもあり、沖縄のガンジーと呼ばれた人です。彼は非暴力でアメリカ軍と対峙することにしました。伊江島は戦争が終わってもまだ平和ではありませんでした。阿波根昌鴻たちは暴力を使わずに平和を実現しようとしました。その活動のひとつに「あいさつさびら」があります。沖縄の言葉で「あいさつしようね」という意味です。畑も家も奪っていくアメリカ軍は、自分たちのことを同じ人間だと思っていないはずだ。だからまず自分たちが同じ人間であることを伝えようとしました。「おはようございます」「こんにちは」と笑顔で挨拶する「あいさつさびら」はお互いが同じ人間同士だと伝えるための平和的な抗議運動として行われました。他にも様々な非暴力運動が行われました。アメリカ軍と何かを話す時は手に何も持たないことにしました。座って話をし、耳より上に手を挙げない、相手の悪口は言わないことをという活動をしました。
それでも困窮が改善しない彼らは「乞食行進」を始めました。乞食・托鉢をしながら沖縄の本土を行進し、その実情を訴えたのです。乞食・托鉢をするのは恥ずかしい事です。恥です。でも彼ら気づきます。自分達が乞食をすること自体が恥なのではなく、本当は自分たちに乞食をさせるアメリカ軍、非人間的行為、基地と武器こそ人間の恥なのだと気づきました。伊江島の人々の乞食行進はやがて沖縄各地の土地返還運動、本土復帰運動へとつながってゆきました。
伊江島の事を短く紹介しました。このことから平和について考えます。伊江島は戦争が終わって平和になったでしょうか?まったく平和は訪れていません。平和とは人々の権利が守られ、自由に平等に生きてゆける状態のことです。伊江島・沖縄はその意味で戦争が終わっても平和ではありません。
沖縄の基地問題はいまもまだ解決していないどころか、新たな基地が作られようとしています。戦争が終われば平和なのではありません。平和とは人々に自由と平等が与えられている状態です。平和を実現する行動とは、伊江島の人々のように、戦争に反対し自由と平等に向けて働いてゆくことです。
その平和は聖書の平和と共通しています。聖書の平和の概念もまた、戦争が無い状態ではありません。聖書における平和の概念は戦争がない、そしてさらにすべての人に自由と平等が保障されている、それが実現されてゆく様子です。神様の平和は不平等と抑圧の解消を指し示しています。今日の聖書からその平和を見てゆきましょう。
イザヤ書40章をお読みいただきました。この個所はイスラエルが戦争に負けた後、人に向けられた神様の言葉です。人々は望まない戦争を戦わされ、財産、土地、家族を失いました。戦争が終わった後もそれが回復するわけではありません。戦争が終わってもまだ平和ではなかったはずです。戦争が起こした苦痛が人々を苦しめていました。そこに神様の声が響いたのです。神様は平和の意味を教え、平和の約束を私たちに下さっています。その言葉が人々に響いたのです。
4節を見ます。「谷はすべて身を起こし、山と丘は低くなる」とあります。これが聖書の平和が実現してゆく様子です。聖書の平和は高いものが低くされ、低いものが高くなっていくことです。それはこのようなゆがんだ丸から説明することができます。現実の世界はゆがんでいます。自分だけが高く飛び抜けようようとしている場所があります。そこには高ぶる者が居ます。高ぶる者は、低くされている人間のことを、人間ではない劣った鬼畜だと言います。自分の民族は優秀で支配にふさわしいと言います。高いことを誇ろうとします。戦争中の日本は徹底的に高みに立とうとしたと言えるでしょう。アジアの人々を劣った人とし、アメリカを鬼畜だと言いました。その発想が平和を壊す始まりです。戦後のアメリカも同じです。アメリカは日本と沖縄、特に伊江島の人々を戦争に負けた劣った者、支配されるべき人間以下の存在として扱いました。
聖書の平和とはこのような不平等と抑圧を解消してゆく働きです。平和とはこのでこぼこな丸が、きれいな丸の状態になってゆく動作です。聖書の平和とはだれも高い人、低い人がいないきれいな丸になる状態です。押し込められていた人が元に戻り、高みにいた人が元に戻される、みんなが対等に、等しく満たされている状態です。ゆがんだ丸が平らになっていくことが平和です。そしてイエス様の十字架を、このへこみの下、低み、一番深い谷、悲しみの底に起きました。イエス様の十字架こそこの谷底にある出来事でした。聖書の平和とはその十字架から歪んだ丸を見つめ、元の美しい丸に戻してゆく動作です。そのダイナミックな動きが聖書の平和です。4節の「高みは低くなれ、低みは高くなれ」「険しい道は平らに、狭い道は広くなれ」とは、神様の平和の宣言です。人間同士に上下のない、優劣のない様子が平和です。神様はそのような平和が私たちの世界に実現すると約束をしています。
5節を見ましょう。5節には「主の栄光が洗われるのを 肉なる者は共に見る」とあります。そうです私たちすべての人間は、共に神を見る者として存在をしています。人間の中にだれ一人、鬼畜はいません。悪魔のような人間はいません。たとえあいつらは人間ではない、悪魔だ、対話できないと教えられても信じてはいけません。すべての者が共に神の栄光を見る、尊い存在です。だから「あいさつさびら」です。私たちは互いにあいさつしましょう。共に言葉を交わし、共に食べ、共に笑いましょう。そのようにして同じ人間として他者がいることを忘れずにいましょう。共に神を見る者として互いを思うことが私たちが平和を実現するための第一歩です。
6~8節を見ましょう7節には「この民は草に等しい」とあります。そうです、私たち人間は葦のように弱い存在です。私たち人間は草に等しい、はかない存在です。どのような人種、宗教、民族であってもすべての人間が弱い草のような存在です。でも私たちはただの草ではありません。私たちには神様の言葉があります。私たちは同じ人間であるという言葉、神が私たちに平和を与えるという言葉が、弱い私たちにはあります。私たちは弱くても、神様の言葉があります。とこしえに立つ、永遠にある、神の言葉が私たちにはあります。その神の言葉によって私たちには希望が与えられます。だから弱くても共に神のことを求め、平和のために働くことができるのです。
私たちの世界は平和ではありません。私たちの国も平和ではありません。沖縄も平和ではありません。まだ様々な場所に、低くされ、抑えつけられ、人間扱いされていない人がいます。また戦争が起きています、基地に苦しむ人がいます、いじめに苦しむ人がいます、私の心の中だけではない場所で、そのようなことは起きています。
私たちはこのような世界でどのように生きてゆけば良いのでしょうか。私たちは特に痛みを覚える人に目を向けましょう。低く抑えつけられている場所を見つめてゆきましょう。きっとそこには十字架があるでしょう。そしてそれが元に戻されるために働きましょう。互いを対等な人間として、共に神の栄光を見上げる存在として大切にしましょう。挨拶をしてゆきましょう。それ以上に自由と平等、平和のために何ができるのか考えてゆきましょう。そして神様の平和の約束を信じましょう。お祈りします。
「平和のために行動をしよう」イザヤ書40章1~8節
谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。
険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。 イザヤ書40章4節
沖縄の伊江島という小さな島から、平和とは単に戦争がないことに加えて、もっと人々が自由で、平等な様子を言うのだということを考えます。
1945年伊江島の人々は日本軍から人間扱いされず、特攻のための箱型爆弾を背負わされました。戦後はアメリカ軍から人間扱いされず土地を奪われました。伊江島は戦争が終わっても平和は訪れていません。真の平和とは人々の権利が守られ、自由に平等に生きてゆける状態のことです。平和を実現する行動とは、伊江島の人々のように、戦争に反対し自由と平等に向けて働いてゆくことです。抗議運動を率いた一人に阿波根昌鴻という人がいました。彼はクリスチャンで、沖縄のガンジーと呼ばれる人です。彼は非暴力でアメリカ軍と対峙することにしました。さまざまな活動のひとつに「あいさつさびら(あいさつしようね)」があります。お互いが同じ人間同士だと伝えるための平和的な抗議運動として行われました。
その働きは聖書の平和と共通しています。イザヤ書40章はイスラエルが戦争に負けた後、戦争が起こした苦痛に苦しむ人々に向けられた神様の言葉です。「谷はすべて身を起こし、山と丘は低くなる」これが聖書の平和が実現してゆく様子です。
それはゆがんだ丸から説明することができます。現実の世界はゆがんでいます。自分だけが高く飛び抜けようようとして高ぶる者が居ます。聖書の平和とは押し込められていた人が元に戻り、高みにいた人が元に戻される、みんなが対等に、等しく満たされている状態です。ゆがんだ丸が平らになっていくことが平和です。
5節、私たちすべての人間は、共に神を見る者として存在をしています。人間の中にだれ一人、鬼畜はいません。すべての者が共に神の栄光を見る、尊い存在です。同じ人間として他者がいることを忘れずにいましょう。共に神を見る者として互いを思いあうことは私たちが平和を実現するための第一歩です。7節には「この民は草に等しい」とあります。私たち人間は葦のように弱い存在です。でも私たちはただの草ではありません。私たちには神様の言葉があります。私たちは同じ人間であるという神様の言葉、神が私たちに平和を与えるという言葉が、弱い私たちにはあります。弱くても共に神のことを求め、平和のために働くことができるのです。
私たちの世界は平和ではありません。まだ様々な場所に、低くされ、抑えつけられ、人間扱いされていない人がいます。私たちは特に痛みを覚える人に目を向けましょう。そしてそれが元に戻されるために働きましょう。互いを対等な人間として、共に神の栄光を見上げる存在として大切にしましょう。挨拶をしてゆきましょう。そして神様の平和の約束を信じましょう。お祈りします。
【全文】「平和の祝宴に招かれる」イザヤ25章4~10節
まことに、あなたは弱い者の砦 苦難に遭う貧しい者の砦 イザヤ書25章4節
みなさん、おはようございます。先週はお休みをいただきました。代わりに奉仕を担ってくださった方々、本当にありがとうございました。今日も共にこの平塚教会で、神様からの招きに応えて、礼拝ができること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日も小さなこどもたちの命がこの礼拝に共にあることを感じながら礼拝をしましょう。
先日は福岡から濱野先生を招いて、宣教の奉仕をしていただき、またその後の主の晩餐の学びをしました。お一人一人はどのようなことを感じたでしょうか。またそれぞれに分かち合ってゆきましょう。礼拝も礼典も、神様からの招きです。招かれたままに、たとえその意味が分からなくても、聞いたまま、伝えられたままに続けてゆくことも大事です。そしてそれと同時に各教会や個人がはっきりとした信仰理解を持ってその礼典を行ってゆくことも大事です。すべてを理解し、言葉にすることはできないかもしれません。でも今日の礼拝、主の晩餐を何のために、誰に向けてするのかを考えて受けてゆきたいと思っています。
8月と9月は平和について考えています。私の心を特に締め付けるのは戦争で壊れた建物の瓦礫の前で泣いているこどもたちや、血だらけになって病院に運ばれたこどもたちです。世界中でその光景が繰り返されるたびに「神様はどこにいるのか」「神様はなぜ戦争を止めないのか」と疑問に思います。そしてこどもたちの笑い声が響きわたるのがどれだけ平和を象徴しているかを想像します。少し考えてみてください。みなさんも戦争の様子を見るたびに、神様がどこにいるのかと感じることは無いでしょうか?
イスラエル・ガザの紛争はイエス様が暮らし、平和を教えて回った場所で起きています。そこで紛争が繰り返され、エスカレートしていくことに特に心を痛めています。ロシアもウクライナももともとキリスト教が盛んな国です。平和の神様を信じている人間が、どうして戦争をしてしまうのかを疑問に思います。神様は一体どこでこの世界の様子を見ているのでしょうか。今日は戦争の中で神様はどこにいるのかを考えたいと思います。今読んでいるイザヤ書は、激しい戦争の時代に書かれた書です。神様が平和を願うメッセージが多く書かれています。今日の聖書から平和を見てゆきたいと思います。
今日はイザヤ書25章4~10節までをお読みいただきました。4節にはまことに神様は弱い者の砦とあります。神様は戦争において弱い者の砦であり、弱い者を守る側にいるということです。戦争の勝敗は神の願い、御心とは一切関係がありません。誰が神に戦争の勝利を祈ろうとも、神はその力でどちらかに勝敗を下すことはありません。神に戦争必勝の祈願をしても意味がありません。戦勝祈願は無意味な祈りです。神様はそのような暴力の衝突について、どちらかの「正しい側」「より熱心な側」に立つお方ではありません。
4節にもあるとおり神様は弱い者の砦です。神様が関わるのは、弱さと貧しさです。神様は弱い者と共にいるということです。戦争は強い者が勝ち、弱い者が負けて死にます。しかし神様は弱い者の砦です。神様は弱くて小さな者を見つけ、それを自分の元に集め、守ろうとします。神様は戦争のために熱心に祈り、戦って、武勲を上げる人を探しているのではありません。敵味方関係なく、戦火に追われる弱くて小さな者を見つけるのが神様の働きです。弱い者、貧しい者の希望となるのが、神様なのです。神様は弱く小さい者を見つけようとしています。私たちがその神様を見つけるためには、小さくならなければいけません。強く、大きく、広く、高くを目指す時、神様は見えなくなるのです。私たちも弱さや小ささ、貧しさに目を向けたいのです。
戦争の報道は、どちらがどのような兵器で、どちらが優勢で、大国がどんな武器の支援をするかに目を向けがちです。でも私たちも戦争に触れる時、神様のように弱さや小ささ、貧しさに目を向けてゆきましょう。私たちは戦争で傷つき、犠牲にされ、人生を壊された人を想像し、目を向けてゆきましょう。その時神様が戦争の中でどこにいるのかを見つけることが出来るはずです。
6節には神様が山で祝宴を開くとあります。神様は戦争の中で、弱い者、苦難にあう者、貧しい者、乾ききった者を山の上で行われる祝宴に招きます。山とは神様を礼拝する場所という意味です。神様は傷つき、疲れ、平和を求めて飢え渇くすべての人を礼拝に集めるのです。それは神様の側からの招待です。人間が場所とごちそうといけにえを準備して神様を招待するではありません。神様が場所も食べ物もすべてを整えて、山の上で待っていてくださるのです。私たちが招かれて礼拝をするのです。戦争で傷つき疲れた人々はそこで平和を願って礼拝するのです。
この個所には「すべて」という言葉が3回出てきます。山の上ではすべての民に神様からの食事が与えられます。ここでも敵味方関係ありません。一人の例外もなく、すべての民が、神様に招かれて、山に集まった者全員が祝宴に参加します。それが神様の礼拝の在り方です。分け隔てのないすべての人との食事が神様の愛を象徴しています。このように神様が山の上から招く祝宴は、神の愛、神の平和、神の招きの象徴です。その祝宴・礼拝ではすべての人に良い肉と古い酒(良いお酒)が提供されます。私たちはその肉と酒を受けとります。そうすると、神様から生きる活力をもらいます。これを食べると、生きよう、他者を愛そうという力が湧いてくるのです。この祝宴・礼拝に出て自分を反省するのではありません。主に招かれたこの時を楽しみ、食べて、力をもらうのが祝宴・礼拝の役割です。
この食べ物と良いお酒、私たちにとって何でしょうか。私たちにとってこの食べ物は、きっと礼拝の中の聖書の言葉でしょう。聖書の言葉から命、愛、祈り、平和をいただきます。あるいは今日いただく主の晩餐も、この食べ物をよく象徴しているでしょう。神様に招かれて、私たちは聖書の言葉と、主の晩餐をいただいて、生きる活力、希望をいただくのです。それが私たちです。神様はこのようにすべての人をこの祝宴・礼拝に招いています。
8節を見ます。主なる神はすべての顔から涙をぬぐうお方です。戦争の光景にはいつも涙があります。あるいは涙もでない悲しみがあります。神様はすべての顔から涙をぬぐってくださるお方です。神様は戦争の悲しみ、命を奪う悲しみ、恥、不名誉、失敗の涙をぬぐってくださるのです。神様は泣くなとは言いません。神様はただひたすら泣く人間の涙を、ぬぐってくださるお方です。涙が渇くまで、涙が枯れるまで、涙がとまるまでただただ涙をぬぐってくださるお方です。そしてそれもきっと味方の涙だけではありません。地上のすべての涙、敵の涙をもぬぐうのでしょう。
神様は戦争の勝敗に関わらない方です。戦争に勝つことを神様に祈ることは無意味です。そもそも神様は戦争を望んでいません。私たちは神様が戦争のどこにいるのかを探します。神様は勝った側にいるのではありません。より熱心に戦争の勝利を祈った側にいるのではありません。神様は敵味方関係なく、涙が流される場所、弱さと貧しさのある場所、安全な場所を求めて逃げまどう人と共にいるのです。神様はそのようにして戦争のただなかに、戦争の一番の悲しみの中にいるのです。
そして神様はすべての人を平和、礼拝へと招いています。だから私たちはこの礼拝で平和を求めましょう。世界では戦争によってたくさんの涙が流されています。そのような世界で、私たちは山の上の礼拝に招かれています。私たちはこの礼拝で平和を祈りましょう。
9節この方こそ私たちの神様です。私たちが待ち望むのはそのような神様です。この方が私たちを救ってくださるのです。私たちを平和へと導いてくださるのです。この方こそが私たちが待ち望んでいた主です。私たちは礼拝で、神様が涙の中に共にいてくれることを共に喜び合います。その礼拝の中で主の働きは豊かに注ぐのです。
私たちは世界の平和を求めて礼拝をしましょう。壊れたがれきと涙するこどもを見て、神様は必ずそこにいる、涙をぬぐってくださると信じましょう。そしてその戦争が早く終わるように祈りましょう。一人一人が平和のためにできることをしましょう。
そして私たちはずっと山の上に留まるのではありません。今日私たちはこの平塚バプテスト教会という山・礼拝から降りて、礼拝から派遣されて、それぞれの場所で暮らしてゆきます。私たちの派遣された場所は平和ではないかもしれません。弱さと涙があるかもしれません。でもその場所に神がおられます。みなさんが平和を実現するために、1週間できることは何でしょうか?私たちは神様の愛と平和を広げることができる、1週間を目指します。一人ひとりがその実現に向けてどのように行動できるかを考えてみましょう。それぞれの生活の中で、神様の平和を広めるための具体的な行動は一体なんでしょうか。そして私たちはまた来週の礼拝にも招かれています。1週間それぞれの場所での平和を求めて、過ごし、また集いましょう。
これから主の晩餐を持ちます。これも神様から招かれている祝宴の一つです。このパンと杯を受けて、平和を実現させるための力と知恵と励ましをいただきましょう。神様は礼拝と平和へと私たちすべての人を招いています。そのことを覚えてこの祝宴にあずかりましょう。お祈りいたします。
「平和の祝宴に招かれる」イザヤ25章4~10節
まことに、あなたは弱い者の砦 苦難に遭う貧しい者の砦 イザヤ書25章4節
8月と9月は平和について考えています。私の心を特に締め付けるのは戦争で泣いているこどもたちや、血だらけになって泣いているこどもたちです。世界中でその光景が繰り返されるたびに「神様はどこにいるのか」「神様はなぜ戦争を止めないのか」と疑問に思います。そしてこどもたちの笑い声が響きわたるのがどれだけ平和を象徴しているかを想像します。神様は一体どこでこの世界の様子を見ているのでしょうか。今日は戦争の中で神様はどこにいるのかを考えたいと思います。
4節は、神様は戦争において弱い者の砦であり、弱い者を守る側にいるということを示しています。誰が神に戦争の勝利を祈ろうとも、神はその力でどちらかに勝敗を下すことはありません。神様は弱い者の砦です。神様が関わるのは、弱さと貧しさです。神様は弱くて小さな者を見つけ、それを自分の元に集め、守ろうとします。弱い者、貧しい者の希望となるのが、神様なのです。戦争の報道は、どちらがどのような兵器で、どちらが優勢かという点に目を向けがちです。でも私たちも戦争に触れる時、傷つき、犠牲にされ、人生を壊された人を想像し、目を向けてゆきましょう。その時神様が戦争の中でどこにいるのかを見つけることが出来るはずです。
6節には神様が山で祝宴を開くとあります。山とは神様を礼拝する場所という意味です。祝宴・礼拝は神様の側からの招待です。この個所には「すべて」という言葉が3回出てきます。すべての民が、神様に招かれて、山に集まった者全員が祝宴に参加します。それが神様の礼拝の在り方です。この祝宴・礼拝に出て楽しみ、食べて、力をもらうのです。私たちにとってこの食べ物は、聖書の言葉です。聖書の言葉から命、愛、祈り、平和をいただきます。あるいは今日いただく主の晩餐も、この食べ物をよく象徴しているでしょう。神様に招かれて、私たちは聖書の言葉と、主の晩餐をいただいて、生きる活力、希望をいただくのです。
8節には主なる神はすべての顔から涙をぬぐうお方だとあります。戦争の光景にはいつも涙があります。神様はただひたすら泣く人間の涙を、ぬぐってくださるお方です。神様は敵味方関係なく、涙が流される場所、弱さと貧しさのある場所、安全な場所を求めて逃げまどう人と共にいるのです。神様はそのようにして戦争のただなかに、戦争の一番の悲しみの中にいるのです。
そして神様はすべての人を平和、礼拝へと招いています。世界では戦争によってたくさんの涙が流されています。そのような世界で、私たちは山の上の礼拝に招かれています。私たちはこの礼拝で平和を祈りましょう。
私たちは世界の平和を求めて礼拝をしましょう。壊れたがれきと涙するこどもを見て、神様は必ずそこにいる、涙をぬぐってくださると信じましょう。そしてその戦争が早く終わるように祈りましょう。一人一人が平和のためにできることをしましょう。そしてこれから主の晩餐を持ちます。このパンと杯を受けて、平和を実現させるための力と知恵と励ましをいただきましょう。お祈りいたします。
【全文】「平和を祈ろう」イザヤ9章1~6節
みんさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声を聞きながら礼拝をしましょう。また今日はバプテスマ式を執り行うことができました。彼だけではなく、私たちにとっても大きな喜びです。彼の信仰告白から神様への思いが伝わってきました。そのバプテスマが人生の転機となるように祈っています。8月11日の平和祈念礼拝でバプテスマをうけることになったのは偶然ではないはずです。平和に向けて働くことも忘れないでいて欲しいと思います。みなさんと一緒に平和を考えることからクリスチャンの歩みをスタートしましょう。今日も平和について考えてゆきましょう。
今日は平良修という牧師を紹介します。戦後沖縄はアメリカ軍に占領され厳しい状況に置かれていました。アメリカの一部、アメリカの植民地とされたのです。植民地のトップにいたのがアメリカから派遣された「高等弁務官」でした。この高等弁務官は沖縄の政治・行政・司法を掌握していました。行政の職員は逆らえばクビにされました。沖縄政府が法律を作ろうとしても高等弁務官には拒否権がありました。裁判官も高等弁務官が任命しました。このように高等弁務官は行政・立法・司法の三権のさらに上に立っていました。高等弁務官は沖縄を植民地支配する絶対的権力を持つ存在でした。それは帝王と呼ばれていました。
15年間の占領で6人の高等弁務官がいましたが、その5人目の就任式に招かれたのが、平良修牧師でした。平良牧師はその就任式で祈ることとなりました。就任式での彼の祈りは次のようなものでした。「神よ、願わくは、世界に一日も早く平和が築き上げられ、新高等弁務官が最後の高等弁務官となり、沖縄が本来の正常な状態に回復されますように、せつに祈ります。」就任式の祝いの席で、この人が最後の弁務官になるように、最後の支配者となるように、沖縄が正常な状態に戻るように、そう祈ったのです。この祈りは大きな驚きと反響を呼びました。帝王、絶対権力者の就任を祝う式で、牧師が神に、最後の権力者となりますようにと祈ったからです。
そしてさらに祈りは続きました。「神よ、沖縄にはあなたのひとり子イエス・キリストが生命を賭けて愛しておられる百万の市民がおります。高等弁務官をしてこれら市民の人権の尊厳の前に深く頭を垂れさせてください。そのようなあり方において、主なるあなたへの服従をなさしめてください。天地のすべての権威を持ちたもう神の子イエス・キリストは、その権威を、人々の足を洗う僕の形においてしか用いられませんでした。沖縄の最高権者、高等弁務官にもそのような権威のありかたをお示しください。」戦争に負け、植民地として暴力的に支配されている側の人間が、絶対権力者を前に、あなたが最後になりますように、そしてその権力者が民衆の足を洗う僕になりますようにと神様に祈ったのです。支配者が民衆の人権を守るようにと神様に祈ったのです。このような祈りは沖縄の人々を大きく励ますことになりました。本土復帰への力となっていったのです。
平良修牧師の就任式での平和の祈り、私たちもこのような祈りを持ちたいと思います。今私たちもトランプかハリスかアメリカのリーダーの変わり目に生きています。そして日本もそう遠くない時期にリーダーが変わるでしょう。私たちは政治と政治家のために祈ります。ただその祈りは、戦争の準備をするリーダーが最後になりますように、戦争をするリーダーが最後になりますようにという祈りです。私たちを抑圧する政治がこの人で終わりますようにという祈りです。
神様が用いるのは人々の足を洗うリーダーです。自分たちの利益や裏金ではなく、人々の足を洗う、命を守るリーダーが選ばれるように祈りましょう。今日の聖書の個所はイザヤ書です。今日の個所も就任式での平和の祈りです。預言者イザヤが就任式で祈った平和の祈りが記録されています。一緒に聖書を読みましょう。
イザヤ書9章1~6節までをお読みいただきました。イエス様が生まれるずっと前の時代、王様がアハズからヒゼキヤ変わる時の事です。当時のイスラエルは戦争直前の状態でした。近隣諸国との緊張関係が高まっていたのです。イスラエルの北側はすでに攻め滅ぼされていました。次は自分たちが戦争に巻き込まれるかもしれません。多くの人は軍備を拡張し、戦争に勝つことでしかこの状況を変えることはできないと考えました。戦争の準備をたくさんしたのです。そんな時に王様の交代がありました。
1節の「闇の中を歩む民」「死の陰の地に住む者」とは、おそらくすでに戦争に負けた、北側の住民たちのことです。望まない戦争を戦わされ、被害にあい、家族の命が奪われ、財産や土地もすべて失い、人権が蹂躙された人々のことです。戦火にさらされた彼らは、暗い闇を生きるように、死を身近に感じたでしょう。しかしイザヤは預言をします。その人々は大いなる光を見ると預言します。光とは人生の希望です。残りの人生に希望が何もないと思える時も、神様が私たちに希望を見せてくれるということです。死に直面した、あるいはすでに死んでしまった人にも神様の希望が輝くと、ここでは約束されています。ここには「輝いた」と未来のことが過去形で記されます。それは実現が確実に約束されていることを示しています。強い約束、確実な約束として、光がある、希望があると記されているのです。神様はこのように戦争の起こる世界の中でも絶望せず、希望があることを私たちに伝えています。
2節、私たちには深い喜びが準備されています。それはたくさんの作物が収穫できた時の喜びに似ています。そのような心も体も満ち足りるような喜びが私たちを待っているのです。私たちが戦争で奪われたものが、もう一度自分の手に戻ってくるような喜びが私たちを待っています。
4節は重要な箇所です。ここでは軍事力の放棄が語られています。平和へと向かう時、兵士たちの靴や軍服は火に投げ込まれます。神様は軍隊の装備、武器をすべて焼き尽くすお方なのです。平和には武器も装備も必要ないのです。私たち人間は自分を守るためだと言って武器や基地を作ります。相手より強い武器を持っていることが最大の安心、抑止力、平和につながると考えます。しかし神様は違います。神様は武器装備をことごとく火に投げ込みます。武器では平和は作れない、必要ないと言うのです。ここには武器や基地がすべてなくなる約束がされています。これも焼き尽くされたという過去形の強い約束です。私たちには平和な世界と、武器と基地の無い世界が神様から約束されているのです。それを信じましょう。
5節「一人の赤ちゃんが、私たちのために生まれた。男の子が私たちに与えられた。」この言葉は新しく就任した王に対して、イザヤから平和への期待が託されています。よく見るとその王とは「私たちみんな」に与えられた王です。王とは特定の人の利益のために、自分のお友達の利益のためにだけいるのではありません。私たちみんなのために、民主的に与えられたのが王です。イザヤの願った王は絶対権力者でも、帝王でもありません。私たちのみんなの命と生活を守る、神の僕です。そしてそのような王は平和の君と呼ばれるとあります。そのような王が平和を実現するリーダーになるということです。イザヤは戦争に勝ちますように、戦争に勝つ強い王になりますようにとは祈っていません。イザヤは平和を実現する王を求めています。
6節その平和は正義と恵みの業によって支えられるとあります。正義とは正しいことです。そして恵みの業とは、恵みが誰かに偏って与えられるのではなく、みんなに与えられることです。それは偏りがなく、公平に与えられる様子です。平和とは戦争がないだけではありません。平和とは正しさと公平さが行き渡る場所で起るのです。神様はそのような正義と公正から、平和を成し遂げてくださるお方です。
神様はこのように平和を私たちに成し遂げると約束してくださっています。そしてイザヤはその約束がこの新しい王によって実現することを祈っています。新しい王に平和の実現のための器として、働くように呼びかけているのです。それが今日の聖書の個所です。イザヤの祈りはどこか平良修牧師の祈りとも重なるように思います。
私たちもこの世界と私たちの周囲の平和の実現について考えます。私たちは平和を大事にするリーダーを選びましょう。人はすぐに強いリーダー、戦争に勝つリーダーを求めるものです。しかし私たちは武器を捨て、正義と、公平さを持ったリーダーを選びましょう。そして私たちが選んだリーダーが平和を選ぶように祈り続けてゆきましょう。預言者イザヤや平良修牧師のように私たちは平和を祈ってゆきましょう。平和を祈り平和を実現する人を私たちのリーダーとしてゆきましょう。そして私たち自身が平和のリーダーとなってゆきましょう。武器を捨て、力を捨て、火に投げ入れ、正しさと公正さを持ったリーダーとなってゆきましょう。
私たちは1週間、自分の強さと勝利を求めるのではありません。私たちはそれぞれの1週間で平和を祈り、実現させましょう。暴力と力を焼き払い、正義と公正さ持ちましょう。そのために神様は私たちに知恵と力を与えて下さるはずです。
神様はそのようにして必ず地上に、私たちに平和を与えて下さいます。そのために祈りましょう。そして平和の実現のためにそれぞれの場所で働きましょう。今日はそのための平和祈念礼拝です。お祈りします。
「平和を祈ろう」イザヤ9章1~6節
地を踏み鳴らした兵士の靴 血にまみれた軍服はことごとく 火に投げ込まれ、焼き尽くされた。
イザヤ書9章4節
今日は平和祈念礼拝です。平良修という牧師を紹介します。戦後沖縄はアメリカ軍に占領され植民地とされました。植民地のトップには帝王と呼ばれる「高等弁務官」がおり、沖縄の政治・行政・司法を掌握していました。その就任式に招かれたのが平良修牧師でした。平良牧師はその就任式で「新高等弁務官が最後の高等弁務官となりますように」と祈りました。戦争に負け、暴力的に支配されている側の人間が、絶対権力者を前に、あなたが最後になりますようにと神様に祈ったのです。この祈りは大きな驚きと反響を呼びましたが、沖縄の人々を大きく励ましました。私たちもこのような祈りを持ちたいと思います。戦争をするリーダーが最後になりますようにという祈りです。今日の個所も就任式での平和の祈りです。
当時のイスラエルは戦争直前の状態でした。多くの人は軍備を拡張し、戦争に勝つことでしかこの状況を変えることはできないと考えました。そんな時に王様の交代がありました。
1節の「闇の中を歩む民」とは、おそらくすでに戦争に負けた、北側の住民たちのことです。望まない戦争を戦わされ、人権が蹂躙された人々のことです。彼らは、暗い闇を生きるように、死を身近に感じたでしょう。しかし神様は戦争の起こる世界の中でも絶望せず、光・希望があることを伝えています。2節、私たちには深い喜びが準備されているのです。4節は軍事力の放棄が語られています。神様は軍隊の装備、武器をすべて焼き尽くすお方なのです。平和には武器も装備も必要ないのです。私たちには平和と武器と基地の無い世界が神様から約束されているのです。それを信じましょう。5節の王とは「私たちみんな」に与えられた王です。王は私たちのみんなの命と生活を守る、神の僕です。そのような王が平和を実現するリーダーになるのです。6節正義とは正しいことです。そして恵みの業とは、偏りがなく公平に与えられる様子です。平和とは戦争がないだけではありません。平和とは正しさと公平さが行き渡る場所で起るのです。神様はそのような正義と公正から、平和を成し遂げてくださるお方です。神様はこのように平和を私たちに成し遂げると約束してくださっています。イザヤの祈りは平良修牧師の祈りとも重なるように思います。
私たちは平和を大事にするリーダーを選びましょう。武器を捨て、正義と、公平さを持ったリーダーを選びましょう。そして私たちが選んだリーダーが平和を選ぶように祈り続けてゆきましょう。
そして私たち自身も1週間、平和のリーダーとなってゆきましょう。私たちは自分の強さと勝利を求めるのではありません。私たちは暴力と力を焼き払い、正義と公正さ持ちましょう。そして平和の実現のためにそれぞれの場所で働きましょう。神様は必ず地上に、私たちに平和を与えて下さいます。今日はそのための平和祈念礼拝です。お祈りをします。
【全文】「お皿洗いの平和」イザヤ書4~5節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの命の存在を確かめながら礼拝を共にしましょう。
8月と9月は平和をテーマに宣教をしてゆきたいと思います。平和をテーマとするとき、戦争の事も考える、重苦しいテーマとなるかもしれません。しかし今日は私たちの身近なことから平和について考えてゆきたいと思います。
ある平和学の教授が、人間同士の対立を理解するために「誰がお皿を洗うか」というたとえを使っていました。二人以上で暮らす家ではよく誰がお皿を洗うのかという対立が起きます。じゃんけんで決めたり、順番を決めることで一見解決したように見えるものです。しかしこの教授は誰がお皿を洗うのかを決めただけでは、対立は解決しないと言います。教授はお皿洗いをどちらがするのかというその対立の中に含まれているものに注目しています。その中には実は互いへの期待や、思いやり、関係性、意思決定の方法など多くの要素が含まれています。お皿洗いはどちらがするのかという問題の中には、どのような関係性でありたいかという問題が隠れているのです。私たちはとりあえずその場しのぎで、お皿は誰が洗うのかを決めて、解決したつもりでいます。しかし、私たちは根本的な問題である、どのような関係性を期待しているのかについては、深く話し合いません。これでは表面的な解決です。奥にある問題を無視せず根本的な関係性に目を向けることが大切です。
お皿洗いの問題だけではありません。いろいろな対立が私たちの家の中にあるはずです。でも私たちはいつも表面的な解決にしか目を向けていません。
一方で何も対立が起こらない家が平和だとは限りません。相手に意見を言えない雰囲気、相手に意見を抑え込まれている状況は平和ではありません。現状に対立がないことをもって平和とはならないのです。また関係を確認しルールを決めれば平和かというとそうではありません。状況は常に変わります。健康や仕事や時間の使い方は常に変化します。一度決めたルールも常に見直しが必要です。
きれいな家とはどんな家でしょうか。一見きれいな家でも、汚れが見えない場所に隠されている家は、本当にきれいな家とは言えません。家は住めば必ず汚れます。絶対に汚れない家は存在しません。きれいな家とは、汚れから目を背けず、汚れても、汚れても、毎日、毎日、繰り返し掃除がされている家のことです。
平和もこのお皿洗いの対立から考えることができます。今日どちらがお皿を洗うかをとりあえず決めるだけでは、平和ではありません、お皿洗いの対立が起きないのが平和なのではありません。常にその問題の中にある関係性、互いへの期待に目を向けてゆくことが大事です。そして常に更新されてゆくことが大事です。このたとえを通じて、教授は次のように勧めています。まず山積みの食器に目を向けるのではなく、その向こう側に目を向けて、問題となっている人間関係や構造を理解しよう。その後から、食器をどのように洗うかを考えようと勧めています。その場しのぎの答えではなく、問題の中の人間関係、構造に目を向けようと言っています。
このたとえ話は平和を考える上で、とても重要な視点を教えてくれます。私たちは一切の対立がない世界の実現を目指しているのではありません。一切の対立がないことが平和なわけではありません。私たちが目指すのは、対立が起きた時、表面的な解決を繰り返さないということです。解決に暴力的な方法をとらないことです。対立の中にある、関係性や構造に目を向けてゆくことが必要です。
そのようにして初めて、対立を平和へと転換させてゆくことが出来るのです。私たちはそのような転換が必要とされています。私にもこのような平和が実現できるでしょうか。解決方法はそれぞれの関係や構造で変わって来るはずです。でもそれを対立の内容よりも、関係性に重点を置いて考えることが大切です。それは家族や職場、友人関係において、心にとめておきたい事です。今日は聖書からも平和と、その実現のために必要な、私たちの転換について考えたいと思います。
聖書を読みましょう。旧約聖書イザヤ書2章4~5節までをお読みいただきました。特にこの言葉は聖書で有名な言葉です。ニューヨークの国連本部の広場にもこのイザヤ書の言葉が刻まれています。世界が平和を求める願いがこの言葉によく表されています。ただ今の世界はこの逆であるとも言われます。生活の糧を奪い、戦争をしています。旧約聖書はイエス様が生まれるずっと前に与えられた神様からの教えですが、このような平和の教えも書かれています。
この文書が書かれた当時、イスラエルは近隣諸国から軍事的な圧力に直面していました。まだ戦争は始まっていません。しかし、すでに対立は深まり、暴力の一歩手前でした。イスラエルは小さな国でした。他の国に怯えずに、自分達らしい国にすることを望んでいました。しかし、近隣諸国と利害が衝突し、戦争直前の状態にありました。
実は同じことはこれまでも繰り返されてきました。すでにイスラエルの北側は攻め滅ぼされていました。この圧力に勝つにはもう暴力・戦争しか方法はないという人が多くいました。他国からの脅威があるとき、戦争しかないと訴える人はどの時代にもいます。このような緊張関係の中、神様はイザヤという人を通じて4節の言葉を人々に伝えました。それは4節「剣を鋤に打ち直せ」「槍を鎌に打ち直せ」という言葉です。
この言葉はまさしく、武器を捨てて平和を求めようということを意味しています。私たちが持っている暴力の道具を捨て、命を養う道具に変え、平和に生きることを促しています。戦争の勝ち負けで物事を決めても本当の平和は訪れません。破壊された建物と、憎しみが残るだけです。それはまるで暴力を使って、無理やりお皿洗いをさせているようなものです。お皿が洗われても、本当の問題は全く解決していません。戦争の後に平和は訪れません。軍事力では平和は実現できません。武器で平和は作れません。神様ははっきりと武器で平和は実現しないことを伝えています。
そして今回、武器で平和は作れないということの他に、私はもう一つここに意味を見出します。それは対立の原因となっている関係や構造に目を向けることが重要だということです。表面的な解決ではなく、短絡的な暴力による解決ではなく、双方の関係性や期待していることに目を向けて解決する必要があるといことです。山積みのお皿の向こう側に目を向けるということです。
「剣を打ち直して、鋤とする」は、対立するのをやめて我慢する様に言っているのではありません。対立してはいけない、逆らってはいけないと言っているのではありません。武器を捨ててそしてさらに、その対立を剣以外の方法で、暴力的でない方法で、表面的でない方法で、解決せよと言っているのです。ですからこの教えは武器を放棄するというだけの教えにとどまりません。武器を捨て、それ以外の方法で問題を解決するようにと教えています。
4節には打ち直せという言葉があります。この言葉は一度バラバラに壊して作り変えてゆくという意味です。暴力的で表面的な解決からの転換が促されているのです。私たちにその場しのぎの解決ではなく、物事を別の角度から見て解決することを促しているのです。問題の見方を転換し、背景にある人間の関係を深く考えるようにと促しています。「剣を打ち直して鋤とする」とは私たちに新しい、創造的な、建設的な方法で、対立を解決するように促しているのです。
これは対立についての内容ではなく関係に重点を置いた受け止め方です。対立をこのように関係に重点を置いて受け止める時、私たちにはどんな変化が起こるでしょうか。私たちはその対立をもっと積極的に受け止めることができるかもしれません。対立をめんどうなものとしてではなく、他者の理解を深める機会とすることができるかもしれません。互いが成長できる機会とすることができるかもしれません。その対立をよく見極める時、いのちといのちの新しい関係に気付くかもしれません。
それは人間同士の対立にも、国と国との対立にも当てはまることなのではないでしょうか?剣の様な互いの気持ちが、鋤になってゆく、命を育むことへと打ち直され、転換してゆくのです。そしてそれが打ち直されるには対話が必要とされるのでしょう。武力ではなく対話が、私たちを打ち直すのです。
人間同士の対立は波のように、何度も繰り返し起きます。その対立は蒸し返したり、変化し続けたりします。私たちにはその対立を表面的、暴力的ではなく、積極的に受け止めてゆくという転換がもとめられているのではないでしょうか。対立を互いが成長できる機会、他者の理解を深める機会とすることを促されているのではないでしょうか。それが剣を鋤に打ち直すということ、自分自身を打ち直すということではないでしょうか。そのように歩むことを5節、光の中を歩むと言うのではないでしょうか?
私たちの周りにはたくさんの対立があります。めんどうなことばかりです。でもその対立について、根本的な人間関係に目を向けたいと思います。それが対立を平和へと転換する努力、打ち直すなのだと思います。剣を鋤に打ち直すとは問題を関係性の視点でとらえ、暴力以外の方法で解決しようとする姿勢です。
私たちは今週それぞれの場所で対立に出会うでしょう。そのような時、剣を鋤に打ち直してゆきましょう。平和を実現するものとして歩んでゆきましょう。お祈りします。
「お皿洗いの平和」イザヤ書4~5節
彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。イザヤ2章4節
8月と9月は平和をテーマに宣教します。ある平和学の教授が、人間同士の対立を理解するために「誰がお皿を洗うか」というたとえを使っています。教授は誰がお皿を洗うのかを決めただけでは、対立は解決しないと言います。その対立の中には実は互いへの期待や、思いやり、関係性、意思決定の方法など多くの要素が含まれています。お皿洗いはどちらがするのかという問題の中には、どのような関係性でありたいかという問題が隠れているのです。今日どちらがお皿を洗うかをとりあえず決めるだけでは、本当の問題は解決しません。常にその問題の中にある関係性、互いへの期待に目を向けてゆくことが大事です。
教授は、まず山積みの食器に目を向けるのではなく、その向こう側に目を向けて、問題となっている人間関係や構造を理解しようと勧めています。その後から、食器をどのように洗うかを考えようと勧めています。その場しのぎの答えではなく、問題の中の人間関係、構造に目を向けようと言っています。このたとえ話は平和を考える上で、とても重要な視点を教えてくれます。今日は聖書からも平和と、その実現のために必要な、私たちの転換について考えたいと思います。
当時イスラエルは近隣諸国から軍事的な圧力に直面していました。他国からの脅威があるとき、戦争しかないと訴える人はどの時代にもいます。このような緊張関係の中、神様はイザヤという人を通じて4節の言葉を人々に伝えました。この言葉は武器を捨てて平和を求めようということを意味しています。
そして今回、私はもう一つの意味を見出します。それは対立の原因となっている関係や構造に目を向けることが重要だということです。「剣を打ち直して、鋤とする」は、対立するのをやめて我慢する様に言っているのではありません。4節には打ち直せという言葉があります。私たちにその場しのぎの解決ではなく、問題の見方を転換し、背景にある人間の関係を深く考えるようにと促しています。「剣を打ち直して鋤とする」とは私たちに新しい方法で、対立を解決するように促しているのです。
これは対立について、内容ではなく関係に重点を置いた受け止め方です。対立をこのように関係に重点を置いて受け止める時、私たちはその対立をもっと積極的に受け止めることができるようになります。他者の理解を深める機会とすることができます。それは人間同士の対立にも、国と国との対立にも当てはまることです。
私たちの周りにはたくさんの対立があります。でもその対立について、根本的な人間関係に目を向けたいと思います。それが対立を平和へと転換する努力、打ち直すなのだと思います。剣を鋤に打ち直すとは問題を関係性の視点でとらえ、暴力以外の方法で解決しようとする姿勢です。私たちは今週それぞれの場所で対立に出会うでしょう。そのような時、私たちは剣を鋤に打ち直してゆきましょう。平和を実現するものとして歩んでゆきましょう。お祈りします。
【全文】「愛を配る使命」マタイによる福音書15章29~39節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの存在と命を感じながら一緒に礼拝をしましょう。今月は主の晩餐について考えています。今日はバリアフリーを手掛かりに主の晩餐のこと、そしてそれにつながる私たちの生き方のことを考えたいと思います。
今年の4月から事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。例えばレストランでは、障がい者の利用を断るなどの行為が禁止されました。また障がいのある人から「バリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、必要かつ合理的な対応をすることも義務となりました。例えば目の見えない人にはメニューを口頭で説明する、タッチパネルの操作を代行するなどの配慮が義務となりました。
教会はどうでしょうか。教会は障がいを理由に来るのを断ったりすることは一切ありません。むしろ障がいのある方を歓迎しています。それでもこの教会に残るバリア、教会の配慮をもう一度見直したいと思います。
私たちの教会は正面の道路から礼拝堂の椅子に座るまで、大小9個の段差があります。若くて目の見える人にはなんてことない段差です。しかし目の見えない人や、杖をついた人、足腰に自信のない人にとっては高いハードル、恐ろしい段差、躓きの原因です。この講壇にはさらに3段の段差の上にあります。高い方が見やすいのですが、せめて手すりがあった方がよいかもしれません。裏手にある牧師室まではさらに6個の段差がある。大規模な修繕をする場合は、できればこれらの段差をなくしたいと思っています。裏口にはスロープがありますが、車いすの方が堂々と正面から入れるようにしたいと思います。このような視点で考えると、教会のバリアフリーはまだまだです。礼拝中に気分がすぐれない時、横になれるスペースも欲しいと思います。こどもの目線からみると、低い洗面台が欲しいと思います。手を洗う洗面台が高く、踏み台の上にのって背伸びをして手を洗うのは危険です。そういった意味では、教会もまだまだ配慮がたりないところがあります。
段差の解消は障がいをもつ人のためだけに行われるのではありません。私は食堂などで重い荷物を移動するときがあります。その時は台車を使いたいのですが、段差が多すぎて使えません。段差が無ければ台車がスムーズに入れるでしょう。段差がなくなればベビーカーや買い物カート、大きなスーツケースも楽になるになるでしょう。これはみんなの問題でもあり、全体の雰囲気にも影響することでしょう。
教会は体に不自由がある人も健康な人も、こどももお年寄りも、だれでも歓迎します。すべての命を大切にします。私たちはそれを心と言葉だけではなく、教会の設備でも実現できたらいいと思っています。私たちがイエス様から愛をいただいたように、その愛を私たちが多くの人に手渡したいと思っています。今日は聖書の中に出て来る、体の不自由な人の物語を見ます。そこから主の晩餐と私たちの愛のある生き方について考えたいと思います。聖書を読みましょう。
今日はマタイによる福音書15章29~39節をお読みいただきました。30節、イエス様に従った人々の中にはたくさんの足の不自由な人、目の見えない人などの障がいを持った人がいました。聖書の時代、病や障がいは罪の結果とされました。障がいをもった人々は、あなたの行いが悪いから病気になった、あなたの先祖が悪い事をしたからあなたは障がいを持ったと指をさされていました。それは当事者の心を深く傷つけました。当事者が負っていたのは体の不自由だけではありませんでした。体の不自由よりももっと重く、もっと深く、心に傷を負わされていたのです。合理的な配慮、支援が一切ない、障がい者差別の時代です。周囲からの強いストレスを感じていたはずです。愛と配慮の不足の中では、本来治る病気も治るはずがありませんでした。イエス様に従う群衆にはそのような障がいと心の傷を負った人がたくさんいたのです。
イエス様はその病気をたくさん治したと記録されています。どう直したのかはわかりません。ただその癒しの一部に、ストレスからの解放が含まれたことは間違えありません。障がい者に無関心で差別的な社会にあって、イエス様は障がいをもった人々を罪人と決めつけるのではなく、人々をいたわり、励まし、手を置いて祈り、人々を癒しました。その愛が人々を回復へと導いたのです。
イエス様はこのあと全員で食事をしょうとしました。4000人の食事です。文脈によれば、この食事には多くの障がい者、障がいから回復した人々が含まれていたはずです。きっとこの中にはイエス様を信じていない異邦人、男女あらゆる性の人も含まれました。多様な人がここに集っていたのです。32節にはイエス様はそのような群衆を見て「かわいそう」だと思ったとあります。この「かわいそう」という言葉はスプラグニゾマイという内臓に由来する言葉で、日本語の「はらわたがちぎれる」に相当する言葉です。正確に言うとイエス様は「かわいそう」と思ったのではありません。
イエス様は、群衆を見てはらわたがちぎれたのです。こんなにたくさんの人が社会から疎外され、差別され、励ましを必要とし、空腹であり、自分を求めるその姿に胸が苦しくなったのです。群衆の心の傷を自分のもののように感じ、痛んだのです。その心の痛みを感じた時、イエス様は皆で食事をすることにしました。心と体が傷ついた人を癒し、励まそうとして、その食事を持ったのです。
聖書によれば当初、パンと魚は全く足りませんでした。それはまるで愛と配慮が不足した社会の様です。愛と配慮がすべての人にいきわたらない社会の様です。愛と配慮がごく一部の人にしか行き渡らない社会とそっくりです。でもイエス様はそのような中で祈りました。すべての人にパンと魚が行き渡るように祈りました。すべての人に愛と配慮が行き届くように祈りました。障がいをもった人への差別がなくなり、愛され、合理的な配慮がなされるように祈ったのです。このパンがすべての人に不思議と行き渡るように、すべての人へ愛と配慮が行き渡るように願ったのです。イエス様が祈ると不思議とパンと魚はすべての人にいきわたり、余るほどになりました。イエス様の愛と配慮はすべての人に届き、有り余るほどなのです。
この食事は主の晩餐でした。パンを取り、祈り、裂き、配るという一連の構文は主の晩餐の構文です。イエス様はこれを主の晩餐として行ったのです。このように主の晩餐はイエス様が差別と無関心のただなかで行ったものだったのです。それからの解放を求め、愛と配慮がゆきわたることを求めるものだったのです。
もう一つ注目をしたいのは、パンと魚は弟子が群衆に配ったということです。イエス様は弟子たちを、パンを受け取り、配る者としました。イエス様が直接群衆に配るのではなく、弟子たちがイエス様からそのパンを一度預かって、配る役割を担ったのです。弟子たち、そして私たちにはそのような役割が与えられているのです。
それはパンを受け取って、また誰かに配るという使命です。それはイエス様の愛を受けて、その愛をまた別の人に配るという使命です。イエス様が愛し、配慮する姿を、弟子たちは同じ様に実践する使命を与えられているのです。それが弟子たちによって群衆に配られたという意味なのです。
今日は4000人の食事を見てきました。障がいと愛と主の晩餐というキーワードで読んできました。この4000人の食事、主の晩餐でイエス様が実現しようとしたものを考えます。イエス様は差別され、排除されている人を励ますためにこの食事を持ちました。その悲しみを自分のものとし、愛と配慮を伝えるために主の晩餐をしたのです。そのようにして社会的なバリアを取り除いてゆこうとしました。社会から追い出された人をもう一度共同体に戻そうとしたのです。そしてイエス様は弟子たちに、私たちにそれを実現する役割を与えました。
きっと私たちの教会が障がいをもった人、弱さをもった人を歓迎するのは、このイエス様の態度、イエスの食事に起源があるのでしょう。イエス様はそのような包容力のある社会、共同体を目指していたはずです。そして食事によってそれを実現しようとしたお方です。私たちもこのような包容力のある人間、包容力のある共同体でありたいと願います。そして私たち自身が、イエス様から受け取ったパンを多くの人に配るものでありたいと思います。イエス様から受け取った愛をたくさんの人に配る人でありたいと思います。
1ヶ月主の晩餐について聖書を読んできました。私たちにはつらくしんどい時がありますが、この主の晩餐に招かれています。イエス様の癒しと愛と励ましに招かれています。そして私たちは自分ひとりには大きすぎる愛をいただいています。これはあなたが一人で食べる分ではなく、あなたがみんなに配る分だよといってパンが与えられています。私たちはこの愛を多くの人に配るそのような使命をイエス様からいただいています。その愛を受けて1週間、1ヶ月、たくさんの人々に愛を配りましょう。
来週の主の晩餐、このことを覚えてパンを食べましょう。そして8月18日には濱野先生にもこのことを教えていただきます。みんなで一緒にこれからのことを考えてゆきましょう。お祈りいたします。
「愛を配る使命」マタイによる福音書15章29~39節
そこで、イエスは地面に座るように群衆に命じ、 七つのパンと魚を取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。人々は皆、食べて満腹した。残ったパンの屑を集めると、七つの籠いっぱいになった。
マタイによる福音書15章35~37節
私たちの教会は正面の道路から礼拝堂の椅子に座るまで、大小9個の段差があります。教会もまだまだ配慮がたりないところがあります。教会は体に不自由がある人も健康な人も、こどももお年寄りも、だれでも歓迎します。私たちはそれを心と言葉だけではなく、教会の設備でも実現できたらいいと思っています。私たちがイエス様から愛をいただいたように、その愛を私たちが多くの人に手渡したいと思っています。今日は聖書の中に出て来る、体の不自由な人の物語から主の晩餐と私たちの愛のある生き方について考えたいと思います。
聖書の時代、病や障がいは罪の結果とされました。障がいをもった人々は、行いが悪いから病気になったと差別されました。それは当事者の心に、体の不自由よりももっと深く傷を負わせるものでした。イエス様は障がい者に無関心で差別的な社会にあって、障がいをもった人々を罪人と決めつけるのではなく、人々をいたわり、励まし、手を置いて祈り、癒しました。その愛が人々を回復へと導いたのです。
イエス様はそのあと全員で食事をしょうとしました。当初パンと魚は全く足りませんでした。それはまるで愛と配慮が不足した社会の様です。でもイエス様はそのような中で祈りました。すべての人にパンと魚が行き渡るように祈りました。障がいをもった人への差別がなくなり、愛され、合理的な配慮がなされるように祈ったのです。イエス様が祈ると不思議とパンと魚はすべての人にゆきわたり、余るほどになりました。イエス様の愛と配慮はすべての人に届き、有り余るほどなのです。この食事は主の晩餐でした。主の晩餐は差別と無関心のただなかで行なれ、そこからの解放と、愛と配慮がゆきわたることを求めるものだったのです。
パンと魚を弟子が群衆に配ったことにも注目します。弟子たちはイエス様からそのパンを一度預かって、配る役割を担ったのです。イエス様が愛し、配慮する姿を、弟子たちは同じ様に実践する使命を与えられたのです。
イエス様は差別され、排除されている人を励ますためにこの食事を持ちました。愛と配慮を伝えるために主の晩餐をしたのです。そのようにして社会的なバリアを取り除いてゆこうとしました。きっと私たちの教会が障がいをもった人、弱さをもった人を歓迎するのは、このイエス様の態度、イエスの食事に起源があるのでしょう。イエス様はそのような包容力のある社会、共同体を目指していたはずです。そして食事によってそれを実現しようとしたお方です。私たちもこのような包容力のある人間、包容力のある共同体でありたいと願います。そして私たち自身が、イエス様から受け取ったパン・愛を多くの人に配る使命をいただいています。来週の主の晩餐、このことを覚えてパンを食べましょう。お祈りいたします。
【全文】「信じるために食べる」ルカによる福音書24章13~35節
みなさん、おはようございます。今日も共に集って礼拝ができること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。こどもたちの命の存在を確かめながら、共に礼拝をしてゆきましょう。
今月は主の晩餐について考えています。今日は信仰とは体験しないとわからない一面がある、信仰とは体験してこそわかるものだということについてお話をしようと思います。
私は若い頃、ソムリエを目指していました。ワインの味だけでなく、その世界観にも惹かれていました。ソムリエになるには、ペーパーテストとテイスティングの実技試験があるのですが、最も大切なのは、実際にワインを見て、香りをかいで、飲んでみることです。ワインのテキストにはこのワインはラズベリーやリンゴのような香り、あのワインはルビー色や黄金色といった表現があります。しかしこれらは実際に飲んで初めて理解できるものです。
一番大事なのはテキストを覚えて知識を持つことではなく、ワインを直接見て、香りをかいで、飲んでみる事です。これに勝ることはありません。「百聞は一見にしかず」のように、「百見は一食にしかず」です。実際に飲んでみないと味や香りはわかりません。
もちろん高いワインとなればただやみくもに飲むということはありません。いろいろ勉強してからじっくり飲みます。それでもきっと知識よりも飲んでみることが何より大事です。どんなに説明をされても味や香りは体験しないとわからないものだからです。
それはいろいろなことにも共通すると思います。スポーツや音楽、料理も知識だけではなく実際に体験してみなければ、わからないことがたくさんあるものです。
今日の聖書の個所もそのような事を教えていると思います。どんなに知識としてそれを知っていても、体験をしなければわからないことがあると教えています。そのことを聖書から見てゆきましょう。
今日はルカによる福音書24章13~35節までをお読みいただきました。今日の個所の登場人物は旅をする2人とイエス様です。この二人はおそらくエマオに住んでいました。二人はイエス様の噂を聞きつけてエマオからエルサレムに向かったのです。行いにも言葉にも力がある預言者がいると聞きつけエルサレムに向かったのです。この方こそイスラエルを開放してくださると思ったのです。そして二人はイエス様の話を人づてに聞くのではなく、直接自分の目と耳で確かめようとして、彼らはエルサレムに向かったのです。
彼らはイエス様に会って直接の話を聞くことができたでしょうか。その願いは十分に叶わなかったでしょう。体験することができなかったでしょう。その代わりに彼らが体験したもの、見たものは、イエス様の十字架でした。直接その話を聞き、力をもらいたいと思っていたのに、自分たちが体験し見たのは残酷な処刑だったのです。
しかし彼らはエルサレムに滞在中にもうひとつ不思議な話を聞きました。それは3日後の朝早く、弟子の女性がイエス様の墓に行ったところ、その遺体がなくなっており、天使たちが現れて「イエスは生きている」と言ったという話でした。イエス様が復活をしたという話を聞いたのです。
二人は、話を聞きたいと思っていた人が殺され、その後復活したという話を聞き、混乱したでしょう。理解できないままエマオに帰ることになり、十字架と復活の意味を論じ合いながら帰りました。
そんな彼らに復活したイエス様はそっと現れます。イエス様は光り輝いて登場するのではありません。イエス様の方から近づいてきて、一緒に歩くように、寄り添うように現れます。覚えておきましょう。私たちの神様はそのように私たちに現れるのです。私たちが良い行いをした時、強い光に包まれた華々しい存在が登場するのではありません。
願いが叶わず、出来事の意味が十分に理解できず、うつむき歩いて帰る時、神様はそっと近づいてきて、寄り添うように現れるのです。そのようにして神様は私たちに伴ってくださるお方です。このことを忘れないでいたいと思っています。
主の晩餐でもそうですが、イエス様がこのように人に他者に寄り添う人だったということを思い出すことが大事です。私たちの人生には苦しいこと、思いどおりにならないことがたくさんあります。そんな中でイエス様は私たちとそっと共にいて、励まし、導いてくださるのです。だから私たちは歩むことができるのです。そのことを覚えておきましょう。この物語の大切なポイントです。
今日はこの物語から主の晩餐について考えたいと思います。旅をする二人はイエス様のことをとても良く知っていました。二人がエルサレムの出来事を説明する様子はまるでキリスト教全体の説明のようです。彼らはイエス様とはどんな人か、どのように生き、どのように死んだのか的確にまとめられています。二人はイエス様のことをよく知っていました。しかし彼らはそれを知っているだけで、経験をしたことはありませんでした。
イエス様は旅路で二人に熱心に説明をしました。地上に生まれた救い主は、苦しみを受けた後に栄光に入ること、聖書全体にそのことが書いてあることを熱心に説明をしました。二人は何かを理解したのでしょうか。そうは書いてありません。二人はよく知っていました、二人は熱心な説明を受けました。しかしそれでもまだ彼らには変化が無いようです。
イエス様は彼らと食事をすることになりました。今度は二人がイエス様を引き留めました。先をいそぐイエス様を無理に引き留めて、一緒に食事をしようと招いたのです。30節に食事の様子が記されています。そこにはこうあります。「イエス様はパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いて渡した」。ここでは明らかに主の晩餐が行われました。そうすると彼らは目が開けたのです。
二人の目が開けたとは、どんな意味でしょうか。二人は目が見えていなかったわけではありません。確かに見えていました。目が開けたとは、今まで見えなかったもの、わからなかったものが、わかるようになったということです。それが一緒に食べたその時に起りました。
一緒に食べた時、一緒にいるのがイエス様だと気づいたのです。彼らは事前に十分に学び、知識を持っていました。イエス様から直接、熱心に教えを受けていました。しかし彼らは目が開いていなかったのです。彼らの目が開かれたのは、主の晩餐を受けた時でした。
この特別な食事を体験して、二人は初めて気付いたのです。彼らが気づいたのは自分と一緒に伴っているのがイエス様だったということです。彼ら気付いたのはイエス様が復活をして私たちと共にいるということでした。二人はこの食事・主の晩餐を通じて、わかったのです。二人はこれに気付き、エルサレムの仲間の元に戻ってゆきました。それが今日の物語です。
この物語は私たちの主の晩餐とどんな関係があるでしょうか。私たちの教会の主の晩餐はバプテスマを受けた方に限定しています。それはイエス様のことをわかった人、すでに信じている人が食べているはずです。しかしどうでしょうか、今日の聖書箇所によれば、食べることによって信仰が深まるようになるのです。
私たちは信じて食べているのでしょうか。それとも食べることによって信じるようになるのでしょうか。私にはどちらなのかよくわかりません。どんなに知識として知っていても、食べなくては目が開かれません。私たちがイエス様を信じるためには知識だけではなく、パンを食べることも必要なのです。
私たちは信じているから食べるのでしょうか?それとも食べるから信じる事ができるのでしょうか?実はそれはどちらが先というものなのではなく、あいまいなのかもしれません。私は信じるために食べているような気がしています。
確かにこの二人のようにイエス様のことを良く知ってから食べるべきなのかもしれません。大切なイエス様の体です。その意味をよく分かってから食べてもらいたいと思います。でもこの二人はどんなに熱心に説明をしても、わかりませんでした。イエス様が直接説明してもだめでした。二人はこの食事を体験をするまでわからなかったのです。食べて初めて、食べたその時、イエス様のことがわかったのです。
この物語は私たちの主の晩餐ともきっと重なる部分があるでしょう。私たちは主の晩餐を勉強したから食べるのではありません。きっとどれだけ勉強をしてもわからないことがあるでしょう。食べてみなければわからないことがあるでしょう。そして食べればわかることがあるのでしょう。私たち自身もこの二人のような存在です。いろいろ知っているけれど、食べてわかるようになる存在なのです。このように今日の物語は、パンを食べる体験を通じて、イエス様がどんな人だったのかをわかったという物語です。
私は信じてからパンを食べるのか、パンを食べてから信じるのか、聖書はどちらの可能性にも開かれていると思います。私たちはどのようにパンを食べるでしょうか。私たちのあの小さなパンにどんな意味があるのでしょうか。私たちは信じているから食べるのでしょうか、食べるから信じるのですしょうか。きっと信仰とは体験しないとわからない一面があるのでしょう。信仰とは体験してこそわかるものなのでしょう。そのことに思いを巡らせながらまた主の晩餐をしてゆきたいと思います。
イエス様はきっとそのような迷いや混乱に伴ってくださる方です。あの出来事にどのような意味があるのか、二人は熱心に論じ合いました。論じ合うそのそばにそっと近づき、導いてくださるお方です。お祈りします。
「信じるために食べる」ルカによる福音書24章13~35節
一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。ルカによる福音書24章13~35節
今月は主の晩餐について考えています。今日は信仰とは体験しないとわからない一面がある、信仰とは体験してこそわかるものだということについて考えます。
ソムリエのためのワインのテキストには様々ことが書かれています。しかし一番大事なのはワインを実際に飲んでみる事です。これに勝ることはありません。どんなに説明をされても味や香りは体験しないとわかりません。それはスポーツや音楽、料理にも共通します。今日の聖書の個所もどんなに知識として持っていても体験をしなければわからないことがあると教えています。
聖書の二人はイエス様を直接確かめようとしてエルサレムに向いました。しかし二人が見たものは、イエス様の十字架でした。そして彼らはイエス様が復活をしたという不思議な話も聞きました。二人は一体に何が起きたのか十分に理解できないまま、帰ることになったのです。そんな彼らに復活したイエス様がそっと現れます。
覚えておきましょう。私たちの神様は私たちが良い行いをした時に登場するのではありません。願いが叶わず、出来事の意味が十分に理解できず、うつむき歩いて帰る時、神様はそっと近づき、寄り添うように現れるのです。そのようにして神様は私たちに伴ってくださるお方です。この物語の大切なポイントです。
今日はこの物語から主の晩餐について考えます。二人がエルサレムの出来事を説明する様子はまるでキリスト教全体の説明のようです。彼らは事前に十分に学び、イエス様から直接、熱心に教えを受けていました。しかし彼らの目が開かれたのは、主の晩餐を受けた時でした。二人はこの特別な食事を体験して、初めてイエス様が復活をして共にいるということに気付きました。二人はこの食事・主の晩餐を通じて、それがわかったのです。
この物語は私たちの主の晩餐とどんな関係があるでしょうか。私たちは信じてから食べているのでしょうか。それとも食べることによって信じるようになるのでしょうか。私はあいまいかもしれません。信じるために食べているような気がしています。私たちは主の晩餐について食べてみなければわからないこと、食べればわかることがあります。私たち自身もこの二人のような存在です。いろいろ知っているけれど、食べてわかるようになる存在なのです。私は信じてからパンを食べるのか、パンを食べてから信じるのか、聖書はどちらの可能性にも開かれていると思います。
私たちはどのようにパンを食べるでしょうか。きっと信仰とは体験しないとわからない一面があるのでしょう。そのことに思いを巡らせながらまた主の晩餐をしてゆきたいと思います。イエス様はきっとそのような迷いや混乱に伴ってくださる方です。論じ合うそのそばにそっと近づき、導いてくださるお方です。お祈りします。
【全文】「よく確かめてから食べる」 Ⅰコリント11章17~34節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日も小さなこどもたちの命を感じながら、礼拝をしましょう。
今月は主の晩餐について考えています。そして教会の運営するこども食堂「こひつじ食堂」のことも分けては考えられないと思っています。
こひつじ食堂で一番混乱するのは、ご飯(ライス)がなくなったときです。次のお客さんの分が足りないとわかってから、お米を研いで、炊飯ボタンを押しても、もう間に合いません。1時間後にご飯が足りるかどうかを逆算しなければいけません。もしご飯がなければ食べに来てもその食事は台無しです。
200人でどれくらいのご飯を準備すれば良いのでしょうか。一人180gのご飯を食べるとします。180gを200食用意すればいいので、36kgのご飯があればいいのです。お米は炊飯すると水を吸収して2.3倍の重さになるということから逆算すると約16kgのお米が必要です。お米は1合150gなので、16kgのお米は104合です。104合炊けば足りる計算です。だいたいでは準備できない数量です。
教会には1升炊きの炊飯器が8個あります。ですから11回炊飯すれば良いのです。しかし1升炊きの炊飯器でも9合くらいの方がおいしく炊けることが分かりました。8個の炊飯器で9合ずつ12回炊飯します。さらに微調整が必要です。220食の時はもう1回炊飯します。180食の時は1回減らします。実際にご飯を盛り付けるときには、目分量で盛り付けると必ずずれがあるので、一つ一つ180gを測りながら盛り付けています。
ここまで計算して準備しても時々ご飯が足りなくなってしまう時があります。確認を忘れてしまっている時、一人でやっている時、後回しにしてしまった時、それが起きます。そんな時は待たせてしまったり、少なくなったりして申し訳ない気持ちでいっぱいになります。これはお米の話ですが、食材ひとつひとつにもこのように注意しなければいけないことがたくさんあります。
何が言いたいかというと、それだけ良く確かめながらやっているということです。配慮をしているということです。全員が楽しく食べるためには、きめ細かい確認と、配慮が必要です。だいたいの人が食べれればいい、一部の人だけ食べればいい、食べられなかったらごめんなさいというのなら簡単です。でもそれをせずに全員で一緒に食べようとする時、様々な確認と配慮が必要です。
ご飯が足りるかどうかは私だけではなく、みんなで気にかけています。私一人では目が行き届かないことが多く、たくさんの人に良く確かめ、気にかけてもらう必要があります。残りがあとどれくらいかを良く確かめて全員分ある、大丈夫だということを確認しながら進めています。みんな自分の分があるかを確かめているのではありません、全員分、足りるかどうかを確かめながら食堂をしています。それはとても大切な配慮だと思います。
今日は聖書の食事の中にどんな配慮があったのか、無かったのかを見てゆきます。そこから聖書が伝えている配慮と、私たちが他者に目を向けてゆく生き方について考えたいと思います。
今日はⅠコリント11章をお読み頂きました。ここにはコリント教会での食事についての記録が残っています。コリント教会では礼拝の後、みんなで持ち寄りの食事会を行っていました。これは垣根のない、誰でも参加できる食事会でした。当初はこれを主の晩餐と呼んでいました。
この食事会は、イエス様が罪人や他の宗教の人々と共に食事をしたように、異なる者同士が互いを大切にする愛の確認の場でした。しかし、ここで問題が発生していました。パウロは17節でこの点を指摘し、良い結果ではなく悪い結果が生じていると述べています。それはどんな問題かというと21節、食事の時に先に食べて、先に飲んでしまう人がいたという問題でした。後から空腹の人がやって来る時には、食べ散らかした残り物しかないという状態でした。パウロはこの点を褒めることはできないと言っています。コリント教会では食事の際に、全員分が足りるかという配慮が全くなく、自分の事だけを考えて食事をしていたのです。少し驚きです。
さらにこのような食事の背景には経済的な格差があったのではないかと言われています。コリント教会の中には、お金持ちの人と貧しい人がいました。お金持ちは仕事を早く終わらせて、おいしいものをたくさん持って来て、先に楽しくやっていたのです。
そこに後から忙しく働かなければいけない貧しい人が来ました。しかし食事に加わろうとすると、食べ散らかした中で余り物を食べました。あるいはもう自分の分は残っていなかったのです。22節これでは貧しい人々は恥をかきました。
コリント教会ではこのような食事会が行われており、それをパウロは注意をしています。食事会をするならば全員が食べることが出来るように、食事の量や内容や、持ち方を良く確かめて、配慮しなさいと言っています。
コリント教会の人はどうすればよかったのでしょうか。パウロはどのような食事を期待したのでしょうか。例えば33節で提案されているのは、みんなが揃うまで待つという方法です。他にも例えば後から来た人の分が食べ残しにならない様に、ちゃんと先に取り分けておいて残しておくというのはどうでしょうか。最初にいる人だけで乾杯をしたのなら、後でまた全員が揃った時もう一度乾杯をしてはどうでしょうか。そういう確認や配慮や工夫は今の私たちには当然のことのように感じます。しかしコリント教会にはそれがまったくなかったのです。
どうしてそのような雰囲気になってしまったのでしょうか。仲間割れが起きてしまったのでしょうか。みんな我先にと食べたのでしょうか。自分の分だけにしか興味がなかったのでしょうか。コリント教会は誰が食べられないのかに対して良く確かめずに食べていました。自分だけ食べてしまう、その根底にはどんな考えがあったのでしょうか。
きっとそこには他者への無関心や無理解があったでしょう。きっとコリント教会の問題は食事会のことだけではなかったはずです。そのような食事をする共同体の中には、忘れられている人、一人になっている人、見下されている人、後回しにされている人がたくさんいたはずです。様々な問題がおきていたはずです。
パウロはそのような共同体になっていないかよく確かめるようにいっています。そのような、後回しにされた仲間がいないかという確かめ合いと、配慮が出来ないのであれば、もう一緒の食事会はやめるようにと言っています。自分の家でそれぞれ食べてから集まるようにしなさいと言っています。実際にこの後コリント教会の人々は一緒に食事をすることを諦めてしまいました。そして主の晩餐は小さなパンとワインを飲む儀式として改めて残ってゆきました。それが私たちの今の主の晩餐のルーツです。
パウロがここで伝えようとしていること、聖書が伝えようとしていることは何でしょうか。ここでは主の晩餐を自分の内面や罪深さと深く向き合って、よく確かめてこのパンを食べる様にと言っているのではありません。
ここでよく確かめるべきことは、他の人との関係性です。他者のことを考えながら食べる様にと言っているのです。自分の食べ物、自分の事、自分の罪を考えて食べるだけではなく、他者の食べもの、他者の事、他者への配慮をよく確かめて食べる様にと言っているのです。ここにどんな他者がいるのか、どんな他者がいないのかをよく確かめてから食べなさいと言っているのです。
パウロはイエス様がどのように人々と食事をしたのか思い出そうと言っています。自分がこれから十字架に掛かるという時において、イエス様が一緒に食事をしたのを思い出そうと言っています。あの時イエス様は十字架の後も互いに仲間であると確認し、その記念として食事をしました。そしてそれを繰り返すように教えたのです。
パウロはふさわしくないままで食べてはいけないとあります。わたしたちはどこまで、その食事にふさわしい者でしょうか。私は自分自身をふさわしくないと思っています。周りの人を良く確かめて配慮することがまだまだ足りないと思っています。そのような中でも、主の晩餐を食べるのですけれども、のども通らないような気持ちで食べています。
私たちはどのように主の晩餐を食べ、生きるでしょうか。私はふさわしい者になりたいと思っています。食べ物が全員にいきわたる配慮ができる人になりたいと思っています。食事の時だけではなく様々な場面で、忘れられている人、一人になっている人、後回しにされている人がいないかに目を配り、よく確かめたいと思います。それは難しい事だと思います。でも精一杯それをしてゆきたいと思います。それが今日の聖書箇所が指し示している生き方ではでしょうか。
ひとりも取り残されず、ひとりも忘れられない、そのようによく確かめられ、配慮された共同体が神の国と呼ばれるのではないでしょうか。私たちは今週1週間、それぞれの場所でそれをよく確かめて生きてゆきましょう。神様はそのようにして私たちのいる場所に働き、導いてくださっています。お祈りします。
「よく確かめてから食べる」 Ⅰコリント11章17~34節
だれでも、自分をよく確かめたうえで、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。
コリントの信徒への手紙Ⅰ 11章28節
こひつじ食堂で一番混乱するのは、ご飯がなくなったときです。計算して準備しても時々ご飯が足りなくなってしまう時があります。全員が楽しく食べるためには、きめ細かい確認と、配慮が必要です。それをみんなで確認します。それぞれ自分の分があるかを確かめているのではありません、全員分、足りるかどうかをみんなで確かめながら食堂をしています。それはとても大切な配慮だと思います。今日は聖書の食事の中にどんな配慮があったのかを見てゆきます。
コリント教会では礼拝の後、みんなで持ち寄りの食事会を行っていました。当初はこれを主の晩餐と呼んでいました。しかし食事の時に先に食べて、先に飲んでしまう人がいました。後から空腹の人がやって来る時には、食べ散らかした残り物しかないという状態でした。コリント教会では食事の際に、全員分が足りるかという配慮が全くなく、自分の事だけを考えて食事をしていたのです。パウロは食事会をするならば全員が食べることが出来るように、食事の量や内容や、持ち方を良く確かめて、配慮しなさいと言っています。
自分だけ食べてしまう、その根底にはどんな考えがあったのでしょうか。他者への無関心や無理解があったでしょう。食事の事だけではなく忘れられている人、一人になっている人、見下されている人、後回しにされた人がたくさんいたはずです。
パウロはそのような共同体になっていないかよく確かめるように言っています。パウロがここで伝えようとしていることは主の晩餐を自分の内面や罪深さと深く向き合って、よく確かめてこのパンを食べる様にと言っているのではありません。
ここでよく確かめるべきことは、他の人との関係性です。自分の食べ物、自分の事、自分の罪を考えて食べるだけではなく、他者の食べもの、他者の事、他者への配慮をよく確かめて食べる様にと言っているのです。
パウロはふさわしくないままで食べてはいけないとあります。わたしたちはどこまで、その食事にふさわしい者でしょうか。私は自分自身をふさわしくないと思っています。周りの人を良く確かめて配慮することがまだまだ足りないと思っています。そのような中でも、主の晩餐を食べるのですけれども、のども通らないような気持ちで食べています。
私たちは食事の時だけではなく様々な場面で、忘れられている人、一人になっている人、後回しにされている人がいないかに目を配り、よく確かめたいと思います。それが今日の聖書箇所が指し示している生き方ではでしょうか。
ひとりも取り残されず、ひとりも忘れられない、そのようによく確かめられ、配慮された共同体が神の国と呼ばれるのではないでしょうか。私たちは今週1週間、それぞれの場所でそれをよく確かめて生きてゆきましょう。神様はそのようにして私たちのいる場所に働き、導いてくださっています。お祈りします。
【全文】「縁食的主の晩餐」マタイによる福音書26章20~30節
夕方になると、イエスは十二人と一緒に食事の席に着かれた。
マタイによる福音書26章20節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの命の声を聞きながら共に礼拝をしましょう。
先月まで使徒言行録を読んでいましたが、7月からは主の晩餐について考えたいと思っています。主の晩餐とはパンを食べ、ブドウジュースを飲む儀式です。この儀式はイエス・キリストを思い出すために行われています。今日もこの後行われます。主の晩餐は多くの教会で行われていますが、その方法や理解は教会によって異なります。私たちの教会では月1回行っていますが、年4回のみという教会もあれば、毎週行うという教会もあります。また私たちの教会では洗礼・バプテスマを受けたクリスチャンが食べるとしていますが、教会によっては洗礼・バプテスマを受けていなくても、信じる気持ちがある人は食べてよい教会、だれでも食べてよい教会など、教会によって様々な考え方があります。大切なのは、なぜこの主の晩餐を行うのか、しっかりと説明できることです。
今月はこの主の晩餐について考えてゆきましょう。また今日はこひつじ食堂で起きている「縁食」ということも参考にゆきたいと思います。私たちの教会で主の晩餐を考える時、こひつじ食堂という教会特有の事柄も考える必要があると思います。先日、200個のクロワッサンと500個のメロンパンの寄付をいただき、食堂で提供をしました。食堂と主の晩餐は別のものですが、同じ場所でパンが分かち合われていることは互いに影響しあうでしょう。
昨年度、こひつじ食堂にボランティアに来ていた大学院生の方が、こひつじ食堂のことを分析し、共生文明学の観点から論文としてまとめてくれました。彼が私に「縁食」という言葉を教えてくれました。どの文明でも共通して、共に食事をすることは仲間であることを確認する意味があるそうです。一緒に食べる「共食」という行為は共同体を作ることにつながります。また反対に誰と食事をしないかは、お互いが別々の共同体であることをはっきりさせる行為です。どのように食べるかは、どのような共同体を作るかにつながっています。多くの文明で共食が文明を作っています。
その中で彼が教えてくれた「縁食」とは、誰かと一緒に食事をしているのかあいまいな食事を指します。一人ではないが、一緒でもない食事です。古い家の縁側が家の中と外の中間地帯であるように、一緒なのかそうでないのかあいまいな食事、それが「縁食」です。
「縁食」はこひつじ食堂でもよく見かける光景です。例えば一人で来たけれど、ボランティアと顔見知りで何か話しながら食べています。食べているのは一人ですから「共食」ではありません。でもそれは決して孤独な食事でもありません。それが「縁食」です。他にもこひつじ食堂にはいろいろな「縁食」があります。相席になって向かい側の人と挨拶するような場面があります。一緒でも孤独でもない、それが縁食です。遠くのテーブルに仲の良い友達が座っていたりして、一緒に食べているのかあいまいです。そのような緩やかなつながりの中で食べるのが「縁食」です。
それはまるで縁側での交流のようです。近所の人が来て家の縁(ふち)でお茶をします。そこは家の中でもなく、外でもない中間地点・縁(ふち)です。あの縁側のような緩やかな関係で食べる食事が縁食です。こども食堂はそのような「縁食」がたくさんあります。私たちは食事の在り方について、もっと自由に考えてもよいかもしれません。私たちは一人で食べるか、みんなと食べるかという2つの基準しか持っていないかもしれません。でももっと緩やかな関係の中の食事があることに気づかされます。その楽しさを私たちは知っています。こひつじ食堂を今後もそのような「縁食」の場所として続けてゆきたいです。
私たちの教会の主の晩餐はどうでしょうか。私たちの教会の主の晩餐は限られた人だけでする食事です。この食事は誰がこの共同体に属しているか、誰が共同体に属していないのかを明確にします。一緒に食べた人は結束します。一方、一緒に食べていない人は何を感じているのでしょうか?どう食べるかは、どんな共同体を作るかを決めています。私たちの主の晩餐においても縁側は必要でしょうか?縁食が必要でしょうか?それはもっと緩やかな食事の可能性に開かれた主の晩餐です。今日は聖書から私たちの主の晩餐にどんな可能性があるのかを考えてゆきたいと思います。
聖書を読みましょう。今日はマタイによる福音書26章20~30節をお読みいただきました。この食事は最後の晩餐と呼ばれる箇所で、イエス様が十字架に掛かる直前に行われた食事会です。この食事にはどんな人々がいたでしょうか?この最後の晩餐はイエス・キリストに従う者に限定された食事でした。
これが私たちの主の晩餐のルーツです。この食事が12人の弟子に限定されていたことには大きな意味があります。イエス様は自分に信じて従う者に“のみ”パンとワインを授けました。現在の私たちが主の晩餐で、クリスチャンだけにパンとブドウジュースを飲むのを限定しているのは、この時の食事が12人の弟子に限定されていた事に起源があるからです。しかし、どこまで私たちの主の晩餐と同じ意味で限定がされているでしょうか。例えばこの時代はまだキリスト教という概念も、入信のための洗礼・バプテスマという儀式もありませんでした。12人の中に洗礼・バプテスマを受けた弟子は一人もいませんでした。彼らは洗礼・バプテスマを条件とせず、ただ主イエスに招かれて、パンを与えられたのです。この食事は洗礼・バプテスマを受けないと参加できないという食事ではありませんでした。信仰を条件とした食事ではありませんでした。その意味において、この食事は私たちの主の晩餐よりももっと緩やかな食事でした。
確かにこの食事はずっと旅を共にし、苦楽を共にしてきた、顔見知りに限定された食事でした。しかし関係はそれだけでもありません。この食事には後にイエス様を裏切るユダも含まれていました。この食事は信じて従った者だけのものではありませんでした。イエス様を理解せず、誤解し、信じるどころか、裏切りを確信している者さえも含んだ食事でした。他の弟子たちも同じです。弟子たちはこの後すぐにイエスを見捨てて逃げだします。彼らは本当に信じて従っていたのでしょうか。この食事会は参加者の中に信じる人も、信じない人もいた非常に幅のある集まりだったのです。
そしてさらにイエス様自身が「この杯は多くの人のために流される血」だ言っています。ワインを自分がこのあと十字架で流す血になぞらえています。しかしそれは弟子に限定されて流される血ではありません。それは多くの人々のために流される血です。それは限定された集団ではなく不特定多数の人を指しています。イエス様の血はクリスチャンのためだけに流されたのではありませんでした。イエス様の顔見知りの仲間内のためだけに流さたのでもありません。イエス様の血と十字架は信じていない人、裏切り者、不特定多数の多くの人々、多様な人々、まだ出会ったことすらない人々のためにも流されるものなのです。この食事はそのように多くの人々との出会いに向けられた食事だったのです。
私はこのように最後の晩餐を見る時、そこに「縁食」の要素があると思います。その食事は、確かに共同体性の強い食事でしたが、でもそれを越える大きな可能性を持った食事でした。その食事は信じて洗礼を受けた人のみならず、裏切る人、まだ見ぬ不特定多数の人、多様な人に開かれる可能性のある食事だったはずです。そのような食事が最後の晩餐だったのです。そのような食事がイエス・キリストを忘れないために行われた食事だったのです。それが私たちの主の晩餐のルーツなのです。
どんな食事をするか、それはどんな共同体を作るかに直結しています。それは共生文明学でも、キリスト教でも同じでしょう。どんな主の晩餐をしてゆくのかは、どんな教会を作るかに直結してゆくでしょう。私たちはどんな主の晩餐をしてゆくのでしょうか?マタイ26章の主の晩餐は何を指し示しているでしょうか。限定されている様に見えて実は開かれている部分がある、縁側のような部分があるのではないでしょうか。
おそらく私たちには一緒に食べるか、別々に食べるかという二者択一ではない選択肢があるはずです。主の晩餐は様々な在り方、緩やかさの可能性に開かれているはずです。きっと縁側のような、開かれた温かい出会いが生まれてくる、主の晩餐があり方があるはずです。
もし縁側があれば、誰が内側で誰が外側かあいまいになるでしょう。誰が共同体のメンバーで、誰が共同体のメンバーではないのかが曖昧になるかもしれません。でもそこに食堂のような思わぬ出会いが待っているのではないでしょうか。これまで決して入ってこなかった人々が、入ってくるような出会いがそこから広がっていくのではないでしょうか。マタイの主の晩餐を、そのような開かれた緩やかな食事の起源とすることができるのではないでしょうか。
そして緩やかに開かれる姿勢はきっと教会の在り方だけにとどまらないはずです。私たち一人一人がどう生きるかにも関わって来るはずです。私たちは日々誰と食事し、誰と食事をしていないでしょうか?私たちはもっとそれに気を配り、私たちはもっと緩やかに考えても良いのかもしれません。異なる他者とどう緩やかな関係を持つかを問いかけているように思います。この後、私たちは主の晩餐を持ちます。共に主イエス・キリストとの食事を思い出しましょう。そしてそこにいた様々な人々を思いめぐらせましょう。お祈りします。
「縁食的主の晩餐」マタイによる福音書26章20~30節
夕方になると、イエスは十二人と一緒に食事の席に着かれた。
マタイによる福音書26章20節
7月から主の晩餐について考えます。主の晩餐とはパンを食べ、ブドウジュースを飲む儀式です。私たちの教会では洗礼を受けたクリスチャンが食べるとしています。私たちの教会で主の晩餐を考える時、こひつじ食堂のことも考える必要があるでしょう。同じ場所でパンが分かち合われていることは互いに影響しあいます。
こひつじ食堂のことを共生文明学の観点から論文としてまとめてくれた方が私に「縁食」という言葉を教えてくれました。どの文明でも共通して、共に食事をすることは仲間であることを確認する意味があるそうです。どのように食べるかは、どのような共同体を作るかにつながっています。その中で彼が教えてくれた「縁食」とは誰と一緒に食事をしているのかあいまいな食事を指します。「縁食」はこひつじ食堂でもよく見かける光景です。例えば一人で来たけれど、ボランティアと顔見知りで何か話しながら食べています。それは「共食」でも孤食でもない「縁食」です。
私たちの教会の主の晩餐はどうでしょうか。私たちの教会の主の晩餐は限られた人だけでする食事です。この食事は誰がこの共同体に属しているか、誰が共同体に属していないのかを明確にします。一緒に食べた人は結束します。一方、一緒に食べていない人は何を感じているのでしょうか?どう食べるかは、どんな共同体を作るかを決めています。私たちの主の晩餐においても縁側が必要でしょうか?今日は聖書から私たちの主の晩餐にどんな可能性があるのかを考えてゆきたいと思います。
マタイによる福音書26章の食事は最後の晩餐と呼ばれます。12人の弟子に限定されていた食事が私たちの主の晩餐のルーツです。しかし12人の中に洗礼を受けた弟子は一人もいませんでした。彼らは洗礼を条件とせず、ただ主イエスに招かれて、パンを与えられたのです。この食事会は参加者の中に信じる人も、信じない人もいた非常に幅のある集まりだったのです。
そしてさらにイエス様の血と十字架は、信じていない人、裏切り者、不特定多数の多くの人々、多様な人々、まだ出会ったことすらない人々のためにも流されるものでした。この食事も多くの人々との出会いに向けられた食事だったのです。
私はこのように最後の晩餐を見る時、そこに「縁食」の要素があると思います。もともとは共同体性の強い食事でしたが、でもそれを越える大きな可能性を持った食事でした。それが私たちの主の晩餐のルーツなのです。どんな食事をするか、それはどんな共同体を作るかに直結しています。どんな主の晩餐をしてゆくのかは、どんな教会を作るかに直結してゆくでしょう。私たちはどんな主の晩餐をしてゆくのでしょうか?マタイ26章の主の晩餐には限定されている様に見えて、実は開かれている部分があります。そこに縁側のような部分があるのではないでしょうか。
この後、私たちは主の晩餐を持ちます。共に主イエス・キリストとの食事を思い出しましょう。そしてそこにいた様々な人々を思いめぐらせましょう。お祈りします。
【全文】「他者を励ます使命」使徒言行録27章13節~44節
しかし今、あなたがたに勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうちだれ一人として命を失う者はないのです。 使徒言行録27章22節
使徒言行録には、イエス様の弟子たちがどのように生き、信仰を実践したかが記されています。今日もこの使徒言行録から、困難の中でも希望を持ち、他者を励ます生き方について学んでゆきましょう。パウロは船でローマに向かう途中、激しい嵐に遭遇しました。人々は積み荷を捨てて、船を軽くしようとしました。しかしそれでも状況は改善しませんでした。彼等は希望を失っていました。
しかしそんな時、一人だけ希望を失わなかった人物がいました。それがイエス・キリストの弟子パウロです。パウロは希望をもって人々を励まし続けました。そしてこのような希望を持った人物が船の中に一人でも存在すると全体の雰囲気は大きく変わります。このように希望を持ち続け、他者を励まし続けることは、キリストの弟子の大事な役割です。希望を持っているのは一人でよいのです。私たちはそのような一人になっているでしょうか。私たちはたった一人になっても、まだ希望があると言える存在になりたいと思います。それがキリストの弟子になるということです。
希望をもってあきらめない人がいる中で、逃げ出した船員がいたとあります。それはとても悲しい光景です。彼らは自分たちだけ助かろうとしました。これは他者を犠牲にし、見捨てるという罪です。キリストの弟子パウロはこのような行動を見逃しません。それは全員が助かる道ではないと引き留めます。全員で助かろうとみなを励ましたのです。全員が生きる道を求める、それがイエス・キリストの教えでした。誰かが十字架に掛かって犠牲になって、みんなが助かればいいのではありません。神様は一人も漏れることなく、命を守ろうとするお方です。
36節、この後船に乗っていた人びとは食事をしたとあります。それはまるで主の晩餐のようです。その食事をすると一同に元気が湧いてきました。全員が励まされて、全員で助かろうと思う様になったのです。船の人々は大きく変えられてゆきました。一人のキリストの弟子から、主の晩餐のような食事から全体が変えられてゆきました。全員が助かるために、すべての食べ物を捨てる決断をしたのです。自分の命だけではなく、みんなが助かるために、大切な荷物を捨てました。そして全員が無事に上陸することができたのです。
今日の物語、船は様々なものに置き換えて考えることができます。教会も一つの船です。家族も一つの船かもしれません。職場や地域も一つの船でしょう。それぞれ困難に直面します。でも一人の弟子の存在が全体の雰囲気を変えるのです。
その船にキリストの弟子が一人いればいいのです。人を励まし、共に命をつないでいこうとする希望を示す人が一人いると、全体の雰囲気は大きく変わります。全員の命をつなぐ選択へと導かれてゆくのです。私たちはそれぞれの置かれた場所で、その一人になってゆきましょう。神様の言葉に聞きながら、他者を励まし、希望を持つその一人になりましょう。お祈りします。
「他者を励ます使命」使徒言行録27章13節~44節
しかし今、あなたがたに勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうちだれ一人として命を失う者はないのです。 使徒言行録27章22節
使徒言行録には、イエス様の弟子たちがどのように生き、信仰を実践したかが記されています。今日もこの使徒言行録から、困難の中でも希望を持ち、他者を励ます生き方について学んでゆきましょう。パウロは船でローマに向かう途中、激しい嵐に遭遇しました。人々は積み荷を捨てて、船を軽くしようとしました。しかしそれでも状況は改善しませんでした。彼等は希望を失っていました。
しかしそんな時、一人だけ希望を失わなかった人物がいました。それがイエス・キリストの弟子パウロです。パウロは希望をもって人々を励まし続けました。そしてこのような希望を持った人物が船の中に一人でも存在すると全体の雰囲気は大きく変わります。このように希望を持ち続け、他者を励まし続けることは、キリストの弟子の大事な役割です。希望を持っているのは一人でよいのです。私たちはそのような一人になっているでしょうか。私たちはたった一人になっても、まだ希望があると言える存在になりたいと思います。それがキリストの弟子になるということです。
希望をもってあきらめない人がいる中で、逃げ出した船員がいたとあります。それはとても悲しい光景です。彼らは自分たちだけ助かろうとしました。これは他者を犠牲にし、見捨てるという罪です。キリストの弟子パウロはこのような行動を見逃しません。それは全員が助かる道ではないと引き留めます。全員で助かろうとみなを励ましたのです。全員が生きる道を求める、それがイエス・キリストの教えでした。誰かが十字架に掛かって犠牲になって、みんなが助かればいいのではありません。神様は一人も漏れることなく、命を守ろうとするお方です。
36節、この後船に乗っていた人びとは食事をしたとあります。それはまるで主の晩餐のようです。その食事をすると一同に元気が湧いてきました。全員が励まされて、全員で助かろうと思う様になったのです。船の人々は大きく変えられてゆきました。一人のキリストの弟子から、主の晩餐のような食事から全体が変えられてゆきました。全員が助かるために、すべての食べ物を捨てる決断をしたのです。自分の命だけではなく、みんなが助かるために、大切な荷物を捨てました。そして全員が無事に上陸することができたのです。
今日の物語、船は様々なものに置き換えて考えることができます。教会も一つの船です。家族も一つの船かもしれません。職場や地域も一つの船でしょう。それぞれ困難に直面します。でも一人の弟子の存在が全体の雰囲気を変えるのです。
その船にキリストの弟子が一人いればいいのです。人を励まし、共に命をつないでいこうとする希望を示す人が一人いると、全体の雰囲気は大きく変わります。全員の命をつなぐ選択へと導かれてゆくのです。私たちはそれぞれの置かれた場所で、その一人になってゆきましょう。神様の言葉に聞きながら、他者を励まし、希望を持つその一人になりましょう。お祈りします。
【全文】「命こそ宝 平和への方向転換」使徒言行録16章16~34節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できることを主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日も命の声に囲まれながら礼拝をしてゆきましょう。
今日6月23日は79年前、沖縄で組織的な戦闘が終わった日です。私たちはこの日を「命どぅ宝の日」と呼び、平和を考える時として大切にしています。79年前、沖縄では激しい地上戦がありました。その時、軍隊や武器は国民を守りませんでした。日本軍は自分が助かるためなら一般市民でも殺しました。それが軍隊の本当の姿です。沖縄の人々は激しい地上戦の中で、洞窟に逃げ込みました。そしてそこで、どう死ぬか、どう殺すかでなく、どうやって命をつなぐかを考えました。彼らは洞窟の中で「命どぅ宝」「命どぅ宝」、命こそ宝だと互いに励ましあい、何とかして生きようとしました。
「命こそ宝」「命こそ宝」。暴力が充満し、殺すか死ぬかの選択肢しかないと思える場所で、沖縄の人々は生きるという選択をしました。生き残った人は決して多くありませんでした。だからこそ、命こそ宝と言う言葉は私たちに問いかけています。私たちは暴力か平和かどちらかを選ばなくてはいけません。暴力を選びながら平和を目指すことはできません。平和のための暴力も存在しません。
沖縄にはあの時から今も大きな基地がいくつも存在します。私たちは普天間、辺野古を含めて沖縄、日本、世界のすべての基地がなくなることを祈り願っています。それが平和の神様の御心だと信じています。
沖縄の普天間基地の前では毎週月曜日、クリスチャンが集まり讃美歌を歌っています。基地の前で暴力ではなく平和が欲しいと歌っています。基地の騒音と犯罪に苦しみ、平和を求める人たちが歌っています。私たちも神を信じる同じ人間だと讃美歌を歌っています。基地の前で神に向けて、兵士に向けて讃美歌を歌っています。それに呼応して戸塚駅の駅前でも月1回、第二月曜日に讃美歌が歌われています。沖縄だけの問題にしないために戸塚駅のコンコースで讃美歌を歌っています。私も何回か参加しています。
なぜ讃美歌を歌うことによって基地反対を訴えるのかとよく聞かれます。もっと効果的な方法があるのではないかと言われます。確かに、大きな基地に対して歌を歌うことにどれだけの意味があるでしょうか。基地問題に対して非常に小さい行動です。でも賛美歌を歌っています。世界に平和に目覚めて欲しいと願って讃美歌を歌っています。神様が必ずそれを実現させてくださると信じて歌っています。世界の人々に暴力ではなく、愛と平和を選んで欲しいと願って歌っています。歌い続けることで神様がきっと軍隊のない世界、平和な世界を実現させてくださると信じて歌っています。
私はこの世界からすべての軍隊と基地がなくなることを願っています。それは聖書の教えるイエス・キリストの平和です、私たちはあらゆる暴力のない、イエス・キリストの平和を模範とします。イエス・キリストの平和には戦争も軍隊も基地も一切必要ありません。暴力によって平和は実現できないからです。軍隊のいない世界、暴力の無い世界がきっと作り出せるはずです。神様がその力を私たちに下さるはずです。小さな行動でも私たちは軍事力に反対をし、暴力の無い平和を求めてゆきたいと思っています。今日は神様の示す平和と、平和を目指す生き方について考えたいと思います。
使徒言行録16章をお読みいただきました。今日の聖書の個所は、イエス様が十字架で死に、3日後に復活した後の物語です。弟子のパウロは、このイエス・キリストが私たちの生き方の模範だと世界中に伝え歩いていました。イエス様が教えた事はたくさんありますが、平和もその一つです。世界が隣人を愛し、敵を憎めと教えている中で、イエス様は敵を愛しなさいと教えました。敵と思える対象とも互いに愛し合う様に教えたのです。この平和の教えは世界中に広まってゆきました。そしてその平和の教えを世界に広めていた弟子がパウロとシラスでした。
16節、パウロはある時、女奴隷の占い師に会いました。彼女は占いで自身の生計を立てていたのではありません。その利益はほとんどは主人が持ってゆきました。彼女は主人の商売道具として、暴力的に搾取されながら、奴隷として占いを続けなければなりませんでした。この占い師はパウロを見た時、彼のことを大声で周囲に伝えようとします。「この人は救いを、イエスの平和を宣べ伝えている」と叫びます。幾日もそれが続き、パウロはたまりかねて「出て行け」と言いました。そうすると女奴隷はそれ以来、主人の金儲けのための占いが出来なくなってしまいました。主人は商売道具を使えなくされたことに怒ってパウロを訴えました。そしてパウロは鞭うたれ、牢獄に入れられることになりました。
牢獄に入れられること、それは暴力のただなかに放り出されるという事態でした。パウロは何度も鞭に打たれ、牢に投げ込まれました。足には足かせをはめられ、自由を奪われました。一切の抵抗ができない状態です。そして暴力の象徴である武器・剣もった看守がそれを見張っていました。暴力がすべてを支配する場所に投げ出されたのです。暴力が支配する牢獄の中で、パウロとシラスは何をしたでしょうか。脱獄するためにどうやって看守を殺そうかを考えたでしょうか。何か武器になるものを探したでしょうか。戦うための準備をしたでしょうか。
そうではありませんでした。彼らはなんと歌いました。暴力に支配される世界の中で歌を歌いました。暴力の渦巻くその中にいながら、彼らは暴力によって状況を変えようとしませんでした。彼らが選んだのは歌を歌うということでした。他の囚人はその歌に聞き入ったとあります。牢獄にはきっとパウロ達と同じ様に、無実の罪を着せられ暴力によってここに閉じ込められている人が多くいたのでしょう。彼らが聞き入ったのはきっと平和を願う歌、自由を願う歌、神様への感謝の歌だったでしょう。でも牢獄で歌って何になるでしょうか。圧倒的な暴力に対して歌を歌って何になるでしょうか。でも彼らは歌いました。その歌から、賛美から奇跡が起こされてゆきます。
地震が起きました。地震は神様が起こす奇跡の象徴です。何かが起こり、牢が開きました。彼らは逃げることができるようになったのです。看守は囚人が逃げ出してしまったと思い、自死を選ぼうとします。これまで武器で、暴力で人を支配してきた看守は、行き詰った時、とっさに選んだ方法はやはり暴力でした。再び力をもってこれを解決しようし、今度は自分への暴力を選びました。彼には殺すか殺されるかしか選択肢が無かったのです。しかしパウロはそれを止めます。死んではいけない、どんな命にも暴力を向けてはいけないと教えたのです。
本当に暴力に支配されていたのは誰でしょうか。それはパウロではなく、看守の方です。看守は武器を持って、暴力で人を支配したつもりになっていました。そして暴力以外の解決方法を知りませんでした。そのように暴力に支配されていたのは看守の方です。看守はパウロに死んではいけないと言われて、たった今そのことに気づきました。そしてパウロに救いを求めました。それは暴力の支配からの救い、平和の願いだったはずです。
パウロは、死んではいけないと言います。私にはこのパウロの行動が「命どぅ宝(命こそ宝)」という言葉に聞こえます。それは平和を望む言葉です。死んではいけないとは、命こそ宝だという姿勢です。命こそ宝です。どんな暴力もあなたを支配することはできない、あなたはどんな暴力をつかっても誰も支配できないという意味です。それは暴力によって命を守ることはできない。平和を求めて、生きようという言葉です。そして看守はそのイエスの平和の福音に救われてゆきます。看守はそれまでの生き方を大きく方向転換します。
彼はパウロの傷を洗いました。彼は暴力で支配してきた態度から、他者の傷の痛みを知り、共感をするものとなったのです。それは暴力から愛への転換でした。敵を愛しなさいという教えの実践でした。彼はバプテスマを受け、そして食事を共にしました。暴力で支配してきた者と同じテーブルで食事をしたのです。看守はこのような転換をしました。相手を暴力で抑えつけ、痛めつけ、支配することから、相手の痛みと傷を知り、いたわり、対等に関わるように転換したのです。平和への方向転換です。
このような転換は人間によってはなかなか起こらないものでしょう。神様によって起こされた出来事です。私にとってこの物語の最大の奇跡は、地震で扉が開いたことではありません。彼がこのように平和を求めて生き方を変えことが、もっとも大きな奇跡です。それは神様を賛美し祈ることがきっかけとなって起きた奇跡でした。私たちもこの看守のような、暴力から愛への転換をしたいと願います。私たち自身に、私たちの世界全体に、暴力から愛への転換が起こって欲しいと願います。それは命どぅ宝の転換です。命こそ宝とする転換です。平和への方向転換です。
神様はどのように世界の平和を実現させてくださるでしょうか?今日の個所によればそれは平和を求める賛美を歌うこと起りました。神様が平和を実現させてくださいます。それを願い賛美しましょう。世界が暴力を辞めて、愛に目覚める様に神様に求めましょう。私たちにできることは賛美歌を歌うことです。神と人に向けて平和の賛美歌を歌いましょう。
沖縄からまずその歌が聞こえます。私たちの賛美から世界に平和が広がるように祈ります。平和こそ宝、命こそ宝であることが伝わるように祈ります。お祈りします。
「命こそ宝 平和への方向転換」使徒言行録16章16~34節
真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌をうたって神に祈っていると、ほかの囚人たちはこれに聞き入っていた。 使徒言行録16章25節
今日6月23日は79年前、沖縄で組織的な戦闘が終わった日です。私たちはこの日を「命どぅ宝の日」と呼び、平和を考える時として大切にしています。沖縄の人々は激しい地上戦の中で、洞窟に逃げ込みました。そしてそこで、どう死ぬか、どう殺すかでなく、どうやって命をつなぐかを考えました。彼らは洞窟の中で「命どぅ宝」命こそ宝だと互いに励ましあい、何とかして生きようとしました。
沖縄にはあの時から今も大きな基地がいくつも存在します。私たちは普天間、辺野古を含めて沖縄、日本、世界のすべての基地がなくなることを祈り願っています。沖縄の普天間基地の前で毎週、戸塚駅の駅前で月1回、基地に反対して讃美歌が歌われています。世界に平和に目覚めて欲しいと願って、世界の人々に暴力ではなく、愛と平和を選んで欲しいと願って歌っています。小さな行動でも私たちは軍事力に反対をし、暴力の無い平和を求めてゆきたいと思っています。今日は神様の示す平和と、平和を目指す生き方について考えたいと思います。
世界が隣人を愛し、敵を憎めと教えている中で、イエス様は敵を愛しなさいと教えました。その平和の教えを世界に広めていた弟子がパウロとシラスでした。しかしパウロは牢獄に入れられることになりました。パウロは何度も鞭に打たれ、牢に投げ込まれました。足には足かせをはめられ、自由を奪われました。そして暴力の象徴である武器・剣もった看守がそれを見張っていました。暴力が支配する牢獄の中で、彼らはなんと歌いました。きっと平和を願う歌、自由を願う歌、神様への感謝の歌だったでしょう。圧倒的な暴力に対して歌を歌って何になるでしょうか。でも彼らは歌いました。その歌から、賛美から奇跡が起こされてゆきます。
地震は神様が起こす奇跡の象徴です。彼らは逃げることができるようになりました。看守は自死を選ぼうとします。しかしパウロはそれを止めます。死んではいけない、どんな命にも暴力を向けてはいけないと教えたのです。私にはこのパウロの言葉が「命どぅ宝(命こそ宝)」という言葉に聞こえます。それは平和を望む言葉です。そして看守はそのイエスの平和の福音に救われ平和へと方向転換します。
彼はパウロの傷を洗いました。他者の傷の痛みを知り、共感をするものとなったのです。それは暴力から愛への転換でした。敵を愛しなさいという教えの実践でした。彼はバプテスマを受け、そして食事を共にしました。暴力で支配してきた者と同じテーブルで食事をしたのです。これは神様によって起こされた出来事です。
私たちもこの看守のような、暴力から愛への転換をしたいと願います。世界が暴力を辞めて、愛に目覚める様に神様に求めましょう。私たちにできることは賛美歌を歌うことです。神と人に向けて平和の賛美歌を歌いましょう。沖縄からまずその歌が聞こえます。私たちの賛美から世界に平和が広がるように祈ります。平和こそ宝、命こそ宝であることが伝わるように祈ります。お祈りします。
【全文】「神が与える調和」使徒言行録15章1~21節
みなさん、おはようございます。今日もこうしてみなさんと共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。こどもたちの命の声に包まれながら礼拝をしてゆきましょう。今日は物事を決める時、妥協、調和、折衷を大事にしてゆこうということを考えたいと思います。
今日は私たち平塚バプテスト教会の創立記念礼拝です。私たちの教会は1950年に神様に導かれ創立され、74周年を迎えることができました。74年間も続いたのは本当に神様のおかげです。とても私たち人間だけではこの教会を続けることが出来なかったはずです。今日は私たちがこの教会に来る前からずっと、神様の働きがあったことを実感する日です。
74年間、この教会は多くの困難を乗り越えてきました。初代長尾先生の後の混乱と分裂、小田原伝道所の問題を経験しました。土地の問題もありました。私たちはこの土地を購入して代金を払っていましたが、名義の変更がされていませんでした。そのことで土地と建物すべてを失う危機もありました。しかし不思議な力に守られて74年間ここに建ち、礼拝が続いています。
74年間、本当に多くの課題があり、そのたびに熱心に議論がされました。バプテストは民主的に話し合って決めることを大切にしています。話し合いは確かに疲れるものです。みんなで考えるよりも誰かが決めてくれた方が楽です。でも私たちは多くの困難を話し合うこと、互いの理解を深めることで乗り越えてきました。
そしてこれからの私たちも大きな決断のための議論を控えています。土地の一部を売却し、建物を修繕する計画があります。現時点ではまだそれができるかどうかもわかりません。しかし、これは間違いなく教会が始まって以来の大仕事になるでしょう。
教会の建築を経験した人たちは口々にその苦労を語ります。ある教会では予算を巡って議論が過熱します。自分達はいくらの予算をたてるのか、お互いの経済事情を知らずに決定をしなければいけない苦労があります。それぞれの教会への新しい期待がぶつかり合います。ある教会は資材費の高騰で当初予算より大幅な支出をしなければなりません。私たちもこれから、そんな議論をしてゆかなければなりません。私たちが信仰を守るためには、どうしてもこの教会・建物が必要だと思います。そのための議論です。
私たちは老朽化に対応し、時代や環境の変化に対応し、それぞれの考えの違いを尊重しながら前に進まなければいけません。想像するだけで大変ですが、もし神様の計画ならば、そしてこの地にこの教会が必要とされ続けるならば80年、100年と続くための計画が成し遂げられてゆくはずです。74年間この教会が守られてきたことに感謝しながら、これからの議論を拡げてゆきたいと思います。
物事を決めてゆく時、大事なことは、時に妥協し、調和し、折衷案を持つことだと思います。それぞれの信仰と違って、建築はどうしても、最終的には一つの形にならざるを得ません。全員の要望を盛り込むことは難しいのです。私たちも大きな議論をするとき、互いに妥協し、調和し、折衷案を持ち前に進んでゆくことを覚えておきましょう。今日は聖書に記録される会議もそのような出来事です。聖書を読んでゆきましょう。
今月は使徒言行録を見ていますが、今日はその中でも15章にあるエルサレム会議と呼ばれる場面をみてゆきたいと思います。
先週からもお伝えしている様に、初期のキリスト教には二つのグループがありました。ユダヤ教の律法を重視するグループと、そうでないグループです。それぞれに熱心に信仰生活を送っていました。この二つのグループは決して対立をしていたわけではありません。時に互いに無関心だった時もありますが、人や献金を送ったりする良好な関係でした。今日の個所の3節にもあるように、何か互いに良いことがあれば、その恵みを喜び合う関係でした。ただユダヤ教の律法の実践を巡っては大きな隔たりがあったのです。
律法を重視する人も、これをやらないと地獄へ行ってしまうと思っていたわけではありません。神様の恵みに感謝して、律法を誠実に実践していました。多くの人はその実践は自由だと考え、絶対に他の人も実践をしなければいけないと思っていたわけではありませんでした。
しかし一部には、すべての人が、すべての律法を守るべきだと主張する人もいました。1節にある主張です。男性器の皮を切り取る、割礼までもすべきだという主張をする人までいました。
どこまで律法の実践を求めるべきか、二つのグループは意見が分かれていました。一部の人のように、すべては求めないにしろ、どこまでを求めるかが議論になりました。もう私とあなたは違う、それぞれ思い思いにやればいいとは思わなかったのです。何か最低限の一致できるはずだと考えたのです。
その妥協点を探るために、エルサレムで会議をすることになりました。このエルサレム会議はどちらが正しいか決着をつける会議ではありません。この会議は、どうすればキリストの弟子として一致し、仲間であり続けられのるかを話し合うために持たれたのです。別々の宗教になるのではなく、どこかで最低限の一致ができるはずだと考えて会議が持たれたのです。
会議はまず、律法を重視しないグループを見てきたペテロの報告から始まります。ペテロ自身ももともとは律法守っていた人です。しかし彼はいままでの立場に固執せず、律法を重視しない人々を好意的に受け止め、報告をしました。
ペテロは8節でこう報告します。私たちが神様から信仰を与えられたように、彼らにも神様からの信仰が与えられています。私たちが神様に受け入れられている様に、異邦人も神様に受け入れられています。神様はきっと彼らを差別しないはずです。神様はその恵みによってみんなを救うはずですと報告をしました。それはこれまで律法を重視していたペテロが、自分とは違う他者のあり方を認める報告でした。
それを受けて律法重視のグループの代表ヤコブが発言します。それは旧約聖書を引用する伝統的な姿勢です。しかし同時に引用した聖書箇所は律法を重視しない人も尊重する箇所でした。そしてヤコブは決断をしました。19節、ヤコブは律法を重視しないグループをこれ以上悩ませないと決断をしたのです。そして20節の決め事が発表されました。
決定の内容は端的には4つでした。これはレビ記に基づく伝統的にユダヤの律法を重視する人が守ってきたことの一部でした。そしてこの4項目以上の事、特に割礼は求めないという寛容な決定でした。
4つの決定を見ます。使徒教令ともよばれますが、ひとつはみだらな行いです。性的暴力や性的搾取をしないようにという教えです。現代にも通じます。そして残りの3つは食べ物に関する取り決めです。他の宗教の祭儀で使われた肉、ユダヤの祈りをせずに屠った肉、生焼けで血の滴る肉、それらを食べないようにという取り決めでした。
さらにおそらくこれは律法を守る人とそうでない人が一緒に食事をする時の決まり事でした。一人の時、律法を重視しない人だけの食事の時は、自由にいままでの習慣どおりに食事をしたでしょう。ただし、律法を重視する人と一緒に食事をするときにおいては、ユダヤの習慣を尊重するように、配慮をするようにと決められたのです。一緒に食事する時は食べられない人に配慮をしてください、それ以外・それ以上は求めませんということを決めたのです。うまい妥協点だと思います。
そしてこの決定は調和を重視しています。別々にいるときは自由だけれども、一緒に食事する時のルールが定められたのです。一緒に食事ができるようにルールが決められたのです。これは最小限の一致でした。一緒にいる時は、律法を守る人に合わせるという折衷案でした。
聖書を読み進めてゆくと、31節にその協議の結果を聞いて人々は喜んだとあります。そしてそれは彼らにとって励ましに満ちた決定だったとあります。その妥協案、折衷案、調和重視の案によって温かい一致が生まれたのです。
そこに絶対に律法を守り抜くという筋の通った考え方は無かったかもしれません。しかしそれはどちらかに合わせるのではなく、互いの言葉を聞き、互いを尊重し、互いに苦しまないための、両方が喜ぶことのできる決定でした。後から来た人が苦しむものではなく、今までいた人が否定されるものではなく、互いを否定、排除しない決定となったのでした。よい決め方だったと思います。
その会議には神様の力が働いたのでしょう。神様が知恵を与えたのでしょう。神様はこのようにして、共同体を導いてくださるお方です。互いに話し合い、互いを聞き合い、折り合いをつけ、私たちを結び付けて下さるのが、神様の働きなのです。それは人が決めたことのように見えるかもしれませんが、神様に導かれたのです。私たちの歩んだ74年間もそれが起り続けて、私たちは今に至るのです。
創立記念の時、これから起きる様々な議論に心を準備したいと思います。その時今日のエルサレム会議を覚えておきましょう。私たちは互いが自由です。そして神様が互いを受け入れていることを覚えておきましょう。私たちはそれぞれ感じ方、考え方が違います。大きなことから、小さなことまでいろいろ違います。そんな私たちがどうやって大きな決断をしてゆけるでしょうか。神様が導いてくださって、きっと互いに妥協し、調和し、折衷となる選びが示されてゆくはずです。
エルサレム教会では互いを尊重し、互いに苦しまない決定が選ばれました。それは誰かの喜びと励ましになる決定でした。私たちもこれからそのような選びへと導かれてゆきましょう。お祈りをいたします。
「神が与える調和」使徒言行録15章1~21節
それで、わたしはこう判断します。神に立ち帰る異邦人を悩ませてはなりません。
使徒言行録15章19節
私たち平塚バプテスト教会は今日、創立74周年を迎えることができました。本当に神様のおかげです。74年間多くの課題がありました。バプテストは民主的に話し合って決めることを大切にしています。話し合いは疲れるものですが、私たちは多くの困難を話し合うこと、互いの理解を深めることで乗り越えてきました。そしてこれからの私たちも大きな決断のための議論を控えています。もし神様のご計画ならば、今後の計画が成し遂げられてゆくはずです。
物事を決めてゆく時、大事なことは、時に妥協し、調和し、折衷案を持つことです。建築はどうしても、全員の要望を盛り込むことは難しいものです。私たちも大きな議論をするとき、互いに妥協し、調和し、折衷案を持ち前に進んでゆくことを覚えておきましょう。今日は聖書に記録される会議もそのような出来事です。
今日は使徒言行録のエルサレム会議をみてゆきます。初期のキリスト教には二つのグループがありました。ユダヤ教の律法を重視するグループと、そうでないグループです。この二つのグループは決して対立をしていたわけではありません。人や献金を送ったりする良好な関係でした。ただどこまで律法の実践を求めるべきか、二つのグループは意見が分かれていました。その妥協点を探るために、エルサレムで会議をすることになりました。このエルサレム会議はどちらが正しいか決着をつける会議ではありません。どうすればキリストの弟子として一致し、仲間であり続けられのるかを話し合うために持たれたのです。
決定の内容は伝統的にユダヤの律法を重視する人が守ってきたことの一部でした。そしてこの4項目以上の事は求めないという寛容な決定でした。大部分は食べ物に関する取り決めです。そしておそらくこれは律法を守る人とそうでない人が一緒に食事をする時の決まり事でした。律法を重視する人と一緒に食事をするときにおいては、ユダヤの習慣を尊重、配慮をするようにと決められたのです。うまい妥協点だと思います。この調和重視の案によって温かい一致が生まれました。両方が喜ぶことのできる決定でした。よい決め方だったと思います。
その会議には神様の力が働いたのでしょう。神様はこのようにして共同体を導いてくださるお方です。互いに話し合い、折り合いをつけ、私たちを結び付けて下さるのが、神様の働きなのです。私たちの歩んだ74年間もそれが起り続けて、私たちは今に至るのでしょう。創立記念の時、これから起きる様々な議論に心を準備したいと思います。その時このエルサレム会議を覚えておきましょう。
私たちはいろいろな違いがあります。でも神様が導いてくださって妥協し、調和し、折衷となる選びが示されてゆくはずです。エルサレム教会では互いを尊重し、互いに苦しまない決定が選ばれました。それは誰かの喜びと励ましになる決定でした。私たちもこれからそのような選びへと導かれてゆくはずです。お祈りします。
【全文】「愛は骨折り損」使徒言行録11章19~30節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもの声を聞きながら、一緒に礼拝をしましょう。今日は無償の愛について考えたいと思います。
私が平塚教会に来て5年、前の先生からホームレスの支援を引き継いでいます。ホームレスの支援をしていると、この支援をしても自分にまったく得がないと思うことがあります。5年間関わり、支援をしてきたホームレスの方がいます。彼は平塚の海岸の砂防林の中で、10年以上テントを張って生活をしています。先日彼は、体調を崩し救急車で市民病院に運ばれました。退院後にテント生活を続けるわけにもいかず、病院を訪ね、新しい施設へ入居する手伝いをしました。しかし数か月後、施設を抜けだし、彼はまた海岸のテントに戻ってきてしまいました。施設で何かすれ違いがあったようです。
さらに数か月後、平塚教会の炊き出しで、やっぱりホームレスを辞めたいと言ってきました。私は半信半疑で本当にホームレスを辞める意思があるかどうか、何度も確認しました。彼はどうしてもホームレスを辞めたいと言います。私は苦労して、再び住む場所を探しました。今度はすれ違いが無いように、事前に一緒に施設を見学し、この部屋で大丈夫かどうか確認し、本人がその施設に住みたいと言うので、その施設を紹介しました。引っ越しの日はもう戻って来ないと約束し、一緒にテントを撤去し、車で送り届けました。しかし、最近また海岸に戻ってきてしまいました。まだ詳しくはわかりませんが、何か嫌なことがあったようです。もうそろそろ関わるのを辞めようかとも思います。
しかしホームレス支援ではよくあることです。時間とお金をかけても、思うような結果にならないことが多くあります。「こんなことをしても1円にもならない」と何度も思ったことでしょうか。骨折り損のくたびれもうけとはまさにこのことです。これは自分にまったく得のないことです。いつでもやめてよいことだと思っています。続けるかどうかについて、私には自由があると思っています。でもなぜかなかなか辞めることができません。不思議と彼を見捨てることができません。腐れ縁かもしれません。もしかするとキリスト教の視点からは、これこそが無償の愛なのかもしれません。いつか私にお返しがあるはず、いつかやりがいと満足感があるはず、いつか感謝と賞賛があるはず。そう思いながら活動をするなら、無償の愛ではないのかもしれません。
本当に何も得がないからこそ、愛なのかもしれません。この愛を本当に続けてゆけるかどうかはわかりません。でももし神様が私に、命にかかわる大事な活動だと示してくださるのなら、続けることができる、そう思っています。そう示されなければ続けることができないと思っています。
みなさんにも人生の中で、一切自分に得が無い、そう思っていても何かをした、あるいはせざるを得なかったということはあるでしょうか。きっとみなさんにもそんな経験があると思います。自分に一切得がないにも関わらず、それでも他者のための苦労する、もしかするとそれこそが本当の愛なのかもしれません。今日は聖書からアンティオキア教会の無償の愛を見てゆきたいと思います。
今日は使徒言行録11章19~30節をお読みいただきました。今日の聖書箇所の背景にある3つのグループを図で紹介します。イエス様の死後、エルサレムには3つのグループがありました。一つは主流派・保守派であり、伝統的なユダヤ教のグループです。熱心に戒律を守って生活をしていました。2つ目はナザレ派とあります。生前のイエス様の教えを信じ、キリストの弟子として生きながらも、ユダヤ教の戒律を守りながら生活した人のことです。ユダヤ教ナザレ派と呼びます。ヤコブやペテロがこのグループでした。そして3つ目はキリストの弟子としてユダヤ教を抜け出ようとしたグループです。後のキリスト教となるグループです。後から加わった外国人も多かったこのグループは、戒律をあまり重視しませんでした。
エルサレム市内ではユダヤ教の戒律を守るべきだという対立がありました。ある日その対立が表面化し、主流派がキリスト者のグループへの排除・虐殺を開始しました。後のキリスト教となるグループはエルサレムに残ることができず、世界に散り散りに逃げてゆきました。それが1節にあるステファノの事件です。エルサレムで殺されそうになり、逃げ出した人々が中心となってアンティオキア教会を作りました。そしてその教会に加わる人が増えていったのです。その噂はエルサレムに届くほどでした。
ナザレ派は23節アンティオキアで始まった新しい運動、後のキリスト教の様子を確かめることにしました。派遣されたバルナバはその教会に到着し、神様の恵みに驚いたとあります。そして29節、ある時、エルサレムで飢饉が起こります。それに対してアンティオキアの教会はこのナザレ派に対して援助の品を送りました、経済的な支援をすることにしたというのです。それが今日書かれている物語です。
この構図から感じることを挙げます。まず迫害・虐殺が起きた時ナザレ派は一体何をしていたのでしょうか。イエスを主と信じる仲間が殺されそうになり、逃げ惑う時、ナザレ派はどのように行動したのでしょうか。ナザレ派がこの迫害と虐殺に反対した様子が記録にありません。もしかすると彼らは「関わって得はない」と感じたのでしょうか。「自分達のことではない」「律法を守らない人が悪い」と思ったのでしょうか。彼らはなぜ反対せず、仲間を見捨ててしまったのでしょうか。
これは人間の罪が現れているかもしれません。身内の安全が守られている限りは声を上げなかった罪、自分達には関係ないと問題から目をそらした罪、自分の命が無事ならいいという罪、あの人たちは殺されてもしょうがないと思う罪です。イエス様を十字架につけた罪もそうです。その罪のため、多くの人が死にました。
一方、キリスト者のグループの行動をみます。彼らはエルサレムで飢饉が起きた時、経済的な援助をそれぞれの力に合わせて行いました。しかしこの行動は驚くべき行動です。以前ナザレ派は自分たちを助けてくれませんでした。あの時無関心でした。そのような過去の関係があったにも関わらず、アンティオケア教会はナザレ派を支援したのです。
彼らに何の得と、どんな義理があったでしょうか。何もありません。でも彼らは自分たちだけの安全を考える人ではありませんでした。あの時自分たちのことを助けてくれなかったけど、でも支援の品を送った。きっと記録に残るくらいのたくさんの品、多額の献金をアンティオケアからエルサレムのナザレ派に送ったのでしょう。あの時、自分を助けてくれなかった人たち、見殺しにした人たちに支援の品を送りました。惜しみなく財産を分かち合ったのです。それがアンティオケア教会の愛だったのです。
それが私たちの教会のルーツとなってゆきます。それは助けてくれたから、お返しに助けるという行動ではありません。それならば助けるのはある人として意味当然です。しかしここではあの時、助けてくれなかった人、関係ないと無視された人、その人を助けたのがアンティオケの教会だったのです。彼らは自分達が良ければいい、自分たちに危害が及ばなければいいとは考えませんでした。自分たちの得にならないことも進んで行ったのです。それがアンティオキア教会の愛でした。それはこちらが一方的に骨を折ることでしたが、それこそ無償の愛だったのです。
自分の利益とは関係なく、惜しみなく与えるのが愛です。アンティオキア教会ではそれを実践していたのです。それは困った時はお互い様を超える、相互扶助ではない、一方的な愛でした。23節でバルナバが見て感動した雰囲気はこの愛だったのではないでしょうか。バルナバが恵みだと感じたのは、人数の増減よりも、他者への無償の愛の姿勢でした。バルナバはその愛を見て、神の恵みを感じたのではないでしょうか。その愛の姿勢こそがキリスト教が世界に広がった原動力だったのではないでしょうか。
さて、私たちの教会もアンティオキア教会のようになることを願います。それはこの教会が良ければよい、この教会がうまくいけばよいという態度ではありません。いつかお世話になるかもしれないから助けるのでもありません。キリスト教の愛は相互扶助ではありません。たとえ今までもこれからも助けてもらえなくても助けるのが、キリスト者の無償の愛です。援助を必要とする人に、無条件に惜しみなく助けるのが愛です。そのようなアンティオキアの無償の愛は、きっと神様をよく証ししたでしょう。それを実践する人がキリスト者と呼ばれたのです。
私たちも同じキリスト者です。無償の愛を私も実践したいと思います。それはこれまでのわだかまりのある関係を超えた愛です。無関心を超える愛です。助けられたから助けるのではない愛です。ただ一方的な支援、教会や自分の損得ではない愛、愛されなくても愛す愛です。そのように神の愛を具体的に実践するとき、新しい生き方は神様の力によって自然と広がってゆくのでしょう。
私たちも教会でも、私たち一人一人でも無償の愛を大事にしてゆきましょう。それは骨折り損かもしれません。でもきっとそれこそが愛なのでしょう。そしてそれこそが神様の愛をもっともよく示す行動なのでしょう。それぞれの一週間があります。他者のために骨を折り、無償の愛を実践してゆきましょう。お祈りいたします
「愛は骨折り損」使徒言行録11章19~30節
すると、たちまち目からうろこのようなものが落ち、サウロは元どおり見えるようになった。そこで、身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。 使徒言行録9章18~19節
今日から聖書の使徒言行録を1ヶ月間読んでゆきます。みなさんは価値観が大きく変わるという体験をしたことがあるでしょうか?キリスト教の洗礼(バプテスマ)が人生の価値観を大きく変えるきっかけになったという人が多くいます。私もその一人です。聖書の教えを価値観の中心にするスタートが洗礼(バプテスマ)です。
洗礼(バプテスマ)に際してキリスト教以外の価値観を劣ったものとは考えないことも大事なことです。異なる価値観や宗教の人と共に生きてゆこうとすること、それがキリスト教の愛なのでしょう。今日は聖書のサウロという人物から、他者を尊重するという方向に生き方を転換した物語を見てゆきたいと思います。
十字架の後、イエス様の教えた愛の輪が広がっていました。そしてもともとの枠組みであるユダヤ教から大きくはずれる様になりました。サウロはユダヤ教を信仰していましたがそのキリスト教を激しく否定していました。それぞれの信仰にはそれぞれの価値観と教えがあり、どの宗教も尊重すべき教えがあります。ただしサウロはこの点で、かなり強引な態度でした。価値観、宗教観の違うものを見つけ出し、縛り上げ、連行し、脅迫し、殺していたのです。
そんなサウロにある日突然、運命を変える出来事が起こりました。それによって彼は自分が否定し、殺そうとしていた人の助けを必要としました。自分がいままで否定してきた人に手を引かれ、手を置いて祈ってもらわなければならなくなりました。それまで敵視していた人々に助けられたことで、彼の心は大きく変わりました。
ここでサウロがどんな奇跡的な体験をしたかは重要ではありません。重要なのはサウロの価値観の転換です。これは単に奇跡が起きて、ユダヤ教からキリスト教へ変わったという、宗教の変更以上のものです。彼の変化とは他者の価値観を暴力的に否定する姿勢から、尊重と平和的な態度への変化でした。彼は弱さと無力の中で、その価値観が、生きる態度、他者に対する態度が変わりました。異なる価値観の人に敬意を持って接するようになったのです。それが彼に起きた変化でした。
神様は私たちにもそのような変化を与えるでしょうか。自分だけでは立ち上がれない時、誰かに頼って生きようとする時に、人生の価値観が大きく変わるのかもしれません。その時、私たちは自分が唯一正しいという態度から、他者を尊重する態度に変わってゆきます。それはきっと私たちにも起こります。神様はきっと私たちにもそのような大きな転換を、新しい道を準備していてくださるはずです。
本日はこの後、主の晩餐を共に分かち合います。サウロはこの主の晩餐を受けて、新しく他者を愛し、敬う生き方を始めました。私達もこのパンを食べ、他者を尊重し、共に生きることを選びましょう。私たちもその第一歩を踏み出してゆきましょう。お祈りします。
【全文】「他者を尊重する方向転換」使徒言行録9章1~22節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。こどもたちの笑顔と声に包まれながら、礼拝をしてゆきましょう。
ここ数か月、初めてキリスト教に触れる方々に向けてお話ししてきました。新しい視点で考えることは、私たち全員にとっても大切なことだと感じました。既に信仰を持っている方々にとっても、自分の信仰を深める機会となったでしょうか。
今日からは聖書の使徒言行録という箇所を1ヶ月間読んでゆきたいと思います。パウロ(旧名サウロ)という人の人生を追いかけてゆきます。初めての人も、ずっと通っている人も聖書から、新しい生き方を考えてゆきましょう。
みなさんは、価値観が大きく変わるという体験をしたことがあるでしょうか?例えば、誰かの言葉や行動によって、自分の考え方が大きく変わった経験はあるでしょうか?今まで思っていたこととまるで違う、正反対の価値観を持つようなったという体験があるでしょうか。大小さまざまあるとは思いますが、人生全体に大きな影響があるような価値観の変化はそう頻繁には起こらないことです。教会にはキリスト教の洗礼(バプテスマ)が人生の価値観を大きく変える、人生を方向づけるきっかけになったという人が多くいます。私もその一人です。みなさんはどうでしょうか?
洗礼(バプテスマ)とは汚れを取り払い、清く聖なる者になることではありません。洗礼(バプテスマ)とは価値観が変わってゆくことです。神様の導きを受けて、自らの価値観を神に向けてゆくこと、聖書の教えを価値観の中心にしてゆこうという表明、キリストの弟子としてその道を歩み始めるスタートが洗礼(バプテスマ)です。洗礼(バプテスマ)に際してキリスト教以外の価値観を劣ったものとは考えないことも大事なことです。価値観は人それぞれにあります。価値観や信じている宗教について他者からとやかく言われる必要はありません。自分が正しい、自分が励まされる、自分が導かれていると思うものに導かれればいいのです。キリスト教だけが正しく、他の宗教は劣っており間違っているという考えは、愛とはいえないでしょう。キリスト教は戦争の無い平和、互いの命が豊かになる平和を求めてゆく宗教です。他者を無理やり変えるのではなく、他者と共に生きようとする宗教です。異なる価値観や宗教の人と共に生きてゆこうとすること、それがキリスト教の愛なのでしょう。相手を批判する力は、自分がキリスト者としてどう共に生きるかに向けられてゆくべきです。洗礼(バプテスマ)はその生き方のスタートです。価値観を神に置き、他者を愛し、共に生きる事のスタートが洗礼(バプテスマ)です。ぜひ皆さんにも、その生き方のスタートをお勧めしたいと思っています。他者を尊重する生き方へと方向転換をしてゆきましょう。
もちろんバプテスマを受けたからと言ってすぐにそれができるようになるわけではありません。バプテスマを受けた方も、もう一度そのことを思い出しましょう。今日は聖書のサウロという人物から、自分が正しいと暴力を振るっていた人が、他者を尊重するという方向に生き方を転換した物語を見てゆきたいと思います。
聖書をお読みいただきました。イエス様の十字架の後、弟子たちは神様からの風・力を受けて活発に活動をしていました。キリスト者の生き方は、互いに愛し合いなさいという教えに代表されるように、神様を愛し、他者を愛する生き方でした。その愛の輪はどんどん広がっていました。そしてそれはもともとの枠組みとしてあったユダヤ教から大きくはみ出すことになりました。やがてそれはキリスト教と呼ばれるようになります。
今日登場するのはサウロという人物です。この人はもともとユダヤ教を信仰していました。そしてそこから生まれようとしているキリスト教を激しく否定していました。サウロがすぐにキリスト教を信じなかったことを責めるつもりはありません。それぞれの信仰にはそれぞれの価値観と教えがあり、どの宗教も尊重すべき教えがあります。ユダヤ教を信じる人の信仰もとても尊いものです。私たちは他者の信仰や価値観を尊重し、理解するために努力をすることが大事です。
ただしサウロはこの点で、かなり強引な態度でした。サウロはユダヤ教以外の人に並々ならぬ敵対心を持っていました。1~3節にはサウロの他者の価値観に対する態度が現れています。彼は主の弟子、この道に従う者、つまりキリスト者を見つけ出したら徹底的に排除をしました。価値観、宗教観の違うものを見つけ出し、縛り上げ、連行し、脅迫し、殺していたのです。彼は熱心なユダヤ人だったと言われます。自分の信じる事への熱心さの行く先は、周囲は間違っている、力づくでもユダヤ教にしようという態度、ユダヤ教からの逸脱をゆるさないという態度でした。他者の価値観と宗教観を一切認めないという価値観でした。彼はそのように自らの価値観と宗教を暴力的な態度と行動で押し付けようとしたのです。多くのキリスト者はサウロを恐れました。彼に自分の信じていることがばれてしまうと、批判され、否定され、暴力的な態度を取られ、殺されたからです。人々はサウロを恐れ、彼を避け、彼には決して自分の気持ちを語ろうとしなかったでしょう。
サウロにとって運命を変える出来事が起こったのは、ある日突然のことでした。道を進む彼に、イエス様が直接語りかけたのです。その瞬間、彼は視力を失い、自分の足で歩くことさえできなくなってしまいました。その出来事によって起こったのは、彼はそれまで自分が否定し、殺そうとしていた人に助けてもらわなければならなくならないということでした。自分がいままで否定してきた人に手を引かれ、手を置いて祈ってもらわなければならなくなりました。それまで否定し、敵視していた人々に助けられたことで、彼の心は大きく変わりました。彼は自分の信じるユダヤ教だけが唯一正しいと信じ、それ以外の価値観と宗教を一切否定していました。その彼は今弱くされ、無力となり、混乱しています。彼の価値観が大きく揺らいでゆきます。
聖書のとおりに出来事が起きたのか、彼に何が起きたのか本当のところはわかりません。後に彼自身が書いた手紙には直接、このダマスコでの出来事の記載がありません。確かなのは彼の中で短期間のうちに、大きな価値観の転換が起きたということです。それは極めて短期間で、劇的に起きました。自分で意図して選択したものではなく、神様から示され、その価値観の転換が起きたのです。サウロはこのように大きく価値観を変えられました。しかし彼の変化は180度の転換ではありませんでした。もし180度の転換というならば、今度は反対にユダヤ教が間違っていると言って攻撃の対象にしたかもしれません。しかしサウロはそのようなことはしませんでした。
サウロはこの後、名前を変えてパウロと名乗るようになります。パウロはこの後、自分と同じようにユダヤ教からキリスト教になった人と、別の宗教からキリスト教になった人との対立の仲裁をしようと働きます。彼の態度はこれまでと大きく変わります。暴力的に一致させるのではなく、平和的に和解と一致をさせようとする態度に変わったのです。
おそらくここでサウロがどんな奇跡的な体験をしたかは重要ではありません。重要なのはサウロが価値観を大きく変えたということです。サウロの価値観の転換とは一体どんなことだったのでしょうか?これは単に奇跡が起きて、ユダヤ教からキリスト教へ変わったという、宗教の変更以上のものです。この個所はきっとそれよりも大事なことを伝えています。神様の導きにより、サウロの心には短期間で劇的な変化が起こりました。その変化とは他者の価値観を暴力的に否定する姿勢から、尊重と平和的な態度への変化です。
彼は弱さと無力の中で、その価値観が大きく変わりました。彼の生きる態度が変わりました。他者に対する態度が変わりました。異なる価値観の人を、敵対心ではなく敬意を持って接するようになったのです。それが彼に起きた一番の変化でした。それが神様から頂いたことでした。サウロが神様からいただいたものは、他者を尊重することへの方向転換だったのです。
神様は私たちにもそのような変化を与えるでしょうか。私たちはどんなときそのような神様からの変化をいただくでしょうか。神様は相手を否定する、暴力的な態度をとることから、相手を尊重し、共に生きる、平和に生きる態度に私たちを変えて下さいます。それはいつ起きるでしょうか?それは私たちが弱くされた時かもしれません。自分だけでは立ち上がれない時、誰かに頼って生きようとする時に、人生の価値観が大きく変わるのかもしれません。それは神様の決めた一方的な時に起こるのでしょう。その時、私たちは自分が唯一正しいという態度から、他者を尊重する態度に変わってゆきます。それはきっと私たちにも起こります。私たちはそのきっかけを神様からいただくのです。私たちは「それは間違っている」から「それも大事」と言えるように変わるのです。神様はきっと私たちにもそのような大きな転換を、新しい道を準備していてくださるはずです。
本日はこの後、主の晩餐を共に分かち合います。これは、イエス様が様々な人々と食事を共にしたことを記念する大切な儀式です。この教会では、洗礼を受けた方々がパンとブドウジュースをいただきます。19節にはサウロは食事をして元気を取り戻したと書いてあります。サウロはこの主の晩餐を受けて、新しく他者を愛し、敬う生き方を始めました。私達もこのパンを食べ、他者を尊重し、共に生きることを選びましょう。私たちもその第一歩を踏み出してゆきましょう。お祈りします。
「他者を尊重する方向転換」使徒言行録9章1~22節
すると、たちまち目からうろこのようなものが落ち、サウロは元どおり見えるようになった。そこで、身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。
使徒言行録9章18~19節
今日から聖書の使徒言行録を1ヶ月間読んでゆきます。みなさんは価値観が大きく変わるという体験をしたことがあるでしょうか?キリスト教の洗礼(バプテスマ)が人生の価値観を大きく変えるきっかけになったという人が多くいます。私もその一人です。聖書の教えを価値観の中心にするスタートが洗礼(バプテスマ)です。
洗礼(バプテスマ)に際してキリスト教以外の価値観を劣ったものとは考えないことも大事なことです。異なる価値観や宗教の人と共に生きてゆこうとすること、それがキリスト教の愛なのでしょう。今日は聖書のサウロという人物から、他者を尊重するという方向に生き方を転換した物語を見てゆきたいと思います。
十字架の後、イエス様の教えた愛の輪が広がっていました。そしてもともとの枠組みであるユダヤ教から大きくはずれる様になりました。サウロはユダヤ教を信仰していましたがそのキリスト教を激しく否定していました。それぞれの信仰にはそれぞれの価値観と教えがあり、どの宗教も尊重すべき教えがあります。ただしサウロはこの点で、かなり強引な態度でした。価値観、宗教観の違うものを見つけ出し、縛り上げ、連行し、脅迫し、殺していたのです。
そんなサウロにある日突然、運命を変える出来事が起こりました。それによって彼は自分が否定し、殺そうとしていた人の助けを必要としました。自分がいままで否定してきた人に手を引かれ、手を置いて祈ってもらわなければならなくなりました。それまで敵視していた人々に助けられたことで、彼の心は大きく変わりました。
ここでサウロがどんな奇跡的な体験をしたかは重要ではありません。重要なのはサウロの価値観の転換です。これは単に奇跡が起きて、ユダヤ教からキリスト教へ変わったという、宗教の変更以上のものです。彼の変化とは他者の価値観を暴力的に否定する姿勢から、尊重と平和的な態度への変化でした。彼は弱さと無力の中で、その価値観が、生きる態度、他者に対する態度が変わりました。異なる価値観の人に敬意を持って接するようになったのです。それが彼に起きた変化でした。
神様は私たちにもそのような変化を与えるでしょうか。自分だけでは立ち上がれない時、誰かに頼って生きようとする時に、人生の価値観が大きく変わるのかもしれません。その時、私たちは自分が唯一正しいという態度から、他者を尊重する態度に変わってゆきます。それはきっと私たちにも起こります。神様はきっと私たちにもそのような大きな転換を、新しい道を準備していてくださるはずです。
本日はこの後、主の晩餐を共に分かち合います。サウロはこの主の晩餐を受けて、新しく他者を愛し、敬う生き方を始めました。私達もこのパンを食べ、他者を尊重し、共に生きることを選びましょう。私たちもその第一歩を踏み出してゆきましょう。お祈りします。
【全文】「つながっていようよ」ヨハネ15章1~10節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声を聞きながら、一緒に礼拝をしましょう。
2か月間にわたってキリスト教に初めて触れる人に向けて話をしてきました。教会では難しい儀式したり、難しい話をしたりしているのではないことだけでも分かってもらえたらうれしいです。集まっている人は普通の人です。それぞれに人生の喜びや苦しみ、日常があります。その中で神様の助けを受けて生きようとして、励まし合う仲間と共に教会に集っています。神様の力を受けて、誰かのために、何かできることをしようと思って集っています。どう生きてゆけばいいかを毎週考えています。ぜひこれからも教会に来て下さい。またYoutubeをご覧になって迷っている方、ぜひお近くの教会に行ってみてください。繰り返し通うと、自分の中に変化が起きてくると思います。ぜひこれからも一緒に礼拝しましょう。
今日は「祈祷会(きとうかい)」という教会の集会をご紹介します。これは毎週水曜日午前10時30分からと夜8時から行われている集まりです。教会では礼拝に次いで大事な集まりと位置付けています。
祈祷会では賛美を歌い、聖書を読み、5分くらい私から解説をします。そのあとは自由に聖書から感じた感想を話し合います。それぞれの感想ですから、正解も不正解もありません。その感じ方が間違っていると否定されることもありません。自分が感じたこと、疑問に思った事、わからないこと、イメージしたことをただただ分かち合ってゆきます。
そして一人一人の感想を聞いていると、わからなかったことが分かるような気がしてきます。神様ってそういう方なのかぁ、こんな風に生きてゆけばいいのかなと思いつきます。そのように、みんながイメージを分かち合うと、聖書が伝えようとしていることが分かるような気がしてくるのです。
祈祷会ではその後に祈りの時を持っています。祈りの課題という教会が互いのこと、みんなで祈りたいことのリストをもとに黙祷し、心の中で神様に祈ります。自分自身のことでみんなに祈って欲しいことがあればそこで分かち合います。「祈祷会」というと大声で激しく祈ったり、地鎮祭のような祈りの儀式をするようなところに思われるかもしれませんが、そうではありません。実際には互いの聖書の感想を聞きあう会、一緒に神様に祈る会です。自分の悩みを打ち明けなくてはいけないということもありません。自己解放の度合いは個人個人に任せられています。教会学校も似た雰囲気です。
私はこの「祈祷会」をとても大事だと感じています。日曜日だけではなく、水曜日にも神様とのつながりを感じることができ、力が湧いてきます。そして祈祷会は神様とのつながりだけではなく、他者とのつながりをも感じることができる場所です。祈祷会は一緒に言葉を交わし、祈ることで、神様とそして仲間とつながっているという実感が持てる場所です。礼拝もそうですが、祈祷会はもっと仲間とのつながりを感じることができる場所です。ぜひ参加してみてください。今日はつながりということをテーマに宣教をしたいと思います。
ヨハネ福音書15章1~10節をお読みいただきました。今日の個所で大事なことを3つのつながりを紹介します。ひとつ目は「あなた方は私につながりなさい」ということ、2つ目は「私はあなたにつながっています」ということ、そして3つ目は「みんながつながる」ということです。まず一つ目のあなた方は私につながっていなさいから見ます。
神様は、私たちにあなたたちは私としっかり「つながっていなさい」と言っています。あなたたち人間は、神様をつかんでいるその手を絶対に放してはダメだよと言っています。神様とつながることを忘れないようにしましょう。神様はいつも私たちを導き、生きるヒントを与えてくれます。だから私たちは忙しい時でも、しんどい時でも、神様につながっていましょう。たとえばなるべく礼拝に集ったり、祈祷会に集ったり、聖書を読んだり、祈ったりすること、大事にしようということです。頑張ってゆきましょう。これがひとつ目に大事なことです
そして2つ目に大事なこととして神様は私はあなたがたに「つながっています」と言っています。それは私達から神様につながるのではなく、神様から私たちにつながってくださっているということです。私が手を離したら、神様が離れてしまうのではありません。私が忙しくて、心がいっぱいいっぱいで、もう捕まっていられない時も、神様の方からつながっていてくださるのです。私たちのどうこうは関係なく、神様から一方的につなげられているということです。これは大きな安心です。悪いことが起きた時、私が頑張って神様につながっていなかったからだと思うかもしれません。でもきっとそれは違います。神様はいつも私につながっているとはっきり言っています。つらい事、悪い事はどんな時でもおこります。でも、どんなにつらい時も、私がどんな状態の時も神様は私たちにつながってくださっています。だから神様を信じる人は安心して生きることができるのです。うまく自分から神様につながれなくても大丈夫です。神様はあなたにもうつながっています。神様は離れることなくあなたと一緒にいてくださいます。神様は私たちを必ず良い方へと導いてくださいます。だから安心してゆきましょう。これが大事なこと2つ目です。
さて大事なことの3つ目を紹介します。大事なことの3つ目は「あなたがた」という言葉に隠れています。あなたがたはつながっていなさい、私はあなたがたとつながっているという言葉には「あなたがた」ということばが含まれています。この「あなたがた」は私個人を指す言葉ではなく「みんな」を指す言葉です。神様は「あなた」はつながっていなさい、私は「あなた」につながっていると言っているのではありません。「あなたがた」みんなで神様につながりなさい、神様はみんなにつながっていますと言っているのです。私が神様とつながることが大事です。しかし今日の個所によれば、私たちみんなでつながるということも大事なことだと言っています。私たちは自分がつながるだけではなく、みんなで神様につながるのです。
そしてみんなで神様につながる時、みんなに神様がつながる時、私たちの間には神様とのつながりだけではなく、私たち同士、人間同士のつながりも生まれるはずです。神様は人と神がつながっていると伝えると同時に、私たちに人間同士も、神様によってつながっているというのです。そのような人間のつながりも、神様がおこしてくださるのです。私たちはみんなでつながると、互いが神様にどうやってつながっているのかを知るようになります。こうやって神様はこのひとにつながって導いているのだとか、この方はこうやって神様につながろうと頑張っているのだということを良く知るようになります。互いがどうやって神様につながり、つながれているかをよく見ることはとても大事なことです。自分はどうやって神様につながればよいのか、仲間をよく見るとわかります。どんな風に神様がつながっていてくださるのか、自分を見るよりも、周りの人を見た方がよくわかります。神様は私たちも互いにつながるように言っています。あなたはみんなとつながりなさい、みんながあなたにつながっているよと言うのです。
礼拝・祈祷会は毎週この3つのつながりを確認する場所と言えるでしょう。一人一人が一生懸命に神様につながろうとする場所です。そしてそれを超えて、神様が私たちにつながってくださっていると感じる場所です。そして集った私たち同士もつながっていると感じる場所です。私たちはそこから生きる力、励ましをいただいて、歩んでゆくのです。特に祈祷会は3つ目のみんなでつながるということを感じることができる場所です。
さて、2か月間はじめてキリスト教に触れる方に向けて、聖書から生き方のヒントを考えてきました。今日は特に神様とつながることの大事さを見てきました。初めて来た方、これからもどうぞ神様につながってゆきましょう。それぞれが神様に一生懸命に祈り、他者を愛し、生きてゆくことを大事にしましょう。神様もあなたにしっかりとつながっています。どんなつらいときも神様はあなたにつながっていて、守り、導いてくださるはずです。神様とつながっているからこそ、励ましを受けたり、慰めを受けたり、勇気をもらうことができます。神様がつながっていてくれるなら、私自身に力がなくても前に進むことが出来るのです。そして私たちはみんなで神様につながりましょう。
毎週教会ではこの礼拝と言う集会を持っています。みんなで神様につながりたい、神様はみんなにつながっている、そう信じている仲間が毎週集まっています。それぞれいろいろな苦労をしているけれど、私たちはみんなで神様につながろうね、わたしたちもつながっていようねと言い合います。それは私たちみんなの人生にとって大きな励ましになっています。私たちはそこから前に進むことができるのです。
神様が私たちみんなにつながっていて、みんなが神様につながっています。そして私たちもつながっています。私たちはみんなで神様につながっていましょう。そして私たち同士もつながっていましょう。そんな風に教会で、神様とのつながり、人とのつながりを感じながら生きてゆく生き方をお勧めします。お祈りします。
「つながっていようよ」ヨハネ15章1~10節
「つながっていようよ」
わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、わたしもその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れては、あなたがたは何もできないからである。 ヨハネによる福音書15章5節
毎週水曜日の「祈祷会(きとうかい)」という集会では聖書から感じた自由な感想を話し合います。互いの感想を聞いていると、神様の事、生き方のことたくさんの気づきを得ます。祈祷会では祈りの時も持っています。互いのこと、みんなで祈りたいことのリストをもとに黙祷し、心の中で神様に祈ります。私はこの「祈祷会」をとても大事だと感じています。祈祷会が神様とのつながりだけではなく、他者とのつながりをも感じる場所だからです。今日はつながりをテーマに宣教します。ヨハネ福音書15章1~10節から3つ大事なつながりを紹介します。
まず一つ目は、神様は私たちにあなたたちは私としっかり「つながっていなさい」と言っています。あなたたち人間は、神様をつかんでいるその手を絶対に放してはダメだと言っています。私たちは忙しい時でも神様につながっていましょう。たとえばなるべく礼拝や祈祷会に集ったり、祈ったりすることを頑張ってゆきましょう。
2つ目に神様は私はあなたがたに「つながっています」と言っています。私が手を離したら、神様が離れてしまうのではありません。私が忙しくて、つかまっていられない時も、どんなにつらい時も、神様の方からつながってくださるのです。だから神様を信じる人は安心して生きることができます。うまく自分から神様につながれなくても、神様はあなたにもうつながっています。これが大事なこと2つ目です。
大事なことの3つ目は「あなたがた」という言葉に隠れています。この「あなたがた」は私個人を指す言葉ではなく「みんな」を指す言葉です。みんなで神様につながりなさい、神様はみんなにつながっていますと言っているのです。
みんなで神様につながる時、私たちの間には神様とのつながりだけではなく、私たち同士、人間同士のつながりも生まれるはずです。神様は人と神がつながっていると伝えると同時に、私たちに人間同士も、神様によってつながっているというのです。そのような人間のつながりも、神様がおこしてくださるのです。
自分はどうやって神様につながればよいのか、仲間をよく見るとわかります。神様はそのように私たちも互いにつながっていることを感じるように言っています。礼拝・祈祷会は毎週この3つのながりを確認する場所だと言えるでしょう。
初めて来た方、これからもどうぞ神様につながってゆきましょう。神様もあなたにしっかりとつながっています。そして私たちはみんなで神様につながりましょう。毎週教会ではこの礼拝・祈祷会という集会を持っています。私たちはみんなで神様につながろうね、わたしたちもつながっていようねと言い合います。それは私たちみんなの人生にとって大きな励ましになっています。私たちはそこから前に進むことができるのです。そんな風に教会で、神様とのつながり、人とのつながりを感じながら生きてゆく生き方をお勧めします。お祈りします。
5月20日(月)10時~17時 こひつじカフェ開催のお知らせ
こひつじカフェは赤ちゃんから大人まで誰でもご利用いただけるカフェです。おひとり様も、お友達を誘ったりする方も、ぜひご利用ください。新しい出会いもあるかもしれません。今回はとりあえずテストのオープンです。ぜひ来てみて下さいね。
【全文】「風に吹かれればいい」
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちの教会はこどもの声がする教会です。今日も大人もこどもも一緒に礼拝をしましょう。先月と今月は初めてキリスト教に触れる方に向けて話をしています。
私たちは毎週日曜日の午前中にこの礼拝という集会を持っています。牧師である私の務めは、毎週の礼拝で聖書の話をすることです。毎週15分ほどのお話をしていますが、実は準備するのが大変です。どんなに頑張ってパソコンにかじりついても、参考書を読んでも、うまくいかない、何かが違うと思う時があります。この勤めを毎週果たし続けるには、みなさんの日頃の祈りと支えが必要です。そして何より神様の導きが必要です。とても自分の力だけではできません。どうしてもうまくいかない時どうしているかと言うと、そんな時は風に吹かれてみることにしています。教会の中庭にはハンモックがありますが、行き詰まった時はハンモックに揺られます。空を見上げながら、風に吹かれながら、何かが違うなぁ、うまくまとまらないぁ、うまく言葉にならないなぁ、どうしようかと思いを巡らせます。そやって風に吹かれていると、時々新しい言葉がひらめいたりします。風に吹かれると、変えるよりもこのままの方がいいかなと思ったりもします。風に吹かれると、やっぱりこの方向性はダメ、やり直そうと思ったりもします。風に吹かれながら、神様の導きを求めています。
今日は新しい仲間の信仰の言葉を聞きました。新しい仲間が増えることは大変うれしいことです。心から歓迎をします。今日のためにご自身の信仰を紹介する言葉を準備してくださいました。きっとこの言葉を紡ぐのも大変だったでしょう。そしてきっとそこにも神様の導きがあったでしょう。この告白ではっきりしていることは、神様は人間の力を超えて、不思議な力で、私たちを教会へと呼び集めるのだということです。
私たちの人生も同じでしょう。私たちの人生の行く先は、神様が導いてくださるのです。神様はまるで私たちの背中を押すように、私たちを信仰へと送り出してくださいます。それはまるで追い風を受けている様です。風が私たちを押し出します。それが神様からの風です。神様はそのような風を私たちに吹かしているのです。神様が私たちを導くとは、神様の吹かす風に押し出されて進むことです。私たちの人生で大事なこと、それは神様の風に吹かれることです。その風を感じて生きることです。そのように神様からの風は私たちに言葉を与え、私たちを新しい行動に導くのです。私の宣教の言葉も、今日の信仰の言葉も、神様からの風に、押し出され、発せられたものです。
聖書・創世記によれば、神様はまず土で人間の形を作りました。そして神様はその土に息・風を送り込みました。そうすると人間は生きるものとなったと書かれています。神様の風とは、私たちに生きる活力をあたえる風です。神様の風とは私たちに生命を吹き込む風です。私たちはそのようにして神様の風に吹かれて生きるようになるのです。神様の風が私たちに命を与え、導くのです。
私たちの人生には様々な課題があります。どうすればいいかわからないこと、どうすることもできないことがあるものです。そんな時、風に吹かれてみてはどうでしょうか?自分の頭で考えるのを少し休憩して、自然いっぱいの風を受けてみたらいいのです。自分を吹き去ってゆく風、自分の呼吸として取り込まれる風、自分の体をここちよく揺らす風にあたればいいのです。どこから来てどこに行くのかわからない風にあたればいいのです。体で風を感じれば、きっと心にも神様の風を感じることができるでしょう。そうすると神様の導く方向が分かるはずです。風を受けて生きましょう。風を受ければきっと新しい生き方、新しい命を神様からいただけるはずです。
キリスト教の神様の風は、宗教や性別を問わずに吹きます。ですからすでに皆さんには神様の風が吹いています。体で感じる風を受ければ、きっと神様が心に吹かす風も分かるはずです。皆さんの心にも神様の風がもう吹いています。それを感じ、神様に導きを感じてみて下さい。今日は聖書から風に吹かれた弟子たちの話をします。
今日は使徒言行録2章1~11節をお読みいただきました。教会では今日はペンテコステという記念日です。これは2000年前に聖霊が人々に下ったこと、風が吹いたことを記念する日です。2000年前、イエス様は様々なことを弟子たちに教えましたが、十字架に掛けられ死んでしまいました。しかし弟子たちはイエス様の死んでしまった後も集まっていました。本来は教祖が死んでしまったのですから、活動が終わってしまってもしょうがないのです。しかしキリスト教はイエス様が死んでしまった後も続いてゆきます。それは弟子たちがイエス様の後を引き継いで一生懸命に頑張ったからではありません。その活動は弟子たちが、神様からの不思議な力、不思議な風を受けることで続けることが出来たのです。
例えば今日の出来事もそうです。イエス様の死後、弟子たちがみんなで集まっている時、突然強い風が吹きました。風は神様の一方的な決断で吹きました。神様からの風は弟子たちが頑張った時、願った時、集まった時にだけ吹くのではありません。神様の風は神様の決めたタイミングで吹きます。私たちの願いと関係なく自由に吹きます。それが神様の風です。
そして神様の風はそこにいたみんなに吹きました。神様の風は後継者や一人の選ばれたリーダーに吹いて、そこから下々に広がるのではありませんでした。何か良い事をした人、キリスト教を信じている人にだけ吹いたのでもありません。神様の風は全員に等しく、全員に直接吹き抜けました。一人一人の頭の上に炎がともるように、全員に風は吹いたのです。神様が全員を選んだとも言えるでしょう。神様は全員に風が吹くように、風を送られたのです。
そして神様の風に吹かれると不思議なことが起こりました。風に吹かれた人たちは他の国の言葉でしゃべり出したのです。それは当然、自分の内側から出てきた言葉ではありませんでした。神様が外側から語るべき言葉を教えてくれたのです。それは様々な国の言葉でした。自分が語るべきことは神様が教えてくださったのです。弟子たちは自分の考えた言葉ではなく、神様の風の吹くままに語ったのです。それは自分の力ではなく、神様の力によって起きた出来事でした。私たちにもきっとそのようなことが起きるでしょう。自分にはできなくても、神様が力を与えて下さって、できることがあるでしょう。私の毎週のメッセージもそうです。教会に続けて来ることもそうです。それぞれの場所でも神様の力を受けるからこそできる、そんなことがきっとあるでしょう。
弟子たちが様々な国のことばで語ったことの意味も考えます。様々な国の言葉で語られたことは、全世界の人に神様の不思議な力が伝えられたということを意味するでしょう。普通では起きないことが、自分の力ではできないことが、神様の力によって起きるという希望は、全世界に伝えられました。それは難しい言葉ではなく、相手に良くわかる言葉で伝えられました。神様の力は、みんなにわかるように届けられたのです。私にもわかる、あなたにもわかる、みんなにわかる言葉で神様の希望が示されたのです。
神様の風はそのように、ひとりひとりに、全員に命と活力と言葉を吹き込みました。このようにして神様の風を受けて人は輝くのです。私にもあなたにも自分では輝く力がないかもしれません。でも神様から力をいただいて輝くことができるのです。私たちはそんな神様からの風を受けて歩むのです。私たちはすでにその風を受けています。私たちは全身でその風を感じ、風に身をゆだねてゆきましょう。
特に今日初めてキリスト教の話を聞く、初めてここに集まったという人にとって、この集いやこの言葉はどう響くでしょうか。毎週集まれるのはすごい熱心だと思うかもしれません。でも私たちが集うことが出来るのは、熱心さや一生懸命さではなく、神様の風に吹かれているからです。私たちが神様の風に身をゆだねているから集うことができるのです。自分で方向を決めるのではなく、神様の風に身をゆだねています。そのようにして私たちは神様の風に招かれるままに集まっています。周りの人からはおかしな集まりに見えるかもしれない。でもそれでもいいと思っています。
皆さんにはこう生きたい、こうなりたいという願いがあると思います。それはとても大事です。でもその願いと共にもう一つ心にとめて欲しいことがあります。それは私たちには神様の風が吹いているということです。神様の風はきっと私たちをどこかへと運ぼうと導いています。すでに私たちにはその風が吹いているはずです。私たちは自分の願いと共に、その神様からの風がどう吹いているのかを感じて生きてゆきたいのです。
神様は私たちに風を送ります。私たちはその風に吹かれながら生きましょう。私たちには何もできなくても、神様が風を吹かせ、導いてくださいます。神様が必要な言葉と力を与えてくれるはずです。だから神様の風に吹かれて生きましょう。その風はきっと私たちを新しい生き方へと導いてくれるはずです。一人一人の命が輝く生き方、互いを愛し、大事にする生き方へと導かれるでしょう。お祈りします。
「風に吹かれればいい」
突然、激しい風が吹いて来るような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。
使徒言行録2章2節
先月と今月は初めてキリスト教に触れる方に向けて話をしています。聖書の話を毎週の礼拝でするのが大変ですが、準備に行き詰まった時は、風に吹かれながら思いを巡らせます。風に吹かれていると、時々新しい言葉がひらめいたり、やり直そうと思えたりします。風に吹かれながら、神様の導きを求めています。
今日は新しい仲間の信仰の言葉を聞きましたが、きっとこの言葉を紡ぐのも大変だったでしょう。この告白ではっきりしていることは、神様は不思議な力で、私たちを教会へと呼び集めるのだということです。神様が私たちを導くとは、神様の吹かす風に押し出されて進むようなことです。私の宣教の言葉も、今日の信仰の言葉も、神様からの風に、押し出され、発せられたものです。
聖書・創世記によれば、神様が土で人間の形を作り、息・風を送り込むと人間は生きるものとなったと書かれています。神様の風とは私たちに生命を吹き込む風です。私たちは神様の風に吹かれると生きるようになるのです。私たちの人生には、どうすればいいかわからないことがあります。そんな時、風に吹かれてみてはどうでしょうか?体で風を感じれば、きっと心にも神様の風を感じることができるはずです。風に吹かれ、神様からもう一度命を、新しい生き方を頂きましょう。今日は聖書から風に吹かれた弟子たちの話をします。
キリスト教はイエス様が死んでしまった後も続いてゆきました。それは弟子たちが一生懸命に頑張ったから続いたのではありません。神様からの不思議な力、不思議な風を受けることで続けることが出来ました。弟子たちがみんなで集まっている時、突然強い風が吹きました。風は神様の一方的な決断で吹きました。神様の風は神様の決めたタイミングで吹きます。そしてそこにいた全員に吹きました。神様の風に吹かれると不思議なことが起こりました。自分にはできないことでも、神様が力を与えて下さって、できるようになったのです。様々な国の言葉で語られたのは、みんなにわかる言葉で神様の希望を示すためでした。そのようにして神様の風は全員に命と活力と言葉を吹き込みました。
私たちもそんな神様からの風を受けて歩んでいるのです。私たちが毎週集まれるのは熱心さや一生懸命さではなく、神様の風に吹かれているからです。私たちが神様の風に身をゆだねているから集うことができるのです。神様の風はきっと私たちをどこかへと運ぼうと導いています。だから私たちは自分の願いだけではなく、神様からの風がどう吹いているのかを感じて生きゆきたいです。
神様が私たちに風を送っていす。私たちはその風に吹かれながら生きましょう。私たちには何もできなくても、神様が風を吹かせ、導いてくださいます。神様の風が私たちに必要な言葉と力、新しい生き方を与えてくださるはずです。お祈りします。
佐々木さんを支援する会を応援しています
私たちの教会では、ルワンダで和解と平和のために働く佐々木和之さんを応援しています。
佐々木さんの活動をぜひこちらからご確認ください。
ぜひルワンダの働きのために寄付をお願いいたします。
【全文】「心洗われる教会」ヨハネ13章1~15節
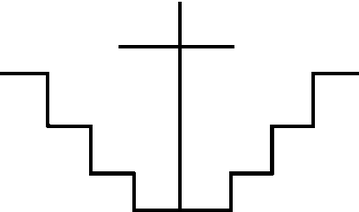
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できることを主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声を聞きながら、一緒に礼拝しましょう。
先月と今月は、初めて教会に来た方、初めてキリスト教に触れる方に向けて話をしています。聖書のヨハネによる福音書という部分から有名な個所を選び、お話をしています。今日ご紹介したのは、イエス様が弟子たちの足を洗う「洗足」という箇所です。2000年前、当時の道はほとんど舗装されていませんし、履物はサンダルでした。舗装されていない道をサンダルで歩けば、足は泥だらけになりました。泥がたくさんついた足は、たくさん歩いて疲れた証拠、苦労の証拠です。もちろん汗と汚れが混ざって、臭いもしたでしょう。
人びとには家に帰ってくると、足を洗うという習慣がありました。毎日たっぷりのお湯でシャワーを浴びることはできません。洗うことが出来るのは足くらいです。足を洗うのは1日の働きが終わって帰って来て、自分をいたわるホッとするひとときでした。ある程度裕福な家には召使いや奴隷がいました。帰ってきた主人の足を洗うのは召使いや奴隷の仕事でした。召使いは主人の疲れた汚い足を、指の間まできれいに洗いました。それは奴隷にとっても嬉しい仕事ではなかったでしょう。現代の私たちが家族の介護で大変なように、人の足を洗うのはなかなか大変な仕事でした。
しかし今日の聖書にはイエス様が弟子の足を洗ったと書いてあります。足を洗うのは本来、召使いや奴隷のするべき仕事でした。今日はそれをイエス様がしたのです。これはイエス様が弟子たちにした他者のために働き、他者を尊重するという模範的、象徴的な行為でした。
2000年前の人々は今の時代よりもずっと名誉を大事にしました。今の時代よりももっと周囲から認められ、地位が高くなることを重視した社会でした。地域の政治や宗教のリーダーであることの名誉は大変大きかったのです。今の時代でも政治家は勘違いして威張り腐っていますが、当時の政治家は同じかもっと威張り腐っていたでしょう。今も昔もリーダーとはだいたいそんなものでした。しかしイエス様は他のリーダーと大きく違いました。イエス様は弟子の足を洗おうとします。弟子たちの汚れたくさい足を洗おうとします。地位や名誉より召使いの仕事を、進んでしようとするのです。キリスト教ではこのイエス様を神様と等しいお方であると信じています。このような弟子の足を洗う、召使いの仕事をする、これがキリスト教の神と等しいとされた人の姿です。神と等しい方は人間の汚れた足を洗いました。このデモンストレーションが他者のために働き、他者を尊重する生き方を示しています。
特にキリスト教に触れることが少ない方は、キリスト教にはちょっと敷居の高いイメージを持っている時があります。私はある方から「教会に行ってはみたいけど、私なんかのような汚れた人間が行ってもよい場所なのでしょうか?興味本位なんかで行ってよい場所ではありませんよね?」と聞かれたことがあります。もちろん、そう思っている方も来て下さい。自分は汚れていると思っている方、ただの興味という方もどうぞ来て下さい。歓迎します。今日ご紹介した物語によれば、教会はきっと修行して、功徳を積んで、清らかになってから来る場所ではありません。キリスト教はこの図のように示されるでしょう。この図は階段を下った一番下にイエス様の象徴である十字架が立っています。そこが神がいる場所です。修行して功徳を積んで、階段を昇りつめた先で神様に手が届くのではありません。神様は徹底的に低みに立っています。神様は低くされている人のために働き、その人を尊重してゆく方なのです。困っている他者に目を向けてゆく、そこに神様がいるのです。それがキリスト教の教えです。
私たちは上へ、上へと昇るのではありません。私たちは下へ下へ向かいます。小さくされた人、弱くされた人、見過ごされた人、隅に追いやられた人がいないか目を配り、その人たちと共に生きようとします。そこに地位と名誉はないかもしれません。でもそこへと向かってゆくのが、キリスト者の在り方です。どちらが強いか、偉いか、大いなるものかを競うのではなく、他者の足を洗う様な生き方をしなさい、イエス様はそう教えています。他者のために働き、他者を尊重する人になりなさいと教えたのです。
このように人の足を洗うような、他者のために働く、汚れるような仕事をするのは実は案外難しいことです。お給料をもらっていれば、がまんできるかもしれません。家族の事だったらしかたなくできるかもしれません。でも仕事でも家族でもなく、無償で、ただ愛でそれをするのはとても難しいことです。しかしイエス様がそれを実践して見せています。これが無償の愛の一例ですよと示すために足を洗ったのです。イエス様は人の足を洗う者となりなさいと言っています。私たちは人の足を無償で洗うような、そんな生き方をしてゆきたいと思います。
そして、この物語はもう一つ重要なことを伝えています。それは自分は洗う側だけではなく、洗われる側に立つことがあるということです。もしかすると誰かの足を洗うよりも、誰かに足を洗われる方が嫌かもしれません。きっと洗うよりも、洗われる方が嫌です。その感情は何を意味するでしょうか。私たちは相手の汚い部分を見て、相手の汚い部分に触れることを、もしかしたら我慢できるかもしれません。
でも反対に、自分の汚い部分を見られたり、自分の汚い部分に触れられたりするのは非常に強い抵抗があるものです。自分の悪い部分、汚い部分を見られるのは嫌です。隠したいものです。いつもきれいで強いと思われたいものです。しかし本当の自分はそうでないことを誰よりも自分が知っています。弱さと疲れを見られるのは恥ずかしいものです。弟子も「決して洗わないでください」と言っています。その気持ちはわかります。自分はいつも洗う側でいたい、洗われる側にはなりたくないのです。
しかしイエス様は14節「互いに洗い合わなければならない」と言っています。8節では洗わなかったら私たちの関係はなくなってしまうと言います。足を洗いあうのが、私たちの関係ではないかというのです。疲れて、汚れた、お互いの足を隠しあったら、我々の関係は成り立たないというのです。私たちはお互いが尊い存在だと確認しあうだけではないということです。私たちの人生はそんなきれい事だけではありません。私たちの人生にはそれぞれに疲れや困難があり、汚れがあります。ここから示されることは、人生に疲れた時、私たちは恥ずかしいですが、誰の支えを必要とするということです。私たちは神様に支えられながら生きます。そして仲間に支えられながら生きます。神様と仲間の支えなしに人生を生きてゆくことはできないのです。私たちはそのことをこの物語から知ります。私たちは足を洗ってもらう様な、励ましや祈りが必要なのです。
教会の人はいつも教会ではニコニコしています。初めて教会に来る方は私のような汚れた人間の行く場所ではないと思ってしまうほどです。自分だけ汚れているようで、自分だけその汚れを見られるのは嫌だと感じるかもしれません。でも安心してください。みんなの足は、本当は汚れています。それぞれに苦労や失敗を持っているのです。教会に来た時は笑っているかもしれません。教会の中に偉い人のように見えた人もいるかもしれません。でも本当は1週間にいろいろなことを体験しています。疲れて、足が汚れるような1週間を過ごしています。みんな本当は汚れた足で来ているのです。
そんなときでも教会では互いを尊重し、励ましあう言葉を交わしています。それはまるで毎週教会で足を洗ってもらっている、互いに足を洗い合っている様です。神様から、仲間から足を洗ってもらっている様です。きっとみんなも1週間大変だったのに疲れて汚れた私に、温かい言葉を掛けてくれます。それが私にとって、足を洗われるということです。同時に誰かに温かい声を掛けます。それが誰かの足を洗うことです。互いに足を洗い合うからこそ1週間が頑張れるのです。
私たちは洗う側と洗われる側に分かれているのではありません。みんな洗われるべき汚い足をしており、みんながやさしく互いの足を洗います。そのような教会に来ると、心洗われたような気持ちになります。ほっとする気持ちになるのです。そしてまた出発することができます。またそこに行けば足が汚れるとわかっていても、そこに向かうことができるのです。そのようにし私たちは1週間を過ごすのです。
私たちはこのように「足を洗いなさい」と言われています。私たちの1週間は他者を見下し、威張るのではありません。隅に追いやられた人に視線を合わせるような生き方をしましょう。そして私たちは「足を洗ってもらいなさい」と言われています。あなたの足は疲れていて、汚れているから、教会の人にやさしく洗ってもらいなさいと言われているのです。教会の誰かに甘えなさいと言われているのです。
イエス様はこのように伝えました。私たちに互いに足を洗い合いなさいと伝えました。足を洗うことによって、他者のために働き、他者を尊重する生き方がキリスト者の生き方だと示しました。そして互いにいたわり合い、励まし合う関係の大事さを私たちに教えてくれたのです。
教会にはそのことを信じる信仰を持つ人が毎週集っています。私はたくさんの人がこの生き方・信仰に加わること、増えることを願っています。お祈りします。
「心洗われる教会」ヨハネ13章1~15節
初めてキリスト教に触れる方に向けて話をしています。2000年前舗装されていない道をサンダルで歩けば、足は泥だらけになりました。汗と汚れが混ざって臭いもしたでしょう。シャワーを浴びることもできません。足を洗うのは、自分をいたわるホッとするひとときでした。裕福な家では足を洗うのは召使いの仕事でした。
しかし今日の聖書にはイエス様が弟子の足を洗ったと書いてあります。これは他者のために働き、他者を尊重するという模範的、象徴的な行為でした。今も昔もリーダーは威張り腐っています。しかしイエス様は他のリーダーと大きく違いました。弟子たちの汚れた足を洗おうとします。これがキリスト教の神と等しいとされた人の姿です。他者のために働き、他者を尊重する生き方を体現しています。神様は徹底的に低みに立つ方なのです。
そして、この物語はもう一つ重要なことを伝えています。もしかすると誰かの足を洗うよりも、誰かに足を洗われる方が嫌かもしれません。自分の悪い部分、汚い部分は隠したいものです。弟子も「決して洗わないでください」と言っています。しかしイエス様は14節「互いに洗い合わなければならない」と言っています。疲れて、汚れた、お互いの足を隠しあったら、我々の関係は成り立たないというのです。
ここから示されることは、私たちの人生にはそれぞれに疲れや困難があり、そのときは恥ずかしいけれど、誰からの支えを必要とするということです。私たちは神様と仲間の支えなしに生きてゆくことはできないのです。私たちは足を洗ってもらう様な、励ましや祈りが必要なのです。
教会では互いを尊重し、励ましあう言葉を交わしています。それはまるで毎週教会で互いに足を洗い合っている様です。神様から、仲間から足を洗ってもらっている様です。誰かが疲れて汚れた私に、温かい言葉を掛けてくれます。それは私にとって足を洗われるということです。同時に誰かに温かい声を掛けます。それが誰かの足を洗うことです。互いに足を洗い合うからこそ1週間が頑張れるのです。
私たちは洗う側と洗われる側に分かれているのではありません。みんな洗われるべき汚い足をしており、みんながやさしく互いの足を洗います。そのような教会に来ると、心洗われたような気持ちになります。ほっとする気持ちになるのです。
イエス様はこのように私たちに互いに足を洗い合いなさいと伝えました。足を洗うことによって、他者のために働き、他者を尊重する生き方がキリスト者の生き方だと示しました。そして互いにいたわり合い、励まし合う関係の大事さを私たちに教えてくれたのです。教会にはそのことを信じる信仰を持つ人が毎週集っています。私はたくさんの人がこの生き方・信仰に加わること、増えることを願っています。お祈りします。
【全文】「こどもの声が世界を変える」ヨハネによる福音書9章1~19節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちの教会はこどもの声がする教会です。今日もこどもたちと一緒に礼拝をしてゆきましょう。今月と来月は、キリスト教が初めてという人に向けて話をしています。今日はこの聖書の中のヨハネ福音書の中にある、ベトザタの池の物語をご紹介します。
2000年前、現在のパレスチナにベトザタという名前の池がありました。この池にはある伝承がありました。その伝承とはこうです。天使がこの池に降りてくると、池の水面にゆらゆらと小さな波ができ、その時、池の中に入ると、一番先に入った人は病気が治るという伝承でした。本当にそんなことが起きていたのかはわかりません。ただその奇跡に期待をして、多くの人がこの池の周りで、小さな波が起こるのをじっと待っていました。治らない病を持っていた人にとってはこの池が最後の望みで、この池だけが希望でした。そのようにして多くの人がこの池の周りに集まり、水面をじっと見つめていたのです。
しかしこの奇跡の伝承は非常に残酷な伝承でもありました。というのはこの伝承によると一番先に水に入った人だけ、病気が治るのです。つまりそれは一番動ける、一番足の速い病人が一人だけ癒されるということです。それが意味することは、この池の周りで寝ている人は全員、自分が一番早く水に入らなくてはと思っていたということです。全員が自分が一番になろうとする敵だったのです。あの人よりも私が早く、隣人よりも私が早く、私が水に入らなければいけないのです。他の人を押しのけてでも、私が一番にならなければいけなかったのです。そのような池の周りの人間関係は最悪だったでしょう。いつ起こるかわからない波を待ち、全員がお互いを出し抜こうと考えていました。弱肉強食で、緊張が張り詰め、ぎくしゃくしています。まるで生存競争ようなの場所だったはずです。皆、どうしたら自分が一番になれるのかばかりを考えていました。
それでも多くの人がこの池の周りに集まりました。4節には目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人が集まっていたとあります。想像するだけで悲しいです。なぜなら彼らは波が起きてもすぐに水の中に入ることがほとんど不可能な人たちだからです。それでも彼らはそこに集まっていたのです。もしかすると見捨てられて、そこしか居場所が無かったのかもしれません。ほとんど期待できない希望をもって、失望と共にそこで待ったのです。
その中に一人、38年間病気の男性がいました。そして池の周りに横たわっていました。イエス様はその人を見て、すぐに病気であることが分かりました。目に見える病気を持っていたのでしょう。彼は自分では起き上がり、立つことができないほどの障がいを持っていました。イエス様はそのような場所に現れました。苦しみと失望と緊張関係に満ちた場所に現れました。イエス様とはそのようなお方です。苦しみと失望の底に現れるのです。
イエス様はそこで問いかけました「良くなりたいか?」。失礼な質問です。当然、良くなりたいに決まっているじゃないですか。良くなりたいと答えるはずです。でも本当にそうでしょうか。38年間の彼の苦痛は想像できません。38年間で何人、この池に飛びこむ人を見たでしょうか。どれほどの我先にとこの池に飛び込む競争を見てきたでしょうか。そして彼はこの生存競争に38年間負け続けていました。彼はまだ良くなりたいと思っていたでしょうか。なんとか次こそは私が入ってやる、次こそ自分だと希望を持つことができていたでしょうか。その思いは38年も続くでしょうか。続かなったのではないでしょうか。きっと良くなりたいということを、もうあきらめていたのではないでしょうか。
イエス様の「良くなりたいか」という問いかけに彼は「良くなりたい」と答えることができませんでした。彼はその代わり「誰も私を運んでくれない」と答えました。彼の失望が伝わって来る言葉です。彼が失望していたのは、もはや自分が病であることではありません。彼が失望していたのは自分の周囲にいた人間でした。自分のことを優先する人間に失望し、助けてくれない隣人に失望していたのです。誰も他者を助けようとしない世界に失望していたのです。
彼のいた世界は自分優先の世界です。自分の幸せを一番優先にする世界です。他人はどうでもよい、幸せは争い奪い合って、勝ち取るという世界です。争って、つかみ取る力のない者には、幸せは訪れない世界でした。希望を持てない彼を責める気にはなれません。彼を失望させたのは彼のいた世界です。奪い合う世界、醜い競争の世界が、彼にそのような世界観を持たせ、失望させたのです。イエス様の「良くなりたいか」という質問はそんな世界を鋭く問う質問でした。
そしてイエス様は言いました「起き上がりなさい」起き上がることのできない、歩くことのできない人に対して命令をしました。そうすると不思議と彼は立ち上がることができました。38年間悩み、様々なことを試し、世界に失望し、あきらめていた彼がもう一度立ち上がって、歩きだしたのです。
イエス様は歩き出すときに一つだけ条件を付けました。それは床を担いで歩きなさいという条件です。「床を担いで歩きなさい」の床とは、横になる時に下に敷くものです。布団よりももっと粗末なマットやゴザの様なものです。それは彼が38年間寝ていたマットです。それには彼の38年間の汗と涙がしみ込んでいました。そして彼の心と同じように擦り切れ、ボロボロになっていました。そのマットは彼の人生を象徴するものです。そして彼がいた池の周りの世界を象徴するものです。彼の苦労と屈辱の象徴でした。自由を奪っていた病と世界の象徴でした。それが床です。イエス様が歩き出すときにつけた唯一の条件は、その床を担ぐようにということでした。彼の人生の苦労と屈辱と汗と涙のすべての象徴である「床」を担いで歩くようにと言ったのです。それは、これからもその現実を背負って生きてゆきなさいという意味です。彼は一切の苦しみから解放されて、病気やこの池の出来事などすべて無かったものとして生きるのではないということです。これからもこの38年間の苦労を忘れずに、あの池で見た世界を忘れずに生きるようにと条件を付けられたのです。そのようにして彼は元の世界へと戻されてゆきます。この悲しみも苦しみも、人間の醜さもすべてを背負ったまま彼は歩み出したのです。
彼が生き始まめると、すぐに白い目で見られました。彼を見て喜んだ人がいたという報告はありません。体調が回復し、病とあの池の環境から抜け出すことができた、それが祝われている様子は報告されません。周囲からの祝福はあったでしょうか。「よかったね」と言われ、喜び合ったでしょうか。しかしその様子は描かれていません。記録されているのは周囲が、今日は荷物を背負ってはいけない決まりがある日なのに、なぜあなたは荷物を背負って歩いているのかと聞いたことです。他人の幸せを喜び合えない世界です。実は外の世界も池の周りと変わらなかったのです。自分が一番先で、周りはどうでもよいと考えたあの池と同じように、ここでは他者と共に喜ぶ姿は存在しなません。誰がそんなことを言ったのか、誰が決まりを破るように指示したのか聞き、足の引っ張ろうとしています。そしてそのようにしてイエス様は十字架にかけられてゆくのです。
さて、今日の物語から私たちはどんなことを考えるでしょうか。まず私が思うことは、この世界はまるでベトザタの池の様だということです。世界はこの池のように、自分中心、自国優先、強い者が勝つ世界です。隣人と愛し合うのではなく、たがいに敵同士のように競争する世界です。互いを喜び合えない世界です。私たちもこのような世界・日常に生きています。
イエス様はそのただなかに現れるお方です。ひどい現実の、どん底の、この世界の真ん中に現れるお方です。そして私たちに問いかけるのです。「良くなりたいか?」。私たちはなんと応えるでしょうか?みんながちゃんとしてくれないから、周りの人が悪いから、彼らのせいでこうなっていると言いたくなる現実です。でもその時イエス様は、私たちを立ち上がらせ下さいます。
人間には立ち上がるすべがないはずなのに、良くするすべがないはずなのに、神様が人間に力を与え、立ち上がることができるのです。神様はそのように、私たちを立ち上がらせてくださるのです。
そして神様は、私たちをただ立ち上がらせるだけではありません。現実を背負って立ち上がるように、私たちに言うのです。世界の悲しみ、苦しみを忘れて、無関係に生きるのではありません。それを背負って生きる、それに責任をもって生きるように、私たちを立ち上がらせるのです。今私たちのいる世界を良くするために、神様は私たちを立ち上げてくださるのです。
この礼拝で、私たちは神様から床を担いで立ち上がれと言われています。私たちは自分では立ち上がることができないけれど、神様が私たちを立ち上げてくださるのです。私たち立ち上がります。現実を背負って立ち上がります。そして小さな力でも世界を「良くしたいか」と問われます。私たちは「良くなりたいです」と答えましょう。私たちは現実を背負って生きましょう。それぞれの場所で、互いに愛し合い、困っている人を助け、隣人と喜びをともにしましょう。それぞれの場所で弱肉強食ではない、愛と慈しみにあふれる世界を創ってゆきましょう。その1週間を今日から歩みましょう。神様が私たちを立ち上げて下さいます。お祈りします。
「こどもの声が世界を変える」ヨハネによる福音書9章1~19節
「ここに大麦のパン五つと魚二匹とを持っている少年がいます。けれども、こんなに大勢の人では、何の役にも立たないでしょう。」ヨハネによる福音書9章9節
今月と来月は初めて教会に来た方に向けてお話をしています。私たちの教会では、月2回会堂でこども食堂を開催しています。最近4名の小学生がボランティアに加わってくれました。このことによって様々なよい変化が起きています。教会員のある方は「こどものボランティアを見て、ヨハネの5000人の食事(今日の個所)の意味がようやくわかった」とおっしゃっていました。私たちは今年度の標語を「こどもの声がする教会」としています。こどもたちの声が私たちの礼拝や食堂の雰囲気と方向性を決定づけています。同じことが聖書にも書いてあります。
2000年前、イエス様は様々な背景や事情を持った人たちと全員で食事をしようとしました。一緒に食事をすることは私たちのこども食堂と同様に友好関係にあることを示す行動です。でも準備が大変です。弟子たちは無理だと思いました。
そこにひとりの少年が声をあげ、少ない食事を差し出しました。それは「僕にできることがあればします」という姿勢でした。この少年ができる精一杯の小さなボランティアでした。弟子たちはそれを笑いました。「どうせ役に立たない」と思ったのです。小さなもので全体は変わらないと思ったのです。
しかしイエス様は小さくて役に立たないと思われているボランティアに目をとめて、いったん座って、何が起きているのか全員でよく考えるように促しました。そしてイエス様は感謝の祈りを唱えました。イエス様はそれが小さくてもどれだけ重要であるかを知り、感謝して祈ったのです。物語全体の雰囲気がここで変わります。イエス様はパンと魚を分けはじめました。そうすると不思議にも全員が満腹になる食べ物が現れたのです。普通は決して起きない奇跡的なことが起きたのです。
私たちは今日の物語からどんなことを考えるでしょうか。私はパンを増やすおまじないには興味がありません。今日の個所で小さな者の声に立ち止まるという生き方を学びます。私たちの社会では強い者の意見が通ります。私はそのような社会だからこそ小さな者の声、少数意見に耳を傾ける必要があると思います。
小さな働きの力を信じるということも、この物語から学びます。私たちそれぞれの前にある課題は大きすぎて、自分はたいして役に立たないと感じることばかりです。でも今日の物語によれば小さなボランティアが全体の雰囲気と方向性を変えたのです。小さなこどもたちのボランティアが私たちの礼拝とこども食堂の雰囲気を決定づけてゆくように、小さな働きが世界の方向を変えるのです。今日の物語から私たちはそれを信じましょう。
このあと私たちは主の晩餐という儀式を持ちます。これは小さなパンと、小さな杯にいれたブドウジュースを飲む儀式です。イエス様がこのような食事をしたことを再現する儀式です。こんな小さなパンですが私たちは大きな変化が起こると信じています。お祈りします。
【全文】「神が私を立ち上げて下さる」ヨハネ5章1~13節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちの教会はこどもの声がする教会です。今日もこどもたちと一緒に礼拝をしてゆきましょう。今月と来月は、キリスト教が初めてという人に向けて話をしています。今日はこの聖書の中のヨハネ福音書の中にある、ベトザタの池の物語をご紹介します。
2000年前、現在のパレスチナにベトザタという名前の池がありました。この池にはある伝承がありました。その伝承とはこうです。天使がこの池に降りてくると、池の水面にゆらゆらと小さな波ができ、その時、池の中に入ると、一番先に入った人は病気が治るという伝承でした。本当にそんなことが起きていたのかはわかりません。ただその奇跡に期待をして、多くの人がこの池の周りで、小さな波が起こるのをじっと待っていました。治らない病を持っていた人にとってはこの池が最後の望みで、この池だけが希望でした。そのようにして多くの人がこの池の周りに集まり、水面をじっと見つめていたのです。
しかしこの奇跡の伝承は非常に残酷な伝承でもありました。というのはこの伝承によると一番先に水に入った人だけ、病気が治るのです。つまりそれは一番動ける、一番足の速い病人が一人だけ癒されるということです。それが意味することは、この池の周りで寝ている人は全員、自分が一番早く水に入らなくてはと思っていたということです。全員が自分が一番になろうとする敵だったのです。あの人よりも私が早く、隣人よりも私が早く、私が水に入らなければいけないのです。他の人を押しのけてでも、私が一番にならなければいけなかったのです。そのような池の周りの人間関係は最悪だったでしょう。いつ起こるかわからない波を待ち、全員がお互いを出し抜こうと考えていました。弱肉強食で、緊張が張り詰め、ぎくしゃくしています。まるで生存競争ようなの場所だったはずです。皆、どうしたら自分が一番になれるのかばかりを考えていました。
それでも多くの人がこの池の周りに集まりました。4節には目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人が集まっていたとあります。想像するだけで悲しいです。なぜなら彼らは波が起きてもすぐに水の中に入ることがほとんど不可能な人たちだからです。それでも彼らはそこに集まっていたのです。もしかすると見捨てられて、そこしか居場所が無かったのかもしれません。ほとんど期待できない希望をもって、失望と共にそこで待ったのです。
その中に一人、38年間病気の男性がいました。そして池の周りに横たわっていました。イエス様はその人を見て、すぐに病気であることが分かりました。目に見える病気を持っていたのでしょう。彼は自分では起き上がり、立つことができないほどの障がいを持っていました。イエス様はそのような場所に現れました。苦しみと失望と緊張関係に満ちた場所に現れました。イエス様とはそのようなお方です。苦しみと失望の底に現れるのです。
イエス様はそこで問いかけました「良くなりたいか?」。失礼な質問です。当然、良くなりたいに決まっているじゃないですか。良くなりたいと答えるはずです。でも本当にそうでしょうか。38年間の彼の苦痛は想像できません。38年間で何人、この池に飛びこむ人を見たでしょうか。どれほどの我先にとこの池に飛び込む競争を見てきたでしょうか。そして彼はこの生存競争に38年間負け続けていました。彼はまだ良くなりたいと思っていたでしょうか。なんとか次こそは私が入ってやる、次こそ自分だと希望を持つことができていたでしょうか。その思いは38年も続くでしょうか。続かなったのではないでしょうか。きっと良くなりたいということを、もうあきらめていたのではないでしょうか。
イエス様の「良くなりたいか」という問いかけに彼は「良くなりたい」と答えることができませんでした。彼はその代わり「誰も私を運んでくれない」と答えました。彼の失望が伝わって来る言葉です。彼が失望していたのは、もはや自分が病であることではありません。彼が失望していたのは自分の周囲にいた人間でした。自分のことを優先する人間に失望し、助けてくれない隣人に失望していたのです。誰も他者を助けようとしない世界に失望していたのです。
彼のいた世界は自分優先の世界です。自分の幸せを一番優先にする世界です。他人はどうでもよい、幸せは争い奪い合って、勝ち取るという世界です。争って、つかみ取る力のない者には、幸せは訪れない世界でした。希望を持てない彼を責める気にはなれません。彼を失望させたのは彼のいた世界です。奪い合う世界、醜い競争の世界が、彼にそのような世界観を持たせ、失望させたのです。イエス様の「良くなりたいか」という質問はそんな世界を鋭く問う質問でした。
そしてイエス様は言いました「起き上がりなさい」起き上がることのできない、歩くことのできない人に対して命令をしました。そうすると不思議と彼は立ち上がることができました。38年間悩み、様々なことを試し、世界に失望し、あきらめていた彼がもう一度立ち上がって、歩きだしたのです。
イエス様は歩き出すときに一つだけ条件を付けました。それは床を担いで歩きなさいという条件です。「床を担いで歩きなさい」の床とは、横になる時に下に敷くものです。布団よりももっと粗末なマットやゴザの様なものです。それは彼が38年間寝ていたマットです。それには彼の38年間の汗と涙がしみ込んでいました。そして彼の心と同じように擦り切れ、ボロボロになっていました。そのマットは彼の人生を象徴するものです。そして彼がいた池の周りの世界を象徴するものです。彼の苦労と屈辱の象徴でした。自由を奪っていた病と世界の象徴でした。それが床です。イエス様が歩き出すときにつけた唯一の条件は、その床を担ぐようにということでした。彼の人生の苦労と屈辱と汗と涙のすべての象徴である「床」を担いで歩くようにと言ったのです。それは、これからもその現実を背負って生きてゆきなさいという意味です。彼は一切の苦しみから解放されて、病気やこの池の出来事などすべて無かったものとして生きるのではないということです。これからもこの38年間の苦労を忘れずに、あの池で見た世界を忘れずに生きるようにと条件を付けられたのです。そのようにして彼は元の世界へと戻されてゆきます。この悲しみも苦しみも、人間の醜さもすべてを背負ったまま彼は歩み出したのです。
彼が生き始まめると、すぐに白い目で見られました。彼を見て喜んだ人がいたという報告はありません。体調が回復し、病とあの池の環境から抜け出すことができた、それが祝われている様子は報告されません。周囲からの祝福はあったでしょうか。「よかったね」と言われ、喜び合ったでしょうか。しかしその様子は描かれていません。記録されているのは周囲が、今日は荷物を背負ってはいけない決まりがある日なのに、なぜあなたは荷物を背負って歩いているのかと聞いたことです。他人の幸せを喜び合えない世界です。実は外の世界も池の周りと変わらなかったのです。自分が一番先で、周りはどうでもよいと考えたあの池と同じように、ここでは他者と共に喜ぶ姿は存在しなません。誰がそんなことを言ったのか、誰が決まりを破るように指示したのか聞き、足の引っ張ろうとしています。そしてそのようにしてイエス様は十字架にかけられてゆくのです。
さて、今日の物語から私たちはどんなことを考えるでしょうか。まず私が思うことは、この世界はまるでベトザタの池の様だということです。世界はこの池のように、自分中心、自国優先、強い者が勝つ世界です。隣人と愛し合うのではなく、たがいに敵同士のように競争する世界です。互いを喜び合えない世界です。私たちもこのような世界・日常に生きています。
イエス様はそのただなかに現れるお方です。ひどい現実の、どん底の、この世界の真ん中に現れるお方です。そして私たちに問いかけるのです。「良くなりたいか?」。私たちはなんと応えるでしょうか?みんながちゃんとしてくれないから、周りの人が悪いから、彼らのせいでこうなっていると言いたくなる現実です。でもその時イエス様は、私たちを立ち上がらせ下さいます。
人間には立ち上がるすべがないはずなのに、良くするすべがないはずなのに、神様が人間に力を与え、立ち上がることができるのです。神様はそのように、私たちを立ち上がらせてくださるのです。
そして神様は、私たちをただ立ち上がらせるだけではありません。現実を背負って立ち上がるように、私たちに言うのです。世界の悲しみ、苦しみを忘れて、無関係に生きるのではありません。それを背負って生きる、それに責任をもって生きるように、私たちを立ち上がらせるのです。今私たちのいる世界を良くするために、神様は私たちを立ち上げてくださるのです。
この礼拝で、私たちは神様から床を担いで立ち上がれと言われています。私たちは自分では立ち上がることができないけれど、神様が私たちを立ち上げてくださるのです。私たち立ち上がります。現実を背負って立ち上がります。そして小さな力でも世界を「良くしたいか」と問われます。私たちは「良くなりたいです」と答えましょう。私たちは現実を背負って生きましょう。それぞれの場所で、互いに愛し合い、困っている人を助け、隣人と喜びをともにしましょう。それぞれの場所で弱肉強食ではない、愛と慈しみにあふれる世界を創ってゆきましょう。その1週間を今日から歩みましょう。神様が私たちを立ち上げて下さいます。お祈りします。
「神が私を立ち上げて下さる」ヨハネ5章1~13節
イエスは言われた。「起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。」
ヨハネによる福音書5章8節
今月と来月は、キリスト教が初めてという人に向けて話をしています。2000年前にベトザタという池がありました。この池には天使が降りてくると、池の水面にゆらゆらと小さな波ができ、その時、池の中に入ると、一番先に入った人は病気が治るという伝承がありました。
しかしこの伝承は残酷です。治るためには他の人を押しのけてでも、誰よりも早く水に入らなければいけないのです。そこは生存競争の場であり、人間関係は最悪でした。その中に38年間病気の男性がいました。彼は自分では起き上がることができませんでした。しかし彼が失望していたのは、もはや自分が病であることではありませんでした。彼が失望していたのは誰も他者を助けようとしない世界です。イエス様はそのような場所に現れました。イエス様は苦しみと失望と緊張関係に満ちた場所に現れるのです。
そこでイエス様は「起き上がりなさい」と言いました。世界に失望し、あきらめていた彼はもう一度立ち上がって、歩きだしました。そしてイエス様は歩き出すときに床を担いで歩きなさいという条件を付けました。床とは38年間寝ていたマットです。マットには汗と涙がしみ込み、擦り切れ、ボロボロになっていました。そのマットは彼の人生を象徴するものです。そして彼がいた池の周りの世界を象徴するものです。彼の苦労と屈辱の象徴でした。その床を担ぐようにとは、これからもその現実を背負って生きてゆきなさいという意味です。この38年間の苦労を忘れずに、あの池で見た世界を忘れずに生きるようにと条件を付けられたのです。
今日の物語から私たちはどんなことを考えるでしょうか。まず私が思うことは、この世界はまるでベトザタの池の様だということです。世界はこの池のように、自分中心、自国優先、強い者が勝つ世界です。隣人と愛し合うのではなく、たがいに敵同士のように競争する世界です。互いを喜び合えない世界です。私たちもこのような世界・日常に生きています。イエス様はそのただなかに現れるお方です。ひどい現実の、どん底の、この世界の真ん中に現れるお方です。
そしてイエス様は、私たちを立ち上がらせ下さいます。私たちは苦しみを忘れて、苦しみと無関係に生きるのではありません。それに責任をもって生きるようになります。神様はそのようにして私たちを立ち上がらせるのです。今私たちのいる世界を良くするために、神様は私たちを立ち上げてくださるのです。
この礼拝で、私たちは神様から床を担いで立ち上がれと言われています。私たちは現実を背負って立ち上がります。私たちはそれぞれの場所で、互いに愛し合い、困っている人を助け、隣人と喜びをともにしましょう。それぞれの場所で弱肉強食ではない、愛と慈しみにあふれる世界を創ってゆきましょう。その1週間を今日から歩みましょう。神様が私たちを立ち上げて下さいます。お祈りします。
【全文】「誤解から始まる信頼」ヨハネ4章1~30、39~42節
みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこうしてこどもたちの声を聞きながら、大人もこどもも共に礼拝をしましょう。
4月と5月は新しくキリスト教に触れる人に向けて話をしたいと思っています。聖書の中でも有名な個所を聞きながら、一緒に考えましょう。特に聖書の中のヨハネ福音書という部分取り上げてゆきたいと思います。
私は会社の勤めていた時、誤解や失敗をきっかけに他者との信頼関係ができるということを何度か経験しました。例えばクレームを頂いた取引先に訪問し、謝罪をしたり、対話したりしてゆくと、以前よりお互いの事情が分かるようになり、信頼関係が生まれることがありました。クレーム対応をきっかけに、個人的な信頼関係が生まれました。そのような経験が何度もありました。もちろんそのような信頼関係がいつもできるわけではないのですが、いつからかクレームを頂く度に、ここから新しい信頼関係ができればいいと思いながら対応をするようになりました。
このように衝突や誤解がきっかけで相互の理解が生まれ、信頼関係につながってゆくということがあります。みなさんにもそんな経験があるでしょうか。第一印象が悪かったのに、誤解が解けて仲が良くなった人がいるでしょうか。昔は嫌いだったのに今は好きな食べ物も同じだと言えるでしょうか。
関係は必ず修復発展できるというわけではないのですが、相互の信頼関係は互いの誤解に向き合うことによって、対話することによって生まれてゆきます。誤解は信頼の入り口でもあります。聖書にもこのような誤解から信頼が始まるエピソードがあります。今日はそのエピソードをご紹介したいと思います。
ヨハネ福音書4章1~30節、39~42節をお読みいただきました。キリスト教の中では有名なサマリアの女という話です。登場人物はサマリアの女性です。実はこのサマリアの女性は幾重にもわたって社会から疎外された人でした。まず当時ユダヤの人々はサマリアという言葉を口に出すのをはばかるほどサマリアの人々を嫌っていました。なぜならサマリアの人々は混血民族と考えられたからです。サマリアの人々は民族の純血を大事にしたユダヤ人から、いわゆる混血とされ、見下され、差別されたのです。
さらに女性という点にも注目します。当時の社会は今よりもっとひどい男性中心社会でした。女性の地位はとても弱く、女性は男性の所有物とみなされ、男性が一方的に離婚することが可能な社会でした。このようにサマリアの女性は、民族的にも性別的にも差別を受けた人でした。
そのサマリアの女性が井戸に水を汲みに来ました。当時、水汲みは女性の仕事でした。通常女性は水汲みを朝の涼しい時間帯にするものでした。しかし聖書には彼女が正午・昼の12時の一番暑い時間に水を汲みに来たとあります。その理由はおそらく彼女が同じサマリアの女性たちからも疎外されていたからです。5回の離婚を経験した彼女の波乱の人生は、村の人から奇異の目で見られていました。彼女はいろいろな噂をされたり、白い目で見られたりしたのでしょう。彼女は村八分にされ、誰もいない時間を見計らってコソコソと井戸に来たのです。
5回の離婚の理由はわかりません。彼女に問題が有ったのか、無かったのかわかりません。しかし当時は男性が一方的に離婚を言い渡しました。戦争や飢餓や暴力が絶えず、今よりずっと死は身近でした。この女性に責任・罪があって今の境遇にいるという推測は、噂をして村八分にした人と同じ誤解でしょう。このようにこの女性は幾重にもわたって社会から疎外された人でした。多くの誤解を受けた人でした。だから彼女は誰とも会わない、関わらないで済む時間に井戸に来たのです。
そんな時、イエス様と出会います。イエス様はそんな社会から疎外された人に、自分から言葉を掛けました。神様はそのようなお方です。人間の世界では差別や、いじめ、仲間外れ、排除があります。でも神様は違います。神様は神様の方からその人を見つけ、声をかけ、招いて下さるお方です。さらに当時は男性が見知らぬ女性に声をかけることもタブーでした。それでもイエス様は、その人に声をかけるのです。神様はそのように働きかけてくるのです。
イエス様との会話を見てゆきましょう。声のかけ方が面白いと思います。イエス様は「水をください」と声をかけるのです。復活した時も「何か食べる物はありますか」と声をかけたのですが、今回は「水をください」です。この問いかけに向き合います。
水を巡ってのイエス様と女性との会話は複雑です。特に10節はイエス様が水をくださいと言っているのか、イエス様が水をあげると言っているのか、よくわからない箇所です。読んでいる私たちも混乱する話、誤解が生じやすい話です。
どうやらイエス様が与える水というのは、肉体的にのどを潤す水分補給のことではないようです。その水とは心と魂を潤す水のことを言っています。それは心の内面に染み渡るような何かです。彼女の心と魂は何かを求めているのに埋まりません。心と魂が満たされず、渇いている状態です。その心と魂が求めていることを、満たしてくれるものが、イエス様の渡そうとしている水です。それは彼女にとっては周囲からの誤解と差別から解放されることだったでしょう。
しかしイエス様と女性の会話にも誤解があります。心と魂の水のことは女性には伝わっていません。女性は引き続き、のどを潤す水、ここまで汲みに来ないでよい水を求めています。誤解が続きます。
16節でイエス様は突然話題を変えます。話題は水の話から、結婚関係の話に話題が変わります。イエス様は対話をあきらめていないようです。伝えたいことが伝わらなくても、対話をあきらめずにまた別の角度から伝えようとしています。そして20節以降からはさらに話題が礼拝へと変わってゆきます。全体をみるとかなりかみ合わない会話です。ちぐはぐな会話です。会話は終始かみ合っていませんが、それでも二人が対話を続けていることはとても印象深いことです。
20節からイエス様は繰り返し礼拝という言葉を使っています。イエス様の言った心と魂を潤す水、それは礼拝と言い換えることができるでしょう。
この今私たちの持っている礼拝とは、自分の生き方を考える集まりです。自分はどう生きるのか、神様の言葉、神様の語り掛けを聞きながら考える集まり、それが礼拝です。一人ではなく、みんなとそれを考えます。イエス様はその礼拝が、あなたの心と魂を潤す水となると言ったのです。この礼拝というキーワードからようやく二人の話がかみ合ってきます。
女性はこのような対話からイエス様を信頼するようになりました。彼女はイエス様を、私に何が必要かを知り、私の心の渇きを知り、それを礼拝によって潤してくださるお方、私に新しい生き方を教えてくださるお方だと信頼をしたのです。イエス様との対話によって誤解が解かれ、この女性はイエス様を信頼するようになりました。そして彼女はその信頼を村の人々に告げ広めたのです。
村の人々も、最初は半信半疑でした。しかし村の人々は言います。自分で聞いたからよくわかった。それはイエス様の話を直接聞いて、誤解しなかったからこそ信頼できたという出来事でした。
イエス様とこの女性はすれ違いながらも、忍耐強く対話を続けることによって信頼が生まれました。誤解は信頼へと変わってゆきました。今日この個所を見て私は改めて対話の大切さを感じます。私たち人間にはたくさんの誤解があります。誤解に基づいて様々な戦争が起き、誤解に基づいてうまくいかない人間関係が生まれます。誤解は人々を苦しめます。差別も命に優劣があるという誤解から生まれます。
女性が苦しんでいたことは何よりも、周囲に誤解されたことだったはずです。そして彼女の中でもイエス様への誤解がありました。でもそれでよいのです。多くの関係は誤解から始まってゆくからです。その誤解は徐々に解かれてゆくものです。私たちにも今日この個所からそのことが示されているのでしょう。私たちの周りにもたくさんの誤解があります。誤解したり、誤解されたりすることがあります。でも私たちはイエス様のように向き合い、対話することをあきらめずにいたいのです。今日の個所のように誤解から始まる信頼がきっとあるはずだからです。
私たちはどうやって、誤解を信頼に変える力をいただくことができるのでしょうか。私たちが自分を変えるには限界があります。自分では変わりたくても、変わることができないのです。でも私たちはきっとその力を礼拝からいただくことができます。私たち人間は互いに理解できず、誤解が解けない、信頼しあえない存在です。私たちは人間の力だけでは、豊かな信頼関係を築くことができないことを良く知っています。でもだからこそ私たちは神様から、その力をいただきたいのです。この礼拝で神様から他者を理解する力、誤解のある他者と信頼を作ってゆく力を受け取りたいと思うのです。礼拝からその力をもらい、それぞれの場所で誤解を信頼に変えたいのです。
初めての方、まだ教会に来たことのない方にも、ぜひこの礼拝に加わって欲しいと思っています。教会に昔からいる人、最近来るようになった人の間にも、お互いにいろいろな誤解があるかもしれません。でもきっと礼拝を共にしてゆくことで互いに分かり合えると思います。
ぜひ礼拝にお越しください。そしてこれからも共に礼拝を献げ、神様から、誤解を信頼に変える力を互いに頂いてゆきましょう。お祈りします。
「誤解から始まる信頼」ヨハネ4章1~30、39~42節
サマリアの女が水をくみに来た。イエスは、「水を飲ませてください」と言われた。
ヨハネによる福音書4章7節
4月と5月は新しくキリスト教に触れる人に向けて話をしています。今日登場するサマリアの女性は幾重にもわたって社会から疎外された人でした。いわゆる混血とされ見下され、差別されました。さらに女性という点でも差別を受けました。
そのサマリアの女性が、日中の一番暑い時間に井戸に水を汲みに来ました。彼女がサマリアの女性たちからも疎外されていたからです。5回の離婚を経験した彼女の波乱の人生は、村の人から奇異の目で見られていましたのです。
そんな時、イエス様と出会います。水を巡ってのイエス様と女性との会話は誤解が生じやすい話です。イエス様が与える水というのは、肉体的にのどを潤す水分補給のことではないようです。その水とは心と魂を潤す水のこと、心と魂が求めていることを満たしてくれるものが、イエス様の渡そうとしている水です。
しかしイエス様と女性の会話にも誤解があります。16節でイエス様は突然話題を変えます。イエス様は対話をあきらめていないようです。対話をあきらめずにまた別の角度から伝えようとしています。全体をみるとかなりかみ合わない会話です。それでも二人が対話を続けていることはとても印象深いことです。
20節からイエス様は繰り返し礼拝という言葉を使っています。イエス様の言った心と魂を潤す水、それは礼拝と言い換えることができるでしょう。この今私たちの持っている礼拝とは、自分の生き方を考える集まりです。イエス様はその礼拝が、あなたの心と魂を潤す水となると言ったのです。この礼拝というキーワードからようやく二人の話がかみ合ってきます。女性はこのような対話からイエス様を信頼するようになりました。イエス様との対話によって誤解が解かれ、イエス様を信頼するようになりました。そして彼女はその信頼を村の人々に告げ広めたのです。
イエス様とこの女性はすれ違いながらも、忍耐強く対話を続けることによって信頼が生まれました。誤解は信頼へと変わってゆきました。今日この個所を見て私は改めて対話の大切さを感じます。私たち人間にはたくさんの誤解があります。誤解は人々を苦しめます。差別も命に優劣があるという誤解から生まれます。でも私たちはイエス様のように向き合い、対話することをあきらめずにいたいのです。今日の個所のように誤解から始まる信頼がきっとあるはずだからです。
私たちは、誤解を信頼に変える力を礼拝からいただくことができます。私たち人間は人間の力だけでは、豊かな信頼関係を築くことができないことを良く知っています。でもだからこそ私たちは神様から、その力をいただきたいのです。この礼拝で神様から他者を理解する力、誤解のある他者と信頼を作ってゆく力を受け取りたいと思うのです。礼拝からその力をもらい、それぞれの場所で誤解を信頼に変えてゆきたいのです。共に礼拝を献げ、神様から、誤解を信頼に変える力を互いに頂いてゆきましょう。お祈りします。


